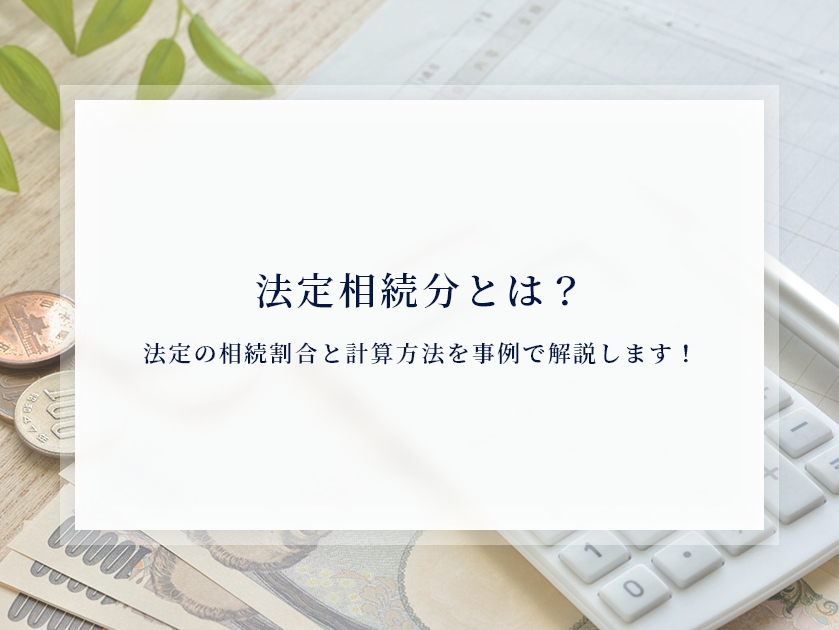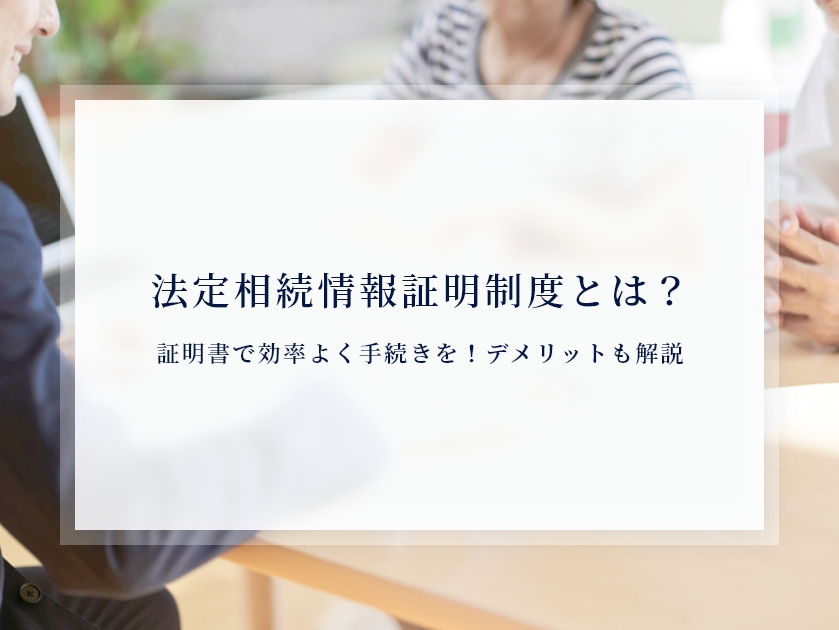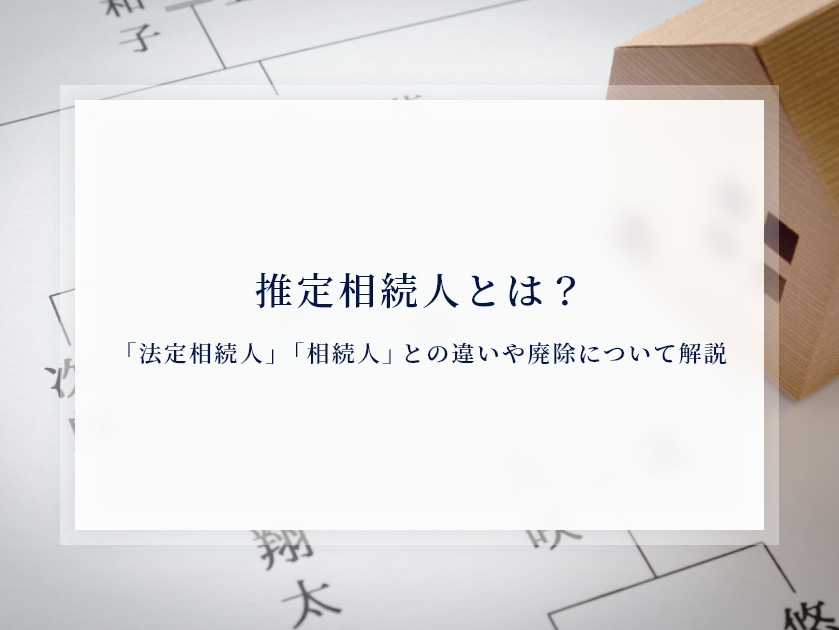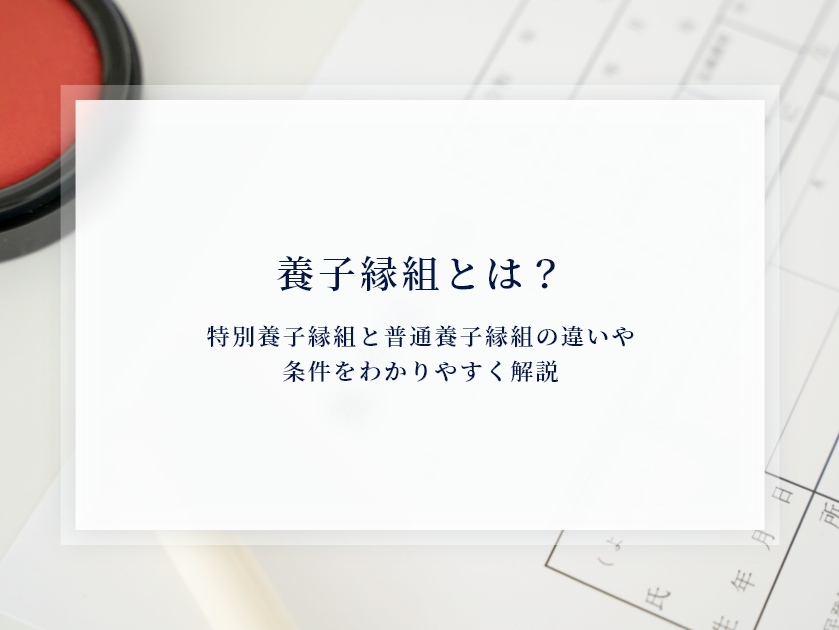配偶者なし・子なし・親なし・兄弟ありの相続|法定相続人はどうなる?
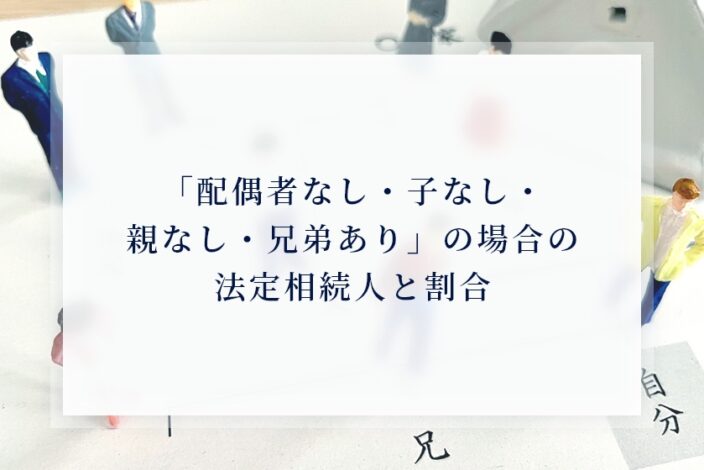
現代社会において、「配偶者なし・子なし・親なし」という状況は珍しくありません。かつては家族を持つことが一般的で、「行き遅れ」などと揶揄する言葉もありましたが、今日では多様な生き方が認められ、独身で生涯を終える人も増えてきています。
さて、「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」の場合、被相続人の遺産はどのように扱われるのでしょうか。
この記事では、配偶者、子ども、親がいない場合に誰が法定相続人になるのかといった疑問や、兄弟が唯一の相続人となる場合の財産の行方について、弁護士が解説させていただきます。
目次
配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり、の相続
日本の家族構造は、時代と共にさまざまな形を見せています。社会が多様なライフスタイルを認めるようになったことで、生涯未婚の人や、子供を持たない選択をする人々の割合が増えているのです。
こうした時代ですから、「配偶者なし・子なし・親なし」といった状況で、兄弟や姉妹だけはいる、という人も珍しくありません。
ところで、このような場合には、誰が法定相続人になるのでしょうか。
配偶者なし・子なし・親なし、の相続は兄弟が法定相続人
被相続人(亡くなった人)の財産は原則として、遺言書によって指定された相続人か、民法のルールによって決まる法定相続人に引き継がれます。
民法で法定相続人として認められているのは、配偶者と特定の親族に限られます。
この中でも、配偶者は常に相続人として相続する権利を持ちます。配偶者以外の親族については、法律で決められた順位によって相続権の有無が決まることになります。自分よりも順位が上の親族がいる場合、下順位の親族は相続権を持たないため、法定相続人にはなりません。
被相続人の配偶者を除いた相続の順位は、次の通りです。
|
第一順位 |
子や孫など直系卑属(民法第887条1項) |
|
第二順位 |
親や祖父母など直系尊属(民法第889条1項1号) |
|
第三順位 |
兄弟姉妹(民法第889条1項2号) |
子あり、親あり、の場合は兄弟は法定相続人になれない
つまり法定相続のルールでは、被相続人に子供がいる場合、その子供が法定相続人として優先的に遺産を受け継ぎます。このとき、たとえ被相続人に親や兄弟姉妹がいたとしても、彼らに相続権はありません。
また、被相続人に子供がいない場合には、第二順位者である親(直系尊属)が法定相続人となります。もちろんこの場合も、第二順位者がいるため第三順位者である兄弟姉妹に相続権は回ってきません。
兄弟姉妹が相続人となるのは、亡くなった人に子供も親もいないという、特定の状況下だけなのです。
「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」の相続分
さて、法定相続人が誰か分かったところで、次に気になるのはどれだけの遺産を受け継ぐか、という点かと思います。
この点、遺言書が存在する場合は、遺言の内容に従って遺産が分配されることになります。「兄弟姉妹で平等に分配するように。」といった遺言もあれば、「長男に不動産を全て相続させる。二男と長女で預貯金を公平に分配すること。」といった遺言もあるでしょう。
遺言書がない場合は、基本的に民法に定められた相続割合(法定相続分)に従って遺産が分配されることになります。この「法定相続分」とは、被相続人の財産を相続人間でどのように分けるかという割合のことです。
具体的な相続割合は、相続人が誰であるか、どういった組合せかによって変わってきます。
例えば、「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」で遺言書がないケースでは、法定相続人は兄弟だけとなりますので、被相続人の遺産全てを兄弟姉妹で均等に分配することになります。
相続人として4人の兄弟姉妹がいる場合、被相続人の遺産は4等分です。具体的には、被相続人が残した財産が4,000万円であれば、それぞれの兄弟姉妹は1,000万円ずつ相続する計算になります。
異母兄弟ありの場合の相続
ところで、兄弟といっても、全員が同じ両親から生まれた兄弟とは限りません。父親や母親が異なる兄弟(異父兄弟、異母兄弟)がいるケースもあるかと思います。
同じ両親から生まれた兄弟と、異父・異母兄弟では、前述した法定相続分が変わってくるため注意が必要です(民法第900条4号ただし書)。
(法定相続分)
民法第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
異父・異母兄弟の相続分は、同じ両親から生まれた兄弟の2分の1、と定められています。「同じ両親から生まれた兄弟:異母兄弟=2:1」という割合で遺産が分配されることになるわけです。
例えば、被相続人に配偶者、子供、親がおらず、4人の兄弟姉妹が法定相続人となるケースを考えてみましょう。この4人のうち、3人は両親が同じですが、1人が異母兄弟であったとします。
それぞれの相続分は、「同じ両親から生まれた兄弟A:兄弟B:兄弟C:異母兄弟=2:2:2:1」となります。仮に被相続人の遺産が700万円であったとすると、「兄弟A:兄弟B:兄弟C:異母兄弟=200万円:200万円:200万円:100万円」という分配になるのです。
兄弟以外に財産を遺すには
以上の通り、「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」の場合、兄弟が法定相続人となります。ですが、兄弟との関係が希薄な被相続人が、兄弟以外の親しい人に財産を残したい、と考えることも少なくありません。
親族以外の人へ財産を確実に渡す方法には、遺言書の作成や生前贈与などがあります。これらの手段を通じて、被相続人は自分の意思に沿った形で財産を分配することが可能です。
生前に適切な準備と手続きが必要となるため、以下では兄弟以外に財産を遺す方法について、具体的な手順や注意点に焦点を当てて見ていきましょう。
①遺言書を作成しておく
法定相続人ではない人物に財産を遺すには、「遺言書を作成しておく」という方法が一般的です。遺言書によって、法定相続人でない人にも、指定した方法で財産を遺すことができます。遺言書による遺産相続を「遺贈(いぞう)」といいます。
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つの主な形式があります。
自筆証書遺言は、全文を遺言者が自分で書き、日付の記載と署名をすることで作成できるため手軽です。反面、形式に誤りがあると、遺言書が無効となってしまうリスクがあります。
一方、公正証書遺言とは、公証人が立ち会い、公証役場で適切な手続きに従って作成される公文書です。あらかじめ内容を公証人が確認するため、形式的な不備により無効となる心配もなく、紛失や盗難のリスクも回避できます。そのため、遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言を作成しておくことをお勧めいたします。
兄弟に遺留分はない
なお、遺贈で法定相続人以外に財産を相続させる場合、通常は遺留分の侵害に気を付ける必要があります。遺留分とは、法律によって特定の法定相続人にのみ保障されている、最低限の取り分のことです。
ですが、法定相続人が兄弟姉妹だけの場合は、遺留分を気に掛ける必要はありません。配偶者、子供や親には認められていますが、被相続人の兄弟には遺留分は認められていないのです(民法第1042条1項)。
(遺留分の帰属及びその割合)
民法第1042条1項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
そのため、もし被相続人が遺言で全財産をある人に遺贈しても、兄弟が遺留分侵害額請求をすることはできません。
②生前贈与しておく
兄弟以外に財産を遺したい場合、生前贈与も有効な手段です。
生前贈与をする相手は、親族である必要がないため、被相続人の意向で誰にでも行うことができます。
生前贈与をする際の注意点としては、贈与税がかかる可能性がある、という点です。
贈与税の税率は、場合によっては相続税の税率よりも高くなり得るため、税の負担が重くならないように計画的に行うことが大切です。
例えば、年間に贈与する金額が110万円以下であれば、贈与税の基礎控除の範囲内となりますので、税金が発生しません。この控除を上手に活用することで、税負担を抑えながら生前贈与をすることが可能です。
③死因贈与する
死因贈与は、特定の人に対し将来的に財産を渡すことを、生前のうちに約束しておく契約のことをいいます。この死因贈与の契約によって、その人が亡くなったときに初めて、指定した人に財産が渡ります。
しかし、この契約は相続人に周知されなければなりません。もし相続人が死因贈与契約を知らない場合、その契約の効力は発生しないことになります。死因贈与の契約内容を相続人に知らせるためには、遺言書に記載しておく方法が最も確実です。
遺言書に死因贈与したことを明記しておくことで、遺言書に基づいた遺産分割の際に、約束された死因贈与が適切に実行されます。
配偶者なし・子なし・親なし・兄弟死亡の場合の相続
もし、配偶者も子も親もおらず、相続権を持つ兄弟が被相続人より先に亡くなっていた場合、相続権はどうなるのでしょうか。
この場合、法定相続人になるはずだった兄弟の子供(被相続人の甥や姪)が、親に代わって相続権を引き継ぐことになります(代襲相続)。
例えば、被相続人に4人兄弟(A、B、C、D)がおり、遺産が800万円あるとします。
このうち、兄弟Dが被相続人より先に亡くなっていた場合、その亡くなったDの相続分は、Dの子供(d1、d2)に移ります。
具体的な金額を算定していきましょう。
遺産800万円は、まず「4人兄弟」で公平に等分されることになります。各兄弟には、それぞれ200万円を相続する権利があるわけです。そして、そのうちの1人であるDは亡くなっていますから、200万円についてはその子供d1、d2が受け継ぎます。d1とd2の相続割合は均等なので、「200万円×2分の1」がd1、d2それぞれの相続分となります。まとめますと、以下の通りになります。
被相続人の兄弟B:200万円
被相続人の兄弟C:200万円
被相続人の甥d1:100万円
被相続人の姪d2:100万円
兄弟の子もいない場合の相続
「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」に加え、それぞれの代襲相続者もない場合は、法定相続人がいません。いわゆる「おひとりさま相続」ですが、この場合は特別な手続きが必要になります。
まず、検察官や利害関係人が家庭裁判所に申立てをし、裁判所が相続財産清算人(相続財産管理人)を選任します。相続財産清算人は、被相続人の遺産を保管・管理します。それと同時に、2ヶ月以上の期間を定めて、相続権を主張する可能性のある相続人を探します。
指定した期間内に相続人が現れない場合、遺産は次の手順で分配されることになります。
特別縁故者がいる場合は分与する
法定相続人がいないことが確定した場合、特別縁故者が相続財産の一部を受け取ることができる可能性があります。
特別縁故者とは、被相続人と特別な関係があった人々のことで、例えば内縁関係の妻や夫、被相続人と共に生計を立てていた人、療養看護を提供していた人などが該当します。
特別縁故者として財産を受け取るためには、相続人の不存在が公告されてから6ヶ月経過した後に、3ヶ月以内に家庭裁判所へ財産分与の申立てを行う必要があります。
家庭裁判所は、被相続人と特別縁故者との関係の深さ、特別縁故者の財産状況、生活状況などを総合的に考慮して、財産分与を認めるかどうか、そして認める場合の具体的な分与内容や範囲を決定します。
最終的には国庫に帰属する
法定相続人も特別縁故者もいない場合や、特別縁故者に財産を分与した後でもまだ財産が残っている場合は、残った遺産は最終的に国庫に帰属することになります。
国庫に帰属した遺産については、被相続人の意向が反映されることはありません。ですので、自分の財産を使ってほしい人がいる場合や、意図した通りに使ってもらいたい場合には、生前にしっかりと遺言書を作成し、財産の分配方法を決めておきましょう。自分の財産の分配について明記し、意思をはっきりと残しておくことで、遺産が望まない形で国庫に帰属してしまうのを防ぐことができます。
配偶者なし・子なし・親なし・兄弟ありの相続のポイント
さて、相続人が兄弟のみの場合、遺産相続は簡単に終わると思うかもしれません。ですが、実際には遺言書の内容でもめることになってしまったり、うまく遺産の分配を進められなかったりすることもあります。
遺産相続に備えて、被相続人は以下のポイントに注意しておきましょう。
- 所有する財産や債務を明確にする
- 誰が相続人になるのか確認しておく
- 具体的な遺言書を作成する
①所有する財産や債務を明確にする
自身の所有する財産や債務の状況を確認し、相続手続きに備えることが大切です。
所有する不動産、車、貯金、株式などの資産はもちろん、住宅ローンや個人ローンなどの債務も正確に把握しておきましょう。財産と債務の詳細を一覧にした財産目録を作成しておくことで、相続人は遺産の分割や手続きを円滑に行うことができます。
また、債務の情報があることで、相続人は相続を放棄するかどうかを冷静に判断することが可能になります。相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に裁判所へ申請する必要があるので、事前の準備が重要です。
②誰が相続人になるのか確認しておく
「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」という状況では、誰が相続人になるのかが分かりにくいことがあります。そのため、自分の相続人が誰になるのかを事前に確認し、法定相続人の有無を明確にしておくことが重要です。
また、もし法定相続人が誰もいない場合でも、特別縁故者となり得る人がいるかについても確認しておく必要があります。あらかじめ特別縁故者に知らせておけば、特別縁故者が相続財産分与の申立てに備えることができます。
他にも、遺言書の作成や生前贈与、死因贈与といった具体的な対策を検討できるため、相続人の確認は非常に重要です。
③具体的な遺言書を作成する
相続トラブルを避けるためには、遺言書を作成しておくことも有効です。
特に、相続人となる兄弟や甥姪が疎遠である場合、話し合いが難しく、相続手続きがスムーズに行われない可能性があります。遺言書によって、自分の財産がどのように分配されるべきかを明確に指示することで、遺産分割をスムーズに進めていくことが期待できます。
遺言書を作成する際は、その内容や形式に注意が必要です。内容に誤りがあったり、正しい形式でなかったりすると、遺言書が無効になることがあり、結果としてトラブルの原因となりかねないのです。
また、葬儀やお墓に関する希望についても、遺言書に書いておくことが大切です。
家系図や仏壇、墓石などの祖先をお祀りするための財産(祭祀財産)は通常、相続財産には含まれませんが、これらを管理する「祭祀主宰者」は被相続人が指定することができます。祭祀財産を引き継いでほしい人がいる場合、その旨を遺言書に記載しておくことで、自分の意思をはっきりと遺しておくことができます。
なお、遺言書ではなく、エンディングノートを作るという方法もあります。
また、葬儀に関する具体的な希望、例えば葬儀の形式や参列者、埋葬の場所などについても、エンディングノートに明記しておくことをお勧めします。葬儀は通常、死後すぐに行われるため、ノートにまとめた内容を、事前に家族や親しい人と共有しておくことも大切です。
Q&A
Q1.配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり、の相続人はどうなりますか?
A: 「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり」の場合の遺産相続は、民法の規定により、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、その子供(被相続人の甥姪)が相続人となり、その親の相続分を受け継ぐことになります。
Q2.兄弟に遺産を一切渡したくない場合の遺言書はどうすればいいですか?
A:兄弟には遺留分の権利がないため、遺言書で兄弟以外の人物に遺贈する意思を記載しておけば、兄弟に遺産が渡ることを防ぐことが可能です。遺言書には、誰に何を遺すのかをはっきり書きましょう。遺言書は正しい形式でなければ無効となってしまうので、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
Q3.相続人が兄弟姉妹だけの場合、相続分はどうなりますか?
A:兄弟姉妹が複数いる場合は、原則として相続分は均等です。ただし、異父兄弟・異母兄弟がいる場合は、両親が同じ兄弟姉妹の相続分の半分となります(民法第900条4号ただし書)。
まとめ
「配偶者なし、子なし、親なし、兄弟あり」という状況で亡くなると、兄弟で遺産を相続することになります。
ですが、普段からあまり連絡を取り合っていなかったり、仲が良くなかったりと、兄弟姉妹での遺産相続は感情的な対立が起きやすく、冷静な遺産分割の話し合いが困難なケースも少なくありません。
被相続人としても、兄弟以外に財産を相続させたい場合もあるかと思います。このような場合には、遺言書の作成、生前贈与、死因贈与など、様々な方法を通じて、自分の意思を最大限反映させることが可能です。
どのような方法で遺産を分配するかは、具体的な状況を踏まえ、生前にしっかり検討しておくことが重要です。
遺産相続に関する疑問や不明点がある場合は、状況が複雑化する前に、法律の専門家である弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。当Webサイトの予約フォームやお電話にて、お気軽にお問合せください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。