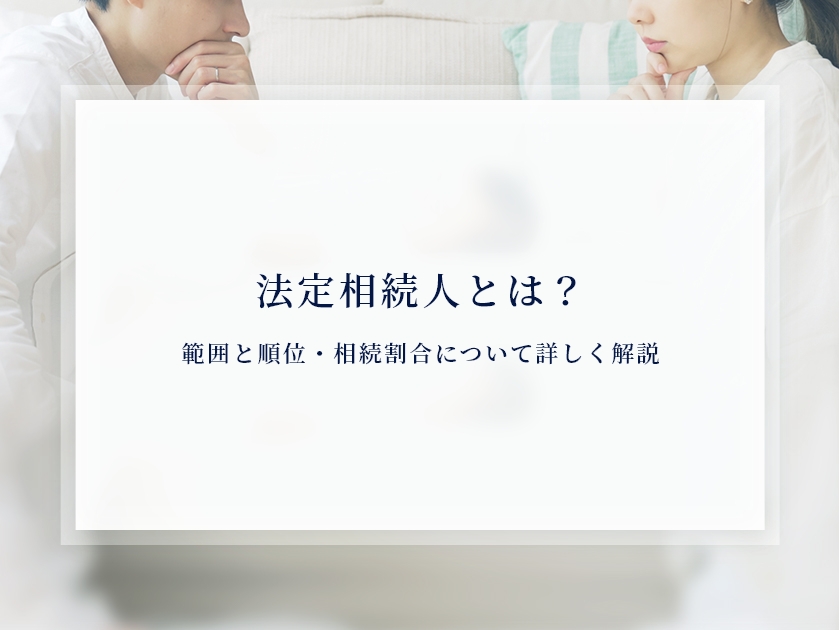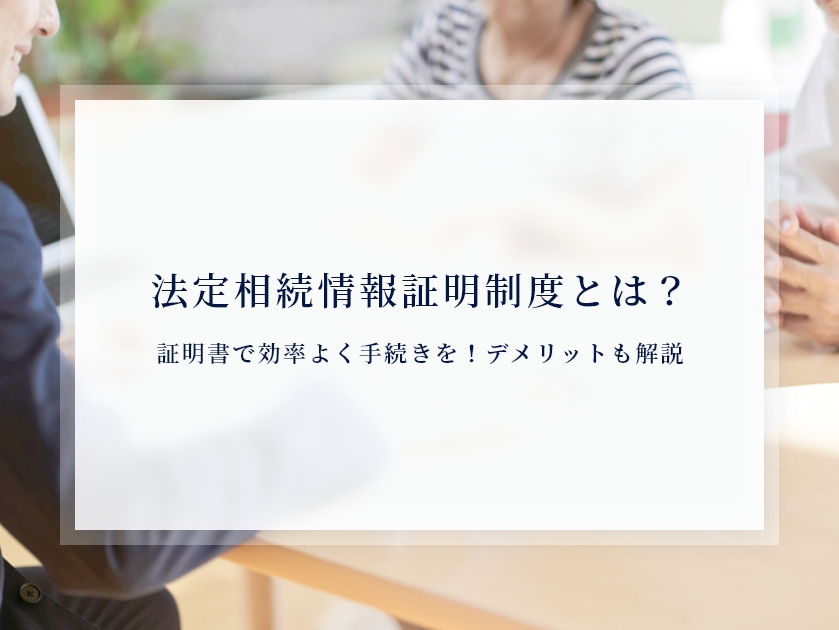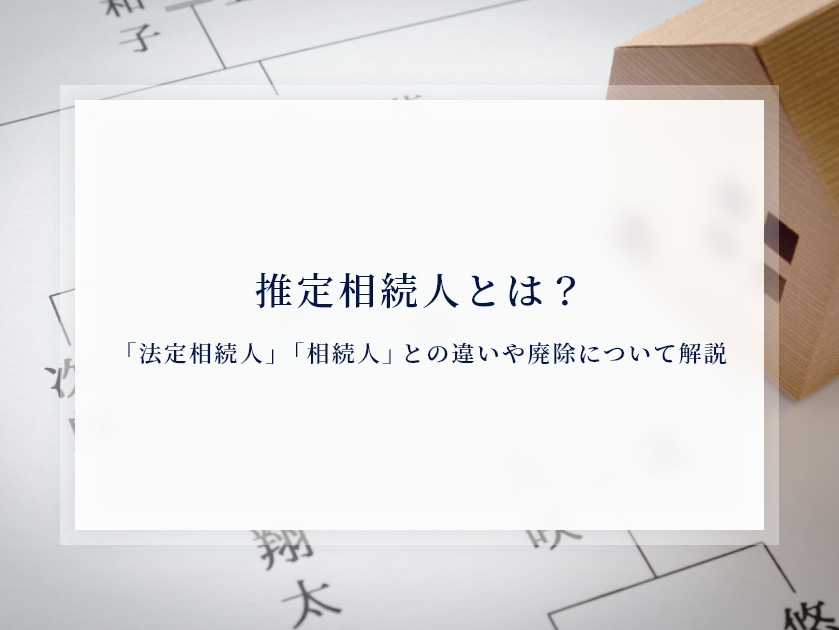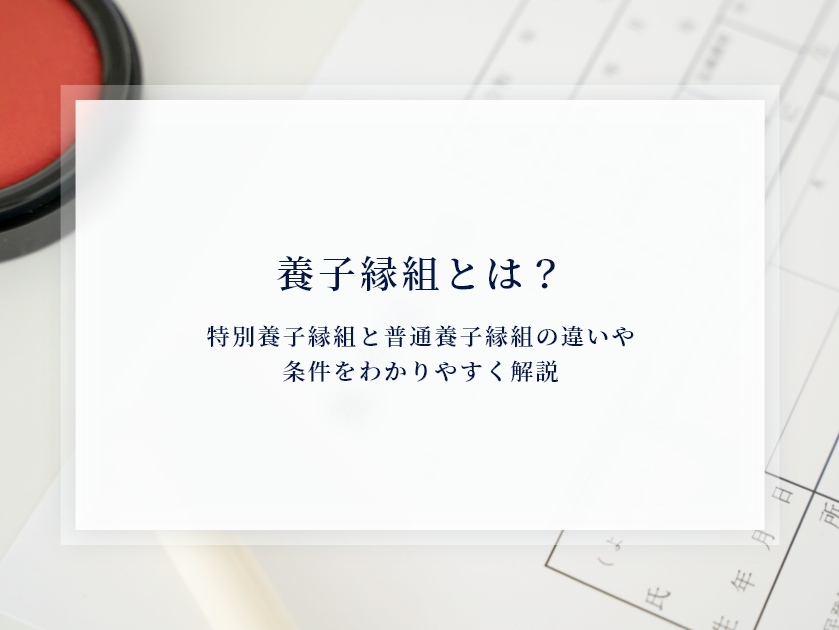夫死亡・子供ありの遺産相続|配偶者と子供2人の相続はどうなる?
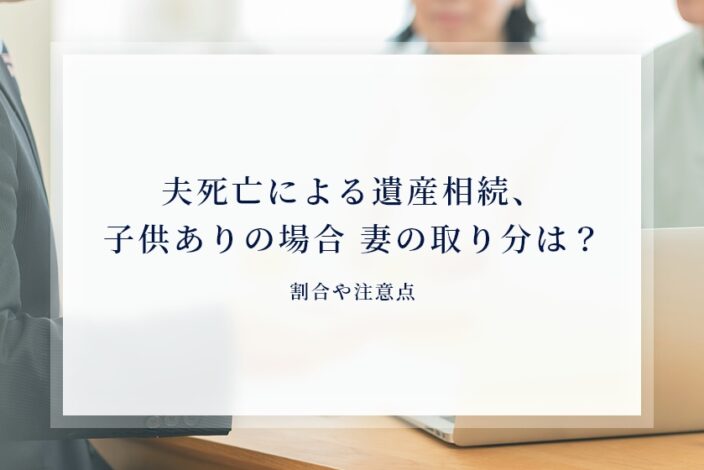
夫が亡くなった場合、妻と子供とで遺産相続をすることになるのが一般的です。
夫が遺言書を残している場合は別として、母親と子供で遺産相続を進める場合、どのように遺産分割の手続きが進んでいくのでしょうか。
本記事では、母親と子供が相続人となるケースを想定し、法定相続分の考え方や遺産分割協議の進め方、実際に注意すべきポイントなどについて、弁護士がわかりやすく解説させていただきます。
家族間の関係性や財産の種類によっては、手続きが思わぬトラブルに発展することもあるため、あらかじめ正しい知識を持っておくことが大切です。相続に直面して戸惑っている方、これから備えたい方にとっても役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
夫死亡・子供ありの遺産相続
それでは、夫が死亡し妻と子供とで遺産相続することになった場合、どのように相続が進むのかを確認しておきましょう。
妻と子供による遺産相続
遺産相続の進め方は大きく2つあります。被相続人が遺言書を作成していた場合は遺言書の指示に従って相続財産が分配され、遺言書がなければ相続人同士が話し合って進めます。
ですので、夫が亡くなる前に遺言書を作成していなかった場合も、妻と子供とが遺産分割協議をして相続手続きを進めることになります。
この際に参考になるのが、民法に定められたルールです。遺言書がないケースでは被相続人の意思が示されていないため、誰がどれくらいの財産を受け取るのか、法律の基準によって話し合いを進めていきます。
配偶者(妻)は常に法定相続人
遺産を受け継ぐ権利(相続権)を持る人のことを「法定相続人」といいますが、誰が法定相続人になるかは個々のケースによって変わります。というのも、法定相続人は①他の相続人の有無に左右されず、常に法定相続人になる配偶者(民法第890条)と、②他の相続人の有無によって相続権が左右される、血筋による相続人(民法第887条、第889条)の2つのタイプがあるからです。
(配偶者の相続権)
民法第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。(子及びその代襲者等の相続権)
民法第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
民法第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
まず、配偶者は常に法定相続人となるため、夫が死亡した場合は妻は法定相続人になります。
配偶者以外の相続人に関しては、民法に決められた順番が回ってきた場合に法定相続人となります。被相続人の子供は第一順位者となるため、配偶者を除いて最優先で法定相続人になります。
|
常に相続人 |
配偶者(民法第890条) |
|
第一順位 |
子や孫など直系卑属(民法第887条1項) |
|
第二順位 |
親や祖父母など直系尊属(民法第889条1項1号) |
|
第三順位 |
兄弟姉妹(民法第889条1項2号) |
配偶者と子供による遺産相続
それでは、配偶者と子供による遺産相続について、具体的な例もまじえながら見ていきましょう。
配偶者と子供の相続割合
民法では、法定相続人になれる人が決まっているだけでなく、相続人が遺産を相続する割合についても決まっています(法定相続分)。
夫が遺言を作成していなかった場合、この法定相続分によって遺産が分配されます。妻と子供とで遺産相続するケースでは、妻は常に遺産の2分の1を受け取り、残りの2分の1を子供が受け取ることになります。
子供が複数いる場合は、子供全体の相続分である「2分の1」を、子供の人数で均等に分けることになります。子供1人の場合は、子供の相続分は2分の1÷1=2分の1ですし、子供が4人であれば子供1人当たりの相続分は2分の1÷4=8分の1となるわけです。
|
家族構成 |
妻の相続分 |
子供1人の相続分 |
|
妻と子供1人 |
2分の1 |
2分の1 |
|
妻と子供2人 |
2分の1 |
4分の1 |
|
妻と子供3人 |
2分の1 |
6分の1 |
このように、子供の数が多くなればなるほど、子供1人当たりの取り分は少なくなりますが、妻は常に1人しかいませんので、妻の受け取る割合は変わりません。
【例】妻と子供2人の遺産相続
上で解説した内容をもとに、相続人が配偶者(妻)と子供2人の場合の遺産相続について、具体的な例を見てみましょう。
例えば、家、預貯金、株式が夫の遺産で、合計で1億円あるとします。
この場合、法定相続分に基づき、妻は半分の5,000万円、子供2人はそれぞれ残りの半分を分け合うため、2,500万円ずつ相続することになります。
なお、相続する遺産に家がある場合、家族としてはその家に住み続けたいと思うのが一般的です。住み続ける場合は家を売ってお金にかえることはできませんので、誰が住み続けるのか、その家の価値はどれくらいかなどを十分に確認しなければなりません。
このケースで妻が家に住み続けるとして、家の評価額が市場価格で3,000万円になった場合、妻は3,000万円の家を相続するわけです。妻の相続分は5,000万円ですから、残る2,000万円分の預貯金や株式などを相続することになります。子供2人は家を相続しないため、それぞれ2,500万円分の預貯金や株式を受け取ります。
妻が既に死亡している場合は?
ちなみに、夫が亡くなる前に妻が既に死亡しており、相続人が子供2人だけの場合、どのような遺産相続になるのでしょうか。
夫が1億円の遺産を残して亡くなったとしましょう。夫と妻には2人の子供(長女、次女)がいましたが、長女はすでに亡くなっています。長女には2人の子供(夫にとっての孫)がいるとします。
法定相続人は本来、長女と二女の2人ですから、それぞれの相続分は2分の1ずつとなります。そのため、生存している子供(次女)は法定相続分として1億円の2分の1、つまり5,000万円を相続することになります。
亡くなった長女が本来受け取るべき遺産も、1億円の2分の1で5,000万円となります。ですが、長女は亡くなっていますので、長女の子供2人が代わりに相続することになります(代襲相続)。その結果、被相続人の孫2人はそれぞれ2,500万円を相続することになります。
夫死亡・子供ありの遺産相続の手続き
それではここで、遺産相続の手続きの流れを確認しておきましょう。
①死亡の届出
・死亡届:死亡を知った日から7日以内に提出が必要です。
・介護保険資格喪失届・世帯主変更届・住民票の抹消届:死亡日から14日以内に提出します。
②相続人の確認と財産調査
・相続人の確認:戸籍謄本を収集して法定相続人を特定します。
・財産調査:不動産評価額や死亡時の預貯金額、生命保険の有無、負債の有無などを確認し、相続財産全体を把握します。
③遺産分割協議
相続人全員の合意で遺産の分配方法を決定します。
④相続税申告と納付
相続税の基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 相続人数)」です。この範囲内であれば税務署への相続税申告や納付は不要です。
相続税が発生する場合、相続の開始を知った翌日から10ヶ月以内に、税務署への相続税申告が必要になります。必要書類を用意して、なるべく早めに相続税の申告手続きを済ませましょう。
- 相続税申告書
- 戸籍謄本:故人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本
- 死亡診断書
- 相続人の本人確認書類
- 遺言書または遺産分割協議書:遺産の分配方法に関する合意が記載された書類
- 印鑑登録証明書:相続人全員分の印鑑登録証明書
- 金融資産証明書:預貯金の残高証明書や通帳のコピー
- 不動産証明書:不動産の登記簿謄本や固定資産税評価証明書
- 葬儀費用の領収書
相続税手続きは複雑ですので、弁護士や税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。
夫死亡・子供ありの遺産相続の注意点
①子供が未成年の場合
夫の死亡による遺産相続の手続きを進める際に、法定相続人である子供が未成年の場合は、以下の点に注意が必要です。
未成年の子供は、成人と同様に遺産を受け継ぐ権利を持ちますが、自身で法律行為を行うことはできません。つまり、遺産分割協議に参加することができないため、通常は親権者である妻が、未成年の子供の法定代理人として遺産分割協議に参加します。
ですがこの場合には、妻と未成年の子供の利益が衝突してしまう可能性があります。
例えば、妻が「子供はまだ幼いから」と遺産全てを自分1人で相続しようとすると、子供の相続権を侵害することになります。こうした問題が生じないよう、子供のために「特別代理人」を選任する必要があります。
特別代理人とは、家庭裁判所の許可を得て、一時的に未成年者の代理を行う第三者のことをいいます。特別代理人は、親権者である妻や他の相続人とは別の親族から選ばることがほとんどです。他に、弁護士や司法書士などに依頼する場合もあります。
特別代理人は、未成年の相続人に代わって遺産分割協議に参加し、子どもの利益を最優先に考えて協議を進める役割を担います。必要に応じて、遺産の取得割合や内容について意見を述べ、話し合いがまとまったら遺産分割協議書に署名・押印を行います。
②夫と前妻との間に子供がいる場合
離婚した妻との間に子供がいる場合、その子供にも夫の財産を受け継ぐ権利があります。
前妻との子供は、夫と現在の妻との間の子供と同じく、第一順位の法定相続人となります。つまり、離婚した前妻との子供は、夫の財産に対して、現在の妻との子供たちと同じ割合で相続権を持つことになります。
遺産分割の話し合いは、全ての法定相続人の同意が必要となりますから、前妻との子供を遺産分割協議に参加させる必要があります。
前妻との子供に遺産を渡したくないという気持ちもあるかもしれませんが、相続に含まれる財産の範囲や詳細を明確に伝え、誠意を持って対応することが重要です。
配偶者のみの遺産相続
夫の遺産が少なかったり、残された妻が高齢で生活が苦しい場合などに、全ての遺産を妻に相続させたいこともあるかと思います。この場合は、あらかじめ遺言書でそのように指定しておくか、遺産分割協議で話し合って決めることになります。
①遺言書がある場合
遺言書で「配偶者にすべての財産を相続させる」と指定されていれば、配偶者は遺言に従って全財産を相続することになります。
ですが、子供が遺言書に納得できず、自分たちにも相続する権利があると主張すると、遺言通りに相続できないことがあります。兄弟姉妹以外の法定相続人には、法律によって最低限保障された相続分が認められているからです(遺留分)。
(遺留分の帰属及びその割合)
民法第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
子供が自身に遺留分があると主張する場合、原則として配偶者は遺留分の請求に応じることになります。ですので、事前に「全財産を妻に相続させる」ことについて子供から合意を得ておくか、遺留分に配慮した遺言書を作成する必要があります。
②遺言書がない場合
遺言書がない場合は、配偶者と子供が話し合い、全財産を配偶者が相続することで合意できれば、全財産を配偶者が相続することができます。話し合いが成立したら、後のトラブル防止のため、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
配偶者のみの遺産相続のメリット
配偶者である妻が全ての財産を相続すると、相続税上の大きなメリットがあります。
通常、相続が発生した際には、故人が残した財産の総額と、それを受け継ぐ相続人の法定相続分に基づいて相続税が計算されます。この時、配偶者に関しては、相続税を軽減する特別な措置が用意されています。
具体的には、配偶者が相続によって取得する正味遺産額が、次の金額のうち高い方の額までは、配偶者の相続税が免除されるのです。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分に相当する額
配偶者の税負担を軽減することで、経済的安定を図っているのです。
他にも、以下のようなメリットがあります。
小規模宅地の特例を適用できる
相続税額を大幅に減らすことができる「小規模宅地等の特例」を適用できます。
小規模宅地等の特例は、被相続人から相続した事業用・居住用の宅地などについて、相続税の課税価格から最大80%を減額できる制度です。
小規模宅地等の特例の適用条件は複雑なので、本記事では割愛させていただきますが、被相続人の配偶者が特定居住用宅地を相続する場合は、無条件でこの特例が適用されることになります。
また、減額後の金額が配偶者の税額軽減の基準となるため、税負担が軽くなることが期待できるのです。
妻が安心して生活できるように遺産を分けましょう
法定相続分に従って遺産相続した場合、妻は自宅の土地や建物といった不動産を相続することになりがちですが、換金の難しい不動産が妻の相続分の大部分を占めてしまうと、妻の手元に必要な現金が不足する可能性があります。これでは、住む家は相続できても、相続税の支払いや生活費に困ってしまいかねません。
妻の安定した生活を維持するためには、年金収入や支出を詳しく計算し、生活に必要な現金を保持できるよう、適切な相続割合と方法で遺産を分けることが重要です。
子供ともよく話し合い、妻が生活に困らないよう、遺産相続の進め方に配慮することが大切です。
被相続人の死亡後に配偶者が死亡した場合
ところで、夫の死亡後に妻が亡くなった場合は、その際に発生する二次相続での相続税が高くなる可能性があります。
二次相続とは、最初に被相続人の妻と子供が相続(一次相続)した後、妻が亡くなった時に子供が行う相続のことです。
夫婦が高齢になるほど、一次相続の後すぐに二次相続が発生する可能性が高まります。
ここで注意が必要なのは、一次相続で相続税を抑えたとしても、二次相続では相続税が多額になる可能性があるということです。
その要因としては以下の2点が挙げられます。
- 相続税の基礎控除額が少なくなる
- 配偶者の税額軽減措置が適用されない
まず、二次相続時は基礎控除が少なくなることが挙げられます。
相続税の基礎控除は、法定相続人の数に応じて増えるものです。反対に言えば、法定相続人の数が少ないと、基礎控除額も減少するため、課税される基準額が大きくなってしまいます。
一次相続では妻と子供が相続人ですが、二次相続では妻がいないので相続人数が減り、結果として基礎控除額が下がるのです。
また、配偶者の税額軽減措置は、二次相続では適用されません。一次相続で配偶者が税額軽減のメリットを受けたとしても、二次相続ではその財産も相続税の対象となります。
加えて二次相続では、母親が受け継いだ父の遺産だけでなく、母親自身の遺産も相続税の計算に含まれることになります。相続財産の総額が増えると、税率が高くなります。その結果、一次相続で節税を図ったとしても、二次相続での税負担が大きくなるリスクがあるのです。
配偶者が安定した生活を送るのに十分な額を確保できるのであれば、あえて全財産を配偶者に相続させる必要はありません。子供にも相続させることで、二次相続の時の税負担を抑えることが可能となるからです。
以上のようなメリットとデメリットを十分に検討し、親子でしっかり話し合うことが重要です。
夫死亡・子供ありの遺産相続に関するQ&A
Q1.夫死亡後の相続手続きを教えてください。
A:夫が亡くなった場合、まずは遺言書の有無を確認し、遺言書がなければ遺産分割協議を行います。遺産の範囲を明らかにし、相続割合について取り決め、合意できたら遺産分割協議書を作成します。
Q2.未成年の子供がいる遺産相続の注意点は何ですか?
A:子供が未成年の場合、通常は法定代理人(一般的には生存している親)が相続手続きを代わりに行います。ただし、相続に関する重要な決定をする際には、子供の利益を守るために家庭裁判所から特別代理人が選任されることがあります。
Q3.妻が夫の全ての遺産を相続する場合の税法上のメリットは何ですか?
A:配偶者が全ての遺産を相続する場合、配偶者の税額軽減措置を利用することができます。これにより、配偶者は一定金額まで相続税が免除されることがあります。さらに、小規模宅地等の特例や配偶者居住権といった制度を通じて、税負担を軽減することが可能です。ただし、これらのメリットは二次相続の税負担に影響を与えることがあるため、長期的な視点での検討が必要です。
まとめ
この記事では、夫が亡くなった場合に、妻と子供がどのように遺産を相続するのかについて、法定相続分や遺産分割協議の流れ、実務上の注意点を中心に解説しました。
母と子供による遺産相続と聞くと、簡単に思われるかもしれません。ですが、子供が未成年の場合の手続きの進め方や、相続税についての特例制度など、あらかじめ正しく理解しておかなければならないポイントは少なくありません。
親子だけの話し合いで、最適な解決策を見つけることが難しい場合もあるかと思います。
スムーズに遺産分割を進めていただくためにも、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。当法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っておりますので、ぜひお気軽にご利用いただければと思います。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。