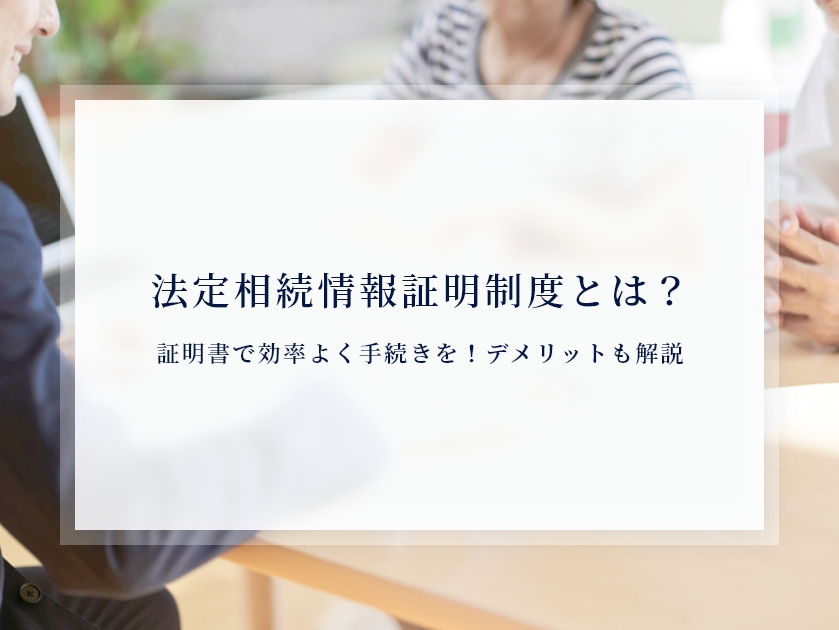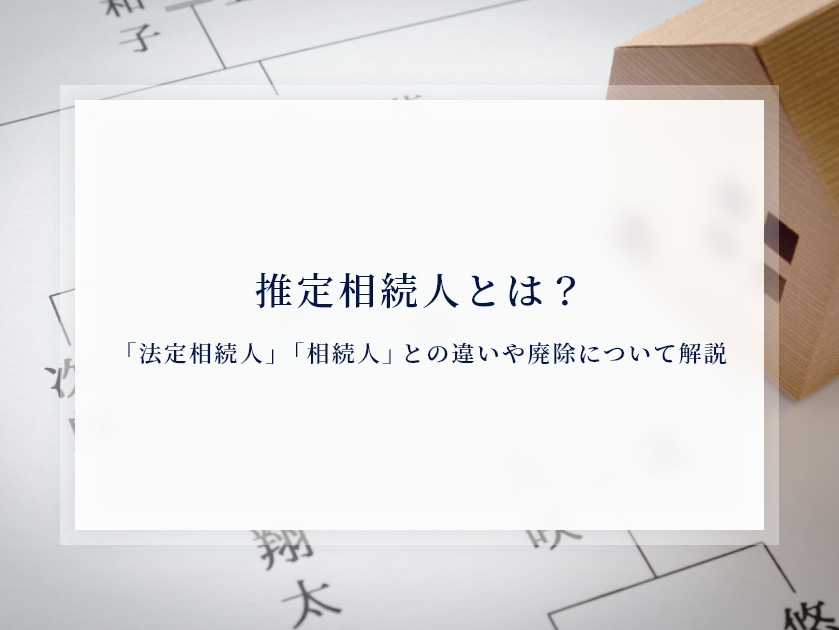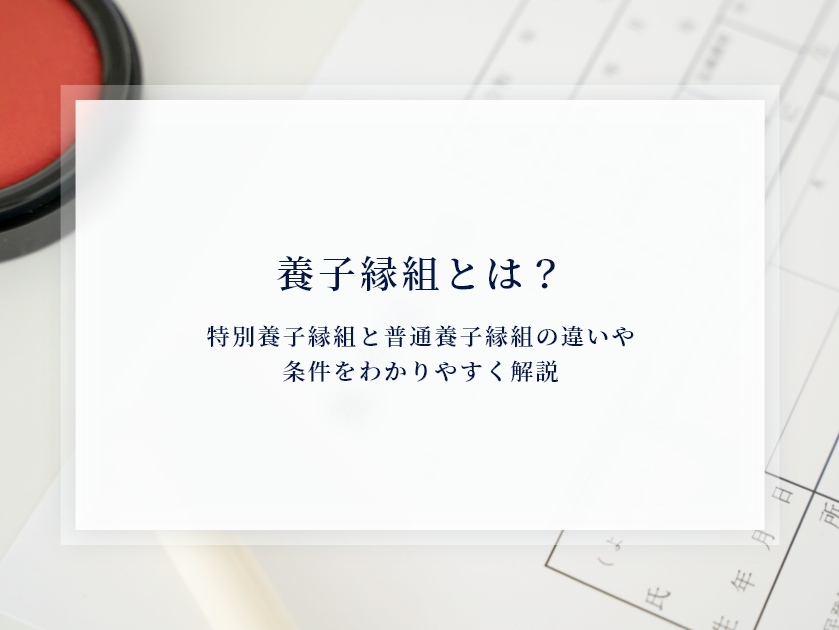配偶者なしの相続|配偶者も子供もいない相続はどうなる?
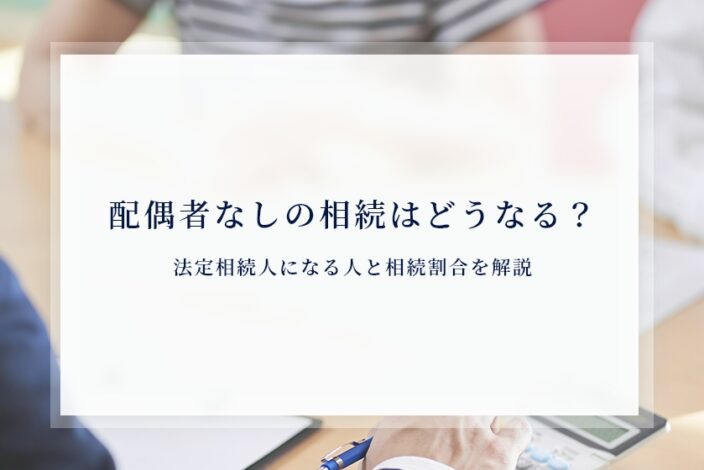
近年は晩婚や未婚率が年々増加しており、単身者世帯が多くなっているといいます。そうした中で遺産相続が発生すると、配偶者なしの相続手続きを進めなければなりません。
亡くなった人に配偶者がいない場合、通常は子供や両親、兄弟姉妹などの近親者が遺産を相続することになります。もし子供や親、兄弟姉妹もいない場合は、最終的に遺産が国に帰属することもあります。
そのため、配偶者なしの場合の遺産相続手続きは、思いのほか複雑化するケースも少なくありません。
そこでこの記事では、配偶者なしの場合の遺産相続について、弁護士が詳しく解説させていただきます。実際に相続人になる人は誰なのか、相続順位や相続割合の基本について確認した上で、親族構成ごとのケースで詳細にご説明いたします。
今や、配偶者なしの遺産相続は珍しくありません。スムーズな相続手続きに備えるため、本記事を少しでもご参考にしていただけましたら幸いです。
目次
配偶者なしの相続
(1)配偶者なしの相続の法定相続人
最初に、配偶者なしの遺産相続の場合に誰が相続人になるのかを見ていきましょう。
原則として、被相続人の遺言書があれば、遺言に書かれている人に対して遺言の内容通りに遺産を分けることになります。「預貯金と不動産は子供Aに、株式は甥Bに引き継がせる。」とあれば、遺言の指示を尊重してその通りに遺産を分配します。
遺言書がない時には、民法に定められたルールを基準にして遺産分割を進めることになります。
本記事で問題にする「配偶者がいないケース」において、相続人となる人は次の通り規定されています。
(子及びその代襲者等の相続権)
民法第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
民法第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
民法のルールによって相続人になる人のことを「法定相続人」といいますが、たとえ被相続人の血縁者といっても、無制限に誰でも法定相続人になれるわけではありません。上記の条文の通り、「被相続人の子」、「被相続人の直系尊属」、「被相続人の兄弟姉妹」と、法定相続人になる人の範囲は限定されています。
(2)配偶者なしの相続の相続順位
そして、上記の「法定相続人になる人」の中でも、さらに「相続順位」によって優先度が異なります。
常に法定相続人となる配偶者を除き、被相続人の子供を含めた親族については、法律で決められた順位によって相続権の有無が決まるのです。自分よりも順位が上の親族が存命の場合は、順位が下の親族が法定相続人になることはできません。
法定相続人の相続の順位は以下のようになります。
|
第一順位 |
子や孫など直系卑属(民法第887条) |
|
第二順位 |
親や祖父母など直系尊属(民法第889条1項1号) |
|
第三順位 |
兄弟姉妹(民法第889条1項2号) |
つまり、配偶者のない被相続人に子供がいる場合、まずは子供が法定相続人として優先的に遺産を受け継ぐことになります。このとき、たとえ被相続人に親や兄弟姉妹がいたとしても、彼らには相続の権利はありません。
被相続人に子供や孫などの直系卑属がいない場合は、次順位の両親や祖父母(直系尊属)が法定相続人となります。亡くなった人に直系卑属も直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
そして、下記の表は、配偶者なしで相続を行う際の、親族構成ごとの相続人と遺産の分け方です。
|
親族の構成 |
相続人 |
備考 |
|
子あり |
子ども |
複数人の場合は均等に分ける |
|
子なし・親あり |
両親 |
複数人の場合は均等に分ける |
|
子なし・親なし・兄弟あり |
兄弟姉妹 |
複数人の場合は均等に分ける |
|
子なし・親なし・兄弟なし・特別縁故者あり |
特別縁故者 |
家庭裁判所の認定が必要 |
|
子なし・親なし・兄弟なし・特別縁故者なし |
なし |
財産は国庫に帰属する |
表の通り、「配偶者なし」の場合、相続人になる人と遺産の分け方には、主に5つのケースがあります。それぞれのケースについて、具体的な事例をもとに確認していきましょう。
配偶者がいない場合の相続
以下のケースでは、被相続人である夫が亡くなる前に、その配偶者である妻が死亡していた場合を前提としています。配偶者がいない場合の相続において、相続人が誰かによって遺産分割がどのように進められていくのかを見ていきたいと思います。
(1)配偶者なし・子ありの場合
夫婦の間に子供がいる場合、被相続人(夫)の遺産は全て子供が相続します。子供が複数いる場合には、均等に遺産を分け合います。
例えば、子供2人の場合は、それぞれ2分の1ずつ遺産を相続することになります。遺産が全部で8,000万円ある場合は、子供1人あたり4,000万円を相続します。
なお、このケースで、子供2人のうち1人が既に亡くなっている場合は、死亡した子供の子(被相続人の孫)が遺産を相続します。
例えば、被相続人に2人の息子がおり、長男Aは存命で、次男Bは被相続人よりも先に亡くなっていたとしましょう。この場合、次男Bに子供がいなければ、生きている長男Aが父親の遺産を全て相続します。
一方で、次男Bに子供Cがいる場合、このCが次男Bの分を相続することになります(代襲相続)。結果として、全部で8,000万円ある場合は、長男Aに4,000万円、孫Cに4,000万円、という遺産分割になるわけです。
(2)配偶者なし・子なしの場合
子なし・親あり・兄弟姉妹ありのケース
夫婦の間に子供や孫がいない場合、第1順位の相続人がいないということになるため、相続権は第2順位の相続人へ移ります。
第2順位の直系尊属、つまり被相続人の両親が法定相続人になります。第2順位の親がいる以上は、第3順位である兄弟姉妹は相続人になれません。
被相続人の両親が2人とも存命の場合、2分の1ずつの割合で両親がそれぞれ遺産を相続します。両親が被相続人よりも先に死亡しており、祖父母が存命の場合は、祖父母が2分の1ずつの割合でそれぞれ遺産を相続します。
なお、両親が存命である以上、仮に被相続人の祖父母が存命だったとしても、法定相続人になるのは両親のみとなります。
子なし・親なし・兄弟姉妹ありのケース
子供や孫などの直系卑属もおらず、両親や祖父母といった直系尊属もいない場合は、第3順位の法定相続人である兄弟姉妹が、均等な割合で遺産を相続することになります。
例えば、被相続人に兄と妹がいる場合、遺産は兄妹で均等に分け合うことになります。
なお、兄弟姉妹のうち1人が既に亡くなっている場合は、死亡した兄弟姉妹の子供(被相続人の甥姪)が遺産を相続します(代襲相続)。
例えば、被相続人に兄Aと妹Bがおり、兄Aが先に死亡していたとしましょう。この場合、兄Aに子供がいなければ、生きている妹Bが遺産を全て相続します。
一方で、兄Aに子供Cがいる場合、Cが亡くなった兄Aの分を相続することになります。兄Aと妹Bのそれぞれの相続分は2分の1ずつなので、子供Cも兄Aの相続分2分の1をそのまま引き継ぐことになります。
兄Aに子供が2人(子C、子D)いる場合は、兄Aの相続分である「2分の1」を子Cと子Dで均等に分け合うことになるため、最終的な相続分は「妹Bが2分の1、子Cが4分の1、子Dが4分の1」となるわけです。
法定相続人がいないケース
被相続人に配偶者や子、親、兄弟姉妹といった法定相続人が一人もおらず、遺言書による指定もないような場合は、法律上「相続人不存在」(民法第951条)の状態になります。この場合、民法の規定に基づいて、家庭裁判所での特別な手続きが必要です。
まず、「相続財産管理人」を選任する手続きが行われます(民法第952条1項)。相続財産管理人は、被相続人の遺産に対する債権者の有無などを確認した上で、債権者がいれば借金などの清算を済ませます。
債権者がいない場合や、清算しても遺産が残った場合には、特別縁故者への遺産の分配が行われることになります。特別縁故者とは、被相続人を長年世話していた親族以外の人や、内縁の配偶者といった、被相続人と特別に親しい関係にあった人のことです。
特別縁故者が相続人として認められるには、家庭裁判所による認定が必要です。
特別縁故者がいない、または特別縁故者への遺産分配をした後にも財産が残っている場合は、被相続人の遺産は、最終的に国庫に帰属することになります(民法第959条)。
配偶者なしの場合にスムーズに遺産相続するために
さて、配偶者がいない場合、「子供もいないし、兄妹とも疎遠だから親しい人に財産を残したい。」と考えることもあるかと思います。
こうした場合、基本的に以下の3つの方法によって特定の人へ遺産を残すことになるでしょう。
- 生前贈与する
- 死因贈与する
- 遺言書を作成する
それぞれの方法と注意点について、簡単にまとめましたので確認しておきましょう。
①生前贈与する
生前贈与とはその字の通り、生前に法定相続人ではない人に財産を贈与しておく方法です。
生前贈与のメリットは、確実に特定の人に財産を引き継ぐことができる点にあります。また、財産を生前に段階的に移転させることで、相続の際に一度に大きな額の相続税が発生するのを避けることができます。
でずが、生前贈与も贈与する財産の金額によっては贈与税が課されることがあるため、注意が必要です。
贈与税の基礎控除額は年間110万円までと定められており、110万円を超える金額の贈与には贈与税が課されてしまいます。年間に贈与する金額が110万円以下であれば、贈与税の基礎控除の範囲内となり税金が発生しませんので、生前贈与の制度を上手に活用することで、税負担を抑えながら遺産の分配を進めておきましょう。
②死因贈与する
死因贈与は、生前に特定の人に将来的に財産を渡すことを約束する契約のことをいいます。生前贈与とは異なり、被相続人が亡くなったときに初めて、あらかじめ指定した人に財産が渡ります。
死因贈与自体に特別な形式はありませんが、口約束だけでは後々の紛争の原因になりかねません。そこで、死因贈与を予定している場合は、その内容を遺言書に書き残しておくことが重要です。遺言書に記載することで、被相続人の意思が明確になり、相続時のトラブルを防ぐことができます。
死因贈与を遺言書に記載する際には、贈与する財産の詳細、贈与を受ける人の氏名、そして財産を渡す条件やタイミングなどを具体的に記載しておくようにしましょう。
③遺言書を作成する
法定相続人でない人物に財産を渡す方法として、一般的に知られているのが遺言書による遺産分配(遺贈)かと思います。
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つの形式があります。自筆証書遺言は、全文を遺言者が自分で書きますが、形式に誤りがあると無効となってしまうリスクがあります。
一方で、公正証書遺言は、公証人が立ち会い、適切な手続きに従って公証役場で作成されるため、内容が無効となる心配がありません。そのため、遺言書を作る際には公正証書遺言を作成しておくことをお勧めいたします。
遺留分に注意
以上の通り、財産を法定相続人以外の人に渡すことは可能ですが、無制限に渡せるわけではないため、注意が必要です。
なぜかというと、一部の法定相続人に関しては、民法が「最低限の遺産を取得する権利」を保障しているからです(遺留)。遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子供や孫、両親や祖父母)に認められた権利です。
遺留分の割合は、法定相続分の半分(両親や祖父母のみが相続人の場合は、法定相続分×3分の1)とされています。
例えば、配偶者と子供がおらず、両親が法定相続人になる場合、両親の法定相続分はそれぞれ2分の1ですので、それぞれの遺留分は2分の1×3分の1=6分の1、となります。
このケースで仮に「親友Eに全財産を相続させる。」と遺言書で指定したとしても、「6分の1ずつ遺産を受け取る権利がある」と被相続人の両親から遺留分を請求される可能性があります。
ですので、法定相続人以外の人に財産を相続させたい場合は、遺留分にも十分に注意しましょう。
配偶者なしの相続に関するQ&A
Q1.配偶者なしの場合、法定相続人は誰になりますか?
A:配偶者がいない場合は、被相続人の子供や両親、兄弟姉妹が、法律によって決められた順番で法定相続人となります。まず子供が法定相続人となり、子供がいなければ被相続人の両親が、両親もいない場合は兄弟姉妹が法定相続人となります。
Q2.配偶者も法定相続人もいない場合、他に相続人になる人はいますか?
A:配偶者がおらず法定相続人もいない場合、被相続人と特別な関係にあった「特別縁故者」が相続人になることがあります。特別縁故者には、被相続人と共同生活をしていた人、療養・看護をしていた人、または師弟関係のような特別な関係があった人が含まれます。特別縁故者として認められるには、家庭裁判所に申し立てを行い、関係性を証明しなければなりません。
Q3.配偶者なし・子ありの場合、相続割合はどのように決まりますか?
A:配偶者がおらず子供が法定相続人となる場合、遺産は子供の人数で均等に分配されることになります。例えば、子供が一人であれば全ての遺産を一人で受け継ぐことになりますし、2人いる場合、遺産は子供2人で2分の1ずつ分けることになります。
また、2人いる子供のうち一人が既に亡くなっていて、死亡した子供に子(被相続人の孫)がいる場合は、孫が被相続人の遺産を相続します。親の相続分を受け継ぐため、例えば孫が3人いる場合は、被相続人の子が2分の1、被相続人の孫がそれぞれ6分の1ずつの割合で遺産相続することになります。
まとめ
配偶者がいない場合の相続は、親族構成によって法定相続人とその相続割合が大きく変化します。
そのため、相続人に配偶者がいない場合、事前に誰が相続人になるのかをしっかり確認しておくことが重要です。また、どのように財産を分割するかを慎重に考え、遺産が意図した相手に確実に渡るように、遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。
相続に関して疑問や不明点がある場合は、状況が複雑になる前に、専門家である弁護士にご相談いただければと思います。当法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。Web予約フォームやお電話にて、ぜひお気軽にお問合せください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。