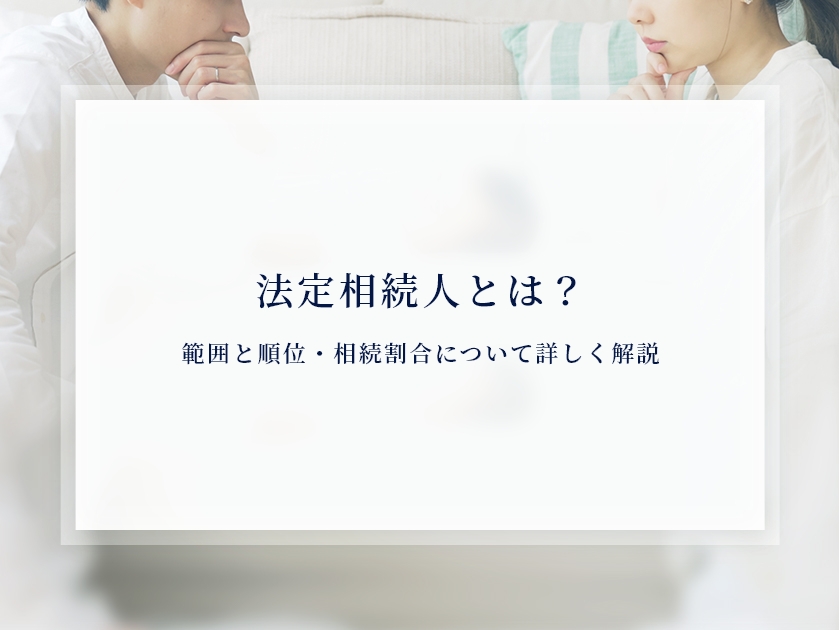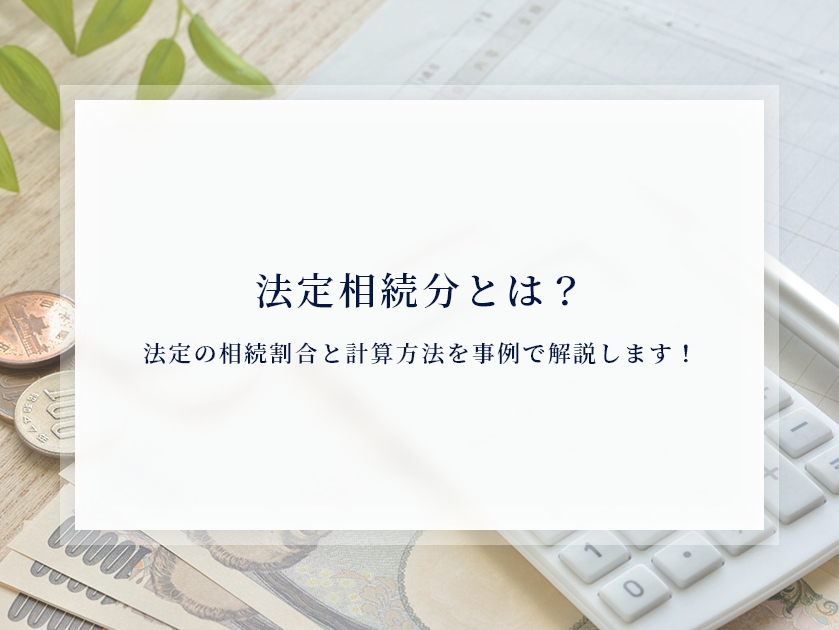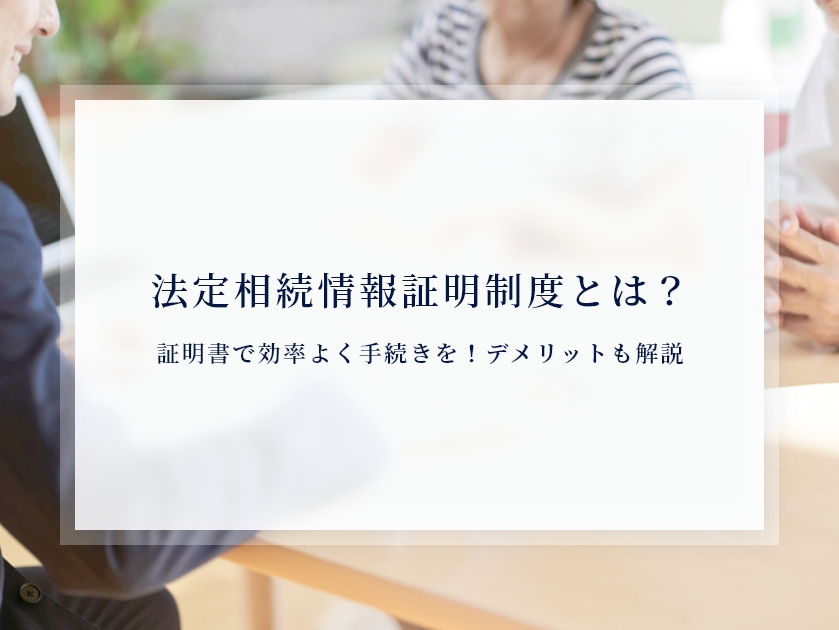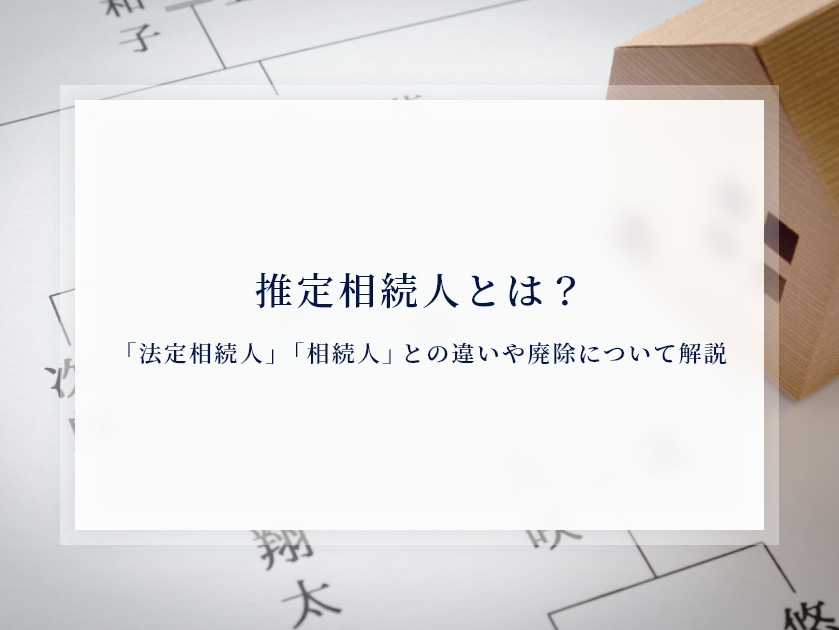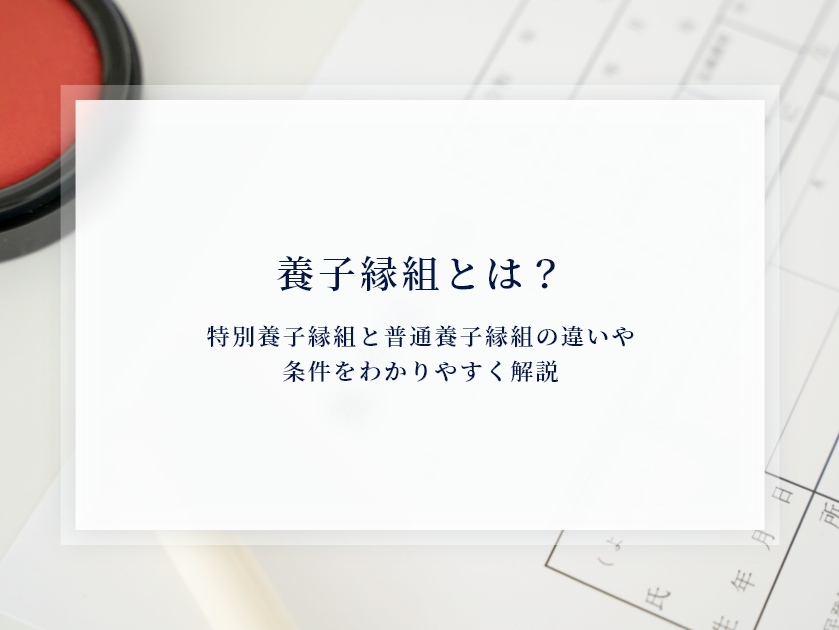法定相続人とは?わかりやすく解説!法定相続人と相続人の違いも
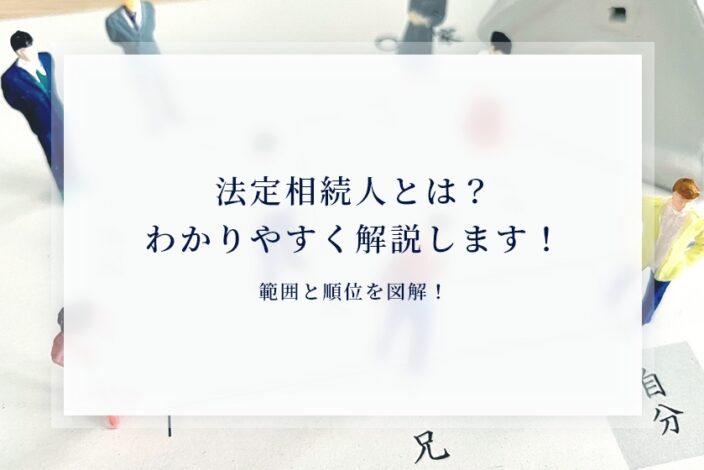
遺産相続が始まると、「法定相続人」という言葉を目にすることが多くなるかと思います。
誰が遺産を相続するのか、どのくらいの割合で遺産分割することになるのか。「法定相続人」の考え方は、そうした遺産相続の基本に密接に関係してきます。
そこでこのコラムでは、法定相続人についての基本的な事項を、「相続人」との違いを中心に弁護士がわかりやすく解説させていただきます。
遺産相続において、「法定相続人」はとても重要です。法定相続人を理解するのに、本記事が少しでもお役に立ちましたら幸いです。
目次
法定相続人とは?わかりやすく
1.法定相続人とは?わかりやすく解説
法定相続人とは、民法の定めにより、当然に遺産を相続する資格を持つ人のことです。
ある人が死亡した場合に、その人の財産を受け取る資格を「法律で」与えられている、特定の家族や親族のことをいいます。
なお、法定相続人といっても、全ての法定相続人が全く同じ扱いを受ける法定相続人というわけではありません。
法定相続人は、大きく次の2つのグループに分けられます。
- 配偶者
被相続人(死亡した人)と法律上の婚姻関係にあった人。 - 血族
被相続人と血縁関係にある親族。例えば、子どもや親、兄弟姉妹など。
被相続人の配偶者と子どもが別のグループに分けられるのは、意外に思われるかもしれません。たしかに配偶者も子どもも、被相続人の「家族」ではありますが、相続手続きにおいては「配偶者」と「血族」とに分けられることになるのです。
具体的には、被相続人の配偶者は常に法定相続人になりますが、子どもをはじめとする「血族による法定相続人」に関しては、実際には法定相続人にならない場合もあるのです。
これには、「相続順位」という法律上の決まりが関わってきます。
血族の法定相続人に関しては、自身が相続人になれる順番というものが決まっています(民法第887条・同第889条)。
(子及びその代襲者等の相続権)
民法第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
民法第889条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
対して、被相続人の配偶者は常に相続人となります(民法第890条)。
(配偶者の相続権)
民法第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
自分の順番が回ってこない限り実際には法定相続人になれない、という点が、常に法定相続人となる配偶者との大きな違いなのです。
2.法定相続人になるには?
法定相続人は前述の通り、「自分より上位の法定相続人がいる場合、下位の順位者は法定相続人になることはできない」という仕組みになっています。
そして、その順位を整理すると以下の通りとなります。
- 第1順位
被相続人の子ども、孫(被相続人の子どもの代襲相続)といった直系卑属 - 第2順位
被相続人の親や祖父母といった直系尊属 - 第3順位
被相続人の兄弟姉妹、甥姪(被相続人の兄弟姉妹の代襲相続)
なお、代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来の法定相続人が被相続人よりも前に死亡している場合などに、その人の子どもが代わりに相続する制度です。
例えば、被相続人の子どもが被相続人より先に死亡している場合は、亡くなった子どもの子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。あるいは、被相続人の兄弟姉妹が親より先に死亡している場合は、兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥姪)が代襲相続人となります。
それでは、法定相続人について、具体的に見ていきましょう。
配偶者は常に法定相続人になる
被相続人の配偶者は、他の法定相続人の相続順位に影響を受けず、常に法定相続人となります。
そして、ここでいう「配偶者」とは、被相続人が死亡した時点で法律上の婚姻関係にあった人を意味しています。つまり、内縁関係や事実婚など、戸籍上の配偶者でない人は、法定相続人にはなれません。
例えば、きちんと婚姻届を提出して、法律上夫婦として認められている男女がいるとしましょう。
その夫は一度離婚歴があり、元妻は存命中です。また、夫には法律婚の妻とは別に、内縁関係にある女性もいるとします。
この夫が亡くなった場合、法的に結婚している妻は夫の法定相続人になりますが、元妻と内縁の妻はどうなるのでしょうか。
内縁の関係にある女性は、社会的には夫のパートナーとして認識されているかもしれませんが、戸籍上での結婚はしていません。このような関係を「事実婚」や、「内縁関係」といいます。
前述の通り、法定相続人となる配偶者は法律婚の配偶者に限られるため、この夫が亡くなった場合、内縁の妻は夫の法定相続人とはならず、婚姻関係にある妻のみが法定相続人となるのです。
また、「元配偶者」の場合も、被相続人の死亡時に法律上の婚姻関係がありません。そのため、夫の死亡時に法律上の婚姻関係にない元妻に関しても、法定相続人としての資格は認められないことになります。
第一順位:子ども、代襲相続人(孫)
それでは、相続順位「第一順位」である子どもや孫についてはどうなるのでしょうか。
被相続人には3人の子ども(長男、二男、三男)がいるとしましょう。長男はすでに亡くなっていますが、長男には2人の子どもがいます。さらに、被相続人の配偶者も存命です。
この場合、被相続人の法定相続人として考えられるのは、以下の三者です。
- 配偶者
- 子ども:二男、三男
- 孫(長男の子ども):2人
前提として、配偶者は他の法定相続人の相続順位に影響を受けず、常に法定相続人となります。
そして、第一順位者である子ども3人のうち、二男と三男は存命のため、二男と三男が法定相続人となります。
第一順位者である子ども3人のうち、長男は相続開始時に亡くなっているため、長男が法定相続人になることはありません。
ただし、長男には子どもが2人いるため、代襲相続人として、長男の子ども2人が法定相続人となります。
第二順位:親、祖父母
次に、第二順位者である親や祖父母について見ていきましょう。
例えば、被相続人が結婚しておらず、子どもや孫もいない場合は、第一順位者がいません。そのため、相続順位は次の第二順位者へと移ります。
したがって、被相続人の法定相続人は、第二順位者である直系尊属(被相続人から見て「上の世代」にあたる血縁者)、つまり両親や祖父母になります。
もし被相続人の父と母がまだ存命であれば、被相続人の遺産は父母で公平に分割して相続することになります。
しかし、もし被相続人の両親が既に亡くなっていて、祖父や祖母がまだ生きている場合、被相続人の遺産は祖父母で公平に分割して相続することになります。
第三順位:兄弟姉妹、代襲相続人(甥姪)
第三順位の法定相続人は、被相続人の兄弟姉妹や、その代襲相続をした甥姪です。
被相続人は結婚しておらず、子どもや孫もいないとしましょう。また、両親や祖父母もすでに亡くなっているとします。被相続人には兄1人と妹1人がいましたが、兄もすでに亡くなっています。
この場合において、兄に子ども(被相続人から見た甥姪)がいない場合、第三順位者である妹が、被相続人の法定相続人として全ての遺産を相続する権利を持ちます。
仮に、兄に子どもが2人いた場合は、その2人の子どもたちが代襲相続人として、兄の代わりに遺産を相続する法定相続人となりますので、被相続人の妹と兄の子ども2人の、あわせて3人が法定相続人となります。
法定相続人が誰であるか、何人いるかによって、それぞれの法定相続分(相続割合)が変動します。法定相続分については、下記記事にて詳しく解説しておりますので、ぜひ本記事とあわせてご参照ください。
法定相続人と相続人との違い
ところで、法定相続人と似た言葉に、「相続人」という言葉があります。普段耳にするのは、法定相続人よりも相続人の方が多いのではないでしょうか。
相続人という言葉は、法定相続人に限らず、遺言によって財産を引き継ぐ者として指定された人も含みます。例えば、被相続人が友人や内縁の妻に財産を譲ることを遺言に書き残していた場合、その友人や内縁の妻が相続人となります。
この場合、友人や内縁の妻は民法によって認められている相続人に当てはまらないため、「相続人」ではあっても、「法定相続人」にはなりません。
簡単に言いますと、法定相続人は「民法で定められた遺産を受け取る資格を持つ人」で、相続人は「実際に遺産を受け取る人」というわけです。
なお、法定相続人が遺産を受け取る権利を持っているとは言っても、その法定相続人が実際に遺産を受け取るかどうかは、また別の問題です。
例えば、法定相続人が相続放棄をすると、その法定相続人は遺産を受け取る資格を失うため、実際の相続人としては認められなくなります。
Q&A
Q1.法定相続人についてわかりやすく教えてください。
A:法定相続人の範囲は、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹などが含まれます。相続の順位としては、まず子どもが法定相続人となります。子どもや孫がいない場合、第二順位者の親が法定相続人となります。親や祖父母もいない場合は、第三順位者である兄弟姉妹が法定相続人となります。
Q2.「法定相続人」と「相続人」の違いは何ですか?
A:「法定相続人」とは、法律で定められた条件に基づき相続の権利を持つ人のことを指します。一方、「相続人」は、実際に遺産を相続するすべての人を指す一般的な用語です。したがって、法定相続人であっても、相続放棄などの理由で遺産を相続しない場合、その人は「相続人」とは言えません。
Q3.相続税の計算において、相続放棄した法定相続人は考慮されますか?
A:相続税の計算時には、法定相続人が相続放棄をしていても、相続放棄がなかったとして、法定相続人の数に含めて相続税を算定します。つまり、相続放棄があっても、相続税の計算においては法定相続人の数に変動は生じません。
まとめ
本記事では、法定相続人についての基本的な知識を、弁護士がわかりやすく解説させていただきました。
「法定相続人」と「相続人」の違いに関しても、本記事でご理解いただけたのではないでしょうか。
法定相続人は、相続において特別な権利を持つ人々を指します。法定相続人の範囲や相続順位、相続割合といった権利については、民法に明確に定められています。
スムーズかつ適切に相続手続きを進めていくためには、こういった基本的な事項を正しく理解し、自身の状況に当てはめてきちんと検討することが重要です。
相続は、ほとんどの方にとって避けて通れない問題です。相続についての正確な知識を持つことで、円滑に遺産分割を行うことができ、将来的なトラブルも防止することができるでしょう。
また、この記事だけでは解決しきれない疑問や問題がありましたら、弁護士法人あおい法律事務所まで、お気軽にお問合せいただければと思います。当法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っておりますので、ぜひご利用ください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。