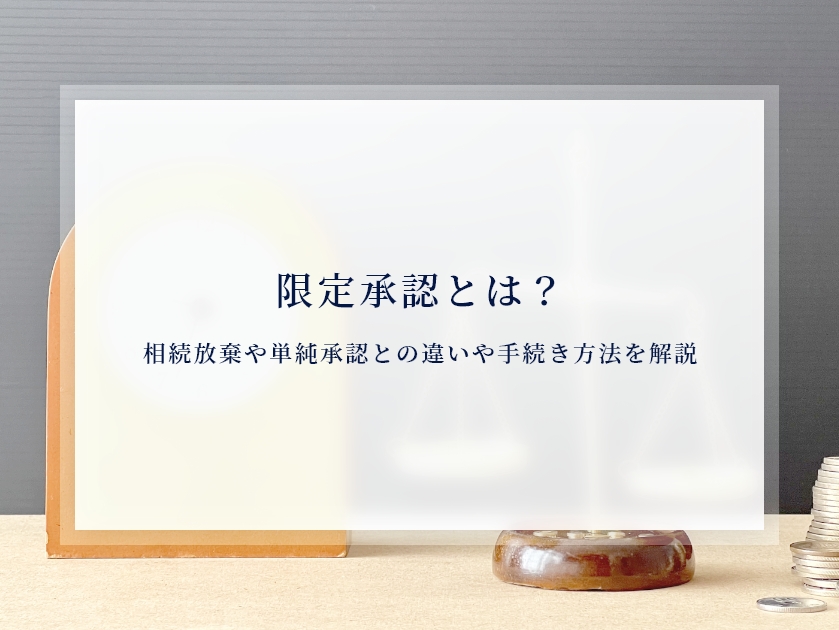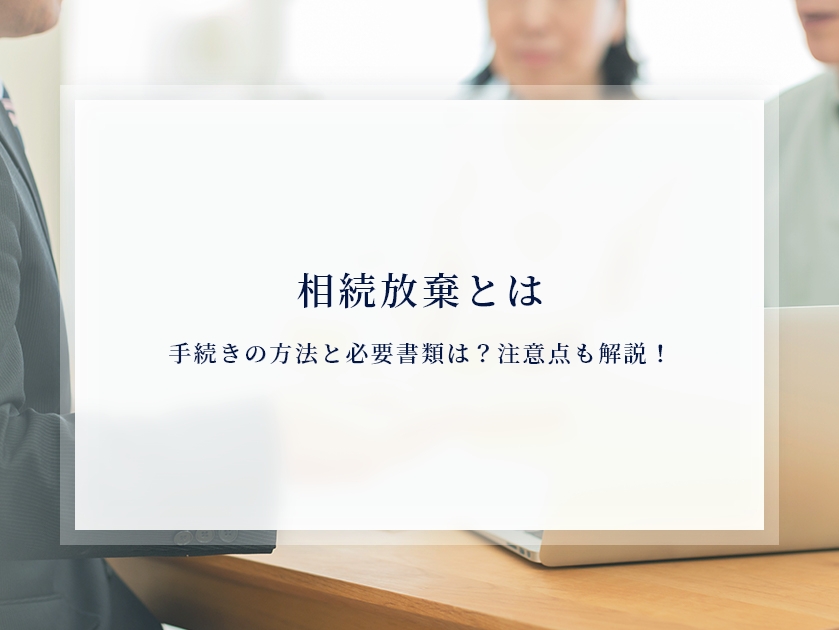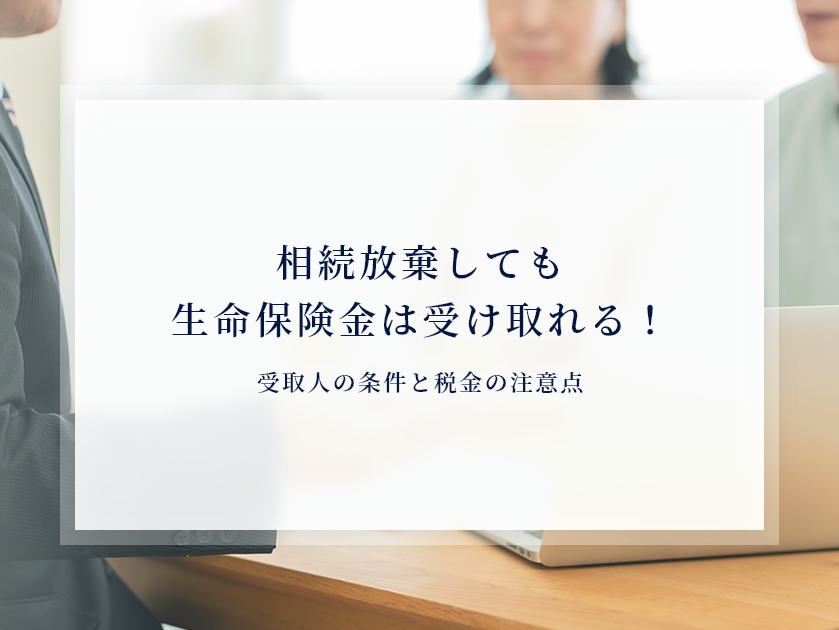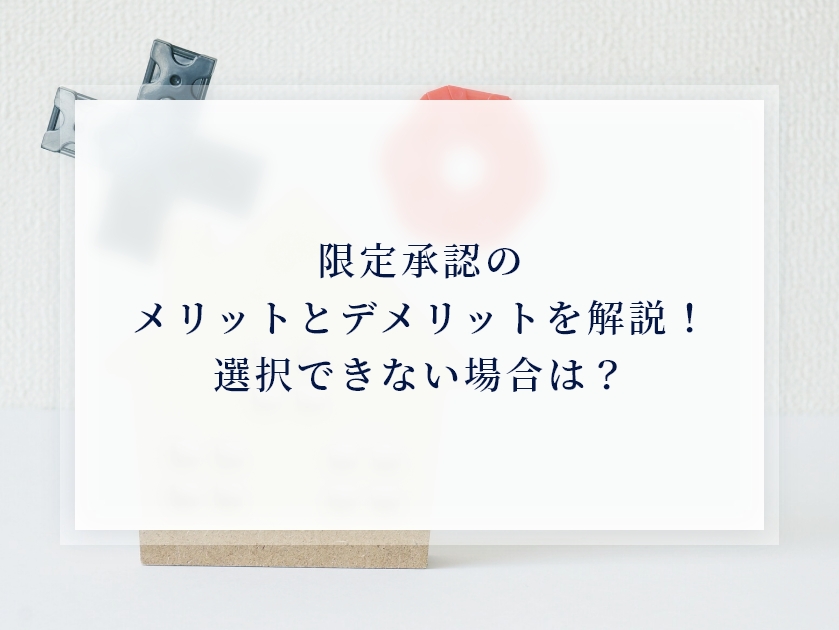単純承認|相続の単純承認とは?限定承認・相続放棄との違い、単純承認とみなされる事由も解説
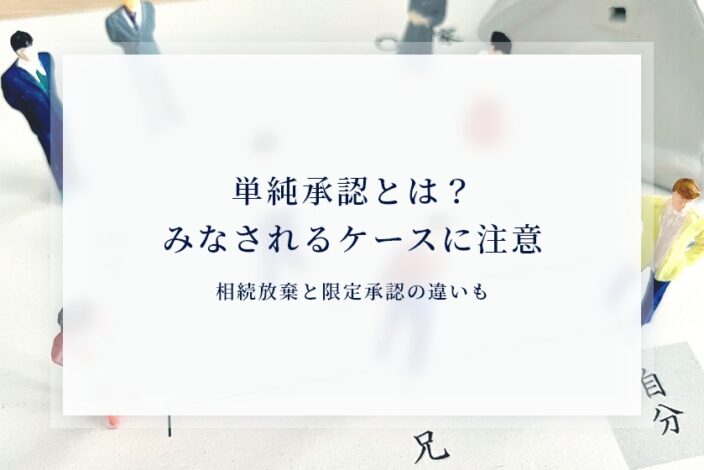
相続人になった際、分配される財産は、預貯金や不動産などプラスの財産だけではありません。遺産には、負債や借金といったマイナスの財産が含まれることがあります。こうした場合に、「借金は相続したくない」と考えるのであれば、注意が必要です。
遺産を相続する方法には「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」という3つの方法があります。
本記事では、この3つのうち、「単純承認」について、弁護士が詳しく解説させていただきます。
単純承認とはどういった方法か、という基本的な事項に加え、単純承認とみなされる行為についても具体的に見ていきます。
また、限定承認・相続放棄との違いについても確認し、最後に注意点をおさえておきましょう。
本記事が、遺産相続で少しでもご参考となりましたら幸いです。
目次
単純承認
単純承認とは、故人の財産をそのまま受け継ぐことを意味します。「遺産相続」と聞いて、一般的にイメージされるのが、この方法ではないでしょうか。
「単純」とある通り、難しい手続きなどはありませんが、思わぬ落とし穴が潜んでいることもあります。
たとえば、プラスの財産(積極財産)だけでなく、借金などのマイナスの財産(消極財産)まで引き継ぐことになる可能性もあるのです。
また、はっきりと「全部相続する」と意思表示したつもりがなくても、「単純承認とみなされる」ケースもあります。
そのため、マイナスの財産を相続したくない人は、特に気を付けなければなりません。
以下では、単純承認とはどういった相続方法か、単純承認とみなされる行為には何があるのかについて解説していきます。自身が相続する遺産について納得の上で相続手続きを進めていけるよう、正しい知識を備えておきましょう。
単純承認とは
1.単純承認とは
単純承認は、被相続人が残した相続財産について、その財産の全てを無条件で相続するという相続方法です(民法第920条)。
(単純承認の効力)
民法第920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
「無限に被相続人の権利義務を承継する」とある通り、被相続人のプラスの財産だけでなく、借金や連帯保証債務などのマイナスの財産も含め、全ての財産を引き継ぐことになります。
以下のような場合には、単純承認によって遺産分割されることが一般的です。
- 被相続人の相続財産の全体が明確で、借金などの負債がない場合
- 被相続人の相続財産の全体が明確で、負債はあるが少ない場合
2.単純承認とみなされる行為(法定単純承認)
さて、民法第920条には「単純承認をしたとき」とありますが、どういった行為が「単純承認」に当たるのでしょうか。
「単純承認の行為」は大きく分けると、①相続人が自ら意思表示する単純承認と、②一定の事由によって単純承認とみなされる場合(法定単純承認)の2つがあります。実務上は、②法定単純承認の場合が多いです。
自らの意思で単純承認する場合はともかくとして、「単純承認するつもりがなかったのに、単純承認とみなされる行為をしてしまっていた」とならないよう、法定単純承認(民法第921条)について具体的に確認しておくことが重要です。
(法定単純承認)
民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
法定単純承認にあたる事由に該当した場合は、単純承認をしたものとみなされ、限定承認や相続放棄をすることができなくなってしまいます。
それでは、民法第921条の法定単純承認について、具体的な行為の内容を詳しく確認していきましょう。
2-1.相続財産の全部または一部の処分
相続財産の全部または一部を処分する行為(民法第921条1号)は、相続人が被相続人の財産を相続する意思があるとみなされ、結果として単純承認したとみなされることがあります。
この「相続財産の処分」ですが、遺産の売却などといった法律上の処分だけではなく、家屋の取り壊しといった事実上の処分も含まれます。具体的には、以下のような行為が単純承認したものとみなされます。
- 被相続人の預貯金を引き出し、自分の支払いに充てた
- 不動産を売却した
- 不動産に抵当権を設定した
- 家屋を取り壊した
- 被相続人の債権を取り立てた
- 被相続人が受取人となっている生命保険の解約返礼金を受け取った
- 株主権を行使した
- 相続人全員での遺産分割協議
なぜこうした行為が単純承認になるかというと、第三者を保護するためです。
例えば、相続人が遺産を処分した後に限定承認や放棄をすることが認められてしまうと、遺産の価値は減少し、範囲も不明確になってしまいます。被相続人の相続財産に対して請求権を持つ債権者(相続債権者)などの第三者の利益や取引安全が害されることを防ぐためには、こうした処分行為があった場合には単純承認をしたとみなすのが最善とされているのです。
2-2.期限(熟慮期間)の経過
「相続人が民法第915条1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。」も、単純承認とみなされます(民法第921条2号)。
民法第915条1項の期間とは、「熟慮期間(考慮期間)」です。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
なぜこうした熟慮期間が設けられているのかというと、相続人が遺産相続するか、あるいはしないか等を選択するためには、相続財産の状況を調査して、自分にとって何が適切なのかを考える期間が必要だからです。
そして、相続開始を知ってから3か月以内の「熟慮期間」において、相続人が相続放棄や限定承認の手続きを行わなかった場合、自動的に単純承認したものとみなされる、ということになります。
また、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」という、3か月の起算点についてですが、被相続人の死亡による相続開始を知っただけではなく、その相続について自分が相続人になったことを知ることが必要である、とされています(大決大正15年8月13日)。
ですので、例えば被相続人の死亡は知っていても、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知らなかった場合は、自分に相続権が移り相続人になったことまでは知らないため、「自分が相続人になった」と認識した時点から熟慮期間が起算されることになります。
なお、民法第915条1項但書にある通り、この熟慮期間については家庭裁判所に対して延長を申し出ることが可能です。ただし、この延長の申し出手続きも熟慮期間内に行う必要があるため、早めの行動が重要になります。
2-3.相続財産の隠匿や消費(背信行為)
「相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。」も、単純承認とみなされます(民法第921条3号)。
「隠匿」とは、相続債権者に財産の存在を認識させないようにすることを意味し、「ひそかに相続財産を消費すること」は、相続債権者の不利益になるのを知りながら、財産の価値を失わせることを意味します。
例えば、以下のような行為が該当します。
- 被相続人の預貯金を勝手に引き出して使った
- 高額の敷金の所在を明らかにせず、その客観的証拠も提出しなかった
- 財産目録に積極財産(プラスの財産)を意図的に記載しなかった
- 財産目録に消極財産(債務)を意図的に記載しなかった
こうした行為は、相続人による「背信行為」とみなされます。
限定承認や相続放棄は、基本的に相続債権者よりも相続人を保護する制度ですが、相続人がこのような背信行為を行った場合、その保護は及ばないことになるのです。
そして、条文にもある通り、これは相続人が限定承認や相続放棄の手続きを行った後であっても適用されます。
ただし、相続放棄をした者による背信行為があった場合でも、その相続放棄によって相続人となった後順位の相続人が既に相続を承認していた場合には、後順位の相続人を保護するため、単純承認とはみなされないため(民法第921条3号但書)、相続放棄の効果が維持されます。
3.単純承認にならない行為は?
相続財産に関して行う全ての行為が法定単純承認とみなされるわけではありません。一定の条件を満たせば、単純承認にはあたらないケースがあります。
3-1.葬儀費用や仏壇や墓石の購入費用の支払い
葬儀費用などを相続財産から支払う場合、「相続財産の処分」に当たらないかが問題となります。
この点につき、その費用が社会通念上妥当とされる範囲であれば、法定単純承認には該当しないとされています。
実際に裁判例も、以下のような理由から、明白に法定単純承認たる「相続財産の処分」に当たるとは断定できないと判断しています(大阪高決平成14年7月3日)。
- 葬儀は人生最後の社会的儀式として必要性が高いこと。
- 相続財産から被相続人の葬儀費用を充当することは、社会的見地から不当ではないこと。
- 相続人に資力がなく、相続財産の使用が許されないために葬儀を行えないとすれば、非常識な結果となること。
なお、ここでいう「社会通念上妥当な範囲」とは、不必要に豪華でない、一般的な葬儀の費用を指します。同様に、仏壇や墓石の購入も、必要最低限の範囲内であれば問題ありません。
具体的な金額基準は示されていないため、個別の事情に応じて判断されることになります。
ですが、例えば相続財産と比較して多額の債務があることが明らかであるにもかかわらず、葬儀費用などを相続財産から支払った場合には、債権者保護の観点から、法定単純承認に該当する可能性が考えられます。
3-2.慣習上の形見分け
慣習上の形見分けも、相続財産の処分には当たらないとする判例があります(大阪高等裁判所昭和54年3月22日決定)。
この事例では、次のような事実がありました。
- 相続人は、行方不明であった被相続人が遠隔地で死亡したことを、所轄警察署から通知された。
- 相続人が同署から被相続人の着衣、ほとんど無価物に近い着衣、財布などの雑品、被相続人の所持金2万余円の引渡を受けた。
- 相続人は、所持金2万余円に自身の所持金を加え、火葬費用や被相続人の治療費の残額の支払いに充てた。
そして、裁判所は次のように判断しています。
右のような些少の金品をもつて相続財産(積極財産)とは社会通念上認めることができない(このような経済的価値が皆無に等しい身回り品や火葬費用等に支払われるべき僅かな所持金は、同法八九七条所定の祭祀供用物の承継ないしこれに準ずるものとして慣習によつて処理すれば足りるものであるから、これをもつて、財産相続の帰趨を決すべきものではない)。のみならず、抗告人らは右所持金に自己の所持金を加えた金員をもつて、前示のとおり遺族として当然なすべき被相続人の火葬費用ならびに治療費残額の支払に充てたのは、人倫と道義上必然の行為であり、公平ないし信義則上やむを得ない事情に由来するものであつて、これをもつて、相続人が相続財産の存在を知つたとか、債務承継の意思を明確に表明したものとはいえないし、民法九二一条一号所定の「相続財産の一部を処分した」場合に該るものともいえないのであつて、右のような事実によつて抗告人が相続の単純承認をしたものと擬制することはできない。
(大阪高等裁判所昭和54年3月22日決定)
一方で、形見分けであっても、高価なものであったり、行為が社会通念上の範囲を超えたりする場合には、単純承認事由である「処分」や「隠匿」に該当すると判断される可能性があります。
3-3.相続人を受取人として指定された生命保険金の受領
生命保険金は原則として、被相続人が死亡した際に、保険契約に基づきあらかじめ指定されている受取人に直接支払われるお金です。つまり、被相続人の遺産として分配されるのではなく、受取人の固有の財産ということになります。
特定の相続人が生命保険金の受取人として指定されている場合、その相続人が保険金を受け取っても、自身の固有の財産を受け取っているだけなので、被相続人の遺産を管理・処分する行為とはみなされません。ですから、生命保険金の受領は法定単純承認にはあたりません。
また、上記のケース以外にも、相続人が被相続人の死亡事実を知らずに相続財産を処分した場合は、単純承認の効果は生じない、とされた裁判例もあります(最高裁判所昭和42年4月27日判決)。
何が単純承認に当たるかは、相続人が相続開始の事実を認識していたかどうかも、重要な要素となるのです。
4.単純承認の手続き
さて、単純承認をするために、特別な手続きを必要としません。
これこそが、単純承認の最大のメリットでもあります。
相続人が被相続人の死亡を知ってから特に何もしなければ、自動的に単純承認したとされるため、迅速かつ手間なく相続が完了します。
ですが、こうしたメリットの一方、「被相続人の負債を全て引き継ぐことになる」というデメリットもあります。
単純承認をすると、被相続人が残した全ての財産がそのまま引き継がれます。つまり、プラスの財産だけでなく、借金や負債といったマイナスの財産も受け継ぐことになるわけです。
マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、相続人自身が残った借金を負うことになります。そうなると、相続人のプラスの財産だけでは弁済しきれないため、相続人自身の固有の財産から弁済する必要があるのです。
そのため、被相続人の財産の全体像をしっかり把握し、プラスの財産とマイナスの財産を総合的に考慮することが大切です。
単純承認と限定承認・相続放棄
ところで、相続方法には「単純承認」のほかに、「限定承認」と「相続放棄」という2つのやり方があります。単純承認とこの2つの相続方法には、どのような違いがあるのでしょうか。
1.単純承認と限定承認との違い
限定承認とは、相続人が被相続人から引き継ぐプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を引き継ぐことです。
限定承認の場合、相続人は被相続人の財産を受け取る際、財産の総額以上の債務を負うリスクがなくなります。
例えば、被相続人が1,000万円の財産と3,000万円の借金を残していた場合に限定承認を選ぶと、相続人は1,000万円までの借金を負うことになりますが、残る2,000万円の借金については支払う必要がなくなります。債権者も、1,000万円を超える分に関しては相続人に弁済を求めることができません。
限定承認を行うには、家庭裁判所への申述手続きが必要です。これは、相続人が財産と債務の全体像を把握し、財産の範囲内でのみ債務を負うことを正式に申し立てる手続きです。
また、相続人が複数いる場合には、全員が限定承認に同意しなければなりません。一人でも反対する相続人がいると、限定承認は行えないので注意してください。
限定承認後の債務の精算手続きは比較的複雑なため、限定承認はあまり一般的ではないのが実情ですが、被相続人の負債が財産を大きく上回っているケースでは、限定承認が最適な選択肢となることもあります。覚えておくと安心です。
2.単純承認と相続放棄との違い
相続放棄とは、相続人が被相続人の全ての財産を引き継がない選択をすることです。
例えば、被相続人が1,000万円の財産と3,000万円の借金を残した場合、相続人が相続放棄を選べば、1,000万円の財産を受け取る権利を放棄すると同時に、3,000万円の借金を支払う責任からも免れることができます。
相続放棄を行うには、限定承認と同じく家庭裁判所での申述手続きが必要です。
なお、相続人が複数いる場合でも、相続放棄は単独で行うことが可能です。他の相続人の合意を得る必要はなく、個々の相続人が自分の状況に応じて自由に相続放棄することができます。
単純承認の注意点
それでは最後に、単純承認の注意点を確認しておきましょう。
1.相続放棄後に財産を処分してしまった!相続放棄後の単純承認
「相続放棄をしたから、もう関係ない」と思って、うっかり故人の家財道具や不動産を処分してしまった、というケースは意外と少なくありません。
ですが、注意が必要です。相続放棄をした後であっても、財産を処分した行為が「単純承認」とみなされると、相続放棄の効力を失ってしまう可能性があります。
前述した通り、民法では、相続人が相続財産の全部または一部を「処分」した場合、それが放棄の後であっても、単純承認したものとみなされると規定されています(民法第921条)。
例えば、遺品整理のつもりで家財を売却したり、故人の口座からお金を引き出したりすると、それが処分行為と見なされ、相続放棄の効力が否定されてしまうおそれがあるのです。
なお、例外的に「保存行為(価値を保つための行動)」や「一部の管理行為」は許されますが、こうした行為と「処分」行為との線引きは非常に難しいのが実情です。
相続放棄をした後も、安易に財産に手をつけてはいけません。処分のつもりがなくても、結果的に相続放棄が無効となってしまえば、借金などのマイナス財産を抱え込むリスクが生じてしまいます。
不安な場合は、早めに専門家に相談し、対応を確認したうえで行動することが大切です。
2.単純承認後に相続放棄はできない
単純承認すると、原則としてその後に相続放棄をすることはできません。相続の承認および放棄は、熟慮期間内であっても撤回することができないと定められているからです(民法第919条1項)。
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
民法第919条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
ただし、民法第919条2項にある通り、民法の総則編・親族編の規定に従って、単純承認を取り消すことは可能です。例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 未成年者(民法第5条2項)・成年被後見人(民法第9条)・被保佐人(民法第13条1項6号)・被補助人(民法第17条4項)による相続の承認・放棄の取消し
- 錯誤(民法第95条1項)を原因とする取消し
- 詐欺・強迫(民法第96条1項)を原因とする取消し
- 後見監督人の必要な同意を得なかったことによる承認・放棄の取消し(民法第864条・同第865条)
3.単純承認と錯誤による取消し
上で少し触れましたが、財産の処分行為をして単純承認とみなされた場合に、錯誤を理由に取り消すことは可能とされています。ただし、取消しにともない、単純承認の効果も遡って否定されるとは限りません。この点は、判例・学説でも判断が分かれています。
例えば、単純承認の効果を否定した裁判例として、遺産分割協議の成立後に相続債務の存在を認識して相続放棄の申述を申し立てたものの、遺産分割協議が法定単純承認に該当するとして、相続放棄の申述が却下された事件の抗告審があります(大阪高決平成10年2月9日)。
この事例では、遺産分割協議は相続財産についての相続分を処分するものであり、法定単純承認事由に該当するとされた上で、多額の相続債務を知らなかったことが要素の錯誤に該当するため、錯誤により無効となり、法定単純承認の効果も発生しない余地がある、と判断されました。
一方で、単純承認の効果を否定しなかった裁判例もありますので、個々の事情によりケースバイケースとなるでしょう。
このように、単純承認することによって後からトラブルが生じないよう、相続が開始されたらなるべく早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
単純承認に関するQ&A
Q1.単純承認は家庭裁判所での手続きが必要?
A: 単純承認をするにあたって、家庭裁判所での特別な手続きは必要ありません。
Q2.単純承認を避けるためにはどんな手続きが必要ですか?
A: 単純承認を避けるには、相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所で限定承認または相続放棄の申述を行う必要があります。限定承認をすると、被相続人の負債はプラスの財産の範囲内でのみ負担すればよく、相続放棄をすると、プラスの財産も負債も一切受け継がないことになります。
Q3.単純承認した後の遺産分割はどのように進めるべきですか?
A: 単純承認した後、相続人間で遺産分割協議を行い、被相続人の財産の分配方法を決定します。この協議は全相続人の合意が必要で、合意に至らない場合は家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てることになります。遺産分割では、相続財産の価値の評価や各相続人の要求を考慮して公平な分配を目指しますが、複雑なケースは弁護士に依頼することをお勧めいたします。
まとめ
単純承認によって遺産を相続する場合、相続人は被相続人の財産をそのまま、つまりプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めて全て引き継ぐことになります。
このため、被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合などは、財産を相続することがかえって相続人の負担となるリスクがあるため、注意が必要です。このリスクを避けるためには、被相続人の相続財産に関してしっかりと調査し、遺産の全体像を把握することが重要です。
相続開始を知った日から数えて3か月の「熟慮期間」を有効に活用し、単純承認するかどうかを慎重に判断しましょう。安易に決断するのではなく、十分な情報収集をして検討してください。
遺産相続についての疑問や悩みがある場合は、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。当法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っておりますので、ぜひお気軽にお問合せいただければと思います。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。