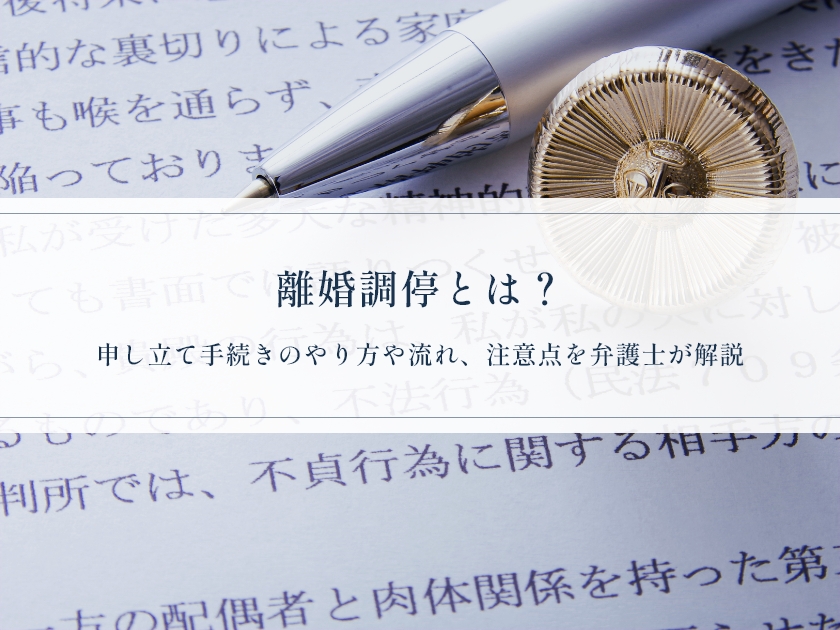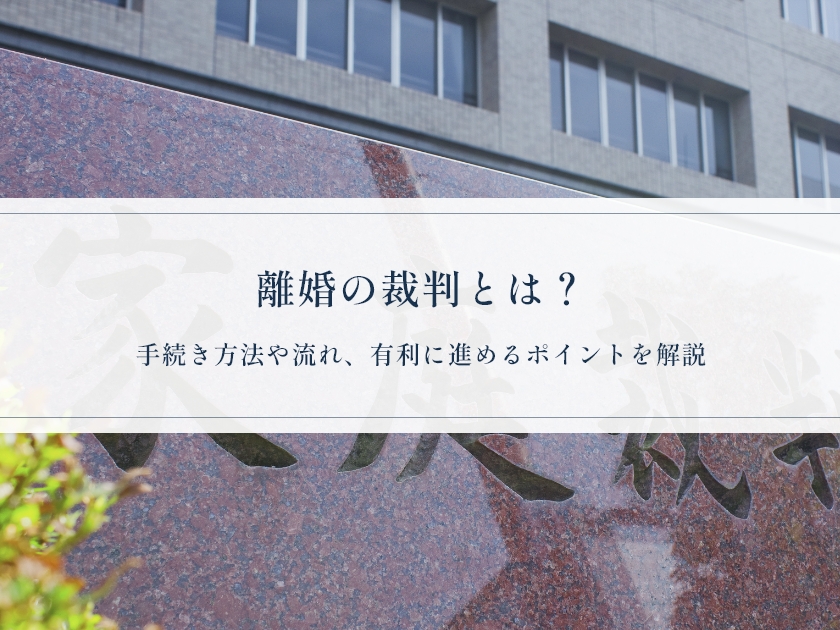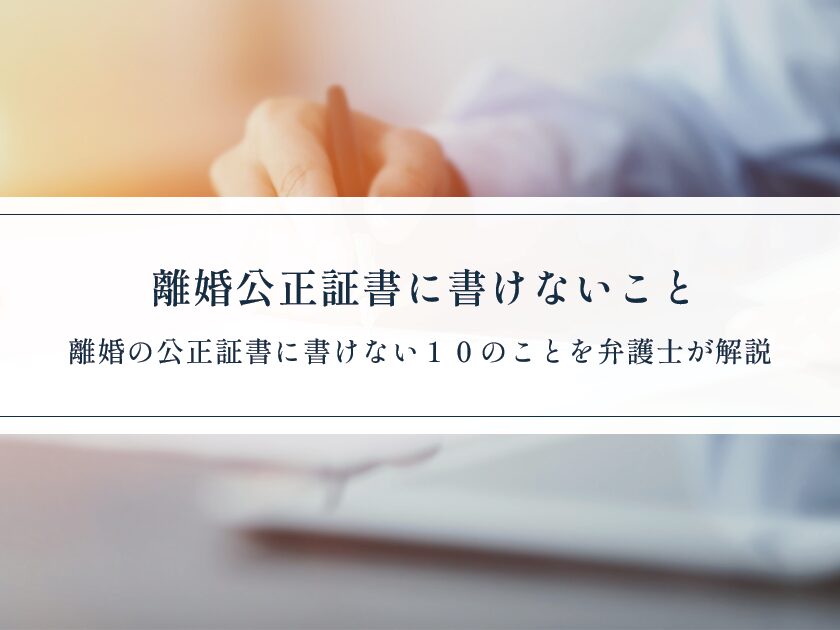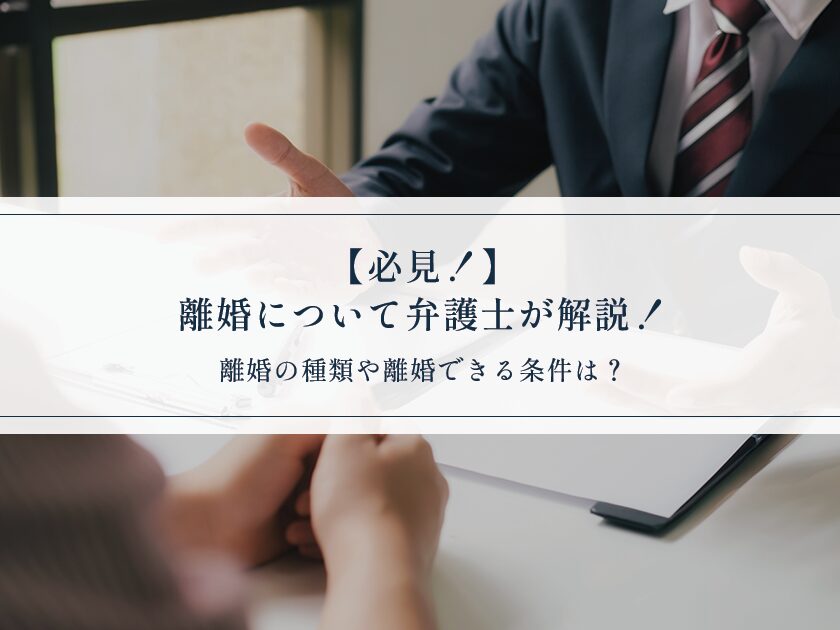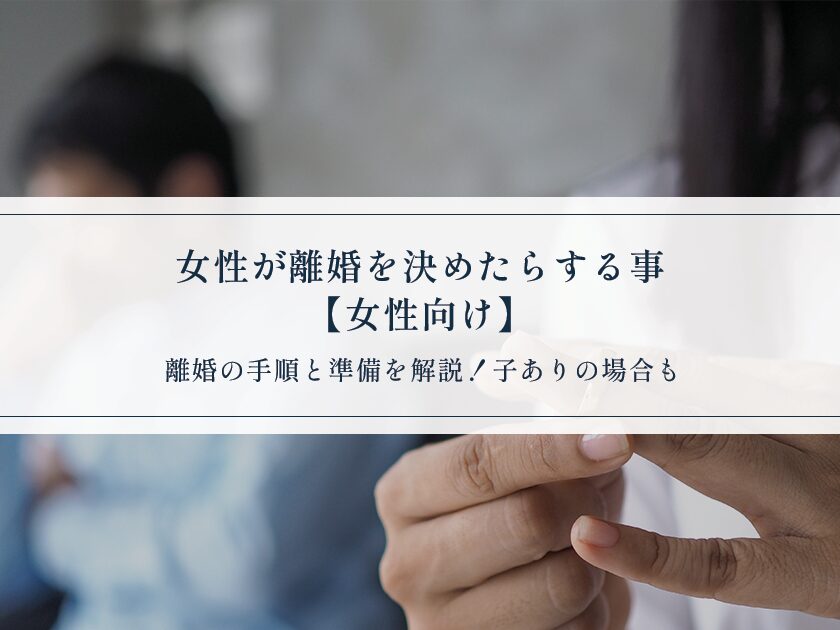離婚の流れ|離婚の具体的な手順は?離婚手続きの流れやスムーズな段取りを解説!

離婚しようと考えた時、まず何から手を付けるべきでしょうか。
自身の状況に応じて、適切な方法で離婚の手続きを進めていかなければ、スムーズに離婚できず、相手との争いが長期化してしまう恐れがあります。
離婚を考えたら、まずは離婚の流れを正しく把握しておくことが重要です。
そこでこの記事では、離婚手続きの全体像を分かりやすく解説し、話し合いから離婚届提出までの進め方を詳しくご紹介いたします。
状況に応じた最適な行動を取れるよう、スムーズな離婚の段取りをおさえ、離婚手続きを進めていただければと思います。
目次
離婚の流れ
離婚手続きは、大きく分けて協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つの方法があります。どの手続きを選ぶかは、夫婦間の話し合いがどの程度スムーズに進められるか、といった当事者の関係性や、財産分与や親権などの解決すべき争点・内容によって異なります。
たとえば、話し合いで円満に条件を決められる場合は協議離婚が最も簡単ですが、意見が対立している場合は、家庭裁判所での離婚調停や離婚裁判による離婚が適していることもあります。
また、そもそも話し合いを経ずに離婚裁判でいきなり離婚することはできないため、「揉めているから裁判で決着をつけたい。」と考えていても、本記事でご紹介する流れに沿って手続きを進めていく必要があります。
それでは、離婚手続きの全体的な流れを見ていきましょう。
離婚手続きの流れ
1.協議離婚
協議離婚は、夫婦が当事者同士で話し合いを行い、離婚条件について合意することで成立する離婚の方法です。
まず、子供の親権や養育費、財産分与、年金分割といった離婚条件について話し合います。これらの条件は離婚後の生活に直結するため、事前に整理し、双方が納得できる内容で合意することが重要です。
離婚条件がまとまったら、離婚届に記入します。離婚届の押印は制度の改正により任意となりましたが、夫婦双方の署名が必要なので、きちんと自署しましょう。
完成した離婚届を役所に提出し、受理されることで、話し合いによる離婚が成立します。
しかし、話し合いで条件がまとまらない場合は、協議離婚を進めることが難しくなります。その場合には、家庭裁判所での離婚調停を検討することになります。
2.調停離婚
夫婦間での話し合いによる離婚が難しい場合は、第三者に間に入ってもらって話し合うことになります。それが、離婚調停による離婚です。
離婚調停は、家庭裁判所で行われる手続きを通じて離婚条件について合意を目指す方法です。協議離婚で条件の合意が得られない場合や、感情的な対立が深刻で話し合いが難しい場合には、離婚調停を申し立てることがおすすめです。
離婚調停は、家庭裁判所で行われる手続きを通じて離婚条件について合意を目指す方法です。協議離婚で条件の合意が得られない場合や、感情的な対立が深刻で話し合いが難しい場合には、離婚調停を申し立てることが適切です。
離婚調停を申し立てるには、戸籍謄本などの必要書類を揃えた上で、離婚調停申立書とともに家庭裁判所に提出します。離婚調停では、裁判官と中立的な立場の調停委員が、夫婦それぞれの意見を個別に聞き取りながら話し合いをサポートします。
離婚調停で双方が合意に至った場合、調停成立となり、調停調書が作成されます。
ただし、離婚調停が成立しても、戸籍上の離婚が成立するためには、市区町村役場に離婚届を提出しなければなりません。ですので、調停調書の謄本を交付申請し、離婚届とあわせて市区町村役場に提出します。
なお、離婚調停によっても離婚ができない場合は、離婚審判や離婚裁判になります。
3.審判離婚
離婚審判は、裁判官が職権で離婚方法や条件を決定する手続きです。夫婦の双方が離婚に同意しているものの、条件面でわずかな意見の違いがある場合や、離婚そのものや条件について争いがないにもかかわらず、一方の当事者が家庭裁判所の調停に出頭できない場合などに離婚調停を不成立としてしまうと、ほとんど離婚について合意できているのに離婚裁判をすることになってしまうため、非常に不経済です。
そこでこのような時には、審判によって離婚についての判断が下されます。
離婚調停とは異なり、裁判所が判断を下すため、必ずしも自分が納得できる条件で離婚が成立するとは限りません。
離婚審判が成立すると、家庭裁判所で審判書が作成されます。ただし、審判が成立しただけでは戸籍上も離婚成立とはなりません。審判書の謄本と離婚届を市区町村役場に提出することで、戸籍上の離婚が成立します。
なお、審判離婚は制度上存在しているものの、実際にはほとんど利用されていない手続きです。
審判の結果に不服がある場合や、離婚調停が不成立となった場合には、離婚裁判に移行することになります。
4.裁判離婚
離婚裁判は、離婚調停が不成立の場合や、審判の結果に異議がある場合に行われます。家庭裁判所に訴訟を提起し、裁判官が夫婦間の争点について判断し、判決が下されます。
離婚裁判で離婚が認められるためには、民法に定められた離婚理由(法定離婚事由)が必要です(民法第770条1項)。
(裁判上の離婚)
民法第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
法定離婚事由のあることを証明して認められれば、離婚裁判によって離婚が成立します。
そして、調停離婚や審判離婚の場合と同様に、戸籍上の離婚を成立させるためには、離婚届と一緒に判決書の謄本を市区町村役場に提出する必要があります。
離婚裁判は時間と費用がかかるうえ、夫婦間の対立がさらに深まる可能性もあります。そのため、可能であれば協議離婚や離婚調停での解決を目指すことが望ましいとされています。しかし、法定離婚事由に該当する事情があり、その他の方法で解決が難しい場合には、離婚裁判による離婚を検討してみるのも一つの手段です。
スムーズな離婚の段取り
以上が基本的な離婚の手続きの流れとなりますが、協議離婚から調停離婚、裁判離婚と進めていくと、当然その分、時間も手間も費用も多くかかってしまいます。ですので、離婚の手続きをスムーズに進めていくためには、事前の段取りが大切です。
まず、離婚条件について事前にしっかりと整理しておきましょう。親権や養育費、財産分与、年金分割などの具体的な離婚条件について、自分の希望を明確にし、現実的な案を考えることが重要です。離婚条件が不明確なままだと、話し合いが進まず、離婚の手続きが長引く原因となってしまいます。
離婚協議を始めるにあたっては、財産や収入状況を事前に整理しておくことが重要です。具体的には、財産目録を作成し、預貯金や不動産、負債の内容をリストアップしておくと、話し合いがスムーズに進みます。
また、必要書類をあらかじめ準備しておくことも欠かせません。戸籍謄本や収入証明書、生活費の試算表などを用意しておくことで、話し合いや手続きが効率的に進みます。
スムーズな離婚を実現するためには、事前に離婚条件や必要書類の準備、財産の整理などを行い、計画的に手続きを進めることが不可欠です。時間や費用の負担を最小限に抑えるために、離婚の話し合いを切り出す前に十分に準備をしておきましょう。
弁護士に依頼しましょう
離婚手続きをスムーズに進めるには、弁護士に依頼するのも有効です。
離婚では、親権や養育費、財産分与、年金分割などの離婚条件を決める必要がありますが、これらの問題は法的な知識や交渉力を求められることが多いです。そのため、法律の専門家である弁護士に依頼することで、スムーズな流れで離婚を進めることが期待できます。
例えば、離婚協議では、弁護士が代理人として相手との話し合いを進めるため、当事者同士の感情的な対立を避けることができます。これにより、話し合いが円滑に進むだけでなく、冷静で合理的な解決が期待できます。
また、離婚調停では、弁護士が夫婦の主張や状況を整理し、調停委員に効果的に伝えることで、有利な条件での合意を目指します。
離婚裁判では、弁護士が当事者の主張を法的に整理し、裁判官にわかりやすく伝えるための書類や証拠を適切に準備します。本人だけでは調べることが難しい情報を調査し、裁判官にきちんと伝わるような書類や証拠にまとめあげ、主張したいこと・主張すべきことを適切に主張できるよう尽力します。
また、離婚調停や離婚裁判では、感情的な対立が激しくなりがちですが、弁護士が冷静な第三者として関与することで、直接的な対立を緩和する効果もあります。これにより、当事者が過度なストレスを抱えることなく、手続きを進められる環境が整います。
離婚は当事者にとって心理的にも負担の大きい手続きですが、弁護士に依頼することで手続きの煩雑さを軽減し、スムーズに進めることが可能です。安心して離婚手続きを進めたい方は、弁護士に依頼することを検討してみてください。
離婚を弁護士に依頼する流れ
離婚の手続きを弁護士に依頼する流れですが、通常は以下の流れが一般的です。
まずは法律事務所に連絡をして、法律相談の予約を取ります。法律相談では、夫婦の現在の状況や希望する離婚条件などについて詳しく弁護士に伝え、弁護士費用や進め方などについても確認します。
弁護士に依頼することを決めたら、委任契約を締結して着手金を支払います。この後は、話し合いや離婚調停などの手続きを、弁護士が依頼者の代理人として行います。
離婚成立後には、必要に応じて戸籍変更や名義変更などのサポートも受けられます。全ての手続きが終了したら、成功報酬と実費を支払い、事件終結となります。
離婚の具体的な手順
さて、以上が離婚の全体的な手続きの流れとなります。
夫婦だけの話し合いで離婚ができなければ、離婚調停や離婚裁判にまで発展する場合があります。とはいっても、日本では約9割の夫婦が離婚協議によって離婚しているため、離婚裁判にまで進むケースはそれほど多くはありません。
ですので、協議離婚の場合の具体的な離婚成立までの流れについて、以下でより詳しく解説していきます。
離婚届提出までの流れ
協議離婚は、夫婦が話し合いによって離婚条件を決定し、その後、離婚届を提出することで成立します。この具体的な流れとしては、次の通りです。
まず、親権や養育費、財産分与、年金分割といった離婚条件について話し合い、離婚条件について夫婦間での合意を形成します。
協議離婚を成立させるにあたって、特に重要な離婚条件は子供の親権についてです。離婚届を提出する際、未成熟の子がいる場合は、必ず子供の親権者を指定する必要があるため、必ず話し合って親権者を決めておく必要があります。言い換えますと、子供の親権者さえ指定しておけば離婚届を問題なく提出できるので、他の離婚条件については離婚後にゆっくり決めることも可能なわけです。
さて、離婚届を記入できたら、市区町村役場に離婚届を提出します。この際、本籍地の市区町村に離婚届を提出する場合は、離婚届を提出するだけで大丈夫です。しかし、本籍地ではない市区町村(現住所地の市区町村など)で離婚届を提出する際には、離婚届に加えて戸籍謄本も提出する必要があります。ですので、あらかじめどの市区町村役場に提出するのかを考えておき、必要であれば早めに戸籍謄本を準備しておきましょう。
役場で離婚届が受理されると、協議離婚が法的に成立し、戸籍にもその内容が反映されます。
以上が、協議離婚における離婚届提出までの具体的な流れです。
離婚の流れに関するQ&A
Q1.全体的な離婚の流れを教えてください。
まずは夫婦間の話し合いで離婚を進めていきます。話し合いでは離婚できなかった場合、離婚調停を申し立て、離婚調停でも離婚が成立しなければ離婚裁判へ進むことになります。
Q2. 離婚の流れの中で最初に行うべきことは何ですか?
離婚の流れの中で最初に行うべきことは、離婚条件の整理と話し合いです。親権、養育費、財産分与、年金分割など、離婚後の生活に関わる事項について自分の希望を明確にし、相手との話し合いを開始することが基本的な流れとなります。
Q3.離婚の流れをスムーズに進めるにはどのような準備が必要ですか?
離婚の流れをスムーズに進めるためには、必要な書類(戸籍謄本や財産目録など)を事前に揃え、離婚条件を整理しておくことが大切です。また、話し合いの進め方や進行状況を記録しておくことで、次の手続きに進む際の参考になります。
まとめ
本記事では、離婚の流れについて解説いたしました。全体的な離婚の流れとしては、話し合いによる協議離婚から始まり、家庭裁判所での離婚調停、そして離婚裁判へと進むことになります。
離婚をスムーズに進めるためには、手続きの進行に応じた準備や対応が欠かせません。特に、離婚条件の整理や必要書類の準備を早めに行い、状況に応じて適切に判断・対処することで、手続きにかかる時間や負担を軽減することができます。
適切な準備を行うためには、離婚がどのように行われるのか、具体的な流れを正しく把握しておくことが重要です。本記事を参考に、全体の流れをしっかりと把握し、状況に応じた行動を取ることで、より安心して手続きを進めていただければと思います。
もし離婚の進め方に関してお悩みやご不安がありましたら、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。Web予約フォームやお電話にて、お気軽にお問合せいただければと思います。
この記事を書いた人

雫田 雄太
弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。