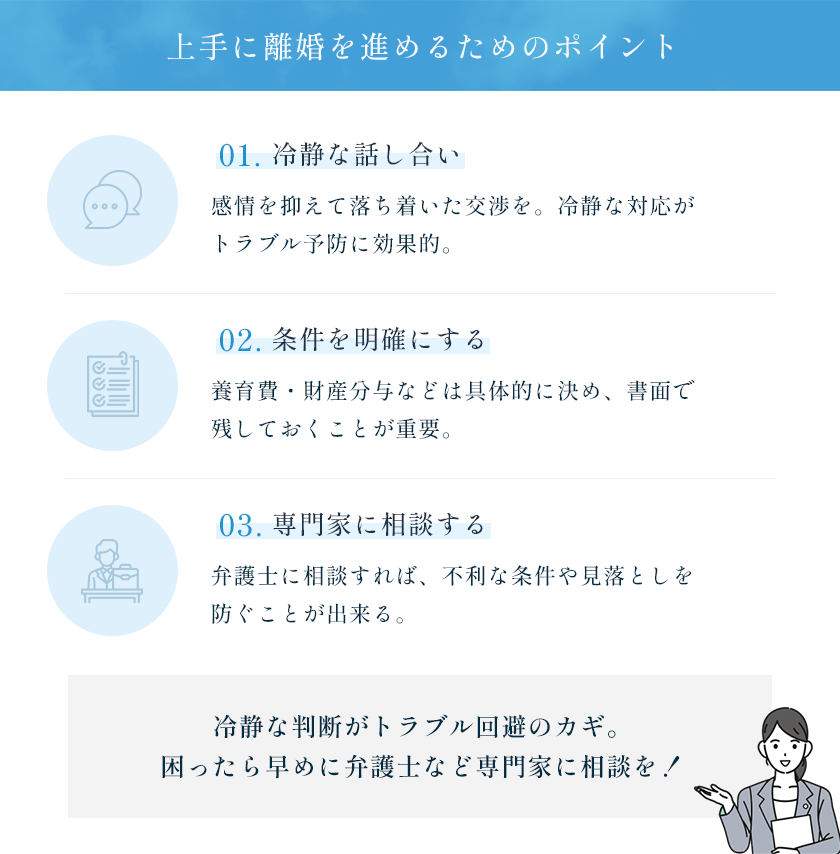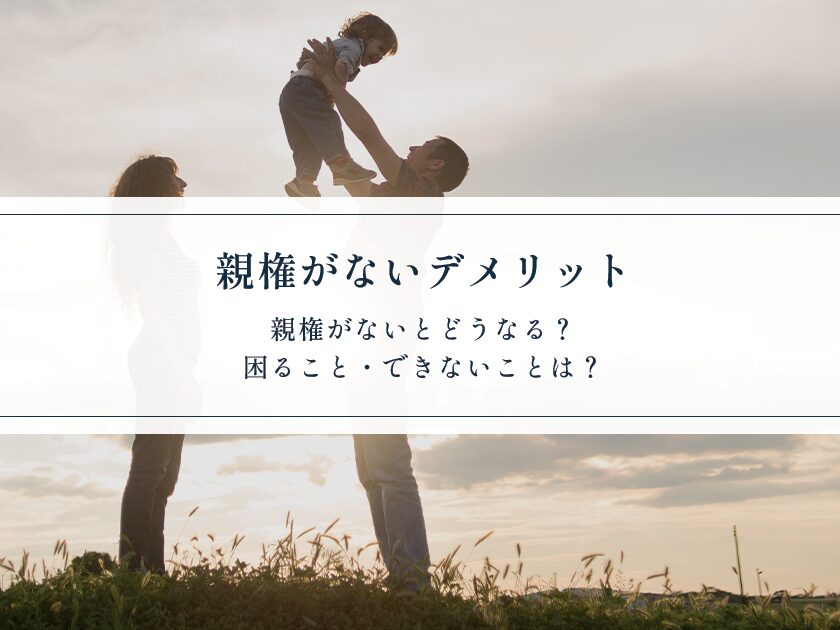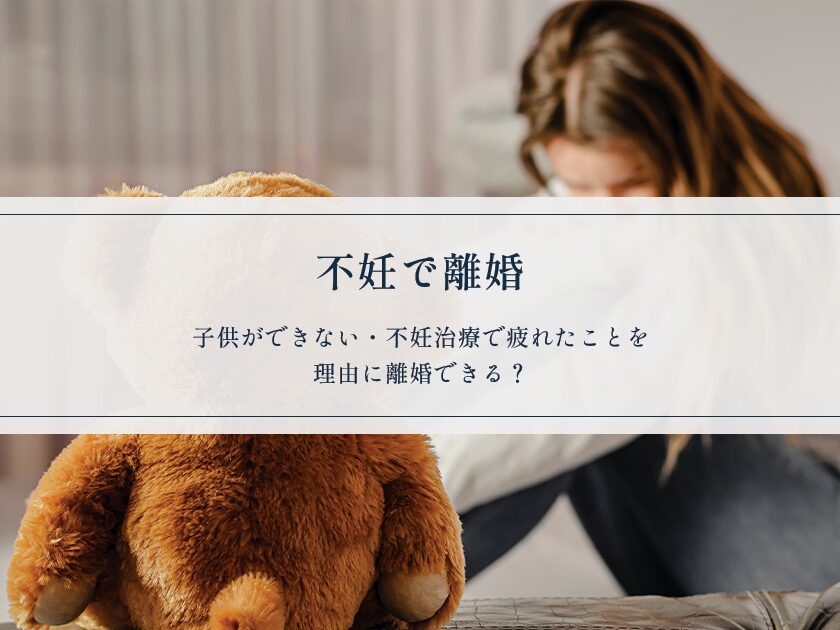離婚するには|うまく離婚するにあたって何から始めるか弁護士が解説

離婚する際には、何から始めたら良いのでしょうか。離婚といっても、あっさりと離婚できるケースもあれば、慰謝料や子どもの親権で相手と揉め、何ヶ月も争いが続くケースもあるでしょう。そのため、離婚手続きの進め方や方法は個々のケースに応じてさまざまです。状況に応じた適切な対応を取るためには、離婚についての正しい知識を身につけておくことが重要となります。
そこでこの記事では、「離婚するには何から始めるか」をテーマに、最初におさえておきたい離婚の知識について、弁護士が詳しく解説させていただきます。
離婚をスムーズに進めるためには、感情的にならず、冷静に対応することが求められます。特に、離婚手続きの基本的な流れや、どのようなことを決める必要があるかを事前に理解しておくことで、無用なトラブルを回避できるようになるでしょう。
本記事を参考に、離婚するために必要な事前知識を身につけ、離婚手続きをスムーズに進めていただけましたら幸いです。
目次
離婚するには
スムーズに離婚するには、事前にさまざまな用意や心構えが必要です。そして、個々のケースによってその内容は大きく異なってくるため、自身の場合に何をしたら良いのかを正確に把握しておくことが大切です。
離婚するには何から始めるか
さて、「離婚するには何から始めるか」ですが、まずは離婚の手続きを進めていく中で、離婚制度や法的側面についての正しい知識を把握しておく必要があります。具体的には、次の5つの事項についておさえておくことが重要です。
- 離婚方法についての知識
- 離婚理由についての知識
- 離婚条件についての知識
- 離婚協議書や公正証書についての知識
- 離婚後の生活についての知識
それでは、以上の5つの事項について、具体的に見ていきましょう。
離婚するにあたって
離婚するにあたっては、事前に次の5つの事項について把握しておくことが重要です。
離婚方法についての知識
離婚の手続きを進める前に、まずおさえておきたいのが「離婚方法」についての知識です。
日本においては、離婚の方法として主に「協議離婚」、「調停離婚」、「裁判離婚」の3つの方法があり、それぞれの手続きに異なる特色があります。
協議離婚
「協議離婚」とは、夫婦が話し合いを行い、お互いが離婚することに合意した上で、離婚届を役所に提出することで成立する方法です(民法第763条)。
(協議上の離婚)
民法第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
手続きが簡便で、費用や時間がほとんどかからないことから、日本ではほとんどの夫婦が協議離婚によって離婚しています。
ただし、協議離婚は夫婦の話し合いのみで進められるため、条件面で曖昧な合意や口約束のまま離婚届を提出してしまうケースも多くあります。その結果、財産分与や養育費の支払いをめぐって、離婚後にトラブルが生じることがあります。離婚後のトラブルを避けるためには、離婚届を提出する前に合意内容を明確に書面化しておくことが非常に重要です。
特に、財産分与や慰謝料、養育費などのお金に関する取り決めについては、離婚協議書を作成したり、場合によっては公証役場で公正証書にしたりしておくと、離婚後のリスクを大きく軽減できます。協議離婚の際には、手続きの簡便さだけでなく、離婚後の生活を見据えた慎重な対応を心がけることが大切です。
調停離婚
離婚協議によっても離婚ができない場合は、離婚調停を検討することになります(調停離婚)。
調停離婚とは、夫婦間の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所で調停委員という第三者を交えて協議を進める離婚方法です(家事事件手続法第244条)。
(調停事項等)
家事事件手続法第244条 家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。
離婚調停は、この家事事件手続法第244条の「人事に関する訴訟事件」についての調停になります。
調停離婚の特徴は、夫婦が直接顔を合わせずに話し合いを進められる点にあります。夫婦が直接やり取りすると感情的になってしまい、話し合いが平行線になりがちですが、調停では調停委員が双方から個別に意見を聞き取り、中立的な立場で調整を進めていきます。そのため、冷静な話し合いが期待でき、夫婦間では折り合いのつかなかった離婚条件についても、第三者である調停委員の意見を参考にしながら合意を目指せるという利点があります。
調停が成立すると、「調停調書」と呼ばれる裁判所が作成する公式な文書に合意内容がまとめられます。調停調書には判決と同等の法的効力があるため、万が一、離婚後に合意した財産分与や養育費などが支払われない場合には、給与や預金口座などを差し押さえる強制執行が可能になります。
調停離婚は協議離婚よりも時間や手間がかかりますが、公平性や法的な安定性が高いという大きなメリットがあります。一方で、調停委員はあくまで中立な立場のため、自らの主張を納得してもらうには根拠や資料を整理し、説得力ある主張を準備することが重要になってきます。
裁判離婚
調停離婚でも合意が難しい場合には、「裁判離婚」という手続きを検討することになります。裁判離婚とは、協議や調停で離婚できない場合に、家庭裁判所の判決によって離婚を成立させる方法です(民法第770条1項)。
(裁判上の離婚)
民法第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判離婚の特徴は、相手がどれだけ離婚を拒否しても、法律で定められた離婚原因(法定離婚事由)を裁判所に認めてもらえれば、判決によって離婚が成立する点にあります。ただし、裁判で離婚が認められるためには、客観的な証拠を提出し、離婚原因が実際に存在することを具体的に立証しなければなりません。そのため、証拠収集や裁判所への書面の提出、期日への出廷など、裁判離婚の手続きでは相当な労力や時間を必要とします。そして、法律の専門的知識が必要になるため、弁護士に依頼して進めるケースが一般的ですが、そうなると裁判費用に加えて、弁護士費用もかかるため、経済的負担も大きくなります。
また、裁判離婚は半年から1年以上の期間が必要になるケースもあり、離婚協議や離婚調停から通算すると、離婚を検討して数年後にやっと離婚成立した、となる場合も少なくないのです。
以上の通り、離婚を円滑に進めるためには、離婚方法のメリットとデメリットを理解した上で、自身の状況に合う最適な方法での離婚を目指すことが大切です。
離婚理由についての知識
離婚の手続きを進めるにあたり、「どのような理由があれば離婚できるのか」ということを事前に理解しておくことが大切です。夫婦双方が離婚に合意し、協議離婚が可能な場合であれば、離婚の理由に特に制限はありません。たとえば、「価値観の違い」や「性格の不一致」といった一般的な理由でも、夫婦が互いに納得しているのであれば離婚届を提出するだけで離婚は成立します。
しかし、夫婦間で離婚の合意が得られず、調停でも解決できずに裁判離婚となる場合には、法律で定められた「法定離婚事由」がなければ離婚が認められません。法定離婚事由とは、民法第770条1項に規定されている離婚の原因であり、具体的には次のようなものが挙げられます。
- 配偶者の不貞行為(肉体関係をともなう浮気・不倫)
- 配偶者による悪意の遺棄(正当な理由のない同居拒否や扶助義務の放棄)
- 配偶者の3年以上の生死不明
- 配偶者の回復見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由(DV・モラハラ・長期間の別居・浪費・ギャンブル癖など)
裁判で離婚を認めてもらうためには、これらの法定離婚事由のうち、いずれかの理由を客観的な証拠で立証する必要があります。
たとえば、配偶者の不貞行為を理由に離婚を求める場合、単なる疑いや噂だけでは裁判所に認めてもらうことは難しいでしょう。この場合は、浮気相手とのメールやLINEなど、実際に浮気をうかがわせるやり取りの記録が重要な証拠となります。また、ホテルの領収書やクレジットカードの利用明細、浮気現場を撮影した写真や動画があれば、より強力な証拠になります。
あるいは、DVやモラハラを理由に離婚を求める場合には、暴力や暴言があったことを客観的に示す証拠を準備する必要があります。暴力を受けた場合は、病院の診断書やケガの写真、警察への被害届の記録が証拠になります。暴言やモラハラについては、相手の発言を録音した音声データや、日記、メール・LINEの記録などが重要な証拠となるでしょう。
裁判離婚を進めるにあたっては、これらの証拠をあらかじめ準備し、どの証拠が離婚理由の立証に適しているかを慎重に見極めておくことが重要です。証拠が不十分だと、裁判で離婚が認められない可能性が高まるため、離婚理由に関する具体的な知識と証拠収集の重要性を十分理解しておくことが大切になります。
離婚条件についての知識
離婚をする際には、単に夫婦関係を解消するだけでなく、その後の生活についてさまざまな条件を取り決める必要があります。具体的には、財産分与や慰謝料、子どもの親権、養育費、面会交流、年金分割などがあり、これを一般的に「離婚条件」といいます。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を公平に分けることです。夫婦が婚姻期間中に取得した財産のほとんどは財産分与の対象になります。たとえば預貯金や不動産、自動車や家財道具、生命保険の解約返戻金なども対象です。また、住宅ローンや借金などの負債も財産分与の対象となるため、どちらが負担するかを離婚前に明確に決めておく必要があります。
慰謝料とは、相手の不貞行為(浮気・不倫)やDV、モラハラなどによって精神的苦痛を受けた場合に支払われる損害賠償金のことをいいます。慰謝料は必ずしも離婚に伴って発生するわけではなく、相手に違法な行為や有責性がある場合に限り請求できます。慰謝料の金額は、婚姻期間や相手の収入状況、不法行為の内容や程度に応じて変わります。
未成年の子どもがいる夫婦の場合、離婚時にはどちらが親権者となるかを必ず決めなければなりません。親権とは、子どもの養育・監護や法定代理を行う権利義務のことです。親権者は離婚届に記載しなければ受理されないため、離婚前の段階で決定しておく必要があります。
養育費は子どもが経済的に自立するまでに必要な生活費や教育費のことです。一般的に親権を持たない親が養育費を支払います。養育費の金額は、夫婦それぞれの収入状況や子どもの人数、子どもの年齢などをもとに決定します。トラブルを避けるためには、養育費の支払い方法や支払い期限についても明確に取り決め、書面に残しておくことが重要になります。
また、親権を持たない親にも子どもとの面会交流をする権利があります。離婚後にトラブルにならないように、面会交流の頻度や方法、時間などについてもあらかじめ取り決めておくことが望ましいでしょう。
年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が納めてきた厚生年金の記録を離婚時に分割し、夫婦の年金額の差を是正する制度です。年金分割の割合は最大で2分の1であり、夫婦間の合意によって決定します。もし話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所で調停・審判により分割割合が決定されることになります。年金分割をする場合は、離婚後2年以内に手続きをしなければなりませんので、こうした請求期限についても事前に把握しておくことが重要です。
これらの離婚条件をあらかじめしっかりと話し合い、明確に決めておくことで、離婚後のトラブルを回避し、安定した生活を送ることが可能になります。特に、財産分与や慰謝料、養育費といった金銭的条件については、後日の紛争防止のため、離婚協議書を作成しておくか、公正証書にしておくことをおすすめいたします。
離婚協議書や公正証書についての知識
離婚するにあたって夫婦間で話し合いがまとまった場合、その合意内容を口頭で済ませるだけでなく、離婚協議書や公正証書などの書面にしておくことが大切です。
離婚協議書を作成するメリットは、合意内容を明確にすることで「言った・言わない」といったトラブルを防ぐことができる点にあります。離婚協議書に夫婦が署名・押印をしておけば、後日に合意内容を証明する証拠として使うことも可能です。
しかし一方で、夫婦間のみで作成した離婚協議書は、あくまで私的な契約書に過ぎません。そのため、離婚後に相手が約束を守らず養育費や慰謝料の支払いが滞った場合でも、離婚協議書だけでは給与や銀行口座の差押えなどの強制執行をすることができないというデメリットがあります。
この離婚協議書のデメリットを解消できるのが、公正証書になります。
公正証書とは、公証役場において公証人が作成する公的な書面であり、裁判の判決文と同様の強い効力を持つことが特徴です。離婚条件を記載した公正証書を作成することにより、万が一相手が金銭の支払いを怠った際には、裁判を起こさなくても直ちに強制執行を行うことが可能になります。
さらに、公正証書には公証人という法律の専門家が介在するため、記載内容の法的妥当性や公平性が保たれるというメリットもあります。また、公正証書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクもありません。
ですが、公正証書を作成するには一定の費用や手間がかかり、作成のためには夫婦が揃って公証役場へ出向く必要がある、というデメリットもあります。作成する際には、あらかじめ弁護士に相談しておくことをおすすめいたします。
離婚協議書や公正証書について、メリット・デメリットを理解しておくことは、スムーズな離婚とその後の生活のために非常に重要です。
離婚後の生活についての知識
離婚を進める際には、離婚そのものに関する手続きや条件だけでなく、離婚後の生活をどのように送っていくかについても事前に考えておく必要があります。
離婚後の生活に関して、戸籍や姓に関する手続きがあります。離婚すると、婚姻中の戸籍から抜け、元の戸籍に戻るか新しい戸籍を作ることになります。原則として旧姓に戻ることになりますが、離婚後も婚姻中の姓を名乗り続けたい場合には、離婚成立後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出する必要があります。
なお、子どもの戸籍は親権者の戸籍に自動的に入るわけではありません。親権者の戸籍に子どもを入れるためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得てから、役所で入籍届を出す必要があります。
離婚後の収入や生活費についても事前に考えておく必要があります。特に、婚姻期間中に収入がほとんどない人や、専業主婦(夫)だった場合、離婚後の生活費が不足する可能性があります。そのため、就職活動や資格取得、職業訓練を検討するなど、離婚後に経済的な自立ができるように生活設計を立てておくことが重要です。
また、ひとり親世帯となる場合には、公的な支援制度を活用することができます。児童扶養手当や住宅手当、医療費助成など、各自治体がひとり親家庭向けにさまざまな支援制度を設けています。自分が住む地域にはどのような支援制度があるのか、離婚前に事前に調べておくと、離婚後の経済的な負担を軽減することができるでしょう。
そして、子どもの精神面にも気を配り、離婚成立前後にケアを欠かさないようにしましょう。両親の離婚が子どもに与える影響は、決して少なくありません。離婚協議や調停を進める間、子どもは家庭内の変化や両親の態度の変化を敏感に感じ取ります。父親や母親と暮らせなるかもしれない、と察すると、今後の生活について不安になり、そうしたストレスが日常生活に悪影響となることもあります。
そのため、離婚手続き中は子どもの様子に目を配り、離婚成立後も、子どもが新生活に慣れるまでは十分にケアする必要があります。
子どもが今後どちらの親と生活することになるのかを早めに伝えてあげたり、新しい住居や転校先の学校について一緒に見学したり、子どもが安心できるようにフォローしてあげましょう。離婚後も継続的に子どもの気持ちを確認し、必要に応じてカウンセリングや専門家のサポートを受けるなど、適切なケアを続けるようにしましょう。
うまく離婚するには
離婚においては、感情的になって十分な話し合いをしないまま別れを急ぐと、財産分与や親権、養育費などの取り決めがあいまいなまま進んでしまい、後々大きなトラブルに発展しやすくなります。特に、子どものいる家庭では、親権や養育費の負担割合が不明確なままだと、子どもの生活や教育・進学に大きな影響が及ぶ可能性もあります。
離婚で失敗しないためには、しっかりと話し合いの時間を設け、双方が納得できる条件を整えることが欠かせません。必要に応じて専門家のアドバイスを取り入れることも重要です。
上手な離婚の進め方
離婚の手続きを進める中で、さまざまな要因から精神的に不安定になりやすく、どうしても感情的な言葉を使ってしまったり、表情や態度に不満を出したりしてしまいがちです。
ですが、上手くスムーズに離婚を進めるためには、できるだけ感情を抑えて、離婚条件の検討や相手との交渉を冷静に行うことが大切です。お互いが感情的になってしまうと、話し合いが進まなくなったり、余計に揉め事が増えて争いが長引いたりする可能性があります。そのため、自分の考えや希望する条件を相手に正確に伝え、円滑に手続きを進めていくためには、落ち着いて感情的にならないよう話し合うことが重要です。
冷静に話し合うことができれば、自分も相手も互いの意見や考えを受け入れやすくなり、離婚条件や離婚することについての合意が得られやすくなります。また、離婚条件の中身についても冷静に判断して結論を出せるため、結果的に離婚後のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。
また、離婚問題を自分だけで抱え込まずに、なるべく早い段階で専門家に相談することも重要です。離婚手続きでは、財産分与や慰謝料、子どもの養育費や親権など、法律的な知識や判断が求められる場面が多いです。そのため、自分一人で手続きを進めると、気づかないうちに不利な合意をしてしまったり、思わぬトラブルに巻き込まれたりする可能性があります。ですので、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。
弁護士は法律に精通していますから、財産分与や慰謝料、養育費や親権など、離婚に関する問題全般に詳しい知識を持っています。そのため、自身の状況に応じた的確なアドバイスやサポートを受けることができます。
特に、財産分与や養育費などの経済的な条件については、交渉が難航することが多く、感情的になってしまいがちです。弁護士に交渉を任せることで、冷静かつ客観的に話し合いを進められ、自分の利益や権利をしっかりと守りながら手続きを進めることができます。
また、裁判となった場合も、複雑な手続きや裁判での主張立証を弁護士が代理しますので、手続きの負担や心理的なストレスを大幅に軽減できます。
さらに、自分では気づかなかった法律的なリスクや、将来的なトラブルの可能性などについても、専門的な視点で早期に指摘・対応してもらえるというメリットもあります。
Q&A
Q1.離婚するには、まず何から始めたらいいですか?
A1:離婚するには、離婚の方法や離婚が認められる理由、離婚条件や離婚制度に関して、正しい知識を把握しておくことが大切です。その上で、自分の考えや希望条件を整理し、夫婦間で冷静に話し合いを進めることが重要です。
Q2.離婚するにはどのような手続きがありますか?
A2:離婚手続きには「協議離婚」、「調停離婚」、「裁判離婚」の3つの方法があります。夫婦間で離婚について合意できれば、離婚届を提出するだけで離婚が成立する協議離婚によって離婚することができます。話し合いがまとまらない場合に家庭裁判所で第三者を交えて話し合う調停離婚となり、調停でも解決しない場合は、裁判所の判決で離婚を成立させる裁判離婚となります。
Q3.離婚するには具体的にどのような理由が必要ですか?
A3:離婚する理由は、夫婦が協議離婚する場合は特に限定されません。ですが、裁判離婚をする場合には、法律で決められた法定離婚事由が必要です。具体的には、不貞行為(浮気・不倫)、悪意の遺棄(生活費を渡さない・理由のない別居など)、3年以上の生死不明、回復見込みのない強度の精神病、婚姻を継続し難い重大な事由(DV、モラハラ、浪費などによる婚姻関係の破綻)があります。
まとめ
本記事では、離婚するにあたって何から始めたら良いのか、というテーマに主軸を置き、弁護士が解説させていただきました。
離婚を考えたら、離婚方法や法律的なルールを正しく理解し、自身のケースで適切な対応を取ることが重要です。配偶者が離婚に前向きか、どういった理由で離婚を考えているのか、相手に対する金銭的請求はあるかなど、一つひとつの要素について十分に検討し、正しい知識を前提に判断する必要があります。
とはいえ、日々の仕事や家事・育児をこなしながら離婚の準備を進めていくのは、負担も少なくないですし、ストレスもたまる一方です。
ですので、離婚問題に無理して一人で対処しようとせず、弁護士のサポートを受けることを検討していただければと思います。
弁護士法人あおい法律事務所では、離婚問題について豊富な解決実績を持つ弁護士が、離婚に関するさまざまな疑問や悩みについてご相談をお受けしております。当法律事務所では、法律相談料は初回無料となっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。誰かに相談はしたいが、弁護士への依頼は迷っている、というような場合にも、お気軽にお問合せください。
この記事を書いた人

雫田 雄太
弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。