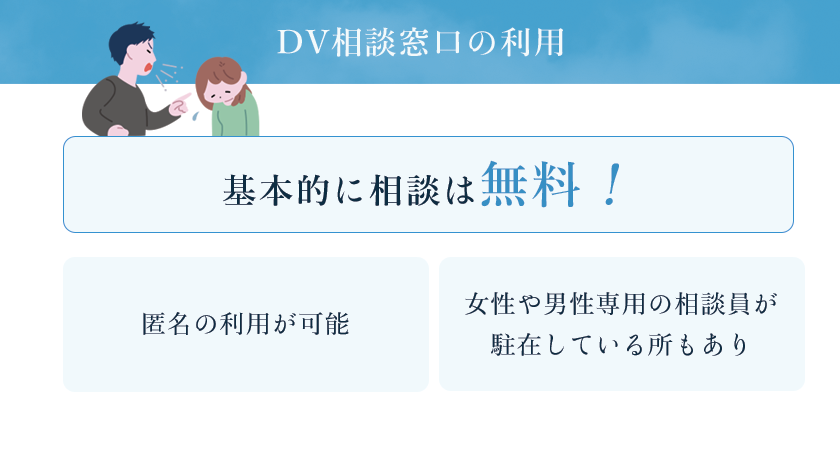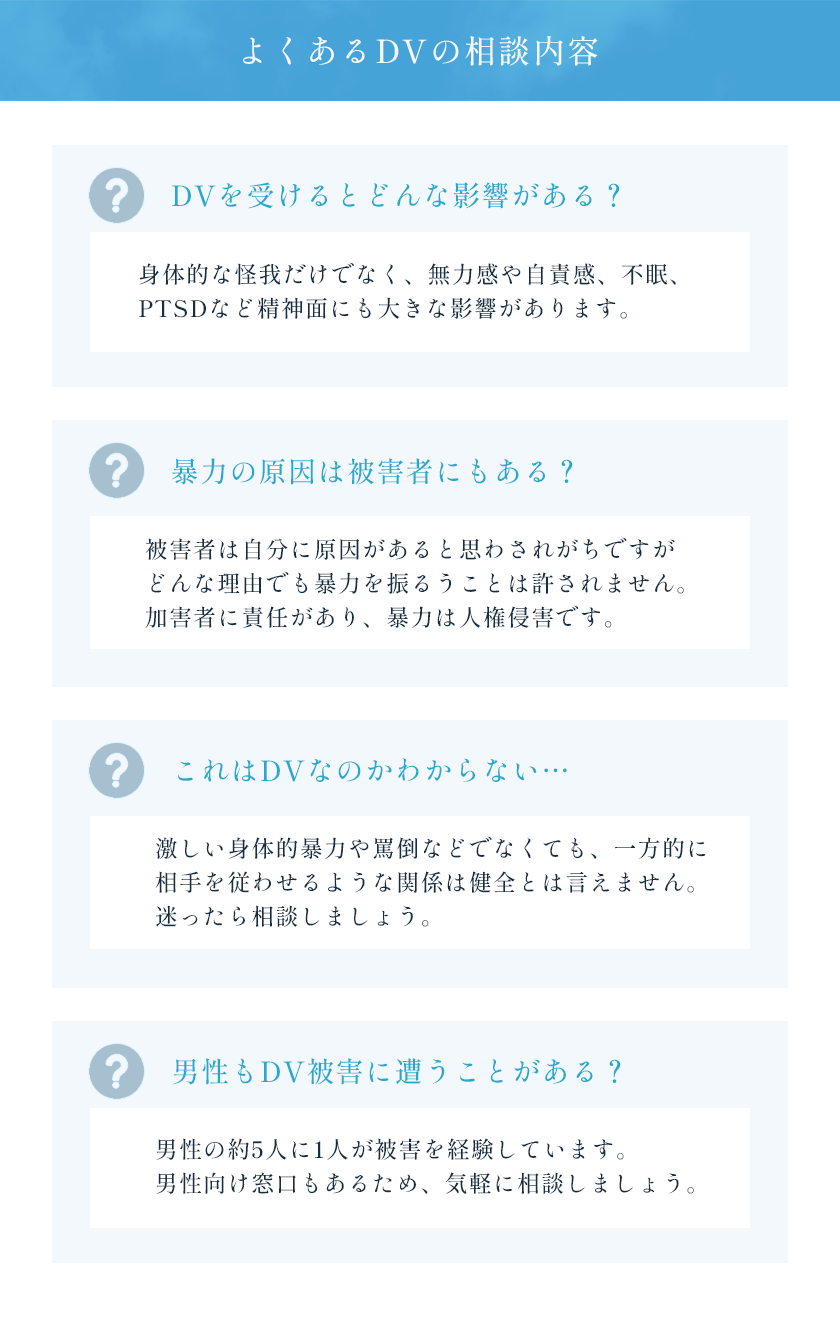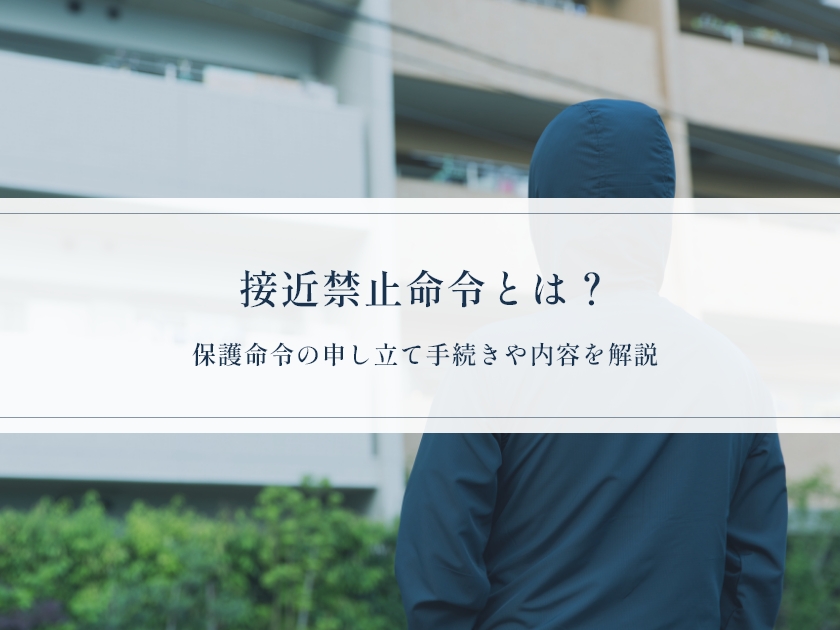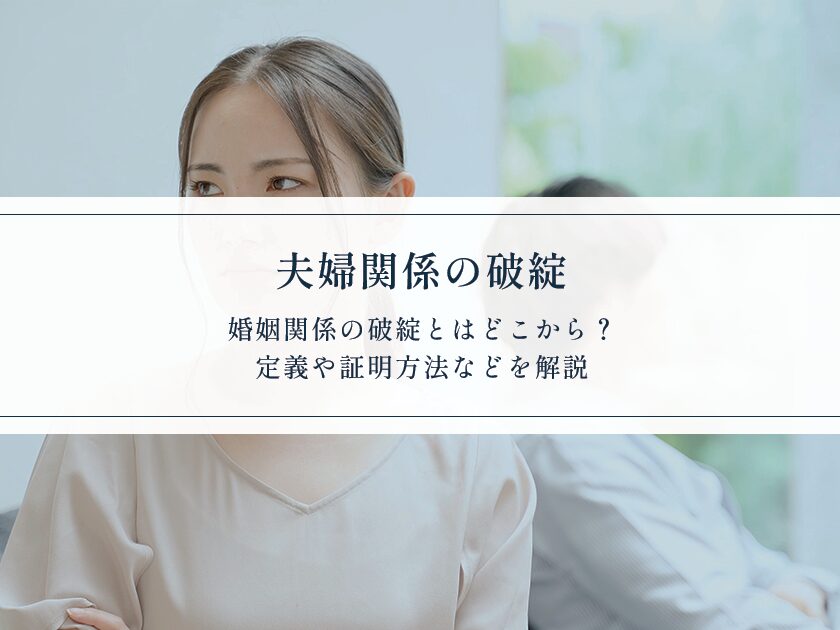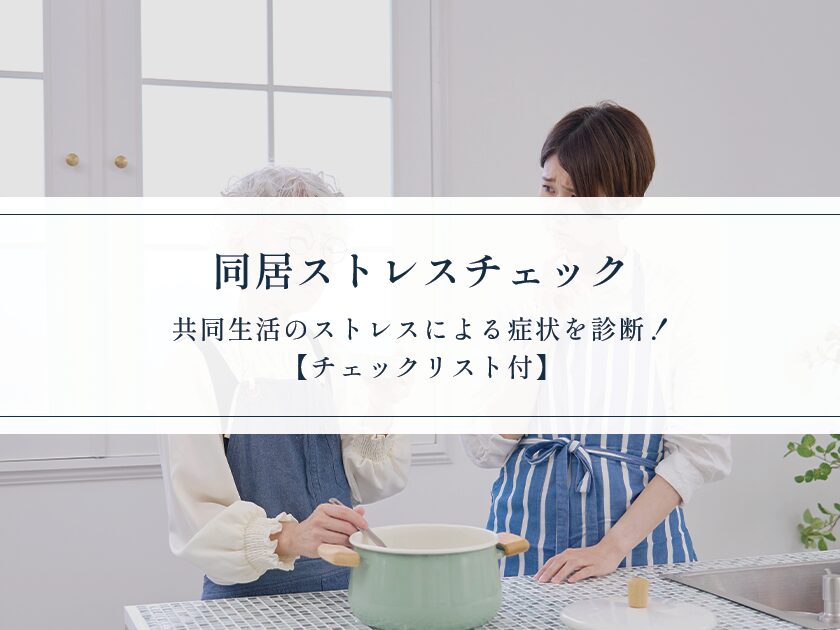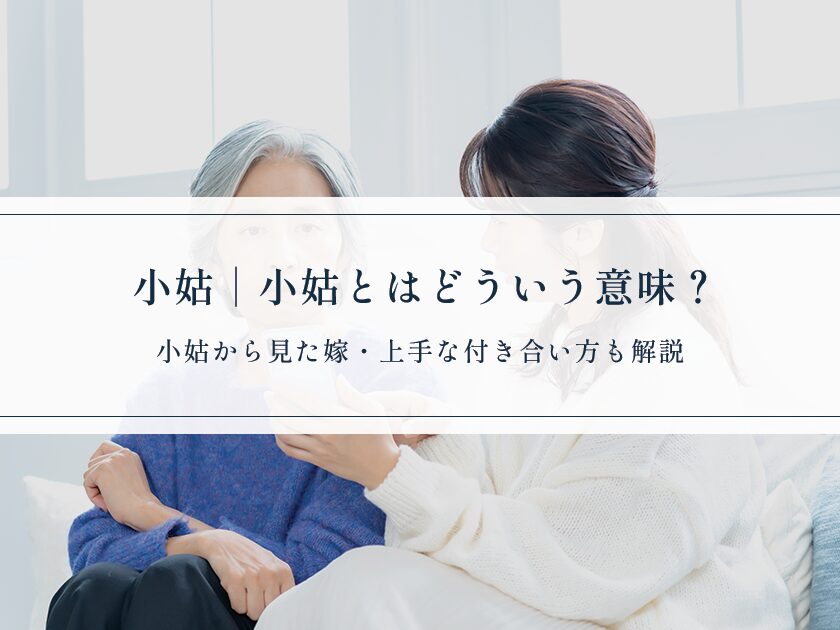DV相談プラスやナビダイヤルを利用して24時間電話窓口で対応!シェルターも検討!
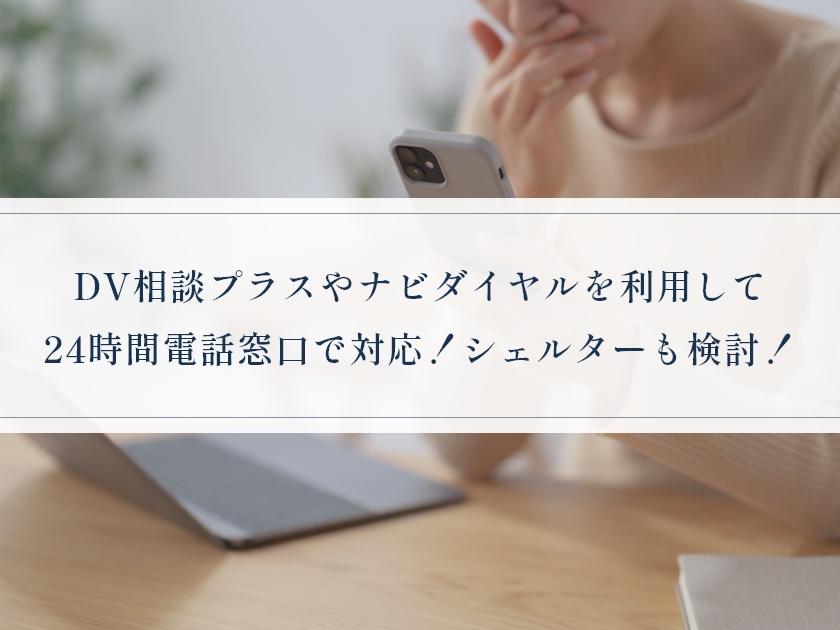
DVとは、ドメスティック・バイオレンス(domestic violence)の略称です。domesticは「家庭内の」という意味がありますが、配偶者に限らず、恋人などの関係も含まれます。
パートナーから暴力を振るわれたり、暴言を吐かれたりして、ひとりで悩みを抱えていませんか?「暴力を振るわれているけど、どうしていいかわからない」「今すぐに逃げたいけど、相手が怖い」など、つらい思いで悩んでいる場合は、国や地方自治体のDV相談サービスを利用することをおすすめします。
特に内閣府が実施している24時間対応の無料相談電話サービスやSNSチャット相談など、専門家があなたの相談を親身に聞いてくれて、適切な解決方法を一緒に探してくれます。
ここでは、DVについて悩んでいる方に向けて、DVの電話相談や窓口について詳しく紹介していきます。
目次
国の相談窓口「DV相談+」:24時間無料電話相談、メールやチャット相談、外国語対応可
内閣府の「DV相談+」なら専門家による24時間の無料電話相談、メールやチャット相談、WEB面談、10か国の外国語対応相談ができます
夫や妻から暴力を振るわれた、毎日ひどい暴言を浴びせられている、恋人から性行為を強要されたなど、一度でもDVの被害に遭い、つらい悩みを抱えている方は少なくありません。
DVを振るわれたことについて、誰かに相談するのが恥ずかしいと思えたり、またパートナーから誰にも言うなと口封じをされて相談できなかったりして、誰に頼ることもできない環境で、どんどん気持ちが追い込まれていくケースがあります。
しかし、DVは収まることなくエスカレートしていく傾向があり、被害が深刻化する前に、できるだけ早い段階でDVについて相談することが賢明といえます。
内閣府の男女共同参画局では、近年のDVの増加及び深刻化問題の懸念を踏まえて、令和2年4月から、DVの被害者を保護する目的で、「DV相談+(プラス)」という新たなDV相談事業が開始されました。
DV相談+では、DVの内容や相談者の性別や住居地にしばりはなく、24時間の電話相談のほか、メールやSNSチャットによる相談、WEB面談、外国語相談にも対応しています。相談先では、DVの専門家が対応し、悩みに寄り添いながら必要なアドバイスをしてくれます。
また、被害者一人では対応しにくい場合(新居探しや警察・弁護士への相談など)に相談相手である専門家が一緒に付き添って援助する同行支援を行ったりしてくれるサービスなどもあります。
連絡先は下記にもまとめていますが、詳しくは、内閣府の専用HPを参照してください。
|
DV相談+ |
|
|
24時間電話無料相談 |
0120-279-889 |
|
24時間メール相談 |
|
|
SNSチャット相談(昼12:00~22:00) |
|
DVに関する悩みはあるけど、窓口で対面で話をするには抵抗がある、行政の窓口の時間に行く暇がない…など、相談窓口に直接に出向くには敷居が高いと感じる方は多いことでしょう。
まずは簡単に話を聞いてみたい、些細なことをちょっとだけ相談してみたいという方には、電話やメールでの相談をおすすめします。
電話やメールは匿名で送ることができますし、顔が見えない相手になら気楽に話せることも多いと思います。
また、電話やメールで話した内容をもとに、専門家が相談にのり、あなたに必要なアドバイスをしてくれます。相談内容によっては近くの行政窓口を紹介してくれることもありますので、まずは気楽に電話やメールから相談することを始めてみましょう。
国の相談窓口「DV相談ナビ(#8008)」:最寄りのDV相談所へ電話転送してくれる相談ナビダイヤル
内閣府では、電話一本で最寄りのDV相談窓口に電話をつなげるDV相談ナビサービスを実施しています
DVで悩んでいるけれど、どこに相談すればいいか迷っているという方のために、DV相談ナビダイヤル(#8008)から、各都道府県の相談機関を案内する内閣府のDV相談ナビサービスがあります。
相談ナビダイヤルでは、発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓口に電話が自動転送され、そのまま転送先の相談窓口で話をすることができます。
電話を1本かけることにも勇気が必要かもしれません。しかし、DVに関することならどのようなことでもかまいません。「これがDVになるのかわからない」「まだ暴力は振るわれていないけれど、不安がある」など、実際にDVの被害を受けていない場合であっても相談は可能です。
まずは、あなたが置かれている状況や不安なことをゆっくりでいいので話してみてください。詳しくは、内閣府のDV相談ナビのHPを参照ください。
相談方法
- 相談者が携帯電話、固定電話、公衆電話等から電話する
電話番号 #8008(まず#ボタンを押して、続けて数字の8008を押す)※一般の固定電話にかけたときと同じ通話料がかかります。 - 各都道府県のDV相談窓口に自動転送される
※転送先は各都道府県指定の1カ所であり、最寄りの相談機関が案内されます。
※各相談機関によって受付時間が異なります。受付時間外の場合は転送できないことがあります。 - 転送先の相談機関でDVを相談する
相談先では、DVに関することならどのようなことでもお話になれます。さらに最寄りの相談機関の紹介、被害者保護のための支援、同行支援など様々な制度案内があります。
各都道府県に設置されている配偶者暴力相談支援センターとは?
配偶者暴力相談支援センターについて
DVの深刻化や相談件数が増加している状況を受け、各都道府県は、DVの被害者を支援する中核的な期間として、配偶者暴力相談支援センターを設置することになっています。
各都道府県によっては、配偶者暴力相談支援センターという名称の機関は存在せず、婦人相談所や男女共同参画センター、児童相談所、福祉事務所などが、「配偶者暴力相談支援センター」の機能を果たしていることがあります。
また、DVの被害者の身近な施設として、一部の男女共同参画センターや福祉事務所にも「配偶者暴力相談支援センター」を設置している場合があります。
配偶者暴力相談支援センターの所在地の一覧についてはこちらをご確認ください。
配偶者暴力相談支援センターの取組み
配偶者暴力相談支援センターの機能では、DVの防止及び被害者の保護を図るために以下のような取組みを行っています。
- 相談や相談機関の紹介
- カウンセリング
- 被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護(※婦人相談所又はその委託先などの施設で一時的に保護してもらうことができます。一時保護施設では、同伴した子供と一緒にしばらく安全に生活することができます。)
- 自立して生活することを促進するための情報提供(援助職業紹介や職業訓練、公営住宅、生活保護などの情報提供を行います)
- 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助(シェルターや保護施設などの情報提供を行います)
- 保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助
相談は基本無料です。また、女性でも男性でも基本的に利用することができます。
内閣府の統計によると、配偶者暴力相談支援センターへのDVの相談件数は年々増加しており、直近でも2019年度は11万9千件の相談数であったのに対し、2020年度は18万2千件に上り、約1.5倍の増加となりました。これは、新型コロナウイルス感染症の流行に伴って自宅待機やリモート勤務などが増えたことで、家庭内で配偶者によるDVが増えたことも影響しています。DVは家庭内で起こり得るため、第三者による発見も遅れがちです。
また、DV被害者の中には、「配偶者に相談していることを知られたくない」という場合も少なくありません。各相談機関は厳重な守秘義務が徹底されていますので、DVの被害に遭われた方は、できるだけ早く最寄りの支援センター等へご相談ください。
全国にある自治体のDV相談窓口を利用しよう。匿名での利用や女性専用、男性専用の相談先もあります
すべての都道府県で、配偶者暴力相談支援センター以外にも、DV防止とDV被害者の保護を目的とした施設や相談先がたくさんあります。DVの被害から抜け出し、自分や子供の安全を守るためにも、まずはそうした身近な窓口に相談してください。
匿名の利用が可能であったり、女性や男性専用の相談員が駐在しているような施設もありますので、女性でも男性でも安心して利用することができますし、県や市が運営する公共の相談施設の場合は、基本的に相談は無料となります。事前に電話などで相談窓口の時間や相談方法などについて問い合わせたうえで相談に行くことをおすすめします。
よくあるDVの相談内容をご紹介
内閣府のDV相談+や各都道府県に設置されている配偶者暴力相談支援センターには毎日のように多くのDV相談が届いています。
初めて相談する人などで、どのようなことを相談すればいいかわからないという人も多いでしょう。ここでは、DVの相談としてよくあるQ&Aをご紹介します。
A DVには、あざや骨折といった身体的な怪我だけでなく、被害者の精神面にも大きな影響を及ぼします。暴力を受け続けた結果として、「誰も助けてくれる人はいない」という諦め・無力感や「相手が暴力を振るうのは、自分に非があるからだ」という自責の念を抱く被害者も多くいます。
また、暴力を受け続けていると眠れない、やる気が出ない、記憶があいまいになる、びくびくする、感情がなくなる感じなど、様々な症状となってあらわれることがあります。それらの症状はうつ病や不安障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断されることもあり、配偶者や恋人との生活から離れた後に回復の過程として起きることもあります。
Q 暴力の原因は被害者にもあるのでしょうか?
A そうではありません。DVは暴力を振るわれる側にも落ち度があるとして被害者が責められることがありますが、DVは立派な人権侵害であり、犯罪となる行為をも含んでいます。
DV加害者は暴力の原因が被害者にあると思わせて「おまえがだらしないから、しつけてやっているんだ」「おまえがバカだから教えてやっているんだ」などと言う事が多く、何度も言われているうちに、被害者は自分に原因があると思わされがちですが、どんな理由でも暴力を振るうことは許されません。
暴力は次第にエスカレートしていくこともあります。パートナーとの関係について、配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関に相談することをお勧めします。
Q 身体的な暴力や精神的な暴力(モラルハラスメント)について、DVであるかわかりません。
A 激しい身体的暴力や罵倒などでなくても、一方的に相手を従わせる(支配する)ような関係は健全とは言えません。相手との関係性に疑問を感じるなら、必ずしもDVという言葉にこだわらず、気軽に専門機関にご相談ください。
Q DVによる被害は男性でもありますか?また、男性の被害者も相談することができますか?
A 令和2年度の内閣府「男女間における暴力の調査」で、配偶者からの被害経験を性別にみると、被害経験が『あった』は女性が 25.9%、男性が 18.4%となっています。男性でもおよそ5人に1人が被害にあっていることになり、決して珍しいことではありません。各都道府県には、男性を対象としたDVの相談窓口もありますので、男性の方でも気軽に相談することが可能です。
DVについてのご相談は弁護士事務所へ 緊急時には警察に相談を!
弁護士に相談することによって、早急に安全な生活を確保することができます
日頃から頻繁に暴力を振るわれたり、暴言を浴び続けてしまうと、感覚が麻痺してしまい、「私にも悪いところがあるから仕方がない」「前よりもマシになってきた」などと、被害を過小評価してしまうことがあります。
また、DVを受けていることが恥ずかしい、周りにどう思われるか気になってしまうと不安になり、第三者に相談できずに一人で抱え込んでしまう人も少なくありません。
DV加害者から避難することは簡単なことではありません。別れを切り出そうとすると暴力を振るわれたり、日々の言動が監視され、別居するために必要な金銭を渡してもらえないこともあります。
弁護士は様々な種類のDVの問題に携わっています。別居や離婚に至るまでの生活費(婚姻費用)、被害者の居住先の調整、DV加害者への接近禁止の申立てなど、DV加害者の行動を把握しながら、できるだけ安全かつ早急に、被害者の生活の平穏を確保するために努めていきます。
また、離婚や慰謝料請求を視野に入れている場合には、必要な書類や証拠記録などを具体的かつ詳細にお伝えしていきます。弁護士事務所に相談する場合、まずは電話一本で、無料相談が可能です。あなたに必要なことをアドバイスすることができますので、まずは是非一度、法律相談をご利用ください。
警察に相談する場合
DVは家庭内の問題ですが、警察に相談したり、近隣の人やDVを知った知人等からの通報によって、警察が動き、DV加害者が逮捕されるケースもあります。特に緊急の場合には、110番に電話するか、最寄りの警察署、交番、駐在所に駆け込んでください。
警察はDV加害者を逮捕するほか、被害者の保護に必要な措置を行います。被害者を保護する制度には、保護命令、接近禁止命令、退去命令というものがあります。保護命令等を申し立てるためには、事前にDVセンターや警察に相談していることが要件となります。保護命令等について詳しい内容を知りたい方はこちらもご覧ください。
DV相談に関するQ&A
DVの相談先にはどのようなものがありますか。
内閣府の事業である「DV相談+」や「DV相談ナビ」があります。また、各都道府県には、配偶者暴力相談支援センターが設置されており、最寄りの相談窓口にてDVを相談することが可能です。
「DV相談+」や「DV相談ナビ」ではどのような取り組みがありますか。
DV相談+は、DVの内容や相談者の性別や住居地にしばりはなく、24時間の電話相談のほか、メールやSNSチャットによる相談、WEB面談、外国語相談にも対応しています。相談先では、DVの専門家が対応し、被害者一人では対応しにくい場合(新居探しや警察・弁護士への相談など)に相談相手である専門家が一緒に付き添って援助する同行支援を行ったりしています。
DV相談ナビでは、発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓口に電話が自動転送され、そのまま転送先の相談窓口で話をすることができます。
配偶者暴力相談支援センターではどのような取組みがありますか。
配偶者暴力相談センターでは、DV防止及び被害者の保護を目的として、相談や相談機関の紹介、カウンセリング、被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護、自立して生活することを促進するための情報提供、被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助、保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助などに取り組んでいます。
最後に
DVの相談件数は増加傾向にあり、DVに悩む方はたくさんいます。しかし、相談したくてもどこに相談すればいいのかわからず一人で抱え込んでいたり、相談先でうまく話すことができるか不安で一歩を踏み出せない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
国や地方自治体を始めとして、現在はDV被害者を守るための多くの制度が確立されています。国や行政が指定した相談先は訓練を受けた専門家が紳士に対応してくれますし、匿名の相談も可能で、相談した内容は必ず秘匿されます。ですので、安心してまずは近くの相談先やDV相談+などに問い合わせてみてください。
また、DVから身の安全を守ることを最優先に、警察や弁護士への相談も積極的に考えてみてください。必ずあなたの力になることでしょう。
この記事を書いた人

雫田 雄太
弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。