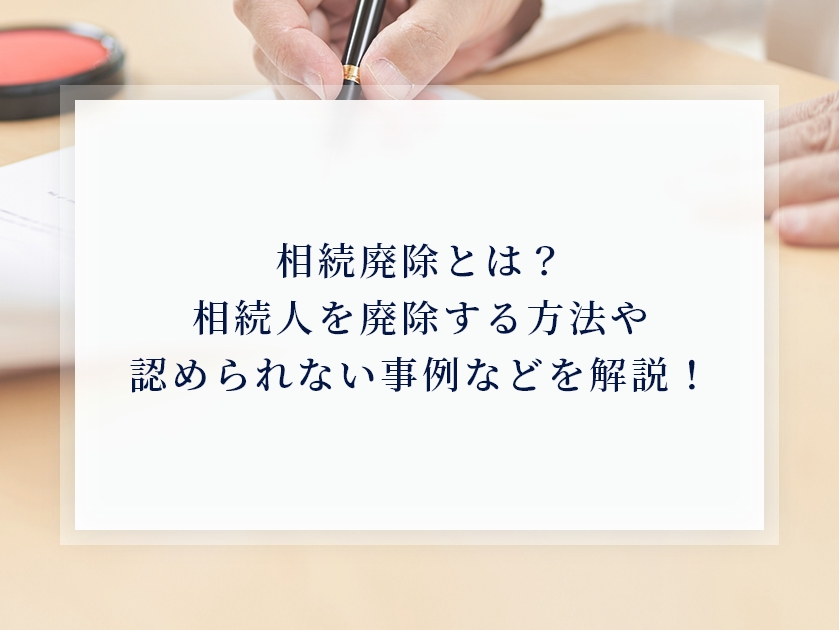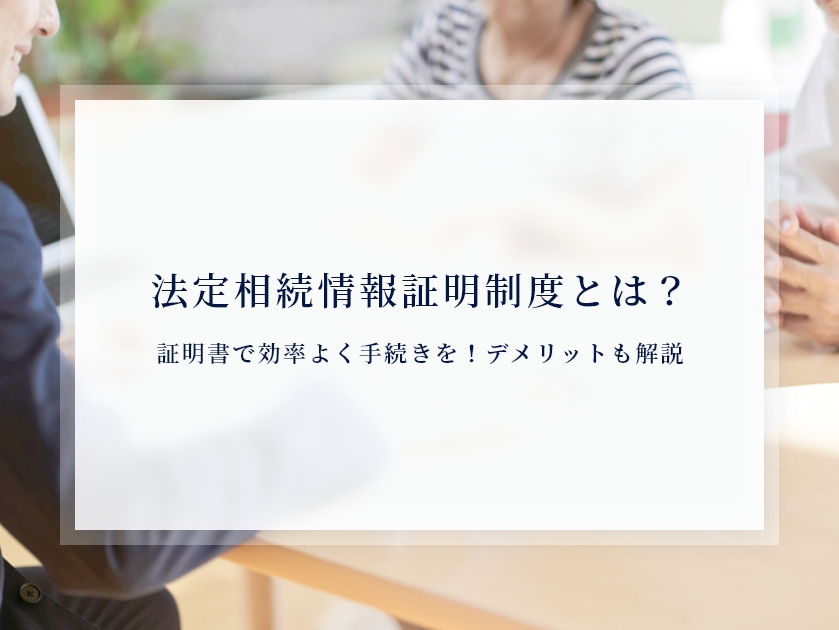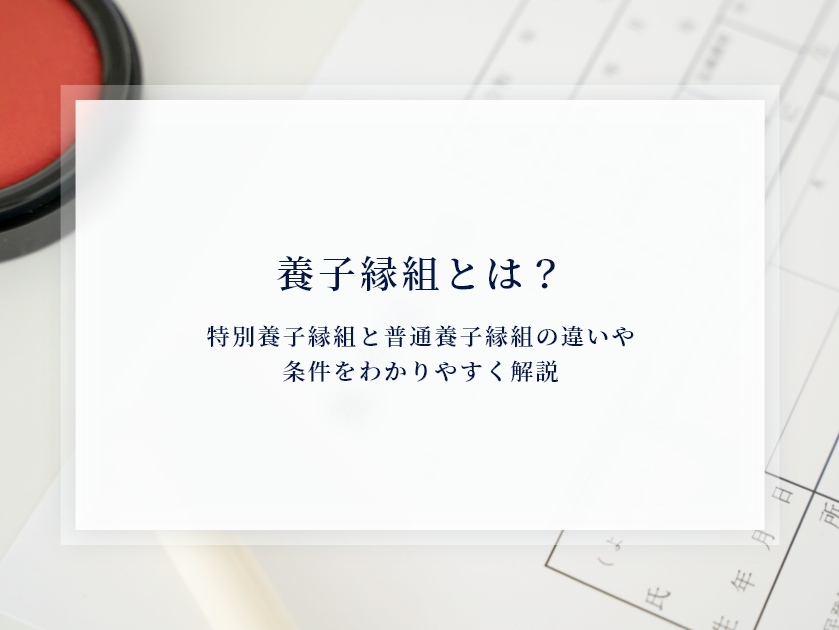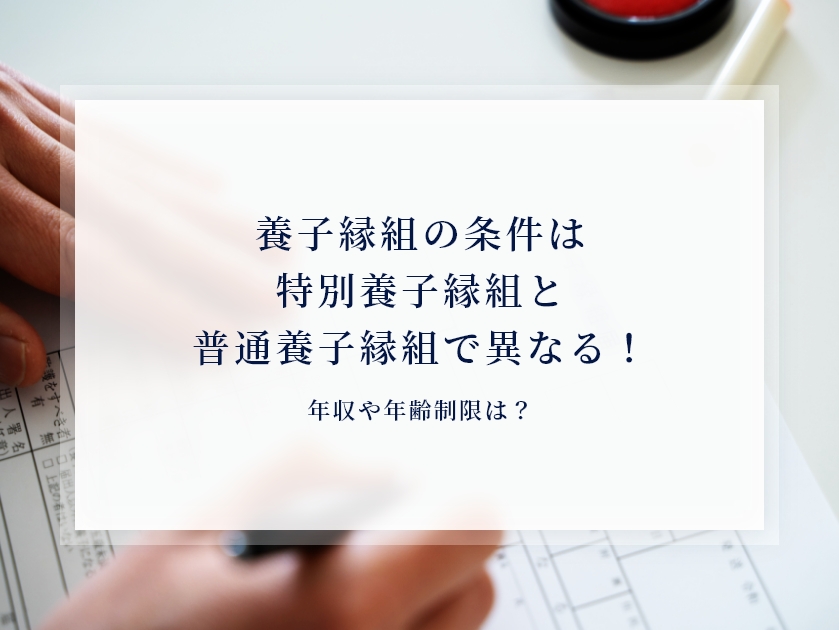推定相続人とは|推定相続人の範囲や確定させる方法、法定相続人との違いも解説
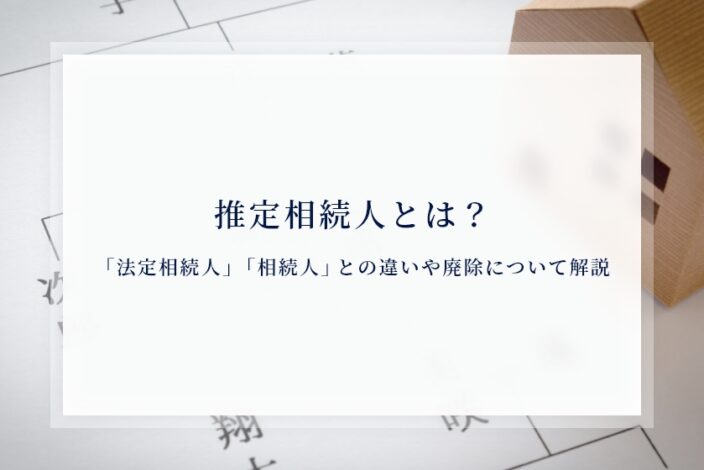
推定相続人という言葉をご存知でしょうか。もしかしたら、「相続人」には馴染みがあっても、「推定相続人」は聞いたことがない、という人が多いかもしれません。
推定相続人とは、まだ相続が発生していない現時点で、相続が発生した場合に遺産を受け取る可能性がある人を指します。とはいえ、「相続人」との違いなど、はっきりイメージしづらいかと思います。
そこで本記事では、推定相続人と法定相続人との違い、推定相続人の具体的な範囲や、推定相続人の確定方法について、弁護士が詳しく解説させていただきます。
遺産相続の手続きを進める上で、将来的に相続人となる可能性のある推定相続人が誰なのか、事前に把握しておくことは非常に重要です。推定相続人の範囲を正確に理解しておくことで、遺言を作成する際に誰にどれだけ遺産を残すかを適切に決められるほか、将来的に起こりかねない相続トラブルに備えておくことも可能です。
この記事で推定相続人とは何かを正確に把握し、役立てていただけますと幸いです。
目次
推定相続人とは
まずは推定相続人とはどういう人かについて、わかりやすく解説いたします。
1.推定相続人とは?わかりやすく解説
推定相続人とは、現時点で相続が発生した場合に、遺産を受け取る権利があると予測される人のことを指します。
例えば、Aさんという男性に妻のB子さん、子のCさん、亡くなった子Dの子供である孫Eさんがいたとしましょう。
この家族構成の場合、もしAさんが亡くなったら、誰が推定相続人になるのでしょうか。
まず推定相続人として考えられるのは、配偶者である妻B子さんです。被相続人の配偶者は常に相続人となるため、この場合も推定相続人になることが考えられます。
次に、子のCも推定相続人になります。被相続人の子供は、最優先で法定相続人になるからです。
孫のEさんについても、推定相続人になると考えられます。孫Eさんは、亡くなった子Dの代襲相続人としてAさんの遺産を相続する相続人になるため、推定相続人に当たるのです。
したがって、B子さん、Cさん、Eさんの3人がAさんの推定相続人となります。
なお、推定相続人とは、あくまで「現時点での予測」に基づくものであり、相続人として正式に確定したものではありません。
例えば、B子さんがAさんと離婚して配偶者ではなくなったり、夫であるAさんより先に死亡したりした場合は、B子さんは相続権を持たない立場になるため、推定相続人ではなくなります。
つまり、Aさんが存命中の間、推定相続人であるB子さん、Cさん、Dさんは「相続するはずの人」に過ぎないのです。
2.推定相続人と法定相続人との違い
さて、推定相続人ですが、似ている言葉に「法定相続人」という言葉があります。どちらも「相続人」とつくため混同されがちですが、明確に意味が異なるため、しっかり違いを把握しておきましょう。また、単に「相続人」という場合との違いについても確認しておきましょう。
「推定相続人」とは前述の通り、被相続人がまだ生存している状態で、現時点で相続が発生した場合に遺産を受け取ると予想される人を指します。つまり、被相続人がまだ亡くなっていない場合に使われる言葉であり、将来的な相続人を予測する概念です。
これに対して「法定相続人」とは、被相続人が亡くなり相続が実際に発生した時点で、法律に基づいて相続権を持つ人のことをいいます。被相続人が既に亡くなっている場合に使われる言葉であり、実際に相続が発生した時点で法律上の相続権を持つ人を指す言葉です。
そのため、推定相続人であっても、例えば以下のような場合には、実際に相続が始まったときに法定相続人になれない、ということもあり得るのです。
- 自分が被相続人より先に亡くなっていた場合
- 被相続人の配偶者であったが、被相続人の死亡前に離婚した場合
- 被相続人の養子であったが、養子縁組を解消した場合
- その他、特別な理由によって相続権を失った場合
なお、単に「相続人」と言うと、実際に相続が発生した際に、遺産を相続する権利を持つ人のことをいいます。
基本的には法定相続人が相続人となりますが、必ずしも「法定相続人=相続人」ではありません。
例えば、遺産相続を辞退した人や、家庭裁判所で相続放棄が認められた人は、相続開始の時点で法定相続人だったとしても、相続権を失うことによって、相続人ではなくなります。反対に、被相続人の愛人や親友といった本来は法定相続人でない人が、「不動産は親友の〇〇に相続させる。」などといった遺言によって相続人になることもあるのです。
推定相続人の確定
「実際に相続が始まらなければ相続人が確定しないのだから、推定相続人はどうでもよいのでは?」と思われるかもしれません。
ですが、誰が相続人になるのかを予想しておくことで、被相続人はより自分の意思を反映させた遺言書を作成したり、生前贈与を行ったりと、適切な準備を進められます。
将来の相続人としても、自分の他に誰が相続人になる可能性があるのか、その人とは遺産分割協議の話し合いをどのようにできそうか、見当をつけておくことができます。
スムーズに遺産相続手続きを進めるためにも、推定相続人が誰かを調査して確定させておくことは重要なのです。
1.自分で戸籍謄本から調べる
推定相続人を確定させる方法としては、被相続人の戸籍謄本を取得する方法が一般的です。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を入手することで、結婚や離婚歴、子供の有無などを把握し、推定相続人を確定させることができます。
まず、被相続人の現在の戸籍謄本を取得します。戸籍謄本は、被相続人の本籍地の市町村役場で、1通あたり450円で発行されます。窓口で直接受け取ることもできますが、本籍地が遠方の場合は郵送で請求することも可能です。
被相続人の本籍地が不明な場合は、最後の住所地の役場で住民票の除票を取得しましょう。住民票の除票は1通300円程度で、本籍地を確認するのに役立ちます。
次に、被相続人の出生まで遡って戸籍謄本を取得します。現在の戸籍謄本だけでは、被相続人の転籍や結婚後の情報しか分かりません。出生から現在までの連続した戸籍謄本を揃えることで、離婚歴の有無、前妻・前夫との間に子供がいるかどうか、養子や認知した非嫡出子がいるか、といった情報が明らかになります。
なお、2024年3月以降、戸籍証明書等の証明書を取得する手続きが大幅に簡便化されました。戸籍情報連携システムの導入により、全国の戸籍情報を最寄りの役所窓口で請求できるようになったのです(戸籍証明書等の広域交付制度)。
参考:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(法務省)
戸籍謄本、特に被相続人が高齢の場合、年代を遡るほど、判読が難しくなっていきます。形式自体も、現在の戸籍謄本類はコンピュータ化されて横書きですが、それ以前には縦書きで、手書きだった時代もありました。また、市町村合併などの影響もあり、現在は存在しない地名で表記されていて、さらに古い戸籍を辿るにはどこへ申請したらいいのか、分かりにくいことも少なくありません。
戸籍謄本類を集めるときには、時間に余裕を持って進めるようにしましょう。
2.専門家に調査を依頼する
被相続人が複数回の転籍や結婚・離婚を経験している場合には、全国各地の役場から戸籍謄本を取得する必要が生じます。大量の戸籍謄本を取得しなければならないとなると、自分で全ての戸籍謄本を申請するのは非常に手間ですし、時間もかかってしまいます。
全て取得し終えるのに数ヶ月から1年程度かかってしまうこともあるため、弁護士などの専門家に依頼するのがお勧めです。
専門家に依頼することで、迅速かつ確実に推定相続人を調査し確定することができます。
推定相続人の範囲
1.推定相続人の範囲【図解】
推定相続人の範囲について、図表をもとにより詳しく見ていきましょう。
前述の通り、推定相続人と法定相続人の違いは、相続が発生する時点における呼び名の違いに過ぎません。そのため、推定相続人の範囲と順位は、法定相続人と同じです。
そんな推定相続人の範囲と順位を図表にまとめますと、以下の通りになります。
|
順位 |
推定相続人の範囲 |
説明 |
|---|---|---|
|
常に相続人 |
配偶者 |
配偶者は常に推定相続人となり、その他の順位の相続人とともに相続権を持つことが法的に定められています。 |
|
第一順位 |
被相続人の子(養子を含む) |
被相続人の子が亡くなっている場合、その子供である孫が推定相続人となります。 |
|
第二順位 |
被相続人の父母または祖父母 |
被相続人の父母が既に亡くなっている場合は、祖父母が推定相続人としての権利を引き継ぎます。 |
|
第三順位 |
被相続人の兄弟姉妹 |
被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子供である甥や姪が推定相続人の地位を持つことになります。 |
2.推定相続人にならない6つのケース
さて、上の図表が推定相続人の範囲となりますが、推定相続人が必ず相続開始時点で相続権を有するとは限りません。推定相続人の範囲に該当しつつも、事情や状況の変動によって、推定相続人ではなくなってしまうケースもあるのです。
以下では、具体的に推定相続人にならない6つのケースをご紹介いたします。
2-1.遺言書を作成していた場合
被相続人が生前に遺言書を作成していた場合、その内容が推定相続人の続柄よりも優先されるため、遺言の内容によっては推定相続人ではなくなってしまうことがあります。
例えば、遺言書において推定相続人以外の人物を指名し、その者にすべての財産を遺贈する旨が記載されている場合、推定相続人は基本的に相続できません。
こうした場合、推定相続人の相続権が完全に消滅してしまうように思えますが、いくつかの例外もあります。
最も代表的な例外が、遺留分です。遺留分とは、法律で保護された一定の相続人に対して最低限の遺産を確保するための割合のことです。兄弟姉妹以外の推定相続人には、遺留分を請求する権利が認められています(民法第1042条1項)。
(遺留分の帰属及びその割合)
民法第1042条1項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
そのため、推定相続人は全く遺産を受け取れないということはなく、遺留分を請求すれば、法律によって認められている最低限の取り分を確保できるのです。
もっと具体的に考えてみましょう。
Aさんが被相続人で、B子さんがAさんの推定相続人であるとします。Aさんが生前、「友人Cさんに全財産を遺贈する」という内容の遺言書を作成していました。この場合でも、推定相続人であるB子さんは、遺言書の内容によって侵害された自身の遺留分をCさんに対して請求することができるのです。
ただし、この遺留分の権利は兄弟姉妹には適用されないため、推定相続人のBさんがAさんの兄弟姉妹であった場合は、遺言書の内容が優先され、Cに遺留分を請求することができません。
2-2.相続開始前に離婚した場合
配偶者は通常、法定相続人として常に相続権を持つため、推定相続人に含まれます。しかし、離婚が成立すると、もはや配偶者ではなくなるため、相手の遺産についての相続権を失うことになります。その結果、相続開始前に離婚した元配偶者は、離婚した時点で推定相続人ではなくなります。
2-3.被相続人よりも先に死亡した場合
推定相続人が被相続人よりも先に亡くなった場合、その推定相続人は相続権を失います。これは、相続が発生する前に、推定相続人が存在しなくなるためです。
例えば、Aさんが被相続人であり、その推定相続人が子のBさんであるとします。もしBさんがAさんより先に亡くなった場合、BさんはAさんの遺産を相続することはできません。
ただし、この場合でもBさんの持つはずだった相続権が完全に消滅するわけではありません。Bさんに子供がいる場合は、その子供がBさんに代わってAさんの遺産を相続することになります(代襲相続)。
2-4.相続欠格者の場合
「相続欠格」の場合も、推定相続人が相続する権利を失うことになります(民法第891条)。
相続欠格とは、推定相続人が重大な非行を犯した場合に、その人の相続権がはく奪される制度です。相続欠格は被相続人の意思に関係なく適用される上に、遺留分の請求権も失われます。
具体的な相続欠格の自由としては、民法第891条の各号に、次の通り定められています。
- 被相続人や他の相続人を殺害した、または殺害しようとして刑に処せられた場合
- 被相続人が殺害されたのを知りながら告発しなかった場合
- 被相続人を騙したり脅迫したりして、遺言書を書き換えさせたり撤回させたりした場合
- 被相続人が遺言書を書き換え・撤回しようとしているのを妨害した場合
- 遺言書を偽造したり勝手に書き換えたりした場合
相続欠格が適用されると、その推定相続人は相続権を失いますが、相続欠格は代襲相続に影響しません。つまり、相続欠格者に子供がいる場合、その子供が繰り上がって相続人となります。
2-5.相続廃除者の場合
「相続廃除」については後述いたしますが、この場合も、推定相続人は遺産相続する権利を失うことになります(民法第892条)。
ただし、相続廃除によって推定相続人から除外されたとしても、廃除されるのはその本人だけです。つまり、相続廃除された相続人に子がいる場合、その子が相続権を代襲して引き継ぐことになります。
2-6.再婚相手の連れ子や非摘出子
再婚相手の連れ子は血族ではないため、家族同然の関係であっても、法的には推定相続人にはなりません。法的な血族関係がないため、再婚相手の連れ子は再婚相手の遺産を相続する権利を持たないからです。
ですが、連れ子でも養子縁組をすると、法律上の血族となるため、養親の推定相続人になります。具体的には、養親が亡くなった場合、養子は第1順位の法定相続人として認められ、実子と同じ相続権を主張することができるのです。
また、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を非嫡出子といいますが、非嫡出子は父親が認知しているかどうかによって、推定相続人になる場合とならない場合があります。
認知されていれば非嫡出子も父親の推定相続人となり、相続権を持ちます。しかし、父親が認知していない非嫡出子は、父親との法的な親子関係が成立していないため、推定相続人にはなりません。
血縁関係があっても、法的に認知されていなければ、相続権を持たないという点に注意しましょう。
3.推定相続人に相続させたくない場合
さて、上記の「推定相続人にならない6つのケース」において触れましたが、推定相続人に遺産を相続させたくない場合、「相続廃除」をすることによって、推定相続人を除外することができます。
相続廃除の方法ですが、遺言で廃除の意思を表示しておく方法(遺言廃除)と、被相続人が生前に家庭裁判所に申立てを行う方法(生前廃除)の2つがあります。
2-1.推定相続人の遺言廃除
遺言廃除は、被相続人が遺言で特定の推定相続人を廃除する意思を示す方法です。この場合、被相続人が亡くなった後に、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の申立てを行います。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人物で、被相続人の意思を尊重して相続廃除の手続きを進めます。
遺言廃除の申立てをすると、家庭裁判所が申立ての内容を審査し、廃除を認めるかどうかを判断します。遺言書に廃除の意思について明確に示されていても、家庭裁判所がその理由を「廃除を認めるのに十分なもの」と判断しなければ、廃除は成立しません。
2-2.推定相続人の生前廃除
生前廃除とは、被相続人が生前に家庭裁判所に対して特定の推定相続人を廃除する請求を行う手続きです。
生前廃除の対象となる推定相続人は、遺留分を有する推定相続人とされています(民法第892条)。
(推定相続人の廃除)
民法第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
遺留分とは、法律で保障されている、一定の相続人が最低限取得できる遺産の割合のことです。遺留分を有する推定相続人には、被相続人の配偶者、子供(養子を含む)、直系尊属(父母や祖父母など)が含まれますが、兄弟姉妹は遺留分を持たないため、相続廃除の対象にはなりません(民法第1042条1項)。
推定相続人の生前廃除が認められるためには、民法第892条に定められたいずれかの事由に当てはまる必要があります。
- 被相続人に対する虐待があった
身体的な暴力だけでなく、精神的な虐待も含まれます。 - 被相続人への重大な侮辱行為があった
被相続人の尊厳を著しく損なう行為や言動を指します。 - その他の著しい非行があった
被相続人の財産を不正に処分する行為や、被相続人の生活を著しく困難にするような行為が該当します。
生前廃除は、家庭裁判所に申立てを行い、審判が確定した後、市区町村に廃除届を提出することで正式に効力が発生します。
相続廃除については、こちらの関連記事で詳しく解説しておりますので、本記事と合わせてぜひご一読ください。
以上のような廃除の手続きを終えると、廃除された相続人はその相続権を失い、代わりに他の相続人がその分を受け取ることになります。相続権を失うため、遺留分を請求する権利も失われます。
推定相続人に関するQ&A
Q1.推定相続人とは誰ですか?
A:推定相続人とは、現時点である人が亡くなったと仮定した場合に、その人の財産を相続することが予想される人を指します。例えば、家族構成が父親、母親、長男、長女の場合に父親が亡くなったと仮定すると、母親、長男、長女の3人が推定相続人となります。
Q2.推定相続人と法定相続人との違いは何ですか?
A:法定相続人とは、実際に相続が発生した際に、民法に基づいて相続する権利を有する人を指します。推定相続人と法定相続人は基本的には同じ意味ですが、相続が発生するまでの間に家族構成が変わらなければ、「推定相続人=法定相続人」となります。
なお、相続発生前に結婚、離婚、養子縁組、死亡などで家族構成が変わった場合、推定相続人が変わる可能性があります。また、相続欠格や相続廃除に該当する場合は、推定相続人でも法定相続人にはなりません。
Q3.推定相続人を確定させるにはどうしたら良いですか?
A:推定相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を調査し、法定相続人が誰であるかを確認する必要があります。これにより、被相続人の配偶者や子供、親、兄弟姉妹など、相続権を持つ人の範囲を明らかにすることができます。
まとめ
本記事では、推定相続人について弁護士がわかりやすく解説させていただきました。
法定相続人や相続人との違いや、推定相続人になる人の範囲がどこまでなのか、といった基本的な知識に加え、推定相続人が相続権を失うケースについても詳しくご紹介いたしました。
遺産相続では、さまざまな立場の人が相続人として関係してくるため、推定相続人についての正しい知識を備えておくことが非常に重要です。
相続に関する正しい知識を持つことは、遺産分配を円滑に進めるだけでなく、無用なトラブルを防ぐためにも大切です。
また、推定相続人について確認しておくことで、遺言書の作成や相続廃除といった対応を事前に検討できるため、スムーズな遺産分割が期待できるでしょう。
早めの準備と理解が、安心して相続手続きを進めるための第一歩となりますので、ぜひ積極的に情報を収集し、必要に応じて専門家の力を借りていただければと思います。
弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。お電話によるご相談もお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。