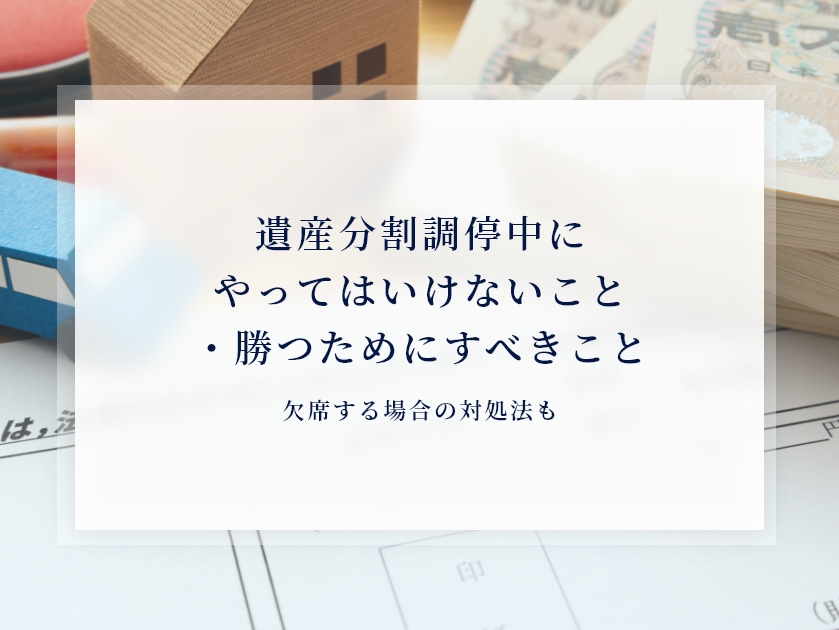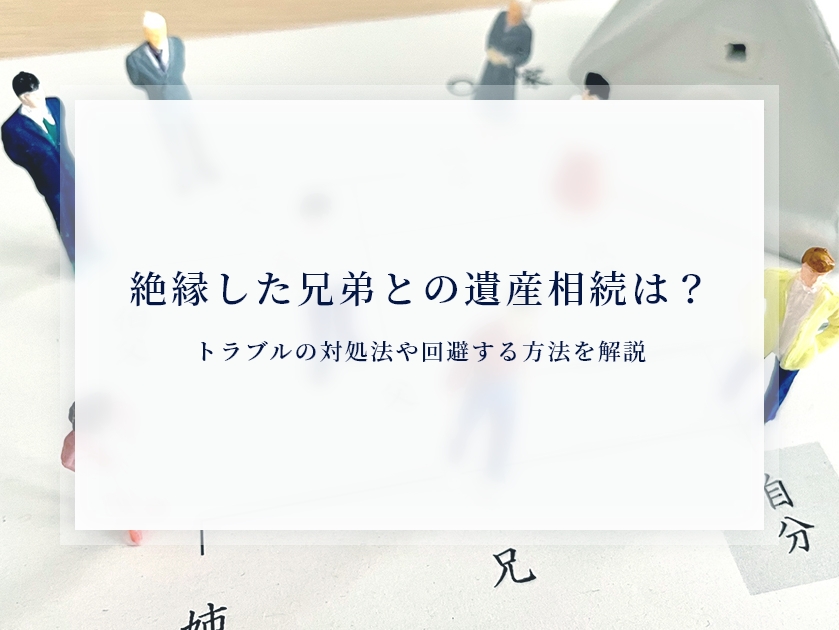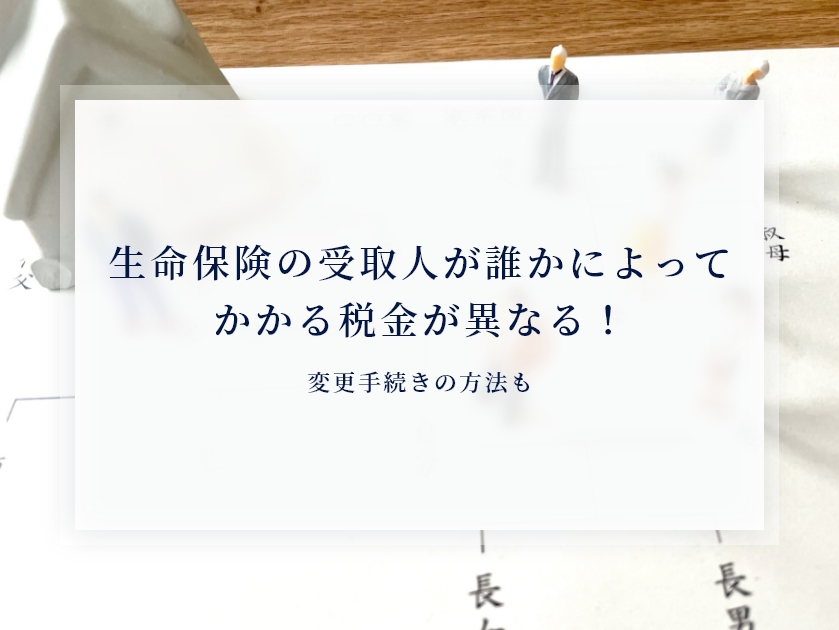遺産分割協議書の割印|割印・契印を押す場所や失敗した場合の押し直し方
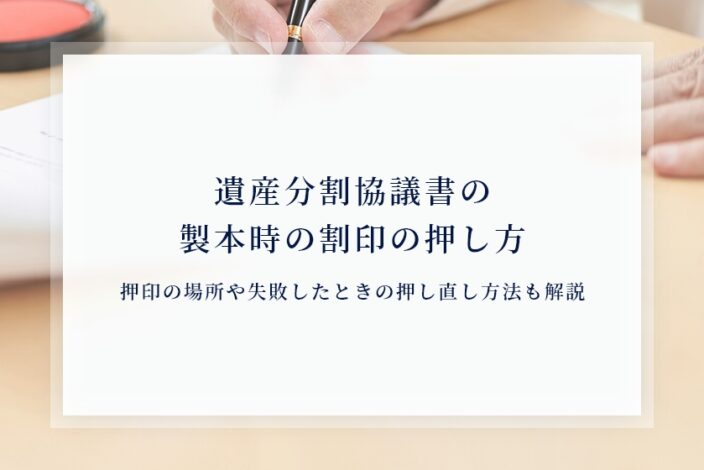
遺産分割協議書は、相続人や相続財産が多ければ多いほど、記載事項も増えていきます。そうなると、必然的に遺産分割協議書のページは2枚、3枚と増えていきますし、相続人の数の分、作る部数も増えるものです。
遺産分割協議書の部数や枚数が複数になる場合、割印や契印が必要なのか、どう押したらいいのか迷われる方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、遺産分割協議書に割印や契印が必要なのか、どの印鑑でどのように押したらいいのか、弁護士が詳しく解説させていただきます。
また、押印に失敗した場合の押し直し方や、遺産分割協議書が複数ページになったときの綴じ方についても、具体的にご説明いたします。
ご自身で遺産分割協議書を作成される際に、本記事を少しでもご参考にしていただけましたら幸いです。
目次
遺産分割協議書と割印
1.遺産分割協議書に割印は不要?
相続人が複数人いる場合、通常は各自が1部ずつ遺産分割協議書を保管することになります。そのため、人数に応じて、複数部作ることが一般的です。
割印・契印とは
ところで、一般的に、当事者がそれぞれ保管する複数通の契約書がある場合などには、「割印」が押されます。
割印とは、2つの契約書にまたがって押される印鑑のことです。押印した契約書を離したときに印影が割れることから、「割印」と呼ばれます。割印があることで、複数の文書が同一のものであることを証明できるのです。
割印と似たものに「契印」がありますが、こちらは1つの文書が複数枚に渡る場合に、それらが一体の文書であることを示すために押す印のことです。各ページの見開きの綴じ目や、製本テープと用紙にまたがって押印することで、改ざんを防ぐ効果があります。
割印と契印は混同されがちなのですが、このように明確な違いがあるため、注意してください。遺産分割協議書を2部以上作るときが「割印」、ページが2枚以上になるときに「契印」と覚えておきましょう。
法律上も、例えば商業登記規則第35条3項や不動産登記規則第46条1項に「申請書が二枚以上のときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない」旨を定めており、割印と契印を区別しています。
ところで、遺産分割協議書を複数作る場合、割印や契印は必須なのでしょうか。
結論としては、遺産分割協議書の割印・契印は任意とされているため、必須ではありません。
割印や契印が押されていなくても、遺産分割協議書が無効になることはありませんし、銀行などでの相続手続きができなくなってしまうこともありません。
契印・割印なしの遺産分割協議書でも登記できる
実際に、相続登記の手続きなどでも、割印や契印のない遺産分割協議書で、問題なく手続きをすることができます。
遺産分割協議書の割印や契印がなくても、相続人全員が合意していることの証明は可能であるからです。
相続登記の際に重要なのは、遺産分割協議書が真正に作成されたかどうか、という点です。そして、真正に作成されたことの証明は、相続人全員の署名、実印による押印と、印鑑証明書の添付によってなされます。
そのため、割印・契印がないからといって、相続登記で遺産分割協議書が使えなくなることはありません。
2.遺産分割協議書に割印が必要な理由
ですが、どうしても押印できないというような理由のない限り、割印を押しておくことが推奨されます。というのも、遺産分割協議書が複数ある場合に割印を押印する目的は、複数作成された文書の同一性を証明することにあるからです。
複数ある遺産分割協議書にまたがるように割印が押されていることによって、同一の機会に作成された同一の内容であることを保証することができます。
また、契印に関しても、押印しておくことが推奨されます。
前述の通り、契印には1つの文書が複数枚に渡る場合に、それらが一体の文書であることを示し、ページの差し替えや抜き取りなどの改ざんを防ぐ効果があります。
遺産分割協議書に割印と契印があることで、複数ある遺産分割協議書の内容が全て同じものであることを保証し、改ざんを防止することができるのです。
なお、割印や契印を含め、すべて実印で押印されていなければ、遺産分割協議書の法的な効力が認められず、無効となってしまうケースもあります。後の無用なトラブルを防止するという観点からも、遺産分割協議書を複数部作成する場合は、割印を押印しておくと良いでしょう。
3.割印を押す場所
遺産分割協議書の割印を押す場所に関してですが、明確な決まりはありません。左右の位置や、押す順番なども自由です。
一般的には、遺産分割協議書の上部に割印を押印します。
4.割印の押し方
割印の押し方は、以下の通りです。
- 作成した複数の遺産分割協議書を、縦か横に少しずつずらし重ねて置く。
- すべての遺産分割協議書にまたがるように、相続人全員が押印する。
- 遺産分割協議書のそれぞれの末尾に、相続人3全員の印鑑登録証明書を添付する。
遺産分割協議書が3通、4通以上ある場合も、基本的な割印の押し方は変わりません。
5.遺産分割協議書の割印は実印で
遺産分割協議書の割印に使う印鑑は認印か実印か、迷う方もいらっしゃるかと思います。
認印とは、役所などで印鑑登録していない、日常的に使われる印鑑のことです。一方、実印とは、市区町村役場で印鑑登録した、公的に認められている印鑑を意味します。
ここで一度、遺産分割協議書に必要な「押印」を整理しておきましょう。
遺産分割協議書では、相続人全員が話し合って合意したことを示すための署名押印、複数部作成した場合の割印、複数ページにまたがる場合の契印という、3つの「押印」があります。
まず、遺産分割協議書の署名押印で使用する印鑑に関しては、法律上の決まりがないため、実印である必要はありません。認印で署名押印した遺産分割協議書も有効です。
ですが、遺産分割協議書の署名押印の印鑑は、実印を使用していただければと思います。
というのも、遺産分割協議書は、「遺産分割協議の内容に同意したのが、間違いなく相続人本人であること」が非常に重要となるからです。
不動産の相続登記の手続きや、被相続人名義の預貯金口座の解約・払い戻しの手続き、相続税の申告手続きにおいては、相続人全員の実印が押された遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書の提出が求められることが一般的です。認印を使用したとしても、遺産分割協議書自体の効力に影響はありません。ですが、相続手続きがスムーズに進まないおそれがあるため、遺産分割協議書の署名押印には実印を使うことをお勧めいたします。
そして、署名押印に実印を使うとなれば、割印に関しても実印を使用するのが自然と言えるでしょう。
もちろん、割印に使用する印鑑は、必ずしも遺産分割協議書の署名捺印の際に使用した実印である必要はありません。ですが、わざわざ割印だけ他の印鑑を使用することはありませんので、署名押印と同じ実印を使用して割印を押すのが一般的です。
6.遺産分割協議書と印鑑証明書の綴じ方
前述の通り、遺産分割協議書には、押印されている印鑑が実印であることを証明するために、印鑑証明書(印鑑登録証明書)を必ず添付しましょう。
「添付」は「書類などに付け添える」ことを意味します。綴ることや貼ることまでは意味しませんので、印鑑証明書を遺産分割協議書と一緒に綴じる必要まではありません。
実印の登録をしていない相続人がいる場合は、その相続人の住所地を管轄する役所において、本人が印鑑登録手続きをする必要があります。15歳未満の未成年者の場合は印鑑登録ができませんので、その場合は特別代理人を選任する必要があります。
遺産分割協議書と契印
続いて、契印について見ていきましょう。
2枚以上の書類が1つの連続した文書であることを証明するために、契印が重要です。
1.遺産分割協議書の製本の仕方と契印の押し方
契印の押し方ですが、遺産分割協議書ページ数によって、そもそもの製本の仕方も変わってきます。製本の仕方によって契印の押し方も異なるため、あわせて確認しておきましょう。
1-1.ページ2~3枚程度ならホッチキスで綴じる
遺産分割協議書の枚数が少なく、2~3枚程度であるときには、以下の方法で製本します。
- 横書きなら左側(縦書きなら右側)をホッチキスで綴じる。
- 全てのページの見開きの部分に、左右の両ページにまたがるように、相続人全員が実印で契印を押す。
- 契印を押した遺産分割協議書を相続人の人数分製本し、割印を押す。
そして、遺産分割協議書の左右両ページにまたがるように、すべてのページのつなぎ目に、相続人全員が実印で契印を押します。
1-2.ページ数が多い場合は袋とじ
遺産分割協議書の枚数が多いときには、すべてのページの見開きに契印を押印するのは手間のかかる作業です。ですので、製本テープを使用して「袋とじ」にする方法をお勧めいたします。
製本テープを使用して袋とじにする場合、以下のように製本します。
- 横書きなら左側、縦書きなら右側をホチキスで綴じる。
- ホチキスで綴じた部分に製本テープを貼る。
- 遺産分割協議書の紙面と製本テープにまたがるように、表表紙と裏表紙の両方に相続人全員が実印で契印を押す。
- 相続人の人数分、同じように契印を押した遺産分割協議書を製本し、割印を押す。
製本テープを使用して袋とじにした場合は、遺産分割協議書の紙面と製本テープにまたがるように、表表紙と裏表紙の両方に実印で契印を押します。こうすることで、各ページの見開きの部分に契印を押す必要はなくなります。
なお、製本テープは押印することを考えて、白いものを選びましょう。光沢があるとインクが定着しづらいため、表面がマットなものがお勧めです。
2.A3用紙で作ると契印が不要な場合も
遺産分割協議書はA4サイズの用紙で作成されることが一般的ですが、実は用紙のサイズに決まりはないため、A4サイズでなくても問題はありません。
A4用紙2枚だと契印が必要になってしまう場合でも、A3用紙1枚に収まるのであれば契印が省略できるので、A3サイズで作成されてみてはいかがでしょうか。
遺産分割協議書の印鑑の押し直し方
割印がずれてしまったり、滲んでしまったりして押印に失敗した場合、どのように押し直したら良いのでしょうか。
1.割印に失敗した場合
遺産分割協議書の割印を押し直す方法は、以下の見本画像の通りです。
- 失敗した印影の一部に被せるように、訂正印として実印で押印する。
- 訂正印のすぐ近くに、新たに実印で割印を押し直す。
なお、失敗した割印を二重線で消して、隣に押印し直す方法は、遺産分割協議書では控えるのが無難です。
二重線で消す方法の場合、さらに二重線で消されて異なる印鑑を押されてしまうリスクがあるためです。
2.契印に失敗した場合
遺産分割協議書の契印を失敗したときも、少しずらして実印で訂正印を押し、その隣に新たに実印で押し直しましょう。
押印に何度も失敗してしまうと、遺産分割協議書が見づらくなってしまいます。その場合は、改めて遺産分割協議書を作り直した方が良いでしょう。
遺産分割協議書の割印に関するQ&A
Q1.遺産分割協議書の押印に使用する印鑑は実印ですか?
A:遺産分割協議書の押印に使用する印鑑は実印と決まっていません。
認印が使用されたとしても遺産分割協議書としての効力を失うわけではありませんが、認印を使用した場合、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなどの相続の手続きがスムーズに進まない恐れがあります。ですので、実印での押印をお勧めいたします。
Q2.遺産分割協議書の割印の押し方は?
A:割印の位置や押す順番などに法律的な指定はありませんが、一般的には、遺産分割協議書の上の部分に押印します。
遺産分割協議書の割印の押し方は、以下の通りです。
- 作成した複数の遺産分割協議書を縦や横に少しずつずらして重ねて置く。
- すべての遺産分割協議書にまたがるように、相続人全員が実印で押印する。
Q3.遺産分割協議書の割印に失敗したときの押し直し方は?
A:遺産分割協議書の割印を失敗したときに押し直す方法は、下記の通りです。
- 失敗した印影の一部に被せるように、訂正印として実印で押印する。
- 訂正印のすぐ近くに、新たに実印で割印を押し直す。
まとめ
遺産分割協議で相続人全員が合意したとしても、その内容を有効な遺産分割協議書にまとめなければ意味がありません。
遺産分割協議書には、必ず相続人全員の署名と、実印の押印が必要となります。また、遺産分割協議書には、押印された印鑑が実印であることを証明する印鑑証明書の添付も必要です。
そして、遺産分割協議書の原本を複数部作成する場合は、それぞれの遺産分割協議書の内容が同一であることを証明するために「割印」が推奨されます。
また、遺産分割協議書が複数枚となった場合は、ページの抜き差しが行われていないことを証明するために「契印」を押印しましょう。
遺産分割協議書に割印や契印がない場合でも、法務局や金融機関などで手続きをすることは可能です。ですが、相続人同士や提出先との無用なトラブルを防ぐためにも、割印と契印を押印しておくことをおすすめします。
弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。当ホームページのWeb予約フォームやお電話にて、お気軽にお問合せください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。