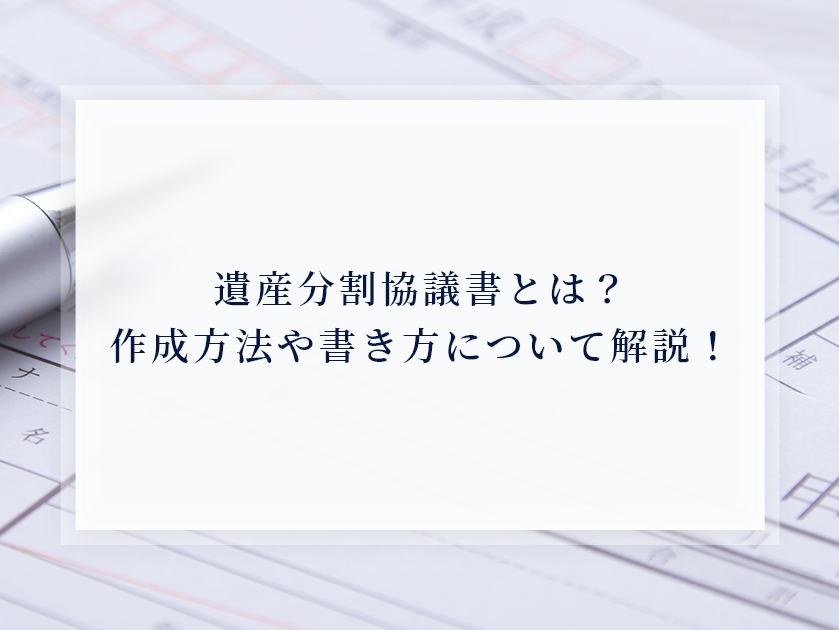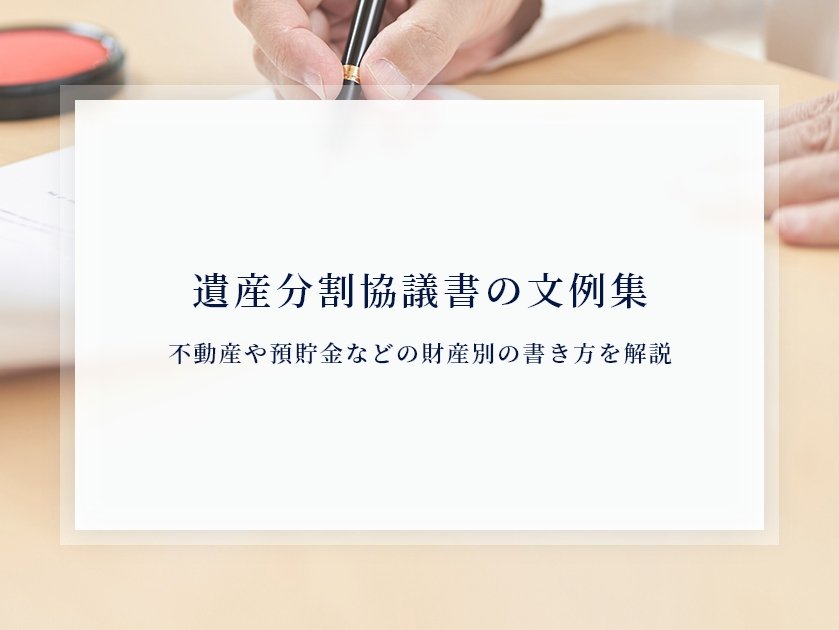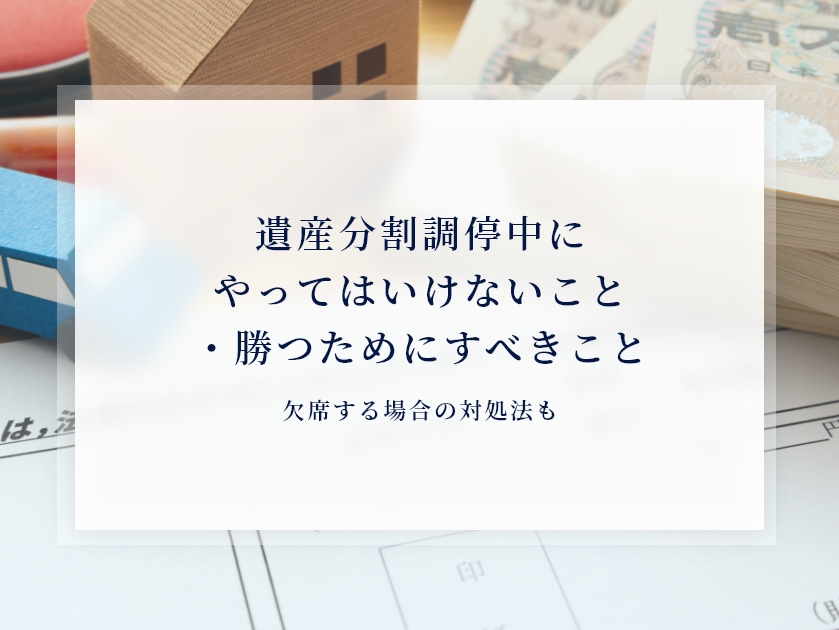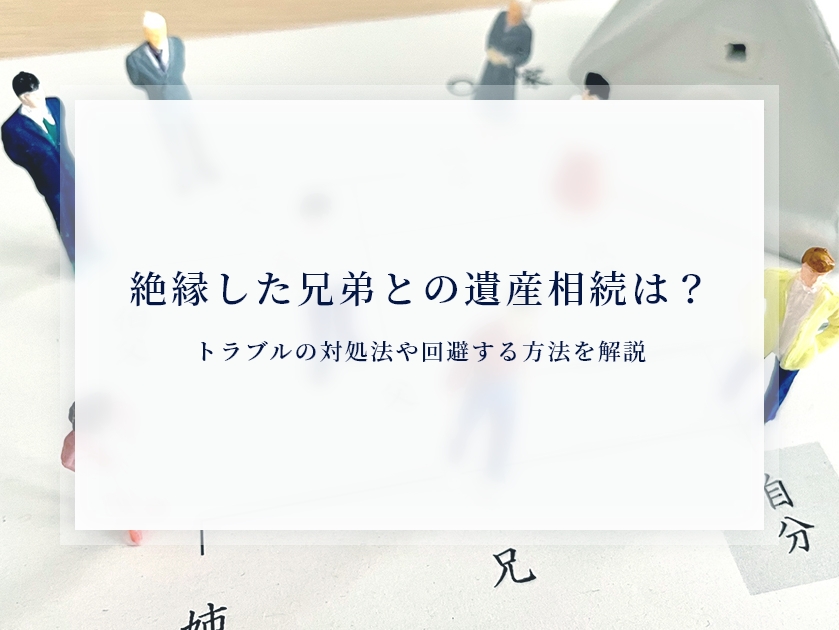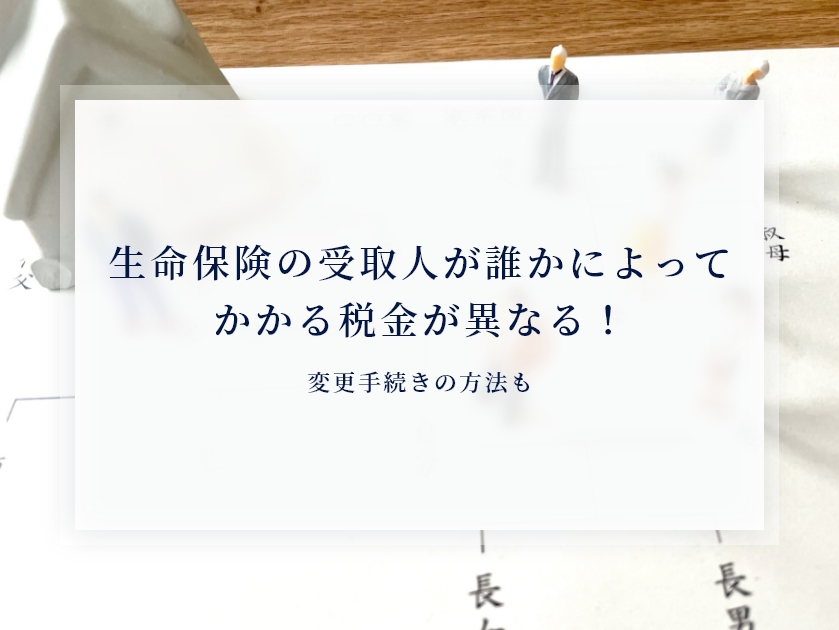遺産分割協議書のひな形|書式テンプレートを無料でダウンロード
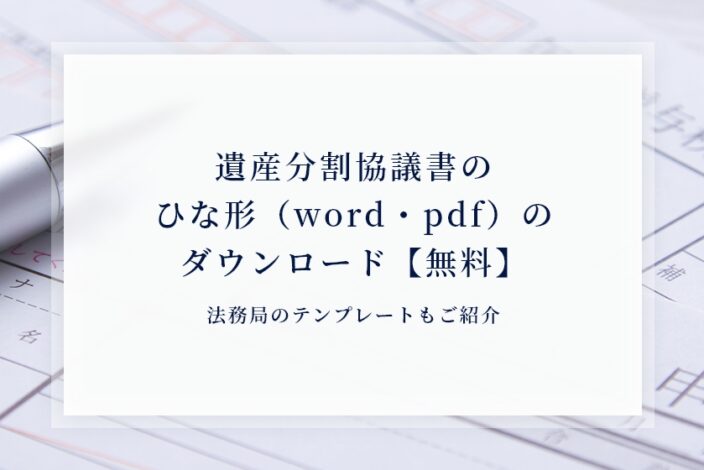
遺産分割協議書を作ろうとなったとき、白紙の状態から作成するのはなかなか大変なことと思います。
そこで本記事では、無料でダウンロードしていただける、遺産分割協議書のひな形・テンプレートをご紹介いたします。
法定相続分によって相続する標準的な場合のほか、一人の相続人が全て相続する場合や、代償分割や換価分割がある場合のひな形もご用意いたしました。
word形式とPDF形式がありますので、遺産分割協議書の作成の際には、本記事をぜひご参考にしていただければと思います。
目次
遺産分割協議書のひな形
それではさっそく、遺産分割協議書のひな形を確認していきましょう。なお、個別のケースにおいては、具体的な書き方のポイントなどもご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
1.遺産分割協議書のテンプレート書式
まずは、標準的な遺産分割協議書のテンプレートをご紹介します。
このテンプレートでは、一般的な例として、相続人3名をそれぞれA、B、Cとし、Aが土地、建物を相続し、Bが預貯金、Cが株式を相続するケースを想定しています。
遺産分割協議書
被 相 続 人 ○○○○
本 籍 ○○○県○○○市○○○町○丁目○番
最後の住所 ○○○県○○○市○○○町○丁目○番○号
生年月日 昭和○年○○月○○日
死亡年月日 令和○年○○月○○日
被相続人○○○○の遺産につき相続人全員で協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。
1.相続人Aは、次の遺産を取得する。
【土地】
所 在 ○○県○○市○○○丁目
地 番 ○○番○○
地 目 宅地
地 積 ○○○.○○平方メートル
【建物】
所 在 ○○県○○市○○○丁目○○番地○
家屋番号 ○○番○
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 ○○.○○平方メートル
2階 ○○.○○平方メートル
2.相続人Bは、次の遺産を取得する。
【預貯金】
○○銀行○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
○○銀行○支店 定期預金 口座番号○○○○○○○
3.相続人Cは、次の遺産を取得する。
【株式】
○○○○株式会社 普通株式 ○○○株
4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人間においてその分割につき別途協議する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を3通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。
令和○年○○月○○日
【相続人Aの署名押印】
住所 ○○県○○市○丁目○番○号
氏名 ㊞
【相続人Bの署名押印】
住所 ×県××市×丁目××番×号
氏名 ㊞
【相続人Cの署名押印】
住所 △△県△市△丁目△番△△号
氏名 ㊞
2.遺産分割協議書のひな形(word・PDF)
また、以下の通り、Word形式とPDF形式のひな形をご用意いたしました。それぞれ無料でダウンロードが可能ですので、ご自身で作成する際の参考例としてご活用ください。
なお、個別のケースによって最適な遺産分割協議書の内容や形式は異なりますので、本記事でご紹介するひな形はあくまで目安となります。
遺産分割協議書(word)
遺産分割協議書(PDF)
エクセルのひな形は不向き
パソコンなどで書類を作成する場合、wordやPDFといったファイル形式のほかに、エクセルも一般的ですが、当事務所ではエクセル形式のひな形はご用意しておりません。
一般的に、Wordは文書を作成するのに適したファイル形式ですが、エクセルは表計算といったデータの集計や分析に適したファイル形式なので、遺産分割協議書を作成するときにエクセル形式は不向きです。
3.遺産分割協議書の表紙
遺産分割協議書の表紙について、法令上の定めは特にありませんので、作成する必要はありません。
ですが、表紙をつけることで次のようなメリットもあります。
- 表紙に水などが掛かって濡れてしまっても、中身の汚損を防止できる。
- 表紙があれば、表紙をめくらないと中身を見られないので、無関係の人に内容を見られてしまうリスクを減らせる。
- 重要な書類に相応しい見た目になる。
また、ページ数が多くなる場合には、ホッチキスではなく製本テープで綴じるため、表紙をつけることもあるようです。
以下の通り、遺産分割協議書の表紙のひな形もご用意いたしました。
遺産分割協議書の書式【無料ダウンロード】
次に、ケース別の遺産分割協議書のひな形をご紹介します。
1.一人が全て相続する場合の遺産分割協議のひな形
まずは、相続人の一人が全て相続する場合の遺産分割協議書のひな形をご紹介します。
具体例として、相続人3人(甲、乙、丙)のうち、甲が全ての遺産を取得するようなケースです。
一人が全て相続する場合
ひな形(word)・ひな形(PDF)
さて、相続人の一人が全て相続する場合は、遺産分割協議書を作成する際に、以下の3つのポイントに特に気を付けていただければと思います。
- 相続財産の内容を具体的に記載する。
- ほかに相続財産が見つかった場合に備えた文言を記載する。
- 全員分の署名押印が必要。
どの相続人がどの遺産を相続したのか客観的に分かるように、相続財産の内容を具体的に記載しましょう。一つ一つの相続財産が、通帳や登記事項証明書などに記載されている内容と間違いがないように記載することも重要です。
また、遺産分割協議をする時点で、全ての遺産を相続人が把握できているとは限りません。遺産分割協議が終わった後に新たに遺産が見つかることもあります。このような場合に備えて、改めて遺産分割協議をするのか、あらかじめ特定の相続人が相続するのかなどを決めておくことも可能です。
そして、相続人の一人が全て相続する場合であっても、遺産分割協議書には、相続人全員分の署名押印が必要になります。相続人全員分の署名押印があれば、遺産分割協議の内容について相続人全員が合意したという証拠になるからです。
ただし、他の相続人が全員相続放棄した場合には、相続人は最初から残った一人だけだった、ということになりますので、そもそも遺産分割協議を行う必要がなくなります。この場合は、遺産分割協議書を作成する必要もありません。
2.預金のみの場合の遺産分割協議書のひな形
次に、相続財産が預貯金のみの場合の遺産分割協議書のひな形をご紹介します。
具体的なケースとして、以下では、「相続財産が預金のみで、相続人の1人が相続するケース」と、「相続財産が預金のみで、複数の相続人で相続するケース」にひな形を分けて掲載しています。
相続財産が預金のみで、相続人の1人が相続する場合
ひな形(word)・ひな形(PDF)
なお、一人の相続人が預金すべてを相続する場合、以下のポイントに気を付けておきましょう。
預金残高は必ずしも記載する必要はありません。ですが、遺産が預金のみの場合や、主な遺産が預金である場合には、記載した方がよいでしょう。預金残高を記載しておくことで、相続により誰がいくら取得したのかが、一目でわかるようになります。
相続財産が預金のみで、複数の相続人で相続する場合
ひな形(word)・ひな形(PDF)
3.不動産を分ける場合の遺産分割協議書のひな形
続いて、不動産を分ける場合の遺産分割協議書のひな形をご紹介します。
不動産の種類(土地・戸建て・マンション)によって遺産分割協議書の記載事項が異なりますので、以下では具体的なケース別にひな形を掲載しています。
不動産を分ける場合
①土地を相続する場合
ひな形(word)・ひな形(PDF)
②一戸建てを相続する場合
ひな形(word)・ひな形(PDF)
③マンションを相続する場合
ひな形(word)・ひな形(PDF)
不動産を相続する場合の遺産分割協議書の書き方のポイントは、以下のとおりです。
- 不動産の情報は、「住所」ではなく「地番」「家屋番号」を記載する。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに正確に記載する。
- 不動産の種類(土地・戸建て・マンション)によって記載方法が変わる。
不動産を相続する場合には、相続される不動産を特定しなければなりません。
まず最初に気をつけておきたいのが、日常で使っている「住所」という表示方法と、不動産登記法上、土地を特定するために使われている「地番」や、建物を特定するために使用されている「家屋番号」という表示方法が、異なるものであるということです。
遺産分割協議書に不動産の情報を書く場合は、「住所」ではなく、「地番」や「家屋番号」を記入する必要があります。
そして、土地や建物などの不動産の情報は、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、記載されているとおりに正確に記載しましょう。不動産は「遺産分割内容」の部分に記載しますが、不動産の種類(土地・戸建て・マンション)によって記載方法が変わります。記載が少しでも間違っていると、法務局で相続登記の手続きが受け付けられない可能性がありますので、注意してください。
4.法定相続分どおりに分割する場合の遺産分割協議のひな形
法定相続分どおりに分割する場合の遺産分割協議書の書式をご紹介します。
例として、以下のひな形では、法定相続人が妻(甲)と子供2人(乙、丙)の場合で、妻が法定相続分として遺産の2分の1、子供2人が法定相続分としてそれぞれ4分の1ずつ分けることを想定しています。
法定相続分どおりの場合
ひな形(word)・ひな形(PDF)
法定相続分どおりに遺産分割を行う場合、不動産の相続登記や相続税申告などの手続きを行う際に、遺産分割協議書を提出する必要はありません。
ですが、将来的な相続人間のトラブルを回避するためには、「法定相続分どおりに遺産分割を行う」という合意を明確化しておくことは非常に重要です。簡易的な内容で構いませんので、遺産分割協議書を作成しておいた方がよいでしょう。
5.代償分割する場合の遺産分割協議書のひな形
続いて、代償分割する場合の遺産分割協議書のひな形をご紹介します。ちなみに、代償分割とは、ある相続人が特定の財産を相続する代わりに、他の相続人に対して代償金を支給して清算する方法です。
代償分割する場合
ひな形(word)・ひな形(PDF)
代償分割をする場合は、「代償分割をする旨」を遺産分割協議書に明記しておかなければなりません。
この点について記載がないと、代償分割の約束が守られなかったときにトラブルとなってしまいます。また、代償金の支払いが贈与とみなされると、贈与税がかかってしまうことがあるため、代償分割をしたことを示しておく必要があるのです。
6.換価分割する場合の遺産分割協議書のひな形
続いて、換価分割する場合の遺産分割協議書のひな形をご紹介します。換価分割とは、不動産などの遺産を売却し、得られた売却金を法定相続人の間で分配する方法のことをいいます。
換価分割の際には、被相続人名義のまま不動産を売却することができません。いったん相続人名義に書き換えて相続登記をし、その後買主へ登記を移転する必要があるからです。
そのため、換価分割をする場合には、①不動産の名義を共同相続人全員の名義に書き換える「共同登記型」と、②不動産の名義を代表者名義に変える「単独登記型」の2つの方法があります。両方のひな形をご用意しましたので、ご参照ください。
換価分割する場合
①不動産の名義を共同相続人全員の名義に書き換えて売却する場合
ひな形(word)・ひな形(PDF)
②不動産の名義を代表者名義に変えて売却する場合
ひな形(word)・ひな形(PDF)
なお、遺産分割協議書の具体的な書き方や文例については、こちらの関連記事をご覧ください。
遺産分割協議書のひな形(法務局・国税庁)
法務局や国税庁のホームページにも、遺産分割協議書のひな形が掲載されていますので、ご紹介いたします。
1.遺産分割協議書のひな形(法務局)
まずは、法務局の遺産分割協議書の記載例を見てみましょう。
参考:登記申請手続のご案内(法務局)
相続財産が不動産のみの場合に、特に有効です。
2.遺産分割協議書のひな形(国税庁)
遺産分割協議書のひな形は、法務局だけでなく国税庁でも公開されています。
なお、下画像のとおり、横書きの書式はなく、縦書きの書式となっております。
参考:「相続税の申告のしかた(平成29年分用)」より「相続税の申告書の記載例 等 ④相続税の申告書の記載例」(国税庁)
遺産分割協議書のひな形に関するQA
Q1.遺産分割協議書のひな形はどこでダウンロードできますか?
A:標準的な遺産分割協議書のひな形は、当法律事務所の本記事内にて無料でダウンロードいただけます。
Q2.法務局の遺産分割協議書のひな形はダウンロードできますか?
法務局の遺産分割協議書のひな形は、法務局のホームページからダウンロードが可能です。詳細は、本記事をご覧ください。
Q3.一人が全て相続する場合の遺産分割協議書のひな形はダウンロードできますか?
一人が全て相続する場合を想定した遺産分割協議書のひな形も、当法律事務所の本記事内にて無料でダウンロードいただけます。
まとめ
本記事では、遺産分割協議書について、標準的なケースのひな形や、具体的なケース別のひな形をご紹介させていただきました。
遺産分割協議書は、対象となる遺産の種類や遺産分割の内容によって、記載すべき内容が異なります。
遺産分割協議書の記載内容に問題があると、遺産分割協議が無効になってしまったり、相続手続きを進めることができなかったりと、トラブルに発展してしまいかねません。
そのため、遺産分割協議書の作成は弁護士にご依頼いただくことをお勧めいたします。
弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。対面によるご相談だけでなく、お電話によるご相談もお受けしております。
当ホームページのWeb予約フォームやお電話にて、ぜひお気軽にお問合せください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。