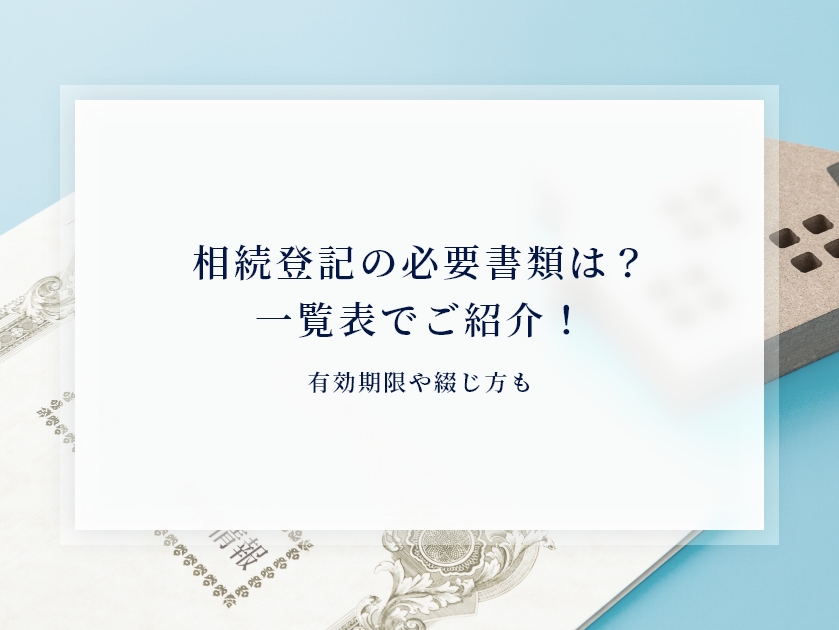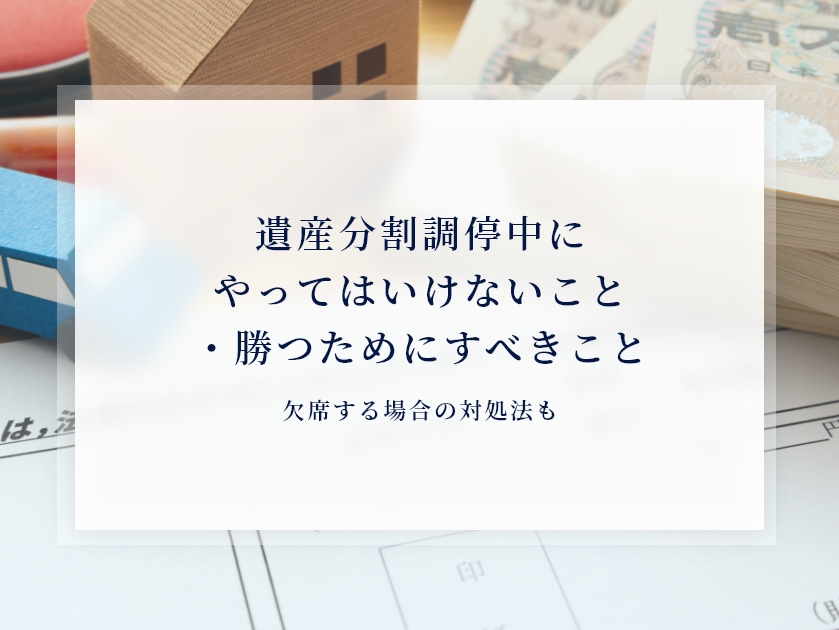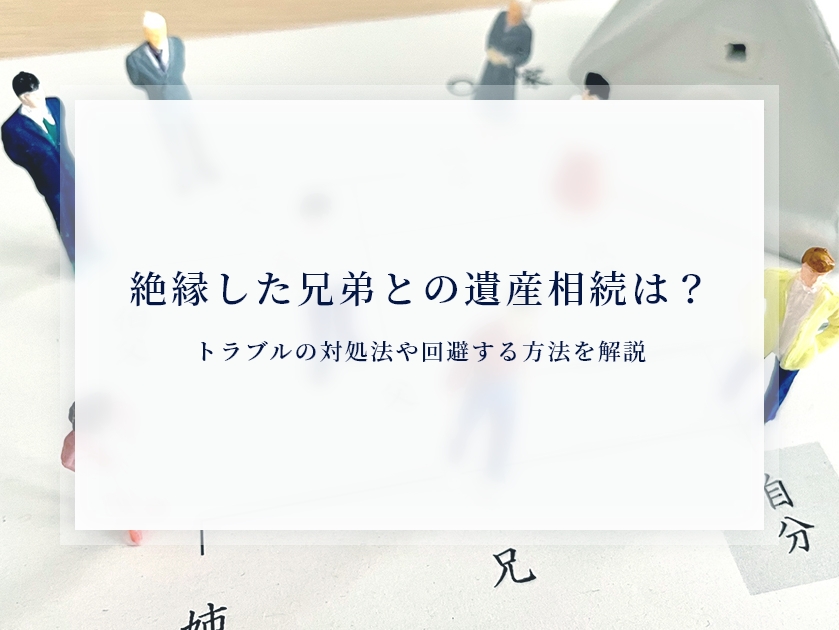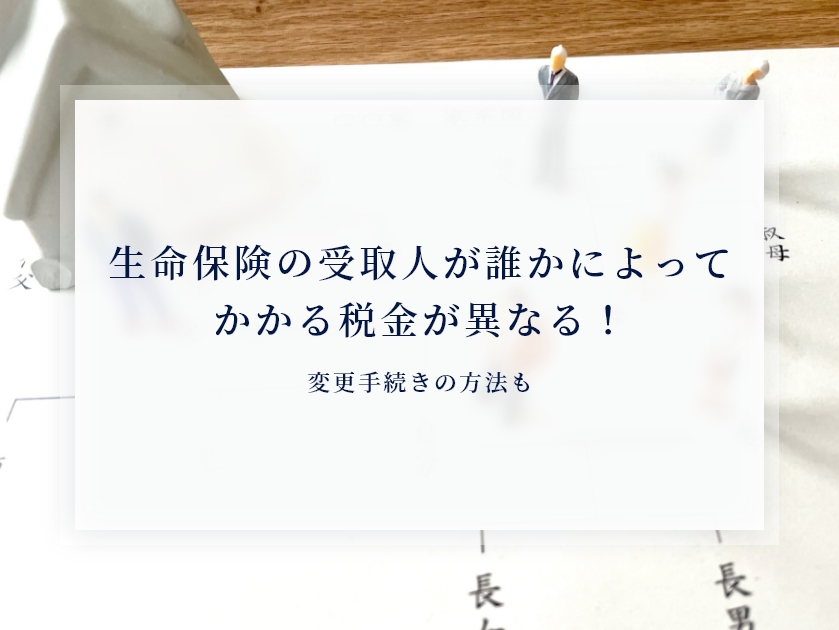遺産分割協議書の必要書類│遺産分割協議書が必要な相続手続きも紹介!
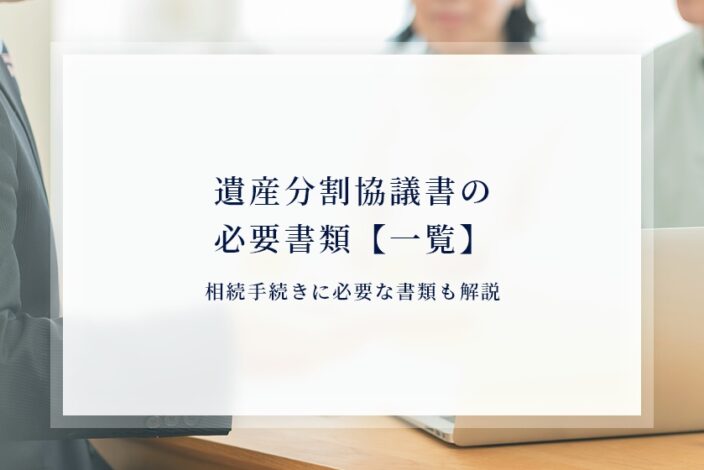
遺言書のない遺産相続では、相続人同士が話し合いをし、合意した内容をもとに遺産分割協議書を作ります。遺産分割協議書は、合意内容を記録しておくだけでなく、不動産の相続登記や預金払戻しといった相続手続きでも使う重要な書類です。
間違いがあって無効とならないよう、遺産分割協議書を作成する際には必要書類を適切に集めて利用しなければなりません。
そこで本記事では、遺産分割協議書を作成する際の必要書類について、弁護士が取得方法なども踏まえ詳しく解説させていただきます。
また、遺産分割協議書を使用する実際の相続手続きについて、遺産分割協議書以外の必要書類もあわせてご紹介いたします。
遺産相続の相続人や相続財産が増えるほど、必要となる書類の種類や枚数も増えていきます。相続が開始してから混乱することのないよう、本記事であらかじめしっかりと確認しておきましょう。
目次
遺産分割協議書の必要書類
被相続人が遺言書を遺していなかった場合には、原則として、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容を遺産分割協議書に記載します。遺産分割協議書は、相続登記や預金払戻しなどの相続手続きの際に使用する重要な書類となりますので、間違いのないよう正確に作成しなければなりません。
遺産分割協議書の書式は、役所や法務局、金融機関などでもらえるものではありません。基本的には自分自身で必要書類を集めて、相続人が協力して作成するものになります。
そのため、遺産分割協議書を作成する場合には、多くの必要書類を集めなければなりません。
遺産分割協議書の作成に必要となる主な書類と取得方法について、以下のとおり一覧にまとめました。
|
必要書類 |
目的 |
取得方法 |
|
被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍謄本類 |
死亡の事実の確認 相続人の特定・証明 |
被相続人の本籍地がある市区町村役場で取得 |
|
相続人全員の戸籍謄本 |
各相続人の本籍地がある市区町村役場で取得 |
|
|
被相続人の住民票除票(または戸籍附票) |
被相続人の最後の住所地の確認 |
被相続人の最後の住所地の市区町村役場(被相続人の本籍地がある市区町村役場)で取得 |
|
相続人全員の印鑑登録証明書(相続放棄者を除く) |
遺産分割協議書の作成 |
各相続人の住所地の市区町村役場で取得 |
|
遺言書 (ある場合) |
遺言書の調査 |
自筆証遺言書:法務局または自宅など 公正証書遺言書:公証役場または自宅など |
|
検認済み証明書 (検認を受けた場合) |
検認は家庭裁判所へ申し立てる |
|
|
相続放棄申述受理証明書 |
相続放棄者の確定 |
家庭裁判所へ申請する |
|
財産目録 |
相続財産の確定 |
遺産内容をもとに自分たちで作成する |
遺産分割協議書の作成に必要な書類を収集する作業は、非常に労力や手間がかかります。
ご自身で必要書類を収集して遺産分割協議書を作成するのが難しい場合には、専門家への依頼を検討されることをお勧めいたします。
それでは以下に、遺産分割協議書の必要書類について、それぞれの概要や取得方法などを詳しく見ていきましょう。
遺産分割協議書の作成に必要な書類
(1)相続人を確認するための戸籍謄本類
遺産分割協議書を作成する際には、相続人の特定をするために、「被相続人が生まれてから死亡するまで」のすべての戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)をもれなく集める必要があります。
- 戸籍謄本:戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する戸籍の写しのこと
- 除籍謄本:戸籍に記載されている全員が除かれて、誰もいなくなったことを証明する戸籍の写しのこと
- 改製原(かいせいげん)戸籍謄本:改正前の戸籍法に基づくフォーマットで作成された戸籍の写しのこと
「戸籍謄本」の正式名称は、「戸籍全部事項証明書」といいます。戸籍謄本には、戸籍の筆頭者や本籍地の他、その戸籍に記載される人全員の氏名や続柄などが記載されています。
「除籍謄本」とは、死亡や結婚などにより、戸籍に記載されている人全員がいなくなった状態の戸籍の写しのことをいいます。
「改製原戸籍」とは、改正前の戸籍法に基づく形式で作成された古い戸籍を指します。被相続人の出生までをたどる際に、改製原戸籍謄本が必要となるケースは少なくありませんので、必要になるかもしれない、と覚えておきましょう。
通常、被相続人の本籍地では、最新の戸籍謄本しか取得できません。そのため、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続したすべての戸籍謄本を取得するためには、以下のような手続きが必要となります。
- 被相続人の亡くなった時点の本籍地の市区町村役場で戸籍謄本(①)を取得する。
- ①に記載されている「移動前の本籍地」の市区町村役場で戸籍謄本(②)を取得する。
- 被相続人の「出生事項がはじめて記載された戸籍」にたどり着くまで、くり返す。
被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本が全部で何通になるのかは、被相続人によって異なります。結婚や離婚などで本籍地が何度も移転しているといったケースでは、必要な戸籍謄本等が増えるため、通数が多くなるでしょう。
戸籍謄本類の日付が途切れることなく連続するように、注意しながら集めていきましょう。
被相続人の戸籍謄本を全て取得し、相続人が特定できたら、次に相続人全員の戸籍謄本を取得します。
これは、被相続人が亡くなった時点での、相続人の生存を証明するためです。
また、孫が代襲相続人として相続する場合や、親・兄弟姉妹などが相続する場合などには、相続人の子どもや親といった、相続人以外の人の戸籍謄本類も必要となる可能性があります。
戸籍謄本の取得方法
戸籍謄本等の取得方法ですが、本籍地の市区町村役場に請求して取得しましょう。
戸籍謄本は、市区町村役場の窓口で直接請求して取得するほか、郵送で請求することもできます。
被相続人や相続人の本籍地が分からなければ、住所のある市区町村役場で「本籍地の記載」を希望して住民票を取得することで調べることが可能です。
転籍している場合は、以前の本籍地の市区町村役場にも戸籍謄本を請求します。
(2)被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
遺産分割協議書の作成に必要な書類として、被相続人の住民票の除票や戸籍の附票があります。
遺産分割協議書には、被相続人の最後の住所地を記載しなければなりません。被相続人の最後の住所地を確認するために、以下のいずれかの書類が必要となるのです。
被相続人の住民票の除票
住民票の除票とは、死亡によってすでに除かれた住民票のことです。被相続人の住民票の除票は、被相続人の最後の住所地のある市区町村役場で取得できます。
被相続人の戸籍の附票
その戸籍が編製された時から、除籍されるまでの住所の履歴を記録したものをいいます。被相続人の戸籍の附票も戸籍謄本と同様に、本籍地のある市区町村役場で取得しましょう。
(3)相続人全員の印鑑登録証明書
遺産分割協議書には、合意したことを示すため、相続人全員が署名押印します。そのため、遺産分割協議書に押印した実印について、相続人全員分の印鑑登録証明書が必要です。
印鑑登録証明書とは、市区町村役場に登録されている実印が本物であるということを証明する書類です。遺産分割協議書に押印された印鑑と、その印鑑が実印として登録されているという証明書があることで、遺産分割協議書の内容に同意したことを第三者に証明できるというわけです。
印鑑登録証明書は、それぞれの相続人の住所地の市区町村役場で取得できます。自治体によっては、マイナンバーカードを利用して、コンビニに設置されている証明書自動交付機で取得することができます。
(4)遺言書(ある場合)
遺産分割協議を行う前に、遺言書が見つかっていれば、遺言書も必要です。
原則として、遺言書がある場合、その内容は相続人の協議よりも優先されます。遺言書が存在する場合、その内容を無視して遺産分割協議を進めてしまうと、遺言書と合意した内容が矛盾し、後に相続人間でトラブルが生じてしまったり、遺産分割自体が無効になったりする可能性があります。
つまり、遺産分割協議書を作成する際は、遺言書の存在とその内容を踏まえた上で、相続人全員が納得して合意した協議書であることを記録しておかなくてはなりません。
そして、遺言書には「自筆遺言書」と「秘密遺言書」、「公正証書遺言書」という3種類の形式があります。どの遺言書かによって保管方法が異なりますので、相続が始まったら以下を参考にしながら遺言書を探してみてください。
遺言書の種類・保管場所
- 自筆遺言書(遺言者が直筆で作成する遺言のこと):自宅や貸金庫で保管されているか、法務局に預けられている。
- 秘密遺言書(内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で証明してもらう遺言のこと):自宅や貸金庫などで本人が保管している。
- 公正証書遺言書(遺言者の代わりに公証人が作成する遺言のこと):自宅や貸金庫などに「正本」が保管されている可能性がある。公証役場で検索すれば、謄本という写しを申請できる。
(5)遺言書の検認済み証明書
「公正証書遺言書」以外の種類の遺言書がある場合には、家庭裁判所で「検認」の手続きを行い、「検認済証明書」を発行してもらいましょう。
民法上、遺言が「公正証書遺言」以外の遺言の場合、つまり「自筆証書遺言」か「秘密証書遺言」である場合、遺言書を保管している人または遺言書を発見した人は、家庭裁判所に対して「検認」の申し立てを行わなければなりません(民法第1004条)。
(遺言書の検認)
民法第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
遺言書の検認とは、家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人などの立会いのもとで遺言書を開封し、遺言書の状態や内容を確認する手続きです。
家庭裁判所における検認手続きをしないまま、遺言書の執行をした場合や開封した場合には、5万円以下の過料に処せられることになりますので注意してください(民法1005条)。
(過料)
民法第1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
「検認済証明書」があれば、「きちんと裁判所で検認を受けた遺言書」である事実を証明することができますので、家庭裁判所で発行してもらいましょう。
(6)相続放棄申述受理証明書(相続放棄者がいる場合)
相続放棄した相続人がいる場合は、家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の交付申請をして取得しましょう。「相続放棄申述受理証明書」とは、申述をした相続人が相続放棄をしたことを、第三者に証明するための書類です。
相続放棄をするには、家庭裁判所に申述書を提出して、受理される必要があります。
相続放棄をした人は、そもそも相続人ではなかったことになりますので、遺産分割協議には参加しないことになります。相続人ではないため、遺産分割協議に合意して遺産分割協議書に署名する必要はありません。
相続放棄をした相続人がいる場合には、そのことを明確にするためにも「相続放棄申述受理証明書」を取得したほうが良いでしょう。なお、相続放棄申述受理証明書を取得する場所は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
(7)財産目録
財産目録とは、被相続人の財産の内容が一覧でわかるようにまとめたものです。遺産分割協議書に添付しておくことで、協議書内に出てきた財産が一目で確認できるようになります。
財産目録の作成自体は義務ではありませんが、財産目録を作成し、どのような遺産があるのかまとめておくと、遺産分割協議を進めやすくなります。遺産分割協議を始める前に、財産内容をまとめた財産目録を作成しておきましょう。
遺産分割協議書が必要書類となる相続手続き
続いて、遺産分割協議書を使用して行う相続手続きと、その際に必要となる書類について解説いたします。
相続手続きには、大きく分けて「不動産の名義変更(相続登記)」、「金融機関での手続き」、「相続税申告」という3つの手続きがあります。
これらの相続手続きにおいて遺産分割協議書が必要となるのは、遺産分割によって財産を取得した場合です。
相続手続きは、遺産分割協議書さえあれば行えるというものではありません。各窓口で所定の申請書などもあり、遺産分割協議書とあわせて提出を求められる添付書類がいくつかあります。
それぞれの手続きについて、遺産分割協議書と一緒に必要となる添付書類を一覧にまとめましたので、ご確認いただければと思います。
遺産分割協議書を使用する相続手続きの必要書類【一覧】
|
手続き場所 |
目的 |
必要書類 |
|
法務局 |
不動産を相続した場合に、不動産の名義変更(相続登記)をするための手続き |
|
|
金融機関 |
預貯金を相続した場合に、口座の名義変更や解約・払い戻しをするための手続き |
|
|
税務署 |
相続税が発生する場合に相続税の申告をするための手続き |
|
上記に記載した3つの手続きのうち、「不動産の名義変更(相続登記)」と「金融機関での手続き」における必要書類について、以下で詳しく見ておきましょう。
(1)法務局での不動産に関する手続きの必要書類
相続によって不動産を取得した時に、必ず行わなければいけない手続きの一つが「相続登記」です。相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を、相続人の名義へ変更することをいいます。
相続登記には、主に「遺産分割協議による相続登記」「法定相続分による相続登記」「遺言による相続登記」の3つのケースがあります。このうち、遺産分割協議書を使うのは、「遺産分割協議による相続登記」を行う場合です。
遺産分割協議を行い、協議の結果にもとづいて登記をする場合、基本的に以下の書類が必要となります。
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 登記する不動産を取得する相続人の住民票:登記する不動産を取得する相続人の住所地の市区町村役場で取得。
- 対象不動産の固定資産評価証明書:不動産所在地の市区町村役場で取得。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員分の印鑑登録証明書:各相続人の住所地の市区町村役場で取得。
以下では、それぞれの必要書類の概要や入手方法などを見ていきましょう。
①被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
被相続人の死亡の事実の確認、また、相続人の特定をするために、被相続人の死亡時の戸籍謄本だけでなく、出生から死亡までの連続した戸籍謄本類が必要となります。
前述の通り、被相続人の戸籍謄本は、まず最初に、被相続人の最後の本籍地の市区町村役場で取得しましょう。転籍している場合は、転籍前の本籍地の市区町村役場にも戸籍謄本を請求します。
②被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)は、被相続人の「亡くなった時点の住所」と「登記記録に記載された住所」が一致しているか照らし合わせ、同一人物であるかを判断するために必要となります。
前述の通り、被相続人の住民票の除票は、被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得することができます。被相続人の戸籍の附票も、被相続人の本籍地がある市区町村役場で取得しましょう。
③相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人全員の現在の戸籍謄本は、被相続人が亡くなった時点において、相続人が確かに存在(存命)しており、相続人となることを確認するために必要となります。
各相続人の本籍地がある市区町村役場で取得しましょう。
④登記する不動産を取得する相続人の住民票
登記する不動産を取得する相続人の住所地の市区町村役場で取得。
⑤対象不動産の固定資産評価証明書
相続登記を申請する際には、登録免許税という税金を法務局に納める必要があります。この登録免許税の算出の根拠となる不動産価格が記載された書面のことを「固定資産評価証明書」といいます。固定資産税評価証明書は、不動産所在地の市区町村役場で取得することができます。
⑥遺産分割協議書
遺産分割協議により遺産の分割方法を決めた場合には、その内容を証明するために、相続人全員が実印で署名押印した「遺産分割協議書」が必要となります。
⑦相続人全員分の印鑑登録証明書
遺産分割協議書に捺印された印鑑が実印であるかどうかを確認するために、相続人全員分の印鑑登録証明書が必要となります。
印鑑登録証明書は、各相続人の住所地の市区町村役場で取得しましょう。
以上が、遺産分割協議によって相続する場合に、相続登記で必要となる書類です。必要書類を集めたら、下記画像の手順で手続きを進めていきます。
なお、遺産分割協議による相続ではなく、法定相続分による相続や、遺言による相続の場合には、ケースに応じて申請に必要な書類も異なります。
参考:相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等(法務局)
相続登記の必要書類については、こちらの関連記事もご参考ください。
(2)金融機関での預金引き出しに必要な書類
銀行などの金融機関における相続手続きとしては、被相続人の口座を解約して預金を払い戻すことが一般的です。
金融機関の相続手続きにおいて、遺産分割協議書を添付書類として使用するのは、遺産分割協議を行ったことより、法定相続分と異なる相続割合で財産を取得した場合になります。
遺産分割協議を行い、協議の結果にもとづいて、金融機関で相続手続きをするためには、通常以下のような書類が必要となります。
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
- すべての相続人の戸籍謄本または抄本
- 遺産分割協議書
- すべての相続人の印鑑登録証明書
- 手続きをする人の実印
- 金融機関の書類
- 印鑑届(払い戻しの場合は不要)
以下では、それぞれの必要書類の概要や入手方法などを見ていきましょう。
①被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
被相続人の死亡の事実の確認、また、相続人の特定をするために、被相続人の死亡時の戸籍謄本だけでなく、出生から死亡までの連続した戸籍謄本類が必要となります。
②すべての相続人の戸籍謄本または抄本
相続人の確認をするために、すべての相続人の戸籍謄本・抄本が必要となります。
各相続人の本籍地がある市区町村役場で取得しましょう。
なお、被相続人の戸籍謄本等で被相続人との関係が確認できる場合には、不要となることもありますので、手続きの準備を始める際に、取引のあった金融機関に問い合わせて確認しておくと安心です。
③遺産分割協議書
遺産分割協議により遺産の分割方法を決めた場合には、その内容を証明するために、相続人全員が実印で署名押印した「遺産分割協議書」が必要となります。
④すべての相続人の印鑑登録証明書
遺産分割協議書に捺印された印鑑が実印であるかどうかを金融機関が確認するために、相続人全員分の印鑑登録証明書が必要となります。
⑤手続きをする人の実印
銀行の預金等の相続手続をする人(預金等を取得する人)の実印が必要となります。
⑥金融機関の書類
取引先の銀行で用紙を入手し、必要事項を記載します。
⑦印鑑届
銀行の預金等を「名義変更」で相続する場合は、「印鑑届」が必要です。銀行で用紙を入手し、必要事項を記載します。
なお、払い戻しの場合には、「印鑑届」は不要となります。
以上が、遺産分割協議によって取得した預貯金の相続手続きで必要となる書類となります。
金融機関によっても必要書類の詳細や書式は異なるため、あらかじめ窓口等で確認しておくことをお勧めいたします。
遺産分割協議書の必要書類に関するQA
Q1.遺産分割協議書作成時の必要書類は何ですか?
A:遺産分割協議書の作成に必要となる主な書類の一覧は、以下のとおりです。
- 被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍謄本類
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
- 相続人全員の印鑑登録証明書(相続放棄者を除く)
- 遺言書(ある場合)
- 検認済み証明書(検認を受けた場合)
- 相続放棄受理証明書
- 財産目録
Q2.遺産分割協議書を使った法務局での手続きで必要な書類は何ですか?
A:遺産分割協議を行い、協議の結果にもとづいて法務局で不動産の相続登記をする場合、基本的に以下の書類が必要となります。
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 登記する不動産を取得する相続人の住民票:登記する不動産を取得する相続人の住所地の市区町村役場で取得。
- 対象不動産の固定資産評価証明書:不動産所在地の市区町村役場で取得。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員分の印鑑登録証明書:各相続人の住所地の市区町村役場で取得。
Q3.遺産分割協議書を使った金融機関での相続手続きの必要書類は何ですか?
A:遺産分割協議を行い、協議の結果にもとづいて金融機関で相続手続きをするためには、以下のような書類が必要となります。
なお、必要書類は金融機関によって異なる可能性があります。
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
- すべての相続人の戸籍謄本または抄本
- 遺産分割協議書
- すべての相続人の印鑑登録証明書
- 手続者の実印
- 金融機関の書類(名称は銀行によって異なる)
- 印鑑届(払い戻しの場合は不要)
まとめ
本記事では、遺産分割協議書を作成する際の必要書類、また、遺産分割協議書を使用して相続手続きを行う際の必要書類について解説いたしました。
遺産分割協議書の作成時には、正確に遺産を分割できるように、多くの書類が必要となります。遺産分割協議書の作成に不備があると、相続登記や預貯金の払い戻しなどの相続手続きが行えなくなってしまうリスクも発生します。
遺産分割協議書の必要書類の収集は、多大な手間がかかる作業ですので、ご自身での対応が難しい場合には、専門家へご依頼いただくことをお勧めいたします。
遺産分割協議書の作成や必要書類、相続人の調査などにおいてご不明点がある場合は、法律の専門家である弁護士へご相談ください。
弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。遺産相続には手続きの期限などもありますので、なるべく早めにご相談いただければと思います。当ホームページのWeb予約フォームやお電話にて、ぜひお気軽にお問合せください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。