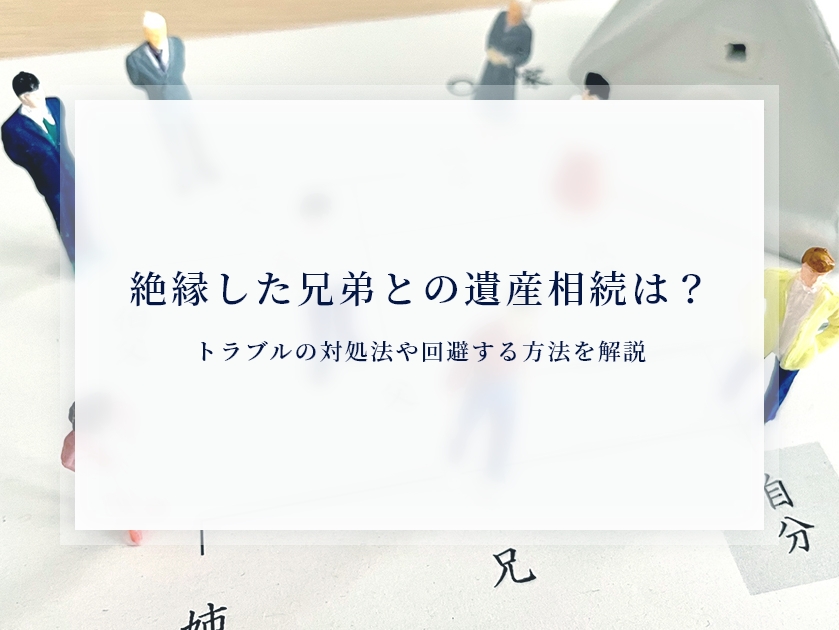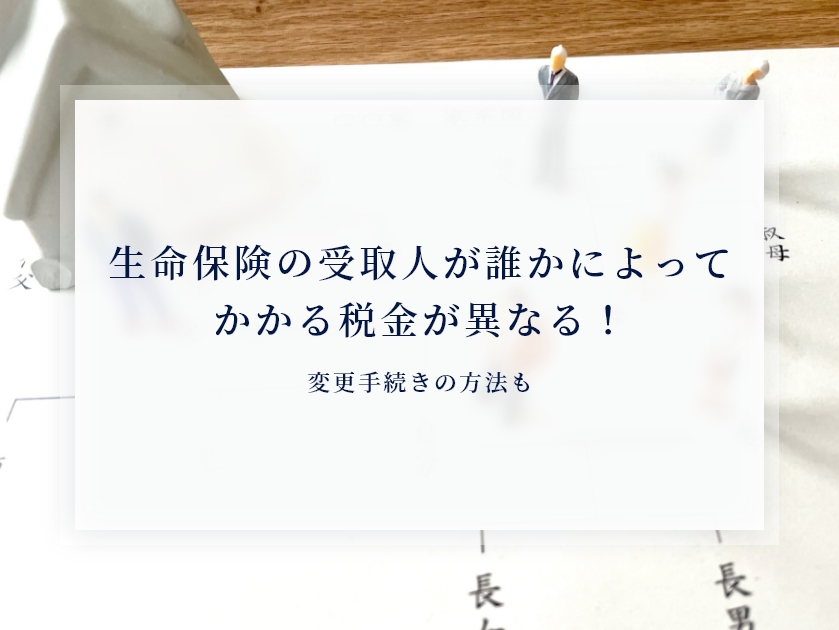遺留分の時効|遺留分侵害額請求の時効や期限は10年?改正でどうなった?
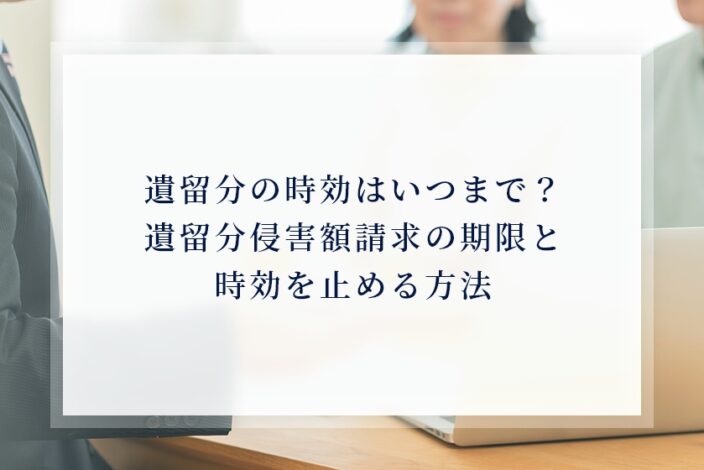
遺産相続で自分の遺留分が侵害されていると分かったら、どのような行動を起こせばいいかご存知でしょうか。
通常、遺留分を侵害している他の相続人に対して、侵害額に相当する金銭を請求することになります。
この請求を「遺留分侵害額請求」といいますが、遺留分を無期限でいつでも請求できるというものではありません。
遺留分を請求する権利には、「時効」が定められています。
時効が完成すると遺留分をもらえなくなってしまいますので、遺留分を侵害されたことがわかった場合には、すぐに適切な手続きを取ることが重要です。
そこでこの記事では、遺留分の時効について、弁護士がわかりやすく解説させていただきます。
目次
遺留分の時効
1.「遺留分の請求」と「時効」
民法には、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される遺産の取得割合「遺留分」が定められています(民法第1042条)。
そして、侵害された遺留分を請求することを「遺留分侵害額請求」といいます。
この遺留分侵害額請求ですが、いつまでも無期限に請求できるものではなく、一定期間が経ってしまうと請求できなくなる「時効」が定められています。
時効とは、法律上の権利や義務に関して、一定の期間内にこれを行使または履行しなかった場合、その権利が消滅し、または義務が免除されるという法的な仕組みのことです。
正当な請求権に期間制限があるなんて、と思われるかもしれません。
ですが、遺産相続に関する紛争を早期に解決し、法律関係を早期に安定させるために、時効は重要な制度なのです。もし遺留分侵害額請求に時効が定められていなければ、遺産相続をしてから30年後に突然「遺留分を侵害された」と請求される、といったことが許されるようになってしまいます。これでは、一度行われた遺産相続の結果がいつまでも不安定なままです。
そのため、遺留分侵害額請求にも時効が適用されているのです。
2.民法改正で遺留分の時効はどうなった?
さて、そんな遺留分の時効に関してですが、2018年の民法改正(2019年7月1日施行)によって、制度は大きく見直されました。ここでは、民法改正前と改正後との違いを確認しておきましょう。
民法改正前は、遺留分を請求する権利を「遺留分減殺請求権」といいましたが、この権利は侵害された遺産そのものの権利を請求するという、物権的請求権でした。
(減殺請求権の期間の制限)
民法第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
そしてこの条文の通り、遺留分請求権には「1年」と「10年」という2つの時効があったのです。
ですが、2018年の民法改正によって、遺留分を請求する権利は、不動産などの遺産そのものについて請求する権利ではなく、一律で「侵害された分のお金を請求する権利」となりました(金銭債権化)。
改正後の遺留分の時効についての規定は以下の通りです。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
民法第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
さらに、「金銭債権」になったことによって、金銭債権の消滅時効も、遺留分の時効とは別に適用されることになりました(民法第166条1項1号)。
金銭債権の消滅時効に関する規定は、2020年4日1日に改正法が施行され、以下の通りになっています。
(債権等の消滅時効)
民法第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
つまり、民法改正によって、遺留分の請求権には3つの時効のいずれかが適用されることとなったのです。
| 遺留分請求権の性質 |
遺留分の時効 |
|
| 民法改正前 | 遺留分を侵害された相続人が「遺留分減殺請求権」を行使すると、遺贈や贈与がその限度で効力を失い、目的物の所有権などが遺留分権利者に当然に戻るという「物権的効果」が生じた。 |
①相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき ②相続開始の時から10年を経過したとき |
| 民法改正後 | 権利を行使すると遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生する「遺留分侵害額請求権」となった。 |
①相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき ②相続開始の時から10年を経過したとき ③債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。 |
遺留分侵害額請求の時効
それでは、民法改正後の3つの時効について、具体的に確認していきましょう。
|
時効の種類 |
適用条件 |
説明 |
|---|---|---|
|
消滅時効 |
相続開始と遺留分侵害を知ってから1年 |
相続開始と遺留分侵害を知った日から1年以内に遺留分侵害額請求権を行使しなければ、時効により権利が失われる。 |
|
除斥期間 |
相続が開始してから10年 |
相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権が除斥され、使用できなくなる。 |
|
金銭債権の消滅時効 |
遺留分侵害額請求を行使してから5年 |
遺留分侵害額請求権を行使した後、5年間金銭請求を行わなければ、その金銭債権が時効により消滅する。 |
1.相続開始と遺留分侵害を知ってから1年(時効)
最も短い時効は、「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」です(民法第1048条前段)。
この場合、遺産相続が開始されたことと、「遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと」を知った時、が時効の起算点となります。つまり、単に遺産相続が始まったことや、贈与があったことを知っただけでは、時効のカウントは始まりません。その贈与や遺贈が「遺留分を侵害するものであったこと」まで知っていることが条件となります。
たとえば、遺産のほとんどが特定の人物に遺贈されている場合、その行為が遺留分権利者の取り分を不当に減少させていることを知っている必要があります。
そして、この1年という時効は、消滅時効です。この期間内に遺留分侵害額請求権を行使しないと、時効によってその権利は消滅し、後になってから権利を主張することはできなくなってしまいます。
1年間という時効の期間は、遺留分権利者が自分の遺留分が侵害されていることを認識し、それに基づいて法的な手続きを開始するための猶予期間なのです。
ただし、1年が経過した後も、遺留分の請求権が自動的に消滅するわけではありません。この時効消滅は、請求される側、つまり遺産を受け取った相続人や受遺者が、時効を主張したときにのみ成立します。当事者による援用が必要なのです(民法第145条)。
(時効の援用)
民法第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
つまり、1年以上経ってから遺留分を請求した場合に、請求された側が「時効が成立している」と主張しなければ、1年の消滅時効が成立しておらず、遺留分の請求が有効になる可能性もあるのです。
そのため、時効期間が経過してからでも遺留分の請求を試みることは可能です。
もっとも、通常は時効を主張するので、時効が成立する前に、迅速に請求手続きを進めましょう。
2.相続が開始してから10年(除斥期間)
二つ目の時効は「相続開始の時から10年を経過したとき」です(民法第1048条後段)。
この10年の時効の性質は、1年の時効と異なり、「除斥期間(じょせききかん)」と考えられています。
除斥期間とは、一定期間が経過することによって、権利が当然に消滅する期間のことです。この除斥期間については、当事者が「10年経った」と主張する必要はありません。
一方で、1年の消滅時効は、当事者が時効の成立を主張することによって初めて権利消滅の効果が生じます。これが、1年の時効と10年の除斥期間との大きな違いです。
また、10年の除斥期間の起算点は、「相続開始の時」という客観的な事実とされています。
1年の時効の場合、起算点は「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」という、主観的な認識です。
つまり、10年の除斥期間が経過すると、相続人が相続の事実を知っていたかどうかにかかわらず、遺留分侵害額請求権は自動的に消滅することになるのです。
遺留分を確保するためには、この10年間という除斥期間に注意し、迅速に手続きを進める必要があります。
3.遺留分侵害額請求を行使してから5年(時効)
遺留分侵害額請求権を行使することで、「金銭支払請求権」が発生します。
この金銭債権に関しては、遺留分の時効のルール(民法第1048条)とは別に、5年間の消滅時効が適用されます(民法第166条1項1号)。
5年の時効の起算点は、遺留分侵害額請求権の行使時です。
つまり、相続人が遺留分の侵害があったと認識し、遺留分侵害額の請求を行った時点から、5年間のカウントが始まることになります。
遺留分を請求する権利者は、遺留分侵害額請求権を行使してから5年間の期限内に、具体的な請求や法的措置を取らなければ、その金銭債権が時効により消滅してしまうのです。
遺留分に相当する金銭を確実に受け取るためには、5年以内に裁判上の請求など具体的な手続きを行い、時効を中断または停止させる必要があります。
そのため、改正法が施行される前、2020年3月31日以前に遺留分侵害額請求を行っていた場合には、金銭債権の消滅時効のルールが適用されないため、10年か1年の時効となります。
5年のルールが適用されるのは、2020年4月1日以降に行った遺留分侵害額請求ですので、注意してください。
4.遺留分の時効の起算点はいつから?
以上の通り、遺留分に関する期間制限には3つの時効があり、それぞれいつから時効のカウントが始まるのか、起算点が異なります。確認しておきましょう。
①1年(消滅時効)の起算点
遺留分権利者が、「相続の開始」および「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと」の両方を知った時から1年です(主観的起算点)。
この「知った時」とは、単に贈与や遺贈の事実を知っただけでは足りず、その贈与や遺贈が自己の遺留分を侵害するものであると認識した時点を指します。
ですので、遺留分権利者が贈与があったことを知っていても、それが遺留分を侵害するほどの財産であると知らなかったような場合には、「遺留分を侵害する贈与」を知らなかったことになるため、時効は進行しないと考えられています。
②10年(除斥期間)の起算点
10年の除斥期間の起算点は、「相続開始の時」からです。当事者の認識によらず、客観的な「相続の開始」という事実が起算点となっています(客観的起算点)。
時効の完成猶予や更新が適用されない除斥期間なので、10年が経過すると、当事者の援用がなくても遺留分の請求権は当然に消滅します。
③5年(金銭債権の消滅時効)の起算点
遺留分侵害額請求権を行使した結果として生じる金銭債権の消滅時効は、遺留分の時効のルールではなく、民法の一般原則に基づく消滅時効にかかります。
そして、この場合の時効の起算点は「債権者が権利を行使することができることを知った時」から5年間となります(主観的起算点)。
起算点の証明は難しい?
相続が始まった時、という客観的な事実と比べ、「遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時」という主観的な起算点は、裁判になった時に、証明が難しいと考えられています。
時効の成立について争いになるような事態を避け、なるべく早めに遺留分侵害額請求をすることがお勧めです。
遺留分請求の期限の注意点
それでは、遺留分請求の時効に関して、いくつかの注意点を確認しておきましょう。
1.公正証書遺言と遺留分の時効
公正証書遺言は、公証人が関与して作成される信頼性の高い遺言方式ですが、その内容が特定の相続人の遺留分を侵害することもあります。そうなった場合、遺留分権利者としては、公正証書遺言の有効性について争うこともあるでしょう。
ですが、遺言書の無効を争う場合も、時効には注意が必要です。
最高裁判所は、特定の事情がない限り、遺留分侵害額請求権に関する時効は通常通り進行すると判示しています(最高裁判所昭和57年11月12日判決)。
この事例では、遺留分権利者が遺言は無効だと思い、遺留分の請求権を行使しませんでした。
民法一〇四二条にいう「減殺すべき贈与があつたことを知つた時」とは、贈与の事実及びこれが減殺できるものであることを知つた時と解すべきである…(中略)民法が遺留分減殺請求権につき特別の短期消滅時効を規定した趣旨に鑑みれば、遺留分権利者が訴訟上無効の主張をしさえすれば、それが根拠のない言いがかりにすぎない場合であつても時効は進行を始めないとするのは相当でないから、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されていて遺留分権利者が右事実を認識しているという場合においては、無効の主張について、一応、事実上及び法律上の根拠があつて、遺留分権利者が右無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかつたことがもつともと首肯しうる特段の事情が認められない限り、右贈与が減殺することのできるものであることを知つていたものと推認するのが相当というべきである。
(最高裁判所昭和57年11月12日判決)
つまり、遺言の無効が争われているようなケースであっても、原則として時効は進行し、例外的に「遺留分請求権を行使しなかったことがもっともと首肯し得る特段の事情」が認められる場合に限って、時効は進行しないと考えられているのです。
特段の事情とは、例えば遺留分権利者が遺言の無効性について知らなかったり、誤解していたりするなど、権利行使を妨げる合理的な理由がある場合を指します。そして、「特段の事情」の証明はかなり難しいといわれています。
遺留分を請求する権利者としては、単に遺言の無効を主張するだけではなく、予備的に遺留分侵害額請求をしておくことが重要です。
2.代襲相続と遺留分の時効
相続人となるべき者(被代襲者)が、相続開始以前に死亡しているときや、相続欠格または廃除により相続権を失ったときに、その被代襲者の直系卑属(代襲者)が被代襲者に代わって相続する制度を、代襲相続といいます。
代襲相続によって相続人となった人(代襲相続人)についても、遺留分の時効は他の相続人と同じように適用されることになります。
3.遺留分侵害額請求権と時効中断
あと1か月で時効が完成してしまう、といった場合に、遺留分の時効のカウントを止めることはできるのでしょうか。
遺留分の時効は1年と10年の2つありますが、10年の時効に関しては「時間の経過によって当然に権利が消滅する除斥期間」であるため、中断することはできません。
1年の消滅時効と5年の消滅時効に関しては、以下の方法によって、時効の成立を防ぐことになります。
①配達証明付きの内容証明郵便を送付する
まず、遺留分侵害額請求権を行使するため、相手に対して請求する旨の意思表示を行います。
口頭による意思表示では、請求した・していないの争いになってしまうため、書面で意思表示をするようにしましょう。特に、相手に文書を送ったことの記録が残る、配達証明付きの内容証明郵便がお勧めです。
書面には、請求者の名前や請求先、請求の対象となる遺贈・贈与・遺言の詳細に加え、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する旨の文言と、請求の日時を具体的に記載しましょう。
大切なのは、時効完成前、つまり権利を行使できることを知ってから1年以内に上記の手続きを行うことです。複数の相手に対して遺留分侵害がある場合は、全ての関係者に対してこの手続きを行う必要があります。判断が難しい場合は、弁護士にご相談ください。
なお、内容証明郵便で通知書を送付することで遺留分の1年の時効を停止したとしても、金銭債権の消滅時効として5年の期限があります。この5年の消滅時効の完成を防ぐためには、上記のような方法で意思表示をした後、時効の「完成猶予」または「更新」の手続きを行う必要があります。
②時効の完成猶予・更新
時効の完成猶予
時効の完成猶予とは、一定の事由がある間は、時効が完成しないことです。
時効の完成猶予が認められる事由としては、次のような方法があります(民法第147条以下)。
- 裁判上の請求、支払督促、和解、調停
- 倒産手続参加
- 強制執行、担保権の実行、競売、仮差押え、仮処分
- 財産開示手続、第三者からの情報取得手続
- 内容証明郵便などによる履行の催告
- 協議の合意
時効の更新
そして、時効を完成猶予した上で、確定判決等によって権利が確定した場合等には、完成猶予事由が終了した時から、新たにその進行が始まります(時効の更新)。
時効の更新には、次のような方法があります(民法第147条以下)。
- 裁判上の請求、支払督促、和解、調停、倒産手続参加をし、その後、権利が確定したこと
- 強制執行、担保権の実行、競売、財産開示手続、第三者からの情報取得手続の終了
- 債務の承認
なお、2020年3月31日以前に発生した遺産相続の場合には、民法改正前の「時効の停止・中断」によって時効の成立を防ぐことになります。
交渉が長期化する場合や複雑なケースでは、迅速な対応が重要です。なるべく早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
遺留分の時効に関するQ&A
Q1.遺留分の1年の消滅時効のカウントはいつから始まりますか?
A: 遺留分の時効は、相続が開始し、かつ相続人が自分の遺留分が侵害されていることを知った時点から始まります。通常、相続開始は被相続人の死亡時点です。遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内に遺留分請求を行わないと、時効により請求権が消滅するため、迅速な対応が重要です。
Q2.遺留分はいつまで請求できますか?
A: 遺留分請求の時効期間は、相続人が遺留分侵害を知った日から1年です。ただし、改正民法では、権利を行使できることを知った日から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い時点まで、とされています。
Q3.遺言書の無効が争われている場合、遺留分請求の時効にどのような影響がありますか?
A: 遺言書の無効が争われている場合でも、一般的には遺留分請求の時効は進行します。遺留分権利者が遺言の無効を信じているだけでは、時効の進行を停止することはできません。例外として、法律上または事実上の特段の事情がある場合にのみ、時効の進行が停止される可能性があります。
まとめ
この記事では、遺留分に関する3つの時効について、それぞれ詳しく解説してきました。
遺留分侵害額請求権には時効があり、期限を過ぎてしまったら、遺留分を請求することができなくなってしまいます。
遺留分をめぐって争いになった場合にも、原則として時効は進行するため、いつが起算点になるのか、自身のケースで時効を中断できるのか、正しく把握し対処することが重要です。
遺留分の時効に関してお悩みやご不明点があるときには、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。対面だけでなく、お電話によるご相談もお受けしておりますので、お気軽にお問合せいただければと思います。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。