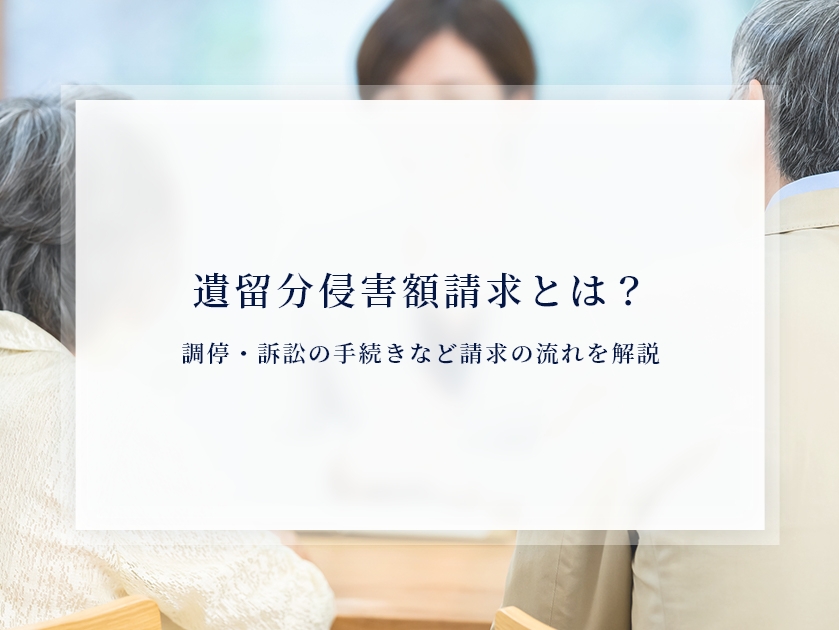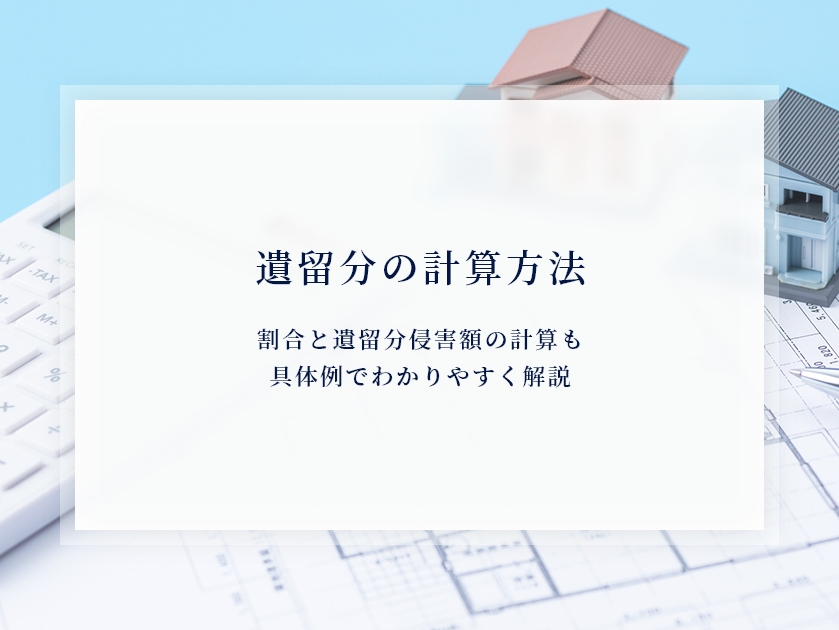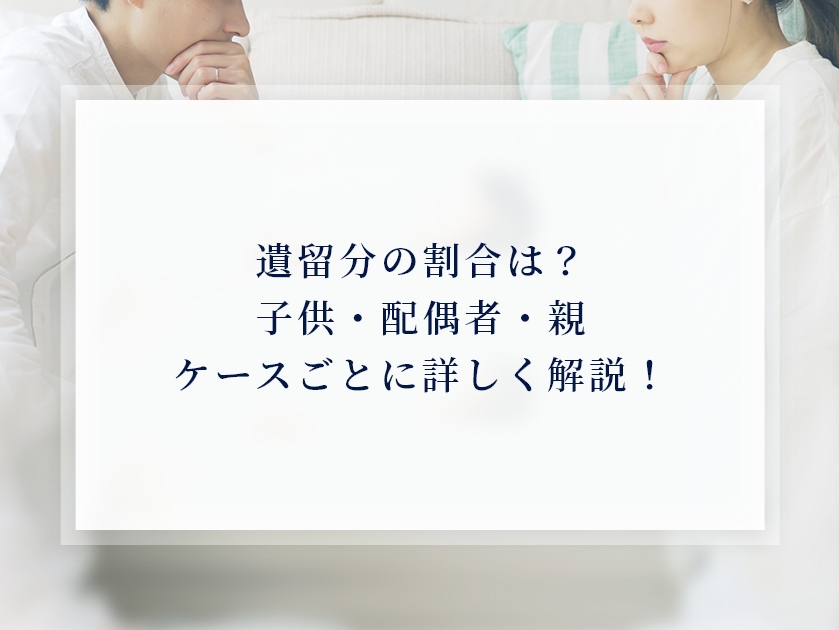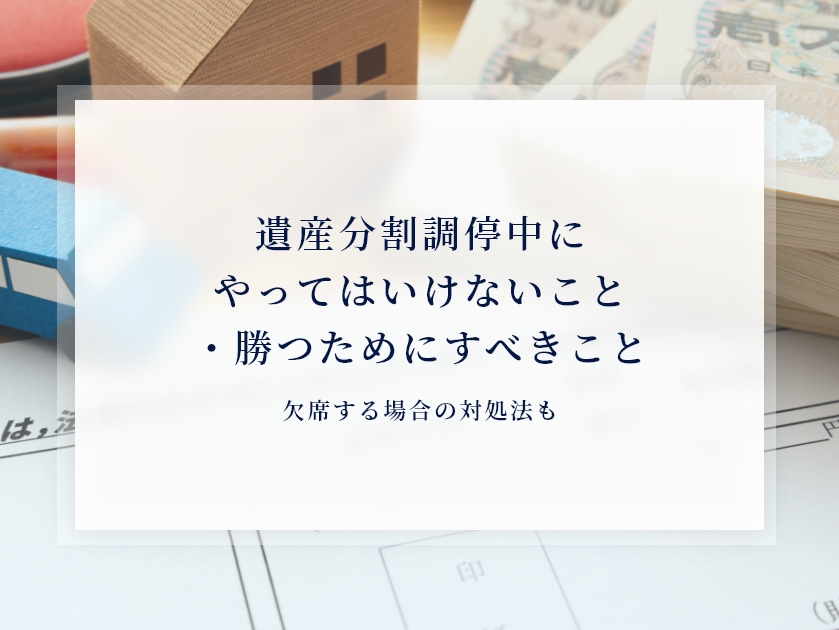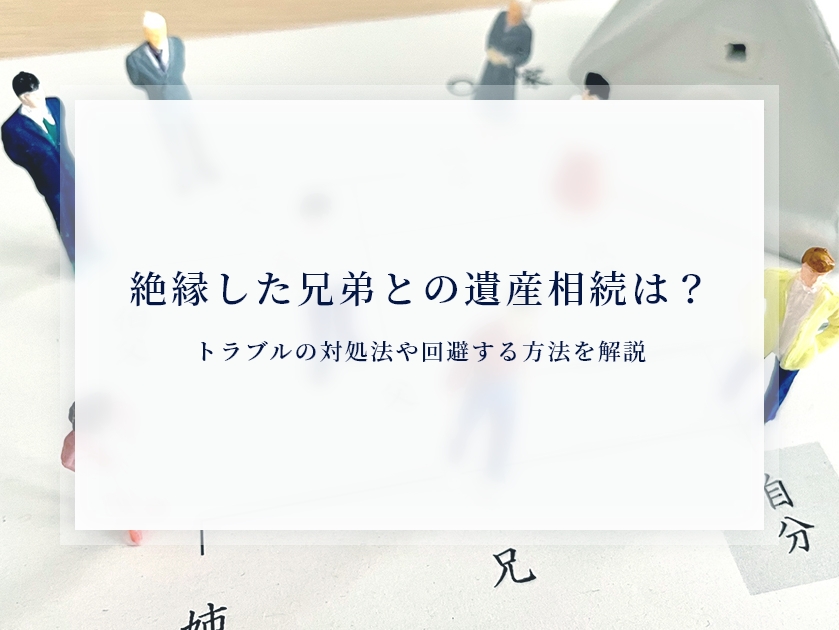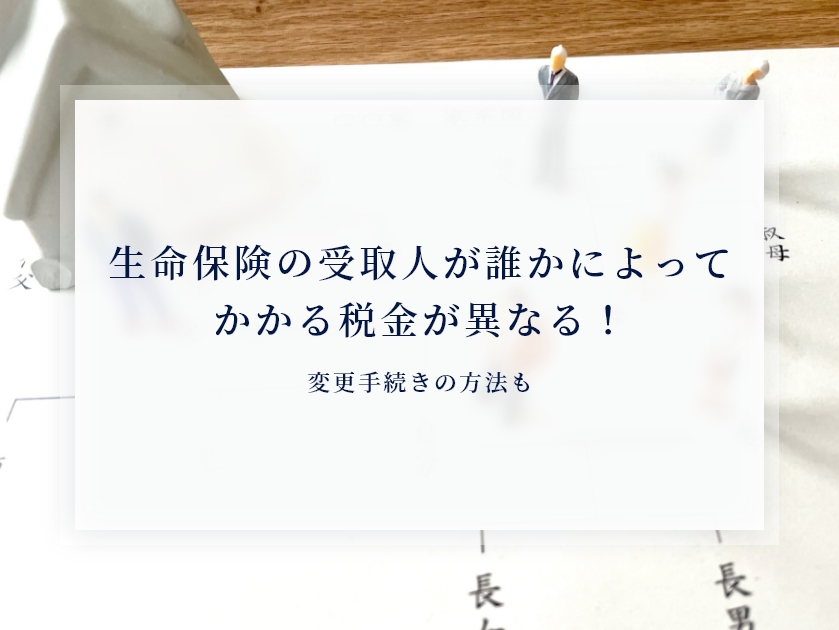遺留分【完全版】遺留分とは?遺産相続における遺留分を弁護士が解説
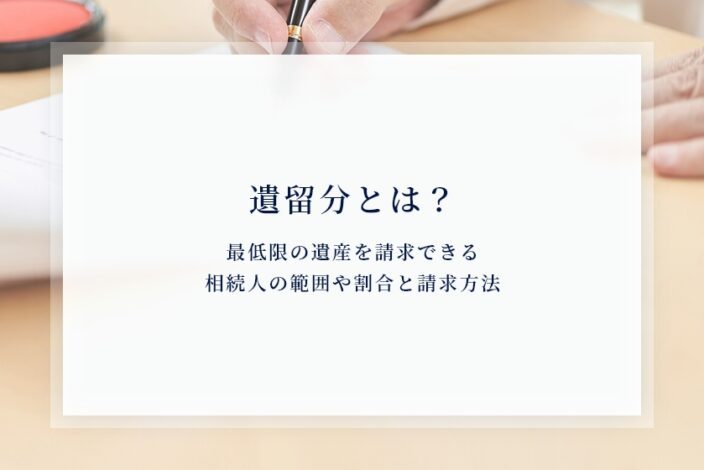
親や配偶者が亡くなり、遺言書を見てみると、想定外の内容が書かれていることも少なくありません。
他の兄弟たちに比べて自分がもらえる遺産が少ない、など納得できない遺産分割になってしまうこともあるかと思います。
このように、相続人にとって不公平な遺産分割がなされた場合に、ある程度公平なバランスを取るのが、「遺留分」です。
遺留分とは、遺言によっても侵すことのできない、特定の相続人に法律で保証された最低限の遺産の取得割合のことをいいます。
ですが、それがどういった場面で問題になり、どのように役立つのか、具体的なことまでは知らない、という方も少なくはないかと思います。
そこでこの記事では、遺留分とは何か、どういった場合に遺留分が認められるのかについて、弁護士がわかりやすく解説させていただきます。
遺留分についての正しい知識を得ることで、相続が発生した際に自分の権利を守ることができます。また、遺言を作成する際にも、遺留分を考慮することで、より公平で納得のいく遺産分割を行うことが可能になります。
本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。
目次
遺留分
遺産相続をしたことのない方には、「遺留分」という言葉はあまり馴染みのない言葉かもしれません。また、聞いたことはあっても、その具体的な内容は知らないという方も少なくないでしょう。
簡単に言いますと、遺留分とは「一定の相続人に対して法律上保障されている最低限の相続財産の取り分」です。
この遺留分について、争いが生じることがあります。
遺留分で争いになる場面
ではどういった場面で遺留分についてが問題になるのかというと、次のようなケースです。
- 特定の人に特定の遺産を与える旨の遺言がされた場合
- 特定の相続人にだけ多額の生前贈与をした場合
- 被相続人が相続分を指定したことによって、一部の共同相続人の遺留分が侵害された場合
- 被相続人が、以前自分が相続人となった遺産相続における相続分を譲渡し、その相続分を譲り受けた人が、被相続人についての遺産相続における相続人になった場合
- 被相続人が生命保険金の受取人に第三者を指定していた場合
例えば、被相続人に5人の子どもがいる場合に、遺言書に「すべての財産を二男Bだけに与える」と書かれていると、二男B以外の4人の子は遺産を一切受け取れないため、不公平感が生じるのが通常です。
あるいは、遺留分という制度そのものを知らなかった相続人が、遺産分割が終わった後に遺留分の存在を知り、「自分も本来であれば財産を受け取る権利があったのだ」と認識することもあるかもしれません。
こういった場合に、「本来なら自分にも一定の財産が与えられるべきだった」と親族間で争いが生じてしまうことも珍しくないのです。
そのため、相続人全員が遺留分という制度を正しく理解し、自分にどのような権利があるのかを事前に把握しておくことが重要です。
それでは以下で、遺産相続における遺留分について、詳しく見ていきましょう。
遺留分とは
(1)遺産相続の「遺留分」とは?
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して法律上保障されている最低限の相続財産の取り分のことです。
遺留分を取得することのできる権利を「遺留分権」といい、その権利を有する人のことを「遺留分権利者」といいます。
被相続人は、本来であれば自分の財産を自由に分配できます。ですが、特定の相続人だけに財産が集中すると、他の相続人が経済的に困ってしまう可能性があります。そのため、相続人の生活の安定や相続人同士の公平性を確保するため、最低限の遺産の取り分を保障する「遺留分」という制度が定められたのです。
具体的にどのように保障されるのかといいますと、相続人が自身の遺留分を侵害されたときに、侵害された分に相当するお金を請求することで、侵害された分を取り戻すことになります(遺留分侵害額請求)。
遺留分侵害額請求については、こちらの関連記事にて詳しく解説しておりますので合わせてご覧いただければと思います。
遺留分制度と法律
こうした遺留分制度については、民法第1042条以下に定められています。
遺留分の帰属及びその割合について:民法第1042条
遺留分を算定するための財産の価額について:民法第1043条~第1045条
遺留分侵害額の請求について:民法第1046条
受遺者又は受贈者の負担額について:民法第1047条
遺留分侵害額請求権の期間の制限について:民法第1048条
遺留分の放棄について:民法第1049条
本コラムで特に重要なのは、民法第1042条です。遺留分を請求できる「遺留分権利者」は誰なのかについては、民法第1042条に定められているため、後ほどこの条文を中心に解説させていただきます。
遺留分制度の意義・目的
さて、なぜこうした遺留分という制度が設けられているのかというと、以下のような意義・目的があると考えられています。
- 遺贈や贈与を受けなかった遺族の生活基盤を保障するため。
- 共同相続人間の公平な財産相続を図るため。
- 被相続人の財産形成に貢献した遺族の潜在的な持分を清算するため。
- 恣意的で不合理・不当な遺言から法定相続人の権利を守るため。
遺産を残す人の意思だけで財産を自由に分配できるようにしてしまうと、一部の相続人の生活が困窮したり、将来が不安定になったりする可能性があります。
本来、自分の財産を誰にどのように残すかは、本人の自由な意思が尊重されるべきです。しかし、もし財産を自由に分けることを全面的に認めてしまうと、例えば家族間で何らかのトラブルがあった場合、特定の相続人が遺産を一切受け取れず、生活に困ってしまうという状況になりかねません。
特に、配偶者や子どもなど、被相続人の財産に頼って生活してきた家族が、突然その支えを失ってしまうのは酷なことです。
そこで、このような相続人の経済的な保護や生活の安定を目的として、遺留分の制度が設けられました。
さらに、遺留分制度は、極端に偏りのある遺産分けを抑制し、家族間の公平感を保つことで、相続争いを未然に防ぐという役割も果たしています。
特定の相続人だけが多額の贈与を受けていたり、一部の相続人に偏った遺言がなされたりすると、「同じ相続人同士で、なぜここまで遺産に差があるの?」と不満が生じかねません。遺留分制度は、このような不公平を是正し、相続人間のバランスを保つ機能もあるのです。
このように、遺留分制度によって、被相続人の財産処分の自由と、被相続人の一定範囲の近親者の利益との調整を図ることとしているのです。
また、被相続人の財産は、相続人の協力や寄与があってこそ形成されたものであり、その貢献分は財産の中に「潜在的持分」として含まれているという考え方もあります。特に、日本の夫婦財産制度と深く関連して、「被相続人の財産形成への配偶者の協力を評価し、その貢献分を遺留分によって保障する」という、潜在的な持分の清算という意味での遺留分制度、とも考えられています。
(2)法定相続分と遺留分
ところで、「法律で保障されている最低限の取得分」と聞くと、「法定相続分のことか。」と思われるかもしれません。
たしかに同じもののように思えますが、「遺留分」と「法定相続分」は、似ているようで全く異なるものなのです。
「法定相続分」とは、民法で定められている、遺産を分ける際の基本的な割合のことです。遺言がない場合に、相続人間で遺産をどのように分けるべきかの基準となります。つまり、法定相続分は相続財産を分けるための原則的な指針にすぎず、「必ずこの割合で遺産を分割せよ」という強制力を持つわけではありません。
言い換えれば、遺言書によって「長男に全財産を与え、他の子には何も与えない」と割合を指定されたら、法定相続分よりも遺言による割合が優先されることになります。法定相続人にとって、法定相続分とは絶対的な保障とはならないのです。
一方で、前述の通り「遺留分」とは、兄弟姉妹を除く相続人について、最低限保証されるべき相続財産の割合を指します。
つまり、遺言によっても侵害できない、法律上保障された権利が遺留分なのです。
また、法定相続分の対象となる人は「法定相続人」ですが、遺留分の権利者となる人は「一部の法定相続人」と、範囲にも違いがあります。
適用に関しても違いがあり、法定相続分は遺言がない限り、原則としてその割合が当然に適用されます。
一方で遺留分は、遺留分権利者が自ら権利を行使しない限り、自然に適用されることはありません。
(3)遺留分の対象財産
次に、遺留分を請求するにあたって、どのような財産が対象となるのか確認しておきましょう。対象となる財産は、大きく分けて①遺贈する財産、②死因贈与する財産、③生前贈与した財産、の3つがあります。
①遺贈する財産
遺贈(いぞう)とは、遺言によって指定して特定の人へ財産を承継させることです。より詳しく見てみると、遺贈には相続分の指定、特定財産承継遺言(相続させる遺言)、包括遺贈、特定遺贈の4つがあります。
- 相続分の指定:法定相続分と異なる相続分で指定した遺言による相続
- 特定財産承継遺言:特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言による相続
- 包括遺贈:遺産の全部または一定の割合を示してする遺言による相続
- 特定遺贈:特定の遺産を指定して与える遺言による相続
こうした遺言による相続(遺贈)があると、それによって相続人の権利が侵害されることがあります。
②死因贈与する財産
死因贈与とは、被相続人の死亡によって効力を発する贈与契約のことです。被相続人の存命中に、被相続人と贈与を受ける人とで、贈与契約を結びます。
死因贈与によって受け取る財産についても、遺留分権が生じることになります。
③生前贈与した財産
生前贈与とは、被相続人が存命中に、相続人やその他の者に財産を贈与することです。生前贈与した財産についても、相続人の権利を侵害している分については遺留分権が生じることとなりますが、全ての生前贈与が対象となるわけではありません。
まず、相続人以外の人になされた生前贈与に関しては、相続開始前の1年間にしたものに限って、遺留分侵害額請求の対象となります(民法第1044条1項前段)。
相続人に対する生前贈与に関しては、相続開始前10年間にしたもので、かつ、「特別受益」に該当するものが、遺留分侵害額請求の対象になります(民法第1044条3項)。
(遺留分を算定するための財産の価額)
民法第1043条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。民法第1044条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
「特別受益」とは、一部の相続人が被相続人から遺贈や生前贈与によって受けた特別な利益のことです。代表的なものに、婚姻の持参金や支度金、不動産の購入資金などの生計資金などが挙げられます。こうした特別な利益については、相続人間の公平を図るため、「相続分の前渡し」とみなし遺留分の対象財産としているのです。
また、生前贈与する側と贈与を受ける側の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与については、相続開始1年前の日より前にした贈与であっても、遺留分の対象財産となります(民法第1044条1項後段)。
一方で、相続開始前10年間にした生前贈与であっても、「特別受益」に当たらない場合は遺留分の対象財産とはなりません。例えば、「被相続人が妻の実家から金融を受けていたことに加え、長年共に農業に従事し、財産の維持に協力した労に報いるために行われた妻への生前贈与は、生計の資本としての贈与ではないため特別受益にはならない」と判断された事例があります(長崎家庭裁判所島原支部昭和40年11月20日審判)。
個々のケースで判断に迷う場合は、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
死亡退職金や生命保険金は対象財産にはならない
死亡退職金や生命保険金などについては、遺留分の対象財産にはならないと考えられています。
例えば死亡退職金は、判例・通説によれば、「遺族の生活保障を目的とする受給者固有の権利」とされています。そのため、そもそも相続財産とはならず、遺留分の対象財産にもならないのです。
生命保険金に関しても、原則として「受取人固有の権利」とされるため、遺留分の対象財産にはなりません。ですが例外的に、共同相続人の一人が生命保険金の受取人で、金額が非常に大きく、他の相続人との間に到底是認することができないほどに著しい不公平があると認められる場合には、特別受益に当たる、と判断された裁判例もあります(最高裁判所平成16年10月29日決定)。
遺留分権利者の範囲
それでは続いて、遺留分を請求できるのは具体的に誰なのかを見ていきましょう。
遺留分を請求できる人とできない人については、民法で明確に定められています。
遺留分を請求できる相続人のことを「遺留分権利者」といいますが、この遺留分権利者の範囲は、民法第1042条1項に「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。」と規定されています。
ですので、具体的な遺留分権利者はこのようになります。
- 配偶者
- 子や孫などの直系卑属
- 親や祖父母などの直系尊属
なお、遺留分権利者であるか否かについては、相続開始時が基準となります。
(1)配偶者と直系卑属
被相続人の配偶者は常に法定相続人となるため、遺留分権利者となります。
被相続人の子や孫などの直系卑属に関しても、第一順位の法定相続人であるため、遺留分権利者となります。
「被相続人の子」には、実子だけでなく養子も含まれます。また、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子(非嫡出子)に関しても、認知することで法律上の父子関係が生じた場合は相続権を持つことになるため、遺留分権利者にもなります。
配偶者や直系卑属(子や孫)が遺留分権利者となる場合の遺留分の割合ですが、遺産の2分の1とされています(民法第1042条1項2号)。
(遺留分の帰属及びその割合)
民法第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
二 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
なお、被相続人の孫が遺留分権利者になるかは、ケースバイケースです。
原則として、孫が遺留分権利者になるのは孫が法定相続人であるときです。つまり、被相続人の子が亡くなっており、代襲相続(民法第887条2項)によって孫が相続人になった場合は、孫が遺留分権利者となります。
胎児に関してですが、「相続については既に生まれたものとみなす」とされています(民法第886条)。そして、「私権の享有は、出生に始まる。」とあるため(民法第3条1項)、胎児は出生して初めて人格を取得するものと考えられています。
(相続に関する胎児の権利能力)
民法第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
この点に関して判例は、「胎児の間は相続人ではないが、生きて出生した場合には相続開始時に遡って相続人となる」という「停止条件説」の立場を取っています(大判大正6年5月18日)。
つまり、胎児は出生して初めて人格を取得するため、出生後に遺留分侵害額請求権を現実に行使できることとなるのです。
遺留分の計算方法
実際に遺留分としてどれくらいの遺産を取得できるのか、金額を計算するには、基本的に次の手順で行います。
ここでは、配偶者と子1人が相続人である場合の、配偶者の遺留分を例に見てみましょう。
まず、相続財産の総額を計算します。
相続財産には、遺贈によって得た財産に加え、亡くなる1年前までの生前贈与、相続開始前10年以内の特別受益も含まれます。被相続人の債務(借金など)は、この総額から差し引きます。
例えば、被相続人が残した財産が1,000万円、生前贈与が200万円、債務が100万円の場合、相続財産の総額は「1,000万円 + 200万円 – 100万円 = 1,100万円」となります。
続いて、算出した財産の総額に、各相続人の遺留分割合を乗算し、遺留分の金額を計算します。
例えば、配偶者の遺留分は「2分の1」、法定相続分は「2分の1」ですから、「1,100万円 × 配偶者の遺留分割合1/2 × 配偶者の法定相続分1/2 = 275万円」ということになります。
遺留分の計算については、こちらの関連記事で詳しく解説しております。ぜひご参照ください。
(2)直系尊属
なお、直系尊属である親や祖父母は、常に遺留分権利者になるわけではありません。
前述の通り、遺留分権利者の前提は「法定相続人」であることです。直系尊属である親や祖父母が法定相続人となるケースは、第一順位の法定相続人である子や孫がいない場合に限られます(民法第889条1項1号)。ですので、遺留分の請求権に関しても、子や孫がいない場合に限り、認められることになるのです。
親や祖父母などの直系尊属のみが相続人である場合、遺留分は遺産の3分の1とされています(民法第1042条1項2号)。
なぜ直系尊属のみが相続人の場合は少ないのかというと、遺留分制度の目的が「遺留分権利者の生活保障」であるためです。親は配偶者や子に比べて、被相続人の財産に依存して生活しているとは限らないため、配偶者や子よりも「被相続人の遺産による生活保障」の必要性が弱い、と考えられており、「3分の1」という割合になっています。
なお、遺留分の割合については、下記記事でより詳しく解説しております。ぜひ本記事とあわせてご一読いただければと思います。
(3)兄弟は法定相続人だが遺留分の権利はなし
一方で、民法第1042条1項は「兄弟姉妹以外の相続人は」と規定しているため、被相続人の兄弟姉妹には、遺留分は認められません。そのため、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合の代襲相続人(甥や姪)にも遺留分は認められません。
これは、遺留分の制度が意図するものが、「被相続人の死亡後に、配偶者や子ども、親といった生活基盤を失う可能性がある家族の保護」であるからです。兄弟姉妹は、被相続人の配偶者や子、親とは異なり、被相続人の生活を直接支えていたり、その経済的な依存度が高いわけではありません。そのため、遺留分として法律で最低限保障する必要まではない、と考えられているのです。
(4)遺留分権利者でなくなる場合
遺留分権利者であるためには、前提として「法定相続人」でなければなりません。
そのため、以下のような場合には、相続権そのものがないことから、遺留分権利者でもなくなるとされています。
- 相続人全員による遺産分割協議が行われた場合
- 相続放棄した人
- 相続欠格者(民法第891条)
- 相続廃除された人(民法第892条)
- 包括受遺者
- 胎児
- 遺留分放棄した人
①相続人全員による遺産分割協議が行われた場合
遺産分割協議による遺産相続は、相続人全員が参加し、全員が合意することで成立します。この場合、その合意した内容を後から蒸し返すことは原則としてできません。
②相続放棄した人
相続放棄した場合、初めから相続人ではなかったものとみなされるため、遺産相続する権利を失います(民法第939条)。遺産相続する権利がないのですから、遺留分を請求する権利も失うことになります。
(相続の放棄の効力)
民法第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
以下でご紹介する③相続欠格者と④相続廃除された人とは異なり、相続放棄の場合は代襲相続が認められないため、相続放棄した人に子がいても子が遺留分権利者になることはありません。
③相続欠格者
相続欠格者(民法第891条)とは、「被相続人や他の相続人を殺した、殺そうとした、遺言を偽造した」などの重大な不正行為をしたことによって、相続権を失った人を意味します。相続欠格者についても、遺産相続する権利を失うため、遺留分を請求する権利も失います。
ただし、相続欠格者に子などの代襲相続人がいる場合、代襲相続人に関しては遺留分が認められます(民法第1042条2項、同第901条)。
④相続廃除された人
相続廃除された人とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行があった場合に、被相続人の意思により、家庭裁判所の手続きを経て相続権を失った人のことです(民法第892条)。
(推定相続人の廃除)
民法第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
相続欠格者と同様に、相続廃除された人も遺留分権利者ではなくなりますが、この場合も代襲相続が認められているため、代襲相続人は遺留分権利者となります。
⑤包括受遺者
包括受遺者とは、遺産の全部または一定の割合による相続を受けた人のことです。包括受遺者は「相続人と同一の権利義務を有する」とされていますが(民法第990条)、相続人そのものではありません。
(包括受遺者の権利義務)
民法第990条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
そのため、「相続人の一部のみに認められる遺留分」の権利は、相続人ではない包括受遺者に関しては認められない、という考え方が通説となっています。
⑥胎児
胎児に関しては、「相続については既に生まれたものとみなす」とされており(民法第886条)、生きて出生することで遺留分権利者になる、と前述いたしました。そのため、まだ出生していない胎児である間は、遺留分権利者とはならないのです。
⑦遺留分放棄した人
遺留分を侵害されたからといって、相続人は必ず遺留分の請求(遺留分侵害額請求)をしなければならない、というものではありません。相続人は、遺留分を請求する権利を放棄することもできます。
そのため、遺留分を放棄した人に関しても、遺留分権利者ではなくなるのです。
遺留分の放棄に関しては、こちらの関連記事をご覧いただければと思います。
遺留分と相続税
遺留分侵害額請求が行われ、遺留分侵害額が確定した場合、相続税の課税関係に影響が生じます。遺留分の権利者が取得する金銭債権は、相続によって取得したものとみなされるため、相続税の課税対象となるからです。
そこで、遺留分と税金の関係についても確認しておきましょう。
遺留分も相続税の課税対象になる
相続税は、被相続人から相続または遺贈によって財産を受け取った場合に課税されます。遺留分に関しても、これは相続財産の一部とみなされるため、相続税の課税対象となります。
ただし、返還された額を含めた遺産の総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、相続税はかかりません。
相続税の申告方法ですが、遺留分の金額が確定するタイミングによって、異なる対応が必要です。以下で簡単にご説明いたします。
①相続税申告期限前に額が確定した場合
相続税申告前に遺留分の額が確定した場合は、遺留分を請求した人と請求された人は、それぞれ受け取った遺産の額に応じて相続税申告を行う必要があります。
遺留分侵害額請求した人は、受け取った遺留分に対する相続税を申告します。
遺留分侵害額請求された人は、遺留分を支払った後に、残った分で相続税を申告します。
②相続税申告期限後に額が確定した場合
遺留分申告期限までに遺留分の額が確定しなかった場合は、一度遺留分の清算をしていないままで相続税申告を行います。つまり、遺留分を受け取る側は支払うべき税金を支払っていない一方で、遺留分を支払う側は相続税を多く払いすぎている状態となっています。
ですので、遺留分の額が確定した際には、納め過ぎた税金や不足した税金を調整するための手続きが必要になります
具体的には、遺留分を請求した人は「修正申告」または「期限後申告」を行い、遺留分を請求された人は「更生の請求」を行います。
ただし、税務署にとっては納められる相続税の総額が変わるわけではありませんので、必ずしも税務署に対して手続きをしなければならないわけではありません。そのため、当事者間で精算してしまうことも可能です。
詳しい手続き方法については、弁護士などの専門家にご相談ください。
遺留分に関するQ&A
Q1.遺留分とは何ですか?
A: 遺留分は、法律によって保護された最低限度の相続分のことです。これは、被相続人の配偶者、子や孫といった直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属に保障されている権利です。被相続人が遺言で遺産の分配を決めても、遺留分は侵害されないように法律で守られているのです。
Q2.被相続人の兄弟にも遺留分はありますか?
A: 兄弟姉妹には原則として遺留分はありません。被相続人に子や両親、配偶者がいない場合に、兄弟姉妹が法定相続人となることがありますが、この場合でも遺留分の権利は発生しません。
Q3.遺言書に「遺留分はなし」と書いておけば、遺留分をなくせますか?
A. いいえ、遺言書に「遺留分はなし」と書いてあったとしても、それだけで遺留分をなくすことはできません。遺留分という制度は、法律で相続人に最低限の相続財産を保障するためのものであり、遺言者の意思で勝手になくすことは、原則として認められていないのです。
ただし、遺留分を持つ相続人自身が、生前に家庭裁判所で正式な手続きを経て遺留分を放棄した場合など、例外的に遺留分をなくすことが可能なケースもあります。
遺言書を作成する際は、この点について注意しておく必要があります。
まとめ
本記事では、遺留分について弁護士が解説させていただきました。
現実で相続が発生すると、遺言や生前贈与の内容が偏っていたり、相続人間で意見が衝突したりすることで、遺留分をめぐるトラブルが起こるケースも少なくありません。
また、遺留分の制度自体をよく知らなかったために、本来取得できたはずの財産を受け取れず、後から問題が発覚することもあります。
特に、相続人が遺留分の制度をよく知らないまま遺産分割を終えてしまうと、後でその権利に気づいたときに納得できず、親族関係が悪化してしまいかねません。
こうした問題を防ぐためには、遺留分という制度の内容を正しく理解しておくことが重要です。
ご自身のケースで遺留分がどのように関係してくるのか、不安や疑問を感じたら、一人で抱え込まずに、ぜひお早めに弁護士へご相談ください。専門家のサポートを受けることで、相続人同士の対立を最小限に抑え、円満な相続を目指すことが期待できます。
当法律事務所の弁護士による法律相談は、初回無料となっております。対面でのご相談だけでなく、お電話によるご相談もお受けしておりますので、お気軽にお問合せいただければと思います。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。