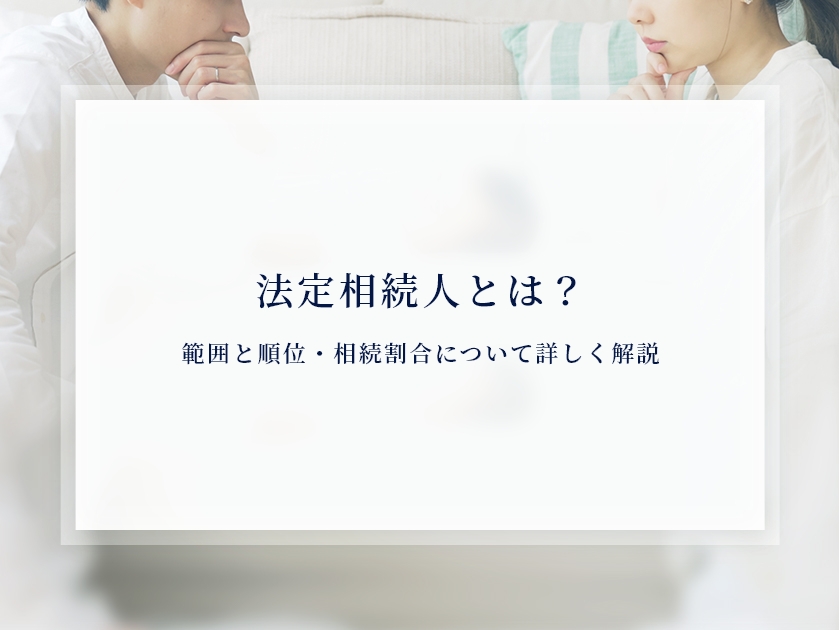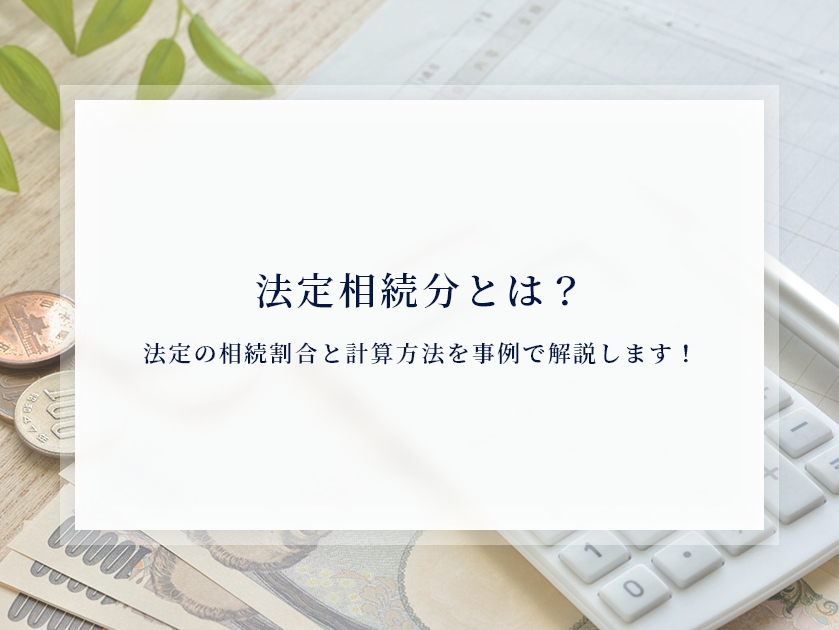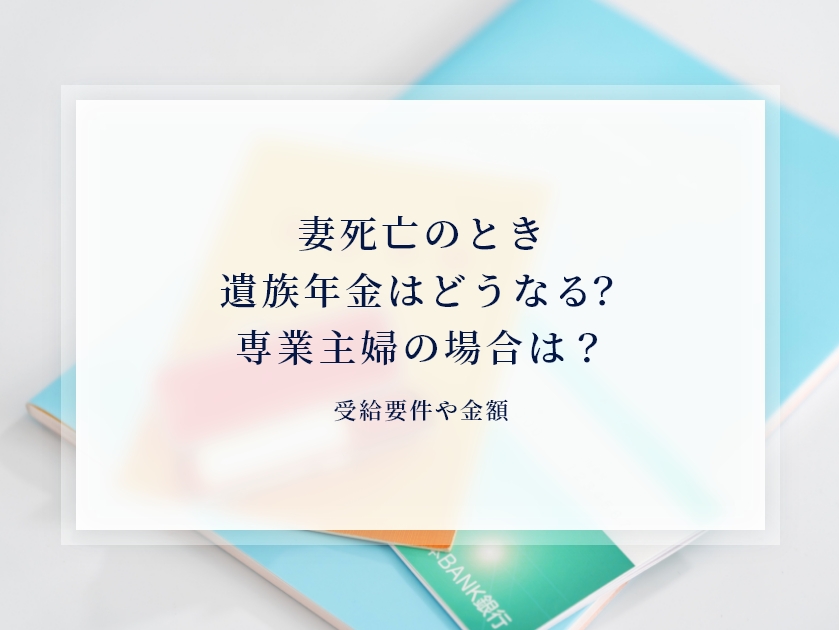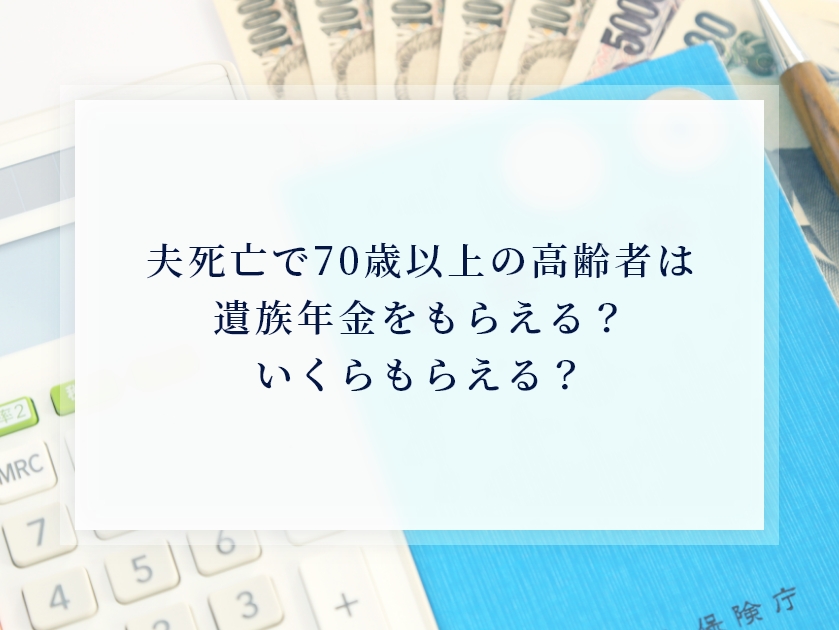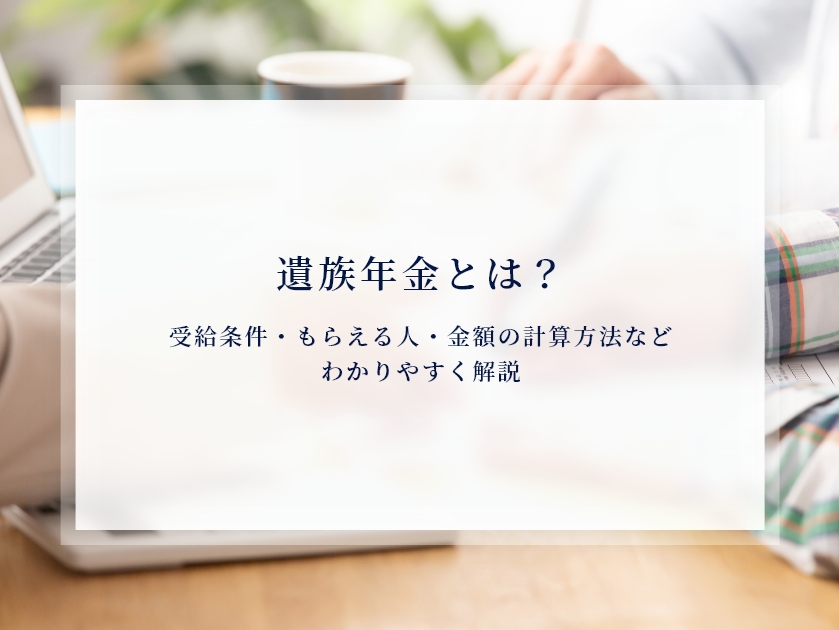被相続人とは|相続人との違いとは?被相続人とは誰か、意味や続柄も解説
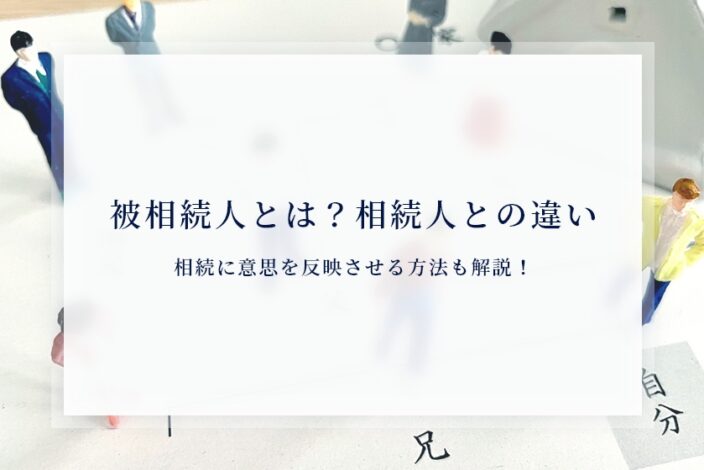
相続には、さまざまな関係者が登場します。その中でも重要な一人が、「被相続人」です。
ところで、この被相続人とは、厳密には誰のことを意味するのでしょうか。
相続といえば「相続人」もいますが、被相続人とはどういった違いがあるのでしょうか。
この記事では、相続の登場人物である「被相続人」とは誰なのか、「相続人」との違いを主軸に、弁護士が解説させていただきます。
被相続人が誰であるかが、相続人にとってどういった影響を及ぼすのか、といったことについても、具体的にご説明させていただきます。
遺産相続を正しく理解するためには、当事者となる被相続人・相続人について理解しておくことが重要です。
相続の疑問や不安が、本記事で少しでも解消できましたら幸いです。
目次
被相続人とは
1.被相続人とは誰?
被相続人とは、亡くなった人で、自身の財産を相続される人のことをいいます。
遺産相続は、この被相続人の死亡によって始まります(民法第882条)。
(相続開始の原因)
民法第882条 相続は、死亡によって開始する。
被相続人の死亡によって相続が開始するのは、財産の処分といった権利や義務の主体となる資格(権利能力)が認められるのは、その人が生きている間だけという原則に基づいて、死亡した人(被相続人)はその権利能力を失うことになるので、別の人(相続人)にその財産上の地位の承継させる必要があるからです。
遺産相続とは、被相続人の死亡によって開始する、相続人への財産上の地位の移転なのです。
2.「被相続人」の意味
さて、「被相続人」の言葉の意味について、もう少し詳しく見ておきましょう。
被相続人の「被」とは
「被相続人」の「被」という漢字には、「何らかの作用を受ける」「~される」という受け身の意味があります。
例えば、「被害者」「被告」などにも同じように使われており、何かの行為や作用を受ける側の人を表す際に用いられる漢字です。これを「相続人」という言葉に当てはめて考えると、「相続される人」、すなわち「自分が持っている財産を誰か他の人に相続される人」という意味になります。
このように、被相続人という言葉は、自らの財産を他の誰かに引き渡すという、受動的な立場にあることを意味しているのです。
3.被相続人の死亡と遺産相続
そして、被相続人は、自分の財産を相続人に引き継がせる権利と義務を持っています。
被相続人は、自分が生きている間、自分自身で自由に財産を使ったり処分したりすることができますが、亡くなった時点で、その管理・処分の権利は受け継ぐ人(=相続人)へと移ることになるのです。
被相続人が亡くなって相続が始まると、被相続人がそれまでに所有していた財産や負債などがすべて相続の対象となります。現金や預貯金、自宅や土地などの不動産、株式や投資信託などの有価証券といったプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどマイナスの財産も含め、被相続人に関するあらゆる権利や義務が移転されることになるのです。
相続人とは
次に、被相続人と並んで遺産相続の当事者となる「相続人」について確認しておきましょう。
1.相続人と被相続人の違い
相続人とは、被相続人が死亡した後、被相続人が遺した相続財産を受け継ぐ権利を持つ人を意味します。
つまり、被相続人と相続人の大きな違いは、被相続人が遺産を「残す側」、相続人が遺産を「受け継ぐ側」であるということです。
この相続人ですが、無制限に誰もがなれるというわけではなく、その範囲や相続人になることのできる優先順位などが、民法によって定められています。
ところで、相続人には「法定相続人」と、「指定相続人」がいます。
法定相続人とは、法律(民法)によって相続を受ける権利が認められている人のことをいいます。
具体的には、亡くなった人(被相続人)の配偶者、子どもや孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹などが法定相続人に当たります。
遺産分割協議や遺言書がない場合には、法定相続人が法律で決められた相続分に従って財産を引き継ぐことになるのです。
一方、指定相続人とは、遺言によって特別に相続人として指定された人のことをいいます。
通常、相続人というのは法律で定められていますが、遺言書を作成することで、本来相続人ではない人を特別に相続人として指定することが可能になります。
例えば、法律上の配偶者ではない内縁関係のパートナーや、血縁関係のない友人、お世話になった第三者や団体などを指定相続人とすることで、被相続人は自分の財産を渡すことができるようになるのです。
指定相続人として遺言に記載された人は、あくまでも遺言の内容に従って財産を受け取る立場になります。そのため、法律で最初から相続人と定められている人とは異なり、最低限の財産の取り分(遺留分)を請求する権利などはありません。
また、指定相続人への財産の引き継ぎは「遺贈」という形で行われます。これは一般的な相続とは区別されるため、財産の種類や価値によっては、相続税などの課税が発生する可能性があります。
通常の法定相続人とは権利や立場が異なることを理解しておくことが重要です。
なお、指定相続人に関しては個々の遺言によって内容が異なりますので、この記事の「相続人」は法律で一律に定められている「法定相続人」を主に意味しています。
2.遺産相続では被相続人との続柄が重要
それでは、被相続人と相続人の関係性について、より詳しく見ていきましょう。
2-1.相続人の優先順位は続柄によって決まる
法定相続人の相続順位は、被相続人との関係性、つまり「続柄(つづきがら)」によって決まります。
続柄とは、主に家族関係や親族関係において、特定の人と他の人との間にどのような関係があるかを表す言葉です。戸籍謄本や住民票に「父」や「母」などと続柄が記載されているため、ほとんどの人が一度は目にしているのではないでしょうか。
この続柄に関して、被相続人を中心に見てみましょう。
被相続人の続柄は、被相続人からみて「本人」です。被相続人の配偶者の続柄は、配偶者が夫であれば「夫」、妻であれば「妻」となります。被相続人の親の続柄は「父」、「母」と記されることになります。
続柄という言葉自体を意識する必要はありませんが、遺産相続においては被相続人との関係性で相続の内容が変わってくるため、実は重要な概念なのです。
具体的には、被相続人との続柄によって、法定相続人の相続順位は下の表の通り変わってきます。
|
相続順位 |
法定相続人の続柄 |
|
常に相続人 |
配偶者(民法第890条) |
|
第1順位 |
子や孫など直系卑属(民法第887条1項・2項) |
|
第2順位 |
親や祖父母など直系尊属(民法第889条1項1号) |
|
第3順位 |
兄弟姉妹(民法第889条1項2号) |
原則として、被相続人の死亡時に婚姻関係にあった配偶者は、常に法定相続人となります(民法第890条)。
配偶者以外の法定相続人については、法律によって定められた順位で、相続する権利が与えられることになります(民法第887条・同第889条)。
なお、自分より順位の高い人がいる場合は、まだ自分の順位が回ってこないため、法定相続人になれません。
2-2.相続の割合も続柄で決まる
そして、法定相続人がどれだけの割合で遺産を受け取ることができるのかという「相続の割合」についても、被相続人との続柄で決まることになっています(民法第900条)。
(法定相続分)
民法第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
例えば、配偶者と3人の子供の合わせて4人が相続人だとしましょう。
配偶者は、相続分が「2分の1」と決められていますから、被相続人の遺産の半分を受け取ることができます(民法第900条1号)。残った半分の遺産については、3人の子供で分けることになります。「子供」の相続分が2分の1で、それを3人で割るわけですから、子供1人につき遺産の6分の1を受け取ることになります。
このように、被相続人との続柄によって、その相続人が受け取ることのできる遺産の割合が変わるのです。
3.被相続人の財産を相続できない人
ここまでは、被相続人の財産を受け継ぐ相続人について確認してきました。
一方で、被相続人と親しくても相続人とはならない人や、相続人の資格を失う人もいます。以下で見ていきましょう。
3-1.法定相続人に含まれない人
遺言によって相続人を指定する場合を除き、原則として相続できる人は法定相続人に限られます。そのため、被相続人と親しい間柄であっても、そもそも民法が法定相続人として想定していない人は、法定相続人として遺産を受け取ることはできません。
例えば、常に法定相続人となる被相続人の「配偶者」ですが、法律は「被相続人の死亡時に法律上の婚姻関係にあった人」を意味しています。ですので、被相続人の死亡時に既に婚姻関係が終了している元配偶者や、法律上の婚姻関係にない内縁の夫や妻、愛人などは、法定相続人にはならないのです。
ただし、遺言で「内縁の妻に預貯金500万円を相続させる。」など指定があった場合は、法定相続人にはなれない人も、遺言によって指定された相続人(指定相続人)になる可能性があります。
ですので、法定相続人に含まれない人に遺産を残したい場合、遺言で指定したり、養子にしたり、正式に認知するなどの方法を検討する必要があります。
3-2.相続権を失った人
法定相続人や指定相続人であっても、相続権を失うことがあります。相続権を失った人は、被相続人の財産を承継することができなくなります。
具体的には、①欠格事由に該当した人(民法第891条)、②相続廃除となった人(民法第892条)、③相続放棄をした人(民法第915条1項)。、の3つの場合が考えられます。
①欠格事由に該当した人とは、被相続人や他の共同相続人に対して、加害行為や不正行為をしたことによって相続権を失った人のことです。
具体的には、次の行為をした人は、相続人としての資格を失うことになります。
- 被相続人や他の相続人を故意に殺害し、または殺害しようとした場合
- 被相続人が殺害されたことを知っていながら、故意に告訴や告発をしなかった場合
- 被相続人に対して詐欺や脅迫を用いて、遺言の作成、撤回、取り消し、変更するのを妨げた場合
- 被相続人に対して詐欺や脅迫を用いて、遺言を作成、撤回、取り消し、変更させた場合
- 被相続人の遺言を不正に妨害、偽造、変造、隠匿、または破棄した場合
②相続廃除となった人とは、次の行為をしたことによって、被相続人が家庭裁判所に相続人から廃除するよう請求し、これが認められて相続権を失った人のことです。
- 被相続人を虐待した
- 被相続人に重大な侮辱行為をした
- その他著しい非行があった
被相続人の生前に家庭裁判所に請求するか、遺言書で廃除の意思を示しておくことで、家庭裁判所が推定相続人について審査を行います。相続廃除が認められると、推定相続人は相続する権利を失うことになるのです。
③相続放棄をした人とは、相続人自ら相続権を放棄して相続人ではなくなった人のことです。相続放棄する人は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述という手続きを行い、相続権を放棄します。相続放棄をすると、最初から相続権がなかったものとみなされるので、遺産を受け取ることができなくなります。
被相続人と遺産相続
ところで、被相続人は相続開始時には亡くなっているため、その後の実際の相続手続きには関与できないと思われるかもしれません。
ですが、生前にきちんと対策しておけば、被相続人の意思を死後も相続に反映させることは可能です。
被相続人の意思を反映させる方法としては、主に以下の4つの方法があります。
①遺言書の作成
最も一般的な方法は、遺言書を作成しておき、誰にどの財産をどれくらい相続させるかを指定しておく方法です。
遺言書を活用することで、具体的には次のようなメリットがあります。
- 法定相続分以外の割合での相続:遺言がない場合は、法律で定められた割合(法定相続分)での相続が行われますが、遺言があれば、法定相続分以外の割合で遺産を相続させることが可能になります。ある特定の家族や親族に、他の相続人よりも多くの遺産を受け継がせたいときなどには、遺言書が役立ちます。
- 法定相続人外への遺贈:長く親しくしてきた友人や、特定の団体、研究機関など、法定相続人でない人に遺産を遺したい場合に、遺言書に指定しておくことで、法定相続人以外への遺贈が可能となります。
- 遺産内容の指定:相続人で全ての遺産を均等に分配させるのではなく、「家については相続人Aに、宝飾品は全て相続人Bに。」といったように、特定の遺産を特定の人に遺贈することを指定できます。
遺言書の大きなメリットは、こうした具体的な被相続人の希望や意向を、正確に反映させることができる点です。さらに、遺言書が法的にも適切に作成されていると、被相続人が亡くなった後、家族間や相続人間でのトラブルを防ぐことが期待できます。
遺言書の書き方などは、被相続人の意思を正確に形にするため、弁護士などの法律の専門家からアドバイスを受けることがお勧めです。
②生前贈与
生前贈与とは、被相続人が生きている間に、特定の人へ自分の財産を「あげる」契約のことです。法定相続人以外の人にも確実に財産を渡したい場合や、あらかじめ財産を贈与して死後の相続手続きをシンプルにしたい場合などに、生前贈与が活用されます。
生前贈与をすると、その財産の所有権は即時に移転し、被相続人の死亡後の相続財産からは除外されます。
なお、莫大な相続税を回避するために生前贈与が利用されることもありますが、生前贈与でも贈与額が一定を超えると贈与税が発生するため、国の控除や減税制度を利用して、うまく生前贈与を活用することが重要です。
相続税申告の際に予期せぬトラブルが生じることも多いため、生前贈与の際には、弁護士や税理士などの税法の知識を持った専門家に相談すると良いでしょう。
③家族信託の活用
家族信託とは、自分の財産を家族や信頼できる人に託して、管理や運用をしてもらう制度のことです。相続において家族信託を活用する場合、財産管理を委託する被相続人が委託者となり、財産を預かる人が受託者となります。被相続人は、財産を管理してもらうことで財産の利益を受けることになるため、委託者であると同時に受益者となるのが通常です。
この信託契約では、財産の管理・運用方法や、被相続人が亡くなった後の財産の分配方法をあらかじめ細かく定めることができるため、被相続人の意思を反映した柔軟な財産承継が可能です。
家族信託の大きなメリットは、遺言よりも柔軟に財産の承継や管理を設定できる点でしょう。遺言は、基本的に遺産分割の方法を指定するだけのものであり、被相続人が亡くなった後に効力を発揮します。一方、家族信託では、被相続人が生前に設定することで、生前の財産管理から死後の財産承継までを一貫してコントロールできるため、より広範な管理が可能です。
さらに、信託契約により、被相続人(委託者)が亡くなった後、次の相続人(例えば子供)を受益者にし、子供の後さらに孫を受益者に指定するなど、代々家族に財産を受け継ぐ仕組みを作ることができ、長期にわたって資産を保全しながら、被相続人の意思を実現し続けることができるのです。
④相続廃除
相続人の資格を失う場合について前述した際にも出てきた「相続廃除」も、被相続人の意思を反映させる方法の一つです。
自分を虐待した人や、侮辱行為をしてきた人に対して、自分が築き上げた財産を喜んで渡す、という人はいないでしょう。虐待や侮辱行為や非行といった特定の行為があることが条件とはなりますが、被相続人が財産を渡したくない人を相続人から廃除できる制度なので、被相続人の「この人には遺産を遺したくない」という意思を反映させられます。
なお、相続廃除の請求手続きは、被相続人が生前に自ら行うもので、被相続人が亡くなった後に他の家族や相続人が代わりに請求することは認められていません。
相続廃除の請求を成功させるためには、不適切な行為の事実やその影響をしっかりと証明する必要がありますので、弁護士などの専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
被相続人に関するQ&A
Q1.被相続人とはどういう人ですか?
A:被相続人とは、亡くなって財産を残した人のことです。相続が発生するときの財産の元の持ち主であり、その財産を相続人に引き継ぐ人のことを指します。
Q2.相続人と被相続人の違いは何ですか?
A: 相続人とは、被相続人(亡くなった人)の財産を引き継ぐ権利を持つ人のことをいいます。これに対して、被相続人とは財産を残して亡くなった本人のことを意味しています。相続人と被相続人は、財産を引き継ぐ側(相続人)と、財産を引き継がせる側(被相続人)という立場の違いがあるのです。
Q3.被相続人が外国籍であった場合、日本の相続法は適用されますか?
A:相続に関しては、被相続人の最後の住所があった国の法律が原則として適用されます。したがって、被相続人が外国籍であっても、最後の住所が日本であれば、日本の相続法が適用されることになります。
まとめ
本記事では、「被相続人」の意味や役割について、対になる「相続人」との関係性もまじえながら、弁護士が解説させていただきました。
被相続人とは、相続において財産を譲り渡す立場にある、亡くなった人のことを指します。
相続が開始するときには、被相続人は亡くなっているため、実際の相続手続きに被相続人はそこまで影響を与えられない、と思っている人もいるかもしれません。
ですが、本記事でご紹介した通り、生前のうちに被相続人の意思を反映させる方法はあります。遺言書の作成や家族信託契約などを適切に行うことができれば、被相続人の意思は尊重され、被相続人の希望通りの遺産分割が実行されることでしょう。
相続に関する手続きや法律は複雑であり、性格な法的知識がなければ、思わぬ問題が発生することもあります。
弁護士法人あおい法律事務所にご相談いただけましたら、弁護士が依頼者の状況に合わせた適切なサポートを行い、円滑な相続手続きをフォローいたします。
まずはお気軽に、初回無料の法律相談をご利用ください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。