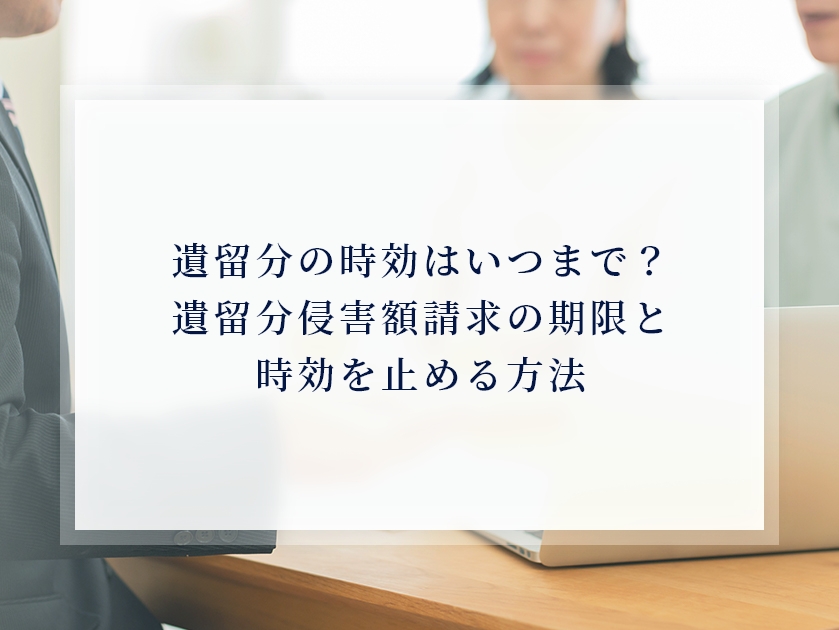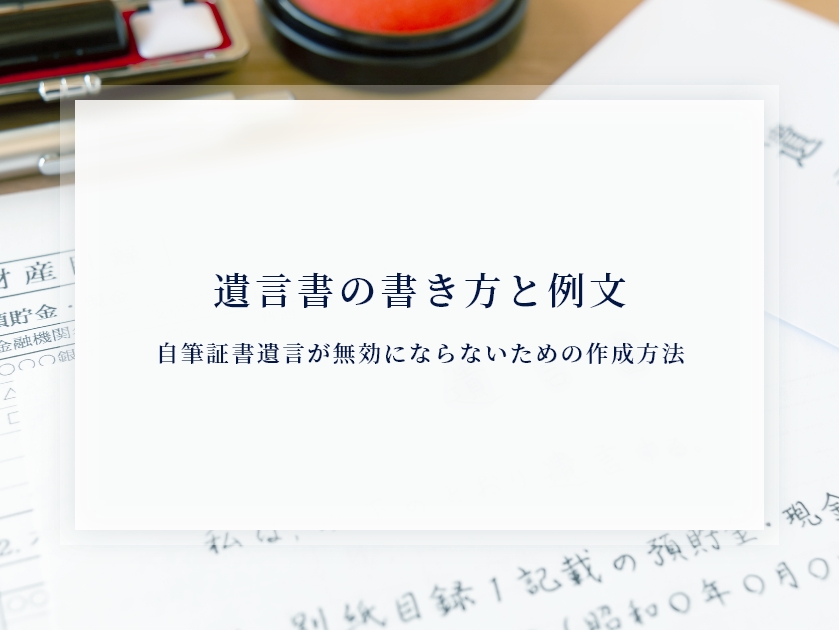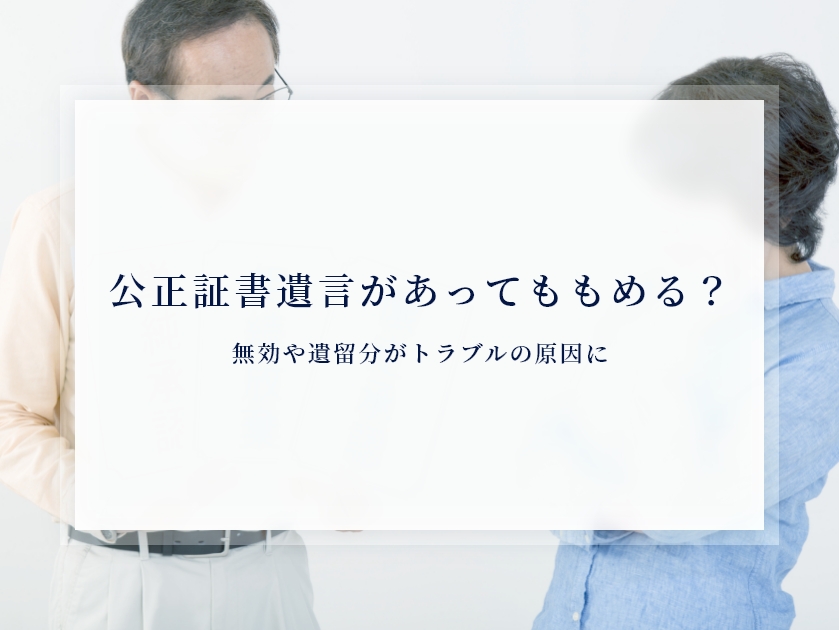遺言と遺留分|遺言書がある場合の遺留分はどうなる?公正証書遺言の効力は遺留分に影響する?
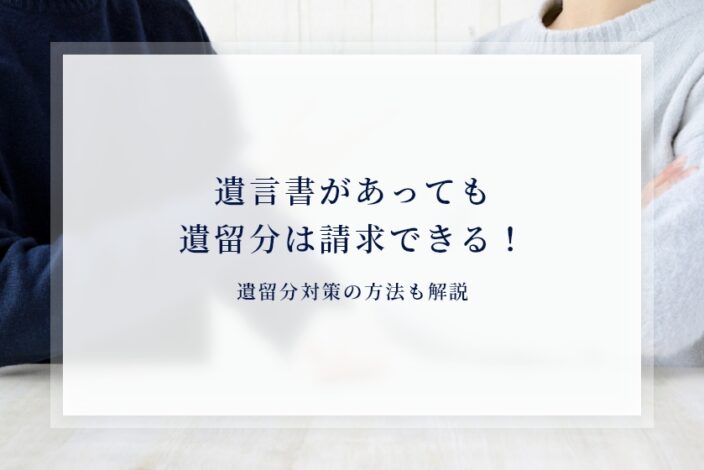
「遺言書があれば、書かれている内容どおりに遺産分割すればいいので、相続人同士でトラブルになることはない。」と思われるかもしれません。たしかに、適切な遺言書があれば、遺産分割協議をせずに相続手続きを進められるため、スムーズです。
ですが、実際の遺産相続では、必ずしも遺言書に記載された内容のとおりに進むとは限らないことがあります。その代表的なものが、「遺留分」の問題です。
一部の法定相続人には、「遺留分」と呼ばれる最低限の相続権が保証されています。そのため、遺言書で「特定の相続人に多くの遺産を残す」などと記されていても、他の相続人の遺留分を侵害している内容となっていると、遺留分をめぐって相続人間でトラブルに発展してしまいかねないのです。
そこでこの記事では、遺言と遺留分の関係について弁護士が詳しく解説させていただきます。
そもそも、遺留分を侵害する内容の遺言にはどういったものがあるのか、遺留分を侵害する内容の遺言が存在する場合、遺言の効力はどうなるのか、といった点について、公正証書遺言の効力などにも触れつつご説明いたします。
遺留分対策をしつつ、適切な遺言を残したい方に必見のコラムとなっております。ぜひ最後までご覧いただければと思います。
目次
遺言と遺留分
1.遺言と遺留分の関係
遺留分とは、相続人が最低限相続できる遺産の額を保障するための法律上の権利です。遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます(民法第1042条1項)。
(遺留分の帰属及びその割合)
民法第1042条1項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
たとえば、遺言書で指定された相続分が極端に少ない場合に、遺留分侵害額請求を行い、最低限の相続分を確保することが可能です。
遺留分は法律で認められた権利ですので、遺言書によってもこの権利を奪うことはできません。つまり、遺留分は遺言に優先するのです。
2.遺留分を侵害する遺言書とは
それでは、遺留分を侵害する遺言書とは、どういった遺言書を意味するのでしょうか。
遺留分を侵害する遺言書とは、相続人が法律で保障された最低限の相続分を受け取ることのできない内容の遺言書を指します。以下で、代表的な例を見ていきましょう。
2-1.全ての財産を一人の相続人に相続させる遺言
「全ての財産を一人の相続人に相続させる」旨の遺言は、特定の遺産を特定の相続人に承継させる、「遺産分割方法の指定」になります。特段の事情がなければ、被相続人の死亡時に、マイナスの財産も含む全ての相続財産が、直ちに指定された相続人に承継されることとなります(最高裁判所平成3年4月19日判決)。
このような遺言にあっては、遺言者の意思に合致するものとして、遺産の一部である当該遺産を当該相続人に帰属させる遺産の一部の分割がなされたのと同様の遺産の承継関係を生ぜしめるものであり、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである。
(最高裁判所平成3年4月19日判決)
全ての財産を一人の相続人に相続させる遺言は、本来遺産を受け取る権利を持っている他の相続人の遺留分を侵害する遺言書です。
たとえば、子供が複数人いるにもかかわらず、長男のみに全ての財産を相続させる内容の遺言などが、これに当たります。長男以外に配偶者や他の子供などの相続人がいる場合、長男に全ての遺産を相続させる遺言書は、配偶者や他の子供などの相続人の遺留分を侵害しているのです。
2-2.土地を一人に相続させる遺言書
遺産の大部分が土地などの不動産で占められている場合、その不動産を一人の相続人に全て相続させる旨の遺言も、他の相続人の遺留分を侵害する可能性が高いです。特に、土地や建物は現実的な分割が難しく、財産としての価値も高額であることが一般的なので、一人に全てを相続させると、他の相続人に十分な遺産が残らないことがあります。
2-3.すべての遺産を相続人以外の他人に遺贈する遺言書
すべての遺産を相続人以外の他人に遺贈する遺言書も、遺言による遺留分侵害の典型例です。
たとえば、被相続人が全財産を親しい友人や慈善団体に遺贈する、といった遺言を残している場合がこれに当たります。このような遺言書が存在すると、被相続人の配偶者や子供といった法定相続人は、遺産を全く受け取れないことになってしまいます。
仮に、「全財産を友人Aに遺贈する。」といった遺言がある場合は、遺産を受け取ることのできない法定相続人は、友人Aに対して遺留分侵害額を請求し、自身の最低限保障された取り分を回復することになります。受遺者(遺贈を受けた人)が慈善団体やNPOなどの法人である場合は、団体や法人に対して遺留分侵害額請求を行います。
遺言書がある場合の遺留分
1.「遺留分を認めない」と書いた遺言書の効力
「遺留分を認めない」という内容や、特定の相続人の遺留分を侵害する内容が書かれた遺言書であっても、その遺言自体は無効にはならず、有効です。
遺留分は法律で保障された相続人の最低限の取り分であり、遺言書で「遺留分を認めない」と記載しても、その文言に法的効力はありません。遺留分は民法によって保護されていますから、被相続人が遺言書でその権利を排除しようとしても、遺留分を請求する権利を取り上げることはできません。
基本的には、遺言に書かれたとおりに遺産分割が実行された上で、遺留分を侵害された人が侵害額を請求する場合に、支払い義務のある相続人が遺留分相当額の金銭を支払うことになるでしょう。
ですので、遺留分を巡るトラブルを避けるためには、遺言書に遺留分を認めない旨を記載するのではなく、あわせて他の対策を講じることが重要です。
2.公正証書遺言によっても遺留分は廃除できない
ところで、遺言には大きく分けて「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つがあります。
自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自分で書き(自書)、押印して作成する方式の遺言です(民法第968条)。対して公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して作成する方式の遺言をいいます(民法第969条)。
公証役場で公証人が関与し、遺言者の遺言能力の確認も行われた上で作成されるため、方式や内容の不備によって遺言が無効になったり、後日その有効性が争われたりする可能性が低くなるため、遺言を作成する際には公正証書遺言が推奨されます。
そういった公正証書遺言の性質から、「公正証書遺言であれば、遺留分の請求を認めない、と書いておけば有効になるのでは?」といった考えをお見受けすることがあります。
ですが、遺言の形式が公正証書遺言か自筆証書遺言であるかにかかわらず、遺留分を認めない旨の記載が有効になることはありません。
3.遺言で侵害された遺留分は必ずもらえる?
それでは、遺言によって自分の相続分が少なかったり、何も相続できなかったりした場合に、必ず遺留分をもらえるものなのでしょうか。
3-1.兄弟姉妹・甥姪に遺留分はない
たとえ相続人であっても、全ての相続人に遺留分が認められるわけではありません。
(遺留分の帰属及びその割合)
民法第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
たとえば、兄弟姉妹やその子供である甥・姪は、遺留分がが認められない相続人です。
兄弟姉妹や甥・姪が遺留分を持たないのは、被相続人との生活上の密接な関係が少ないと考えられるためです。被相続人の配偶者や子供とは異なり、兄弟姉妹は被相続人の生活に直接的な影響を受けにくく、被相続人の財産を受け取れないことで生計を維持できなくなる、といった可能性もほとんどありません。そのため、遺留分による保障が不要とされているのです。
ですから、兄弟姉妹や甥・姪が遺言書によって遺産を全く受け取れなくても、遺留分を請求することができません。
3-2.遺留分を放棄した場合
遺留分を請求することは、義務ではなく権利です。そのため、遺留分を請求する権利をあらかじめ放棄することも可能です。遺留分を放棄した人は、相続権は失わないまま、遺留分侵害額請求する権利を失うことになります。
被相続人の生前に遺留分の放棄をするには、家庭裁判所で申立てを行い、遺留分放棄が認められなければなりません。単に「遺留分はいりません。」と主張するだけでなく、遺留分の放棄が認められるための理由が必要になります。
一度遺留分放棄が認められた場合、後で撤回することは難しいです。
なお、被相続人の死後に遺留分の放棄の手続きは行えません。この場合は、単に「遺留分を請求しない」ことで足ります。
3-3.代襲相続で被代襲者が遺留分を放棄していた場合
たとえば被相続人の子供が法定相続人であるケースで、子供がすでに死亡していた場合には、被相続人の孫に相続権が移ることになります(代襲相続)。このような代襲相続が生じる遺産相続において、被代襲者(被相続人の子供)が遺留分を放棄していた場合には、代襲相続人である孫も遺留分を請求する権利を持たないと考えられています。
代襲相続人の相続分は、被代襲者である相続人が受けるべきものと同じ(民法第901条1項)とされているので、遺留分を放棄した相続権を代襲相続するのだから、代襲相続人にも当然遺留分が認められるべきではない、とされているのです。
(代襲相続人の相続分)
民法第901条1項 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
3-4.遺留分侵害額請求権の時効が成立している
遺留分侵害額請求権の時効は3つありますが、時効が成立している場合には遺留分請求が認められません。
-
1年の消滅時効
相続人が遺留分が侵害されていることを具体的に把握してから1年以内に請求しなければ、時効により遺留分請求権が消滅します(民法第1048条前段)。単に遺留分が侵害されている事実を知っているだけでなく、その侵害の根拠まで理解していることが必要です。
-
10年の除斥期間
相続が開始してから10年経過すると、遺留分の侵害を知らなかった場合でも請求権が消滅します(民法第1048条後段)。そのため、相続人が相続開始から10年以上経過して遺留分の侵害を知ったとしても、遺留分を請求することはできません。
-
5年の金銭債権の時効
遺留分侵害額請求権は、金銭を請求する権利です。そのため、金銭債権の「5年」の時効についても適用を受けることになります(民法第166条1項1号)。
これらの時効が成立している場合、遺言書で遺留分が侵害されていても、法的に遺留分を請求することができなくなります。遺留分を確実に請求するためには、時効期間内に適切な手続きを行うことが重要です。
3-5.相続権を失った人
自分の意思で相続権を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとみなされるため、相続する権利を失うことになります(相続放棄)。そのため、遺留分を請求する権利も失います。
故意に被相続人や他の相続人を死亡させるなどの重大な犯罪を犯した者についても、相続権を失うことになるため、遺留分を請求する権利もありません(相続欠格)。
また、被相続人に対して著しい非行や悪行があった場合、被相続人は家庭裁判所に申し立てることで、その相続人を廃除することができます(相続廃除)。相続権を廃除された人も相続権を失うため、遺留分を請求する権利がありません。
3-6.権利の濫用に該当する場合
遺留分を請求することが、「権利の濫用」に当たるとみなされた場合に、請求が認められないことがあります。たとえば、判例上は以下のようなケースが権利の濫用と判断されました。
- 裁判上の和解において「将来の相続分及び遺留分を請求しない」と約束したにもかかわらず、家庭裁判所の許可手続きを経ていないことを理由に遺留分を請求したケース(東京地判平成11年7月27日)。
- 共同相続人である兄弟間で、親の面倒を見る代償として特定の土地を取得することに合意し、他の兄弟が遺留分を主張しない旨の約束をしていたにもかかわらず、その約束に反して遺留分を請求したケース(東京高判平成4年2月24日)。
- 高齢で病身の被相続人と同居して介護に尽くした一方の養子に全財産が遺贈されたのに対し、縁組から5か月で別居し、その後25年間音信不通で事実上の離縁状態にあった他方の養子が遺留分を請求したケース(名古屋地判昭和51年11月30日)。
- 養家が経済的に困窮している状況で、老齢の養父母を見捨て、「養家の財産は一切いらない」と表明して家を出た養子が、後に養家の財産形成に貢献した者への贈与に対して遺留分を請求したケース(仙台高裁秋田支部昭和36年1月25日)。
ご紹介した裁判例の中から、③の音信不通にあった養子が遺留分を請求した裁判例を見てみましょう。
被相続人には、3人の養子がいました。被相続人は、養子Aに対して相続財産である不動産をすべて遺贈させ、Aは所有権移転登記を済ませていました。これに対して養子B・Cが、遺贈によって自身の遺留分を侵害されたとし、A(被告)へ遺留分減殺請求を行った事例です(民法改正前の裁判例なので、遺留分侵害額請求ではなく「遺留分減殺請求」と表記しています)。
養子B・Cと被相続人の関係性は、当時68歳で病弱であった被相続人を見捨てて家を出て以来、被相続人が死亡するまでの25年間、被相続人に対して養子らしいことは何一つとしてしたことはなく、ほとんど音信普通の状態で、事実上全くの離縁状態にあり、実質上の養親子関係は消滅していた、といえるものでした。
一方で、養子Aは、実の子でも及ばないような誠意をつくして被相続人の面倒をみ、介護に尽力し、被相続人の財産を守っていた、という事実が認められています。
裁判所は、被相続人と事実上全くの離縁状態にあり、実質上の養親子関係は消滅していたというべき養子から、一生をかけて被相続人の面倒をみて、その財産を守った養子に対し、形式的な遺留分減殺請求権を根拠に遺贈の減殺を求めることは、「法が設けた遺留分制度の趣旨にもとるものであり、権利の濫用として許されないものと認めるのが相当である。」と判断しました。
(名古屋地判昭和51年11月30日)
以上のとおり、遺留分権利者について、離縁や相続廃除が認められるのに相当するような重大な事情があることや、遺留分の請求を認めることが遺留分制度の趣旨に反し、著しく正義・衡平の理念に反する特段の事情がある場合には、権利の濫用として遺留分の請求が認められない傾向があるといえます。
遺言によって遺留分侵害された相続人が取り得る対応
遺言によって自身の遺留分を侵害された相続人は、どういった対応を取り得るのでしょうか。以下で確認しておきましょう。
1.遺言無効の主張
遺言によって遺留分が侵害された場合、遺言の有効性そのものを争う「遺言無効の主張」をすることが考えられます。遺言が無効と判断されれば、遺言は初めからなかったことになり、法定相続分に従って遺産分割が行われるため、遺留分侵害の問題も解消されることになります。
法律で定められた要件を満たさないなどの事情がある場合には、その遺言全体が無効となることがあります。遺言が無効となる主な原因には、以下のようなものがあります。
- 遺言書が民法の形式要件(民法第960条)を満たしていない
- 遺言当時、被相続人に遺言能力がなかった(民法第961条、同第963条)
- 遺言の内容が不明確
- 遺言の内容が公序良俗(民法第90条)に反する
- 遺言書が偽造されたものだった
遺言の無効を争う場合、まずは他の相続人や受遺者・受贈者などの利害関係者に対し、遺言が無効であると考える理由を説明し、話し合いを行います。当事者全員が遺言の無効に合意すれば、あらためて遺産分割協議で遺産相続を進めることになります。
話し合いがまとまらない場合、原則として、まず家庭裁判所に「遺言無効確認調停」を申し立てる必要があります(調停前置主義)。そして、調停が不成立に終わった場合、地方裁判所に「遺言無効確認訴訟」を提起して、裁判所の判断を求めることになります。
2.遺留分侵害額請求
遺留分を侵害している人に対して、遺留分を請求する意思を伝えます。この意思表示の通知方法に特に決まりはありませんが、請求した記録を残せるため、内容証明郵便を利用するのが一般的です。
前述の通り、遺留分侵害額請求権には時効がありますので、早めに対応することが重要です。
交渉に応じてもらえる場合は、相手方と支払い額や支払い期限について話し合います。双方が合意に達したら、遺留分の支払いに関する合意書を作成し、支払われれば解決となります。
相手方との話し合いがまとまらない場合や、相手方が話し合いに応じない場合は、遺留分侵害額請求の調停や訴訟を検討します。調停は、裁判所の第三者が関与して話し合いを進める手続きで、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。訴訟は、裁判所に強制的な判断を求める手続きで、亡くなった人の最後の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所に提起します。
遺言書で遺留分が侵害されている場合でも、これらの手続きを適切に進めることで、自分の正当な取り分を確保することが可能です。弁護士の助けを借りながら、しっかりと対処していきましょう。
遺言書があるのに遺留分請求されたら
1.遺留分対策した遺言を作っておきましょう
遺言書は、被相続人の意思を明確にする重要な文書ですが、遺留分が優先されるため、遺言書で相続分を指定しても相続人の遺留分を奪うことはできません。しかし、事前に適切な対策を講じることで、被相続人の希望通りの相続を実現することが可能です。
その対策というのが、遺言書の「付言事項(ふげんじこう)」になります。
「付言事項」とは、遺言書の中で法的な効力が発生しない文言になります。たとえば、「兄弟仲良く助け合って生きていくように。」といった付言事項が一般的です。
誰か特定の一人に遺産の全てを相続させたい場合、遺言書に「遺留分侵害額請求をしないで欲しい」という旨の付言事項を残すのも一つの対策です。付言事項には法的強制力がないため、遺留分権利者の意思に訴えかける手段に過ぎませんが、故人の最後のメッセージとなるため、心情的に考慮してもらえることが期待できます。
この際、直接的に「遺留分侵害額請求をしないで欲しい」と書くだけでなく、特定の一人に相続させる理由や気持ちを、真摯に伝えることがより効果的です。遺言者の明確な意思が伝わるような文章を心掛けることで、遺言者の真意が伝わり、遺留分請求を控えることを前向きに考慮してもらえるかもしれません。
付言事項の例
「私が次男に多くの財産を残したのは、彼が長年私の介護をしてくれたことに対する感謝の気持ちからです。また、次男には家業を継いで発展させてほしいという願いも込められています。どうか、私が亡くなった後も兄弟仲良く助け合い、家族全員が円満に過ごせるようにしてください。遺産相続で争うことがないよう、心から願っています。」
ただし、最終的には遺留分権利者の意思に従うことになる点には注意が必要です。
2.遺言以外での遺留分対策
また、遺留分対策をした遺言を作成する以外にも、以下のような遺留分対策があります。
-
遺産総額そのものを減らすことで、遺留分も減少するため、生前贈与や個人的に使用するなどして相続財産を減らしておくことは、遺留分トラブルの予防として有効です。ただし、「法定相続人に対する死亡前10年間に行われた贈与」や「法定相続人以外の人に対する死亡前1年以内にされた贈与」は遺留分侵害額請求の対象となるため、生前贈与はできるだけ早めに、贈与税の非課税枠を活用しながら計画的に行うことが重要です。
-
遺留分を請求する可能性のある相続人がいる場合には、生前に遺留分を放棄してもらう方法もあります。遺留分権利者本人が家庭裁判所に対して遺留分放棄の許可を申し立てる必要があり、認められるためには、遺留分の放棄に見合う理由や、現金や財産などの対価が必要です。遺言書の作成とあわせて進めることで、円満な遺産相続が期待できます。
-
生命保険を遺留分対策に活用することも可能です。遺留分権利者を受取人に指定して遺留分侵害額を請求しない約束をする方法や、受遺者や受贈者を受取人に指定し、遺留分侵害額請求があった場合に生命保険金を代償金として支払う方法が考えられます。
-
遺言で弁護士などの専門家を遺言執行者に選任しておくことで、遺言の内容を実現する手続きを適切に進めやすくなり、当事者間の感情的な対立を軽減することも期待できます。
遺言と遺留分に関するQ&A
Q1.遺言書があったら遺留分を請求できなくなりますか?
A:なりません。遺留分は、相続人が最低限受け取るべき取り分として法律で保障されている権利です。遺言書で相続分が指定されていても、相続人が遺留分を請求する権利は失われません。
Q2.「遺留分を認めない」と記載されていた遺言書に効力はありますか?
A:遺言書そのものは有効です。遺言書に「遺留分を認めない」と記載されていた場合、遺言書自体が有効に成立したものであれば、遺言どおりに遺産分割が行われることになります。ただし、遺言書が有効だからといって、遺留分の請求を妨げることはできません。
Q3.どういう遺言が遺留分侵害をする遺言ですか?
A:遺留分を侵害する遺言書とは、相続人が法律で保障された最低限の相続分を受け取ることのできない内容の遺言書をいいます。相続人が複数いる場合の「遺産の全てを長男に相続させる」といった遺言などが、これに当たります。
まとめ
本記事で解説させていただいたとおり、遺留分は法律で保障された相続人の最低限の取り分です。遺言書によって遺留分が侵害された場合でも、遺留分侵害額請求を行うことで自身の取り分を獲得することが可能です。
遺言書を残す場合、遺留分に関するトラブルを未然に防ぐためには、生前から適切な対策を講じることが重要です。
たとえば、遺言書に付言事項を記載する方法や、生前贈与を行って相続財産を減らす方法、遺留分の請求権を放棄してもらう方法などがあります。これらの対策を適切に実施するためには、法律の専門知識が必要不可欠です。
遺言書の作成や遺留分対策に不安がある方は、ぜひ当法律事務所にご相談ください。弁護士が一人ひとりの状況に応じたアドバイスを提供し、円満な相続の実現をサポートいたします。
弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。対面だけでなく、お電話によるご相談もお受けしておりますので、お気軽にお問合せください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。