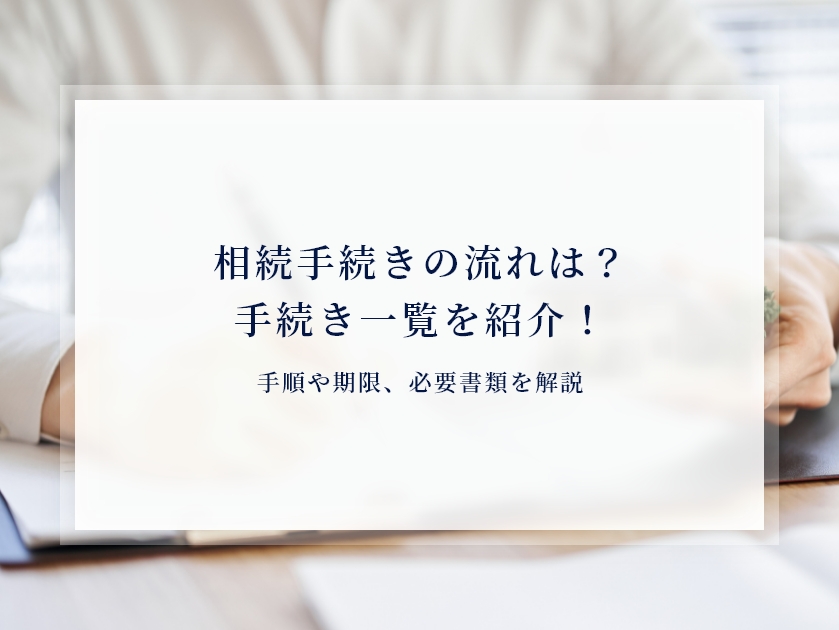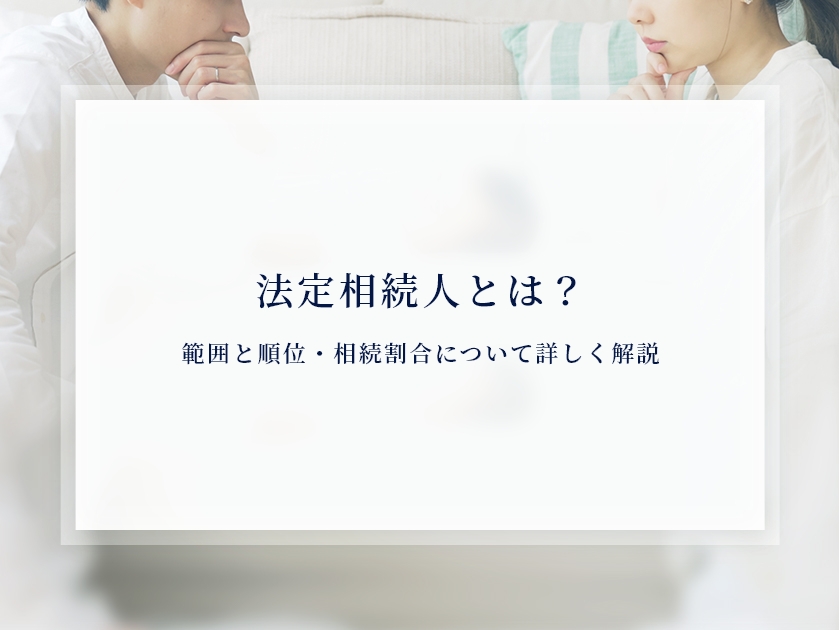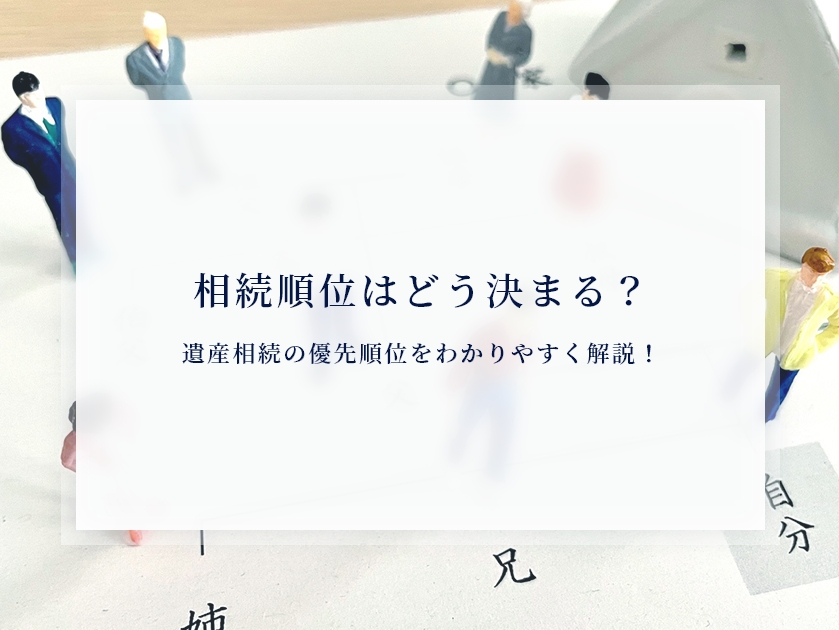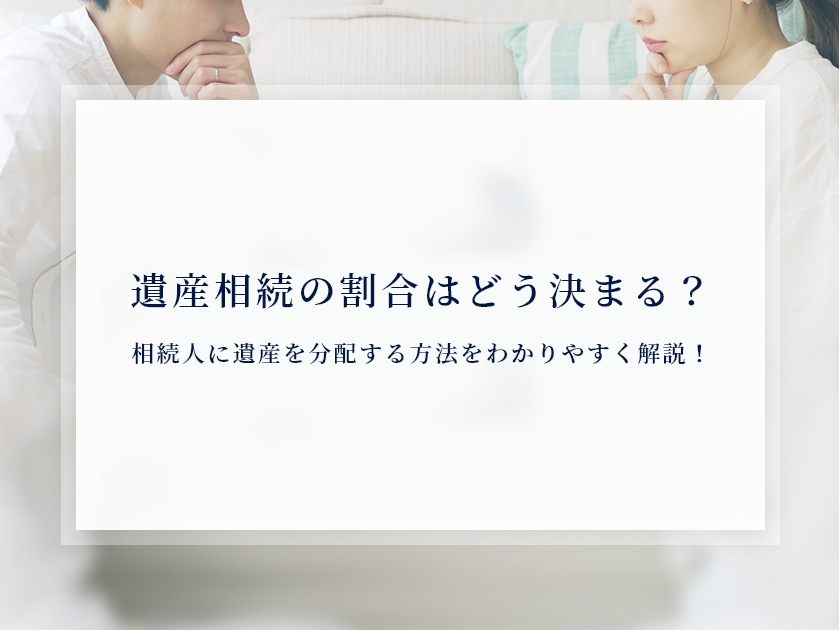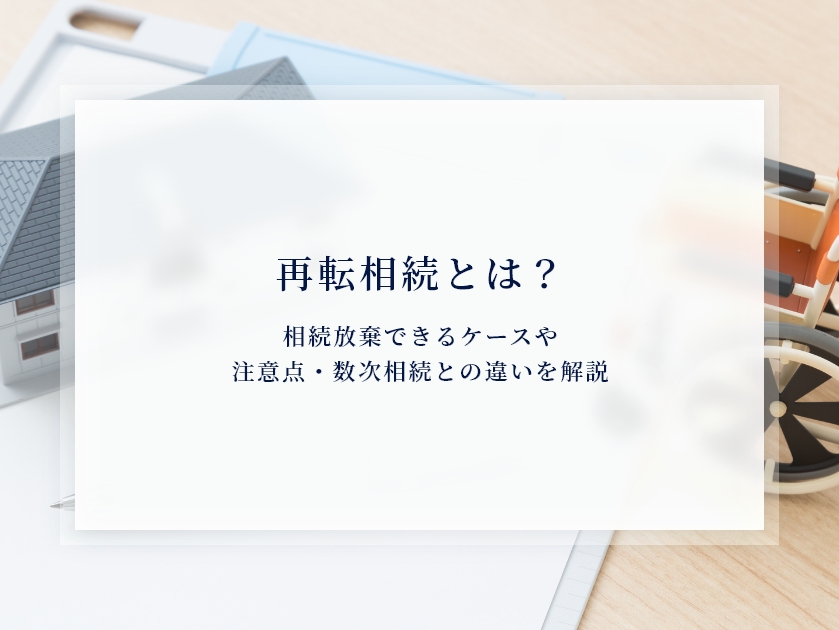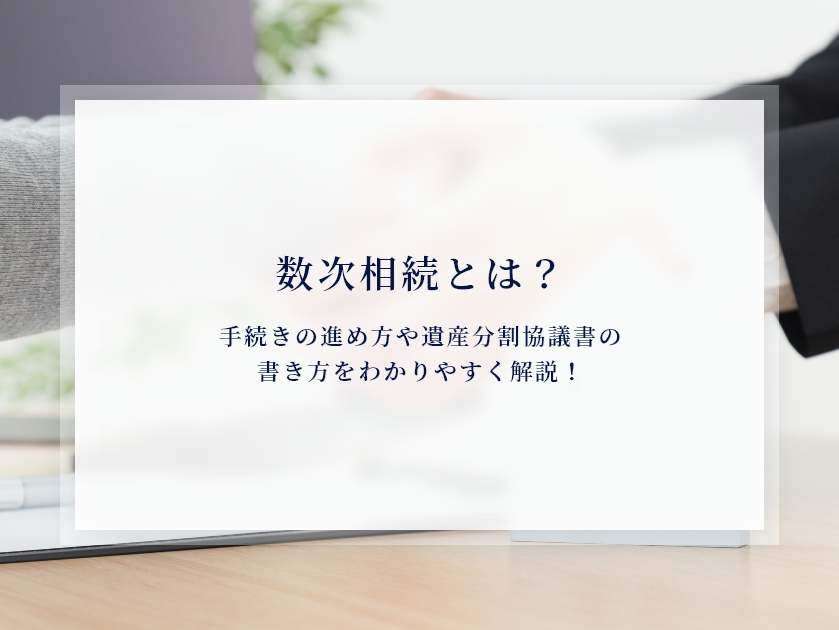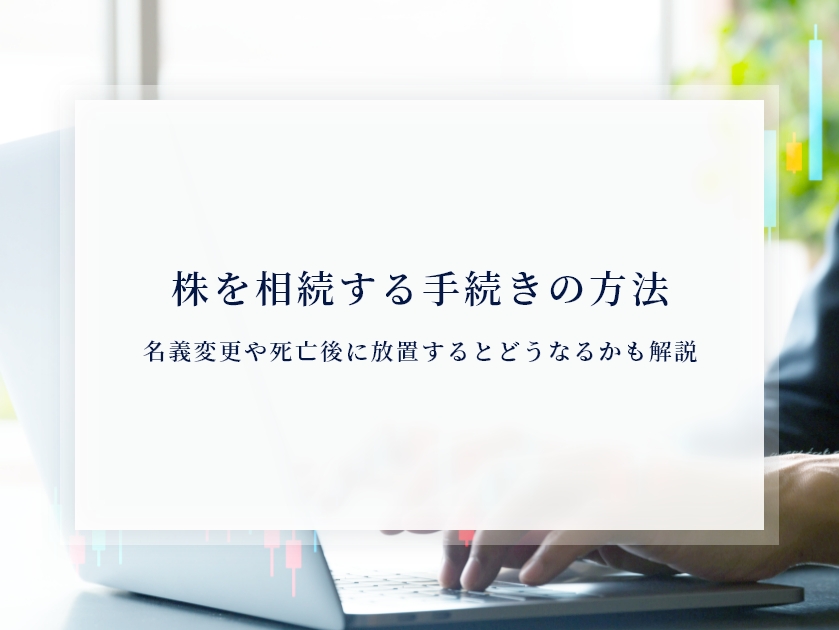遺産相続【完全版】相続とは?遺言や相続財産など基本を解説
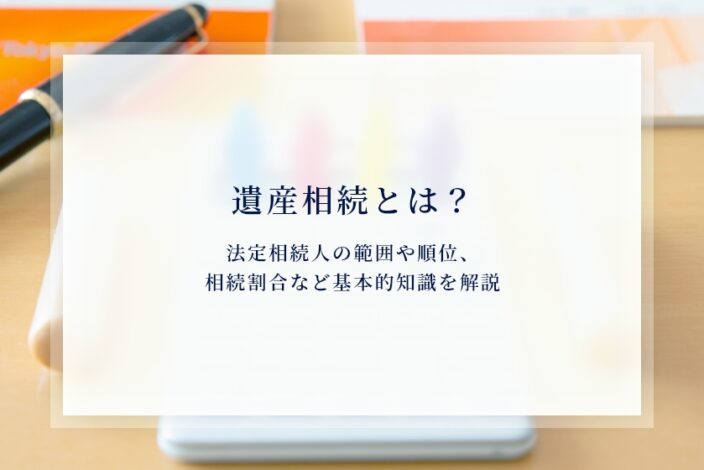
家族や親族の死によって遺産相続を始めようとしても、何から手を付けて良いか分からない、という方も多いかと思います。
そこで、この記事では「遺産相続とはどういった手続きなのか」をテーマに、弁護士が解説させていただきます。
遺産相続は、まずは法定相続人の範囲や順位、相続割合を把握することから始まります。誰が相続人で、どのくらいの遺産を受け取ることになるのかを確認しなければ、具体的な遺産相続の手続きを進めていくことができません。
また、遺言があるケースと遺言がないケースでは、その手続きも異なるため注意が必要です。
こういった一連の手続きを、親族が亡くなり慌ただしい中、法律で決まっている期限内に済ませなくてはいけないため、遺産相続にはかなりの労力を必要とします。
ですので、いざ遺産相続が始まったときに困らないよう、本コラムで遺産相続について必ず知っておきたい基本知識をおさえておきましょう。
遺産相続でお困りの方にとって、本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。
目次
遺産相続
日々の生活を送る中で遺産相続について意識することはないかもしれませんが、遺産相続の問題は意外と起こっているものです。
実際に、令和3年の最高裁判所事務総局による司法統計年報によると、家庭裁判所で扱われた遺産分割の事案は6,934件にのぼります。その中で、遺産総額が1,000万円以下の事案が2,279件、1,000万円超から5,000万円以下の事案が3,037件と報告されており、5,000万円以下の事案が全体の約76%を占めています。
参考:令和3年 司法統計年報(家事編)第52表(裁判所)
このデータからも明らかなように、遺産の額の多い・少ないに関わらず、遺産相続のトラブルが発生することは少なくないのです。
相続争いを防ぐためには、遺産相続が誰にでも起こり得る身近な問題であると認識し、適切な対策や準備を事前に考えておくことが重要です。
以下で、遺産相続についての基本を確認していきましょう。
遺産相続とは?
そもそも、遺産相続とはどういった手続きなのでしょうか。
(1)遺産相続の基本
遺産相続とは、ある人が亡くなった際に、その人が持っていた全ての財産や権利、義務が法的に特定の人々に引き継がれることを指します。この遺産相続手続きにおいて、亡くなった人のことを「被相続人」といい、財産を引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。遺産相続のことを単に「相続」と呼ぶことが一般的です。
遺産相続の3つの方法
遺産相続には、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3つの方法があります。被相続人が残した財産の内容や相続人の事情に応じて、適切な方法を選びましょう。
遺産相続の手続きについては、下記記事で詳しく解説していますので、本記事とあわせてご一読ください。
遺産を相続する人
遺産相続の権利者は、大きく「法定相続人」と「受遺者(じゅいしゃ)」の二つに分けられます。
法定相続人とは、民法により自動的に相続人となる人のことです。
受遺者とは、被相続人が遺言によって明確に指名した遺産の受取人のことです。
遺言書が存在する場合、その内容は法定相続人の権利より優先されるため、遺言書に記載された指示に従って遺産が分配されます。遺言書による指定がない場合は、自動的に法定相続人が遺産を相続することになります。
遺言書が存在しない場合、または遺言書による指定がない財産がある場合は、法定相続人が遺産を受け取ることになります。法定相続人には、配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹が含まれます。
遺産相続の権利者や相続順位については、下記の関連記事で詳しく解説しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。
誰がどれだけ相続するか
遺産相続を進めるにあたって、相続人の間で争いになりやすいのが、誰がどれだけの財産を受け取るかという相続割合の問題かと思います。
原則として、遺言書による財産指定が存在する場合、通常はその内容に従って遺産が分配されます。遺言書では、具体的な財産や相続人ごとの相続分が指定されていることが多いです。
なお、遺言書がない場合は、法定相続分に基づいて遺産を分配するか、遺産分割協議で話し合って決めた分配方法で遺産相続を進めることになります。
法定相続分とは、民法で定められた、相続人が取得できる遺産の割合のことです。相続割合に関する基本的な指針とされますが、法定といっても必ず守らなければならない絶対的なルールではありません。相続人の間で合意があれば、法定相続分にとらわれず、自由な割合で遺産相続することが可能です。
相続の開始時期である「死亡」の定義
ところで、遺産相続には開始する時期が決められていることをご存知でしょうか。現実的には、葬儀などを終えてから親族で集まって始まることが多いのでしょうが、日本においては民法第882条で「相続は死亡によって開始する。」と定められています。
「死亡によって開始する」とは、被相続人が死亡した瞬間に、その人の持っていた財産や権利、義務が相続人に法的に引き継がれるという意味です。
なお、遺産相続の開始時期の原因となる「死亡」についてですが、民法第882条の「死亡」という用語に含まれるものは、老衰や病死といった自然死や、事件や事故による死だけではありません。具体的には、「失踪宣告」と「認定死亡」という、法的な意味での「死亡」も含まれています。
失踪宣告とは、一定期間行方不明になっている者に対し、法律上死亡したものとみなすために家庭裁判所が行う宣告のことです。具体的には、行方不明者の生死が7年間分からない場合(民法第30条1項)や、天災や事故などで行方不明になり生死が1年間分からない場合(民法第30条2項)などが、失踪宣告に当たります。実際の生死は分からないものの、法的には死亡したものとみなされることになるのです。
認定死亡とは、事故や災害などで明確な死亡確認ができない場合に、その人の死亡が確実と認められる場合に適用される制度です。「水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。」(戸籍法第89条)とある通り、こちらは家庭裁判所での手続きを経ずに、市町村で手続きが行われます。
どの死亡のケースでも、法的に死亡が認定されることによって相続が開始されます。失踪宣告や認定死亡は、相続の開始時期や手続きに大きく影響を与えるため、こうした特殊なケースでは専門家の助言を受けることが望ましいです。
(2)遺産(相続財産)とは
遺産相続の対象になる財産のことを「相続財産」といいますが、この相続財産とは、被相続人が亡くなった時点で有していた全ての財産を指します。具体的には、現金、銀行預金、不動産、株式や債券などの有価証券、自動車や美術品のような動産、そして著作権や特許権などの知的財産権も含まれます。また、被相続人が生前に権利を有していた保険金の受取権や退職金の請求権も、相続財産として考慮されます。
金銭的価値のあるものは全て相続財産になると思われるかもしれませんが、法律で明確に相続財産から除外されているものもあります。例えば、特定の生命保険金の受取権や、使用貸借における借主の地位といった個人的な権利の性質を持つものは、相続財産には含まれません。
相続財産を正確に把握することは、遺産分割をしっかりと適正に実施するために不可欠です。被相続人の財産の全容を知ることで、相続人間での紛争を防ぎ、手続きを円滑に進めることが可能となります。そのためには、被相続人の死亡前後に財産目録を作成し、どの財産が相続に含まれるのかを明確にすることが大切となります。
そして、相続財産はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も相続財産になります。
プラスの財産とは、現金、不動産、株式などの価値を持つ資産のことを指します。一方、マイナスの財産とは、被相続人が亡くなる時点で残された借金や未払いの税金などの負債を指します。
相続財産と聞くと、プラスの財産に目が行きがちですが、マイナスの財産も承継することになりますので、注意が必要です。もし、マイナスの方が大きい場合には、相続しないという選択も考えるべきでしょう。
プラスの財産
|
種類 |
例 |
|
現金 |
紙幣、硬貨 |
|
預貯金 |
銀行預金、郵便貯金 |
|
有価証券 |
株式、債券、投資信託 |
|
不動産 |
土地、建物 |
|
貴金属 |
金、銀、プラチナ |
|
美術品 |
絵画、彫刻、骨董品 |
|
車 |
自動車、オートバイ |
|
家具・家電 |
テレビ、冷蔵庫、洗濯機 |
|
権利 |
著作権、特許権、商標権 |
|
その他 |
生命保険金、退職金、慰謝料 |
マイナスの財産
|
種類 |
例 |
|
借金 |
銀行からの借金、消費者金融からの借金 |
|
負債 |
不払いの賃料、損害賠償金 |
|
未納税金 |
所得税、住民税 |
|
その他 |
葬儀費用 |
遺産相続の対象とならない財産
上でも少し触れましたが、個人の身分に関わる権利や義務、個人的な性質を持つ財産、そして一部の特定の財産については、遺産相続の対象財産にはなりません。そのため、遺産相続の手続きで相続人に分配されることはないのです。
一身専属的な権利義務
生活保護受給権、国家資格、親権、扶養義務など、その性質上、個人に固有のものであり、他人に譲渡や相続ができないものは、相続財産に含まれません。
生命保険金と死亡退職金
生命保険金や死亡退職金については、被相続人が直接の受取人となっている場合を除いて、民法上の相続財産には含まれません。なお、税法上は「みなし相続財産」として扱われ、相続税の計算において課税対象となることがありますので、注意が必要です。
香典、弔慰金、葬儀費用
これらは葬儀に関連する費用や受け取りであり、遺産としての性質を持たず、通常、遺産分割の対象外とされます。
祭祀関連の財産
墓地、墓石、仏壇、祭具、系譜などの祭祀に関連する財産は、遺産分割の対象とはなりません。これらは通常、特定の家族成員や祭祀主催者が承継しますが、民法上の相続財産としては扱われません。
相続と遺言
(1)相続では遺言が最優先
さて、被相続人の死亡によって相続が開始すると、相続人全員が被相続人の財産を共同で所有する「共有」状態になります。この共有状態を解消し、各相続人が個別に財産を受け取るために、遺産分割の手続きを進めていかなければなりません。
遺産分割の手続きは、最初に被相続人の遺言の有無を確認するところから始まります。
「遺言(いごん・ゆいごん)」とは、自分が亡くなったあとに自分の財産をどのように分けるか、また、自分の意思をどのように実現してほしいかを、生前にあらかじめ決めておく制度のことです。
遺言は自分が残す財産についての希望を明確に示すものであり、遺産分割の方法や財産を相続する人を自由に指定することができます。また、相続人以外の人に財産を譲る(遺贈する)ことも可能です。
遺言の内容が有効であれば、遺言による指示が最優先されます。遺言によって財産の分配が明確に決定されていて、記載に不備がなく内容が有効である場合、遺言内容に従って遺産分割が行われることになります。
(2)「遺言」と「遺言書」
ところで、遺言が有効であるためには、必ず書面化されていなければならないとされています。原則として、口頭による遺言は認められていないのです。
そのため、被相続人が有効な遺言を遺すためには、「遺言書」を作成しておく必要があります。
遺言書とは、自分が亡くなった後に、自分の財産を誰にどのように分けたいかという意思を明確に記載した書面のことです。遺言書を作成すれば、法定相続分とは異なる割合で相続人に財産を分配したり、家族ではない第三者や団体などに財産を譲ったりすることもできます。また、遺産の配分方法だけでなく、子どもの認知や未成年の子どもの後見人を指定するなど、財産以外のことも遺言書で決めることが可能です。
ただし、遺言書は単なる手紙やメモ書きでは法律的な効力を持ちません。民法が定めたルールに従って作成されていなければ、法的に無効になってしまう可能性があるため、正しい形式で作成する必要があります。
遺言書には、主に次の3つの種類があります。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者本人がすべての内容を手書きで記入し、日付、署名、押印をして作成する遺言書です。手軽に作成でき費用もかからず、自分だけで秘密に保管できるという利点がありますが、記載方法や内容に不備があると無効になる可能性があります。また、自宅で保管すると紛失や改ざん、破棄されるリスクもあるため、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して安全に保管することが望ましいでしょう。
②公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が遺言者の意思を聞き取り、内容を法的に有効な形でまとめて作成する遺言書です。作成時には証人が2名必要で、公証役場に原本が保管されます。このため、遺言の紛失や偽造・改ざんの心配がなく、相続発生後もスムーズに遺産分割を行えるメリットがあります。安全性や確実性が最も高い方法ですが、公証役場に対して手数料がかかること、作成に手間がかかることがデメリットです。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者本人が自分で遺言書を作成し、それを封筒に入れて封印した状態で公証役場に持参し、遺言書の存在のみを証明してもらう遺言書です。遺言書の内容自体は秘密にできますが、公証人が内容を確認することはないため、内容に不備があると無効になる危険性があります。また、実務ではほとんど使われていません。
遺言書が存在しなかったり、遺言書に記載されていない財産があったりと、遺言書だけでは遺産分割を行えない場合は、相続人同士で遺産分割協議を行うことになります。遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要なので、相続人それぞれの要望や法定相続分を考慮しながら、話し合いを進めていくことになります。
相続についての注意点
(1)相続人をしっかり特定すること
相続人を一人でも見落としたまま遺産分割協議を進めてしまうと、あとから新たな相続人が見つかり、協議が無効になったり、やり直しになったりする可能性があります。相続人の人数や関係を正確に把握するため、被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍を取り寄せ、離婚や再婚、認知した子どもなど、特に見落としがちな事情に注意して丁寧に調査しましょう。
(2)財産の調査を正確に行うこと
遺産の分割後に新たな財産や負債が判明すると、再度協議が必要になったり、思わぬ負担が生じたりする恐れがあります。不動産や預貯金、株式、生命保険、借金やローンなど、プラスとマイナス両方の財産を詳細に調査し、財産目録を漏れなく作成するように心がけてください。
(3)遺言書の有無を確認すること
遺産分割協議を始める前に必ず遺言書の有無を確認しましょう。もし遺言書の存在を知らずに協議を進めてしまうと、遺言書が後から発見された場合、遺産分割がやり直しになる可能性があります。自宅のほか、公正証書遺言が公証役場に保管されている場合もありますので、慎重な確認が重要です。
(4)遺留分に配慮すること
遺言や生前贈与で特定の相続人に遺産が偏ると、遺留分を侵害された相続人が後から返還を求めるトラブルに発展することがあります。相続人間で感情的な対立を避けるためにも、遺産分割の話し合いや遺言書作成の際には、相続人それぞれの遺留分を考慮し、できる限り公平な内容になるよう配慮しましょう。
(5)遺産分割協議書をきちんと作成すること
相続人全員の話し合いが円満にまとまった場合でも、遺産分割の内容を口約束や曖昧なままにすると、後で「話が違う」といったトラブルが起きる可能性があります。分割する遺産の種類や金額、分け方などを明確に記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・実印で押印し、印鑑証明書も添付して法的に効力のある形に整えておきましょう。
(6)税金の申告は正確に
遺産分割の手続きが終わったら、最後に税金の申告と納付を行うことになります。相続税は金額が大きくなりがちなので、いくら用意しておけば大丈夫なのか心配な方もいらっしゃるかと思います。ここで簡単に、相続税について確認しておきましょう。
遺産相続が行われると、遺産の総額に応じて相続税が課される場合があります。相続税の計算は複雑で、単に遺産の総額から算出するのではなく、さまざまな控除を適用した上で、金額を算出します。
基礎控除、配偶者控除、未成年者控除、障碍者控除、さらには相次相続控除など、相続税における控除にはさまざまな種類があるため、自身のケースで該当するものを適切に適用し計算することが重要です。
その中でももっとも基本的な「基礎控除」ですが、相続税が課税される前に控除できる金額のことを指します。基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」で算出し、この金額を相続財産の額が超える場合に、課税対象となる額に対して相続税が課税されることになります。相続税率は、課税対象額によって累進課税方式で適用されます。
参考:相続税の税率(国税庁)
ここで重要なのは、基礎控除額の計算においては、相続放棄をした人も含めて計算するという点です。
また、法定相続人に養子がいる場合、実子がいれば養子は1人まで、実子がいなければ2人までを、法定相続人として計算に含めることができます。
この基礎控除額を超える遺産がある場合にのみ、相続税の申告と納付が必要になります。ですので、遺産の総額を正確に把握し、適切な控除を適用して課税価格を計算することが重要です。
相続税の計算が済んだら、相続税の申告を行います。相続税の申告も、内容に抜け漏れのないように注意してください。無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されるリスクを避けるためには、正確な申告が重要です。
申告や計算を自分でするのが難しい場合には、専門家の助けを借りることも検討してみてください。
遺産相続に関するQ&A
Q1. 遺産相続ではどのような手続きを行う必要がありますか?
A. 遺産相続では、まず遺言書の有無を確認し、相続財産を調査したうえで、遺産分割協議を行って相続財産の分け方を決定します。その後、名義変更や税務申告などを行います。
Q2.相続財産には具体的にどんなものが含まれますか?
A. 相続財産には、預貯金や現金、不動産、株式などの有価証券、生命保険金、そして借金やローンなどのマイナス財産も含まれます。
Q3.相続財産を遺言によって自由に分配することは可能ですか?
A. 原則として遺言で自由に相続財産を指定することができますが、一部の相続人には法律上の最低限の取り分(遺留分)が保障されているため、完全に自由に分けられるとは限りません。
まとめ
この記事では、遺産相続の基本的な知識、法定相続人の範囲や順位、相続割合について解説させていただきました。
遺産相続は複雑な場合が多く、遺言書の確認、財産の調査から始まりますが、これらは専門的な知識が必要なことも多いです。トラブルを未然に防ぐためには、相続に関する適切な理解が不可欠です。
本記事の解説が、少しでもお役に立てましたら幸いです。
遺産相続は、相続人間での遺産分割に納得がいかない場合や、遺言書の内容に異議がある場合など、様々な問題が生じることがあります。このような状況で自力で解決するのが困難な場合や、特定の問題に直面した場合には、お気軽に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。弁護士は遺産相続に関する法的なアドバイスを提供するだけでなく、依頼者の代理として他の相続人との交渉を行い、依頼者の利益を最大限に守るよう、適切にサポートいたします。
問題を抱えている場合や不安な点がある場合は、法律の専門家である弁護士に早めにご相談いただくことが、安心して遺産相続を進めるための鍵となります。遺産相続に関しては一つ一つのケースが独自の特性を持っているため、専門家の意見を聞くことで、より適切な対応が可能になります。
弁護士法人あおい法律事務所では、困った時にお気軽にご相談いただけるよう、初回の法律相談を無料とさせていただいております。当ホームページのWeb予約フォームや、お電話からでもお問合せいただけますので、まずは一度、ご相談ください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。