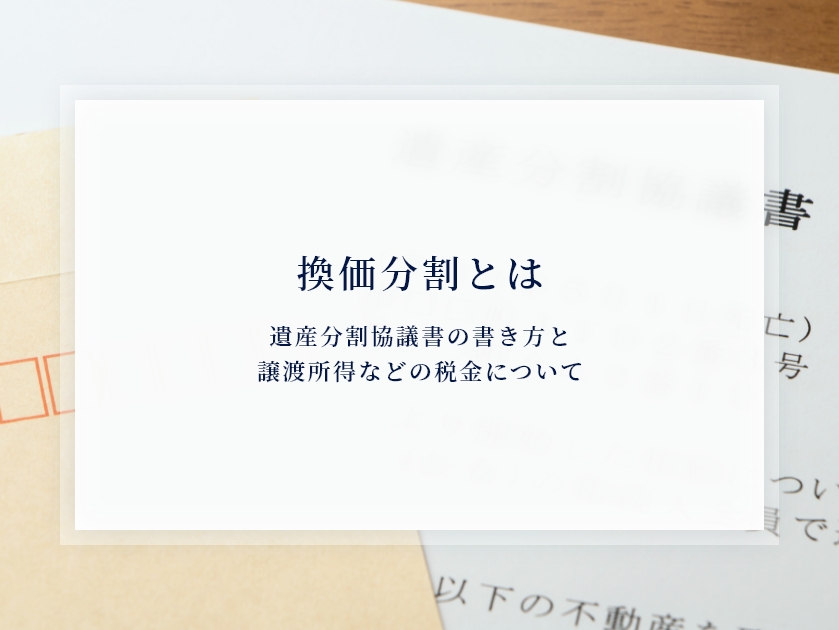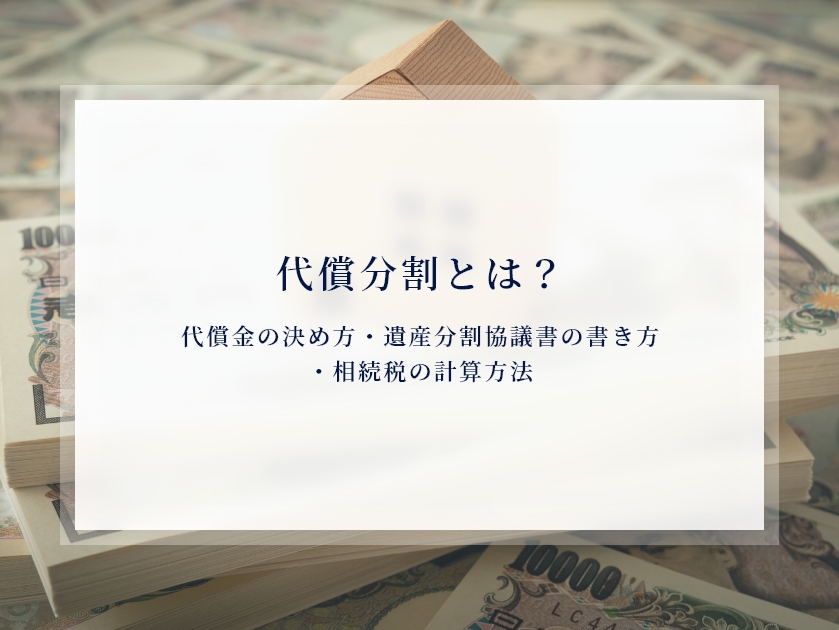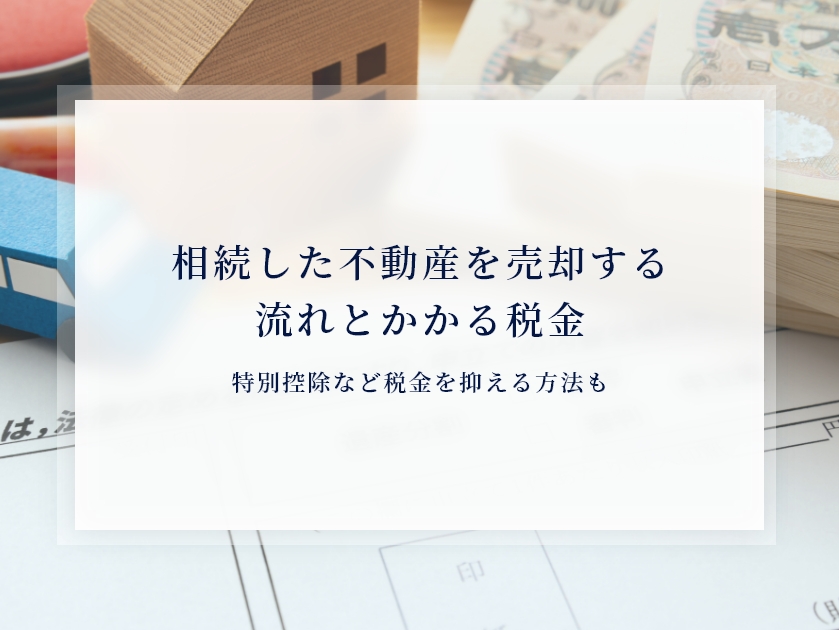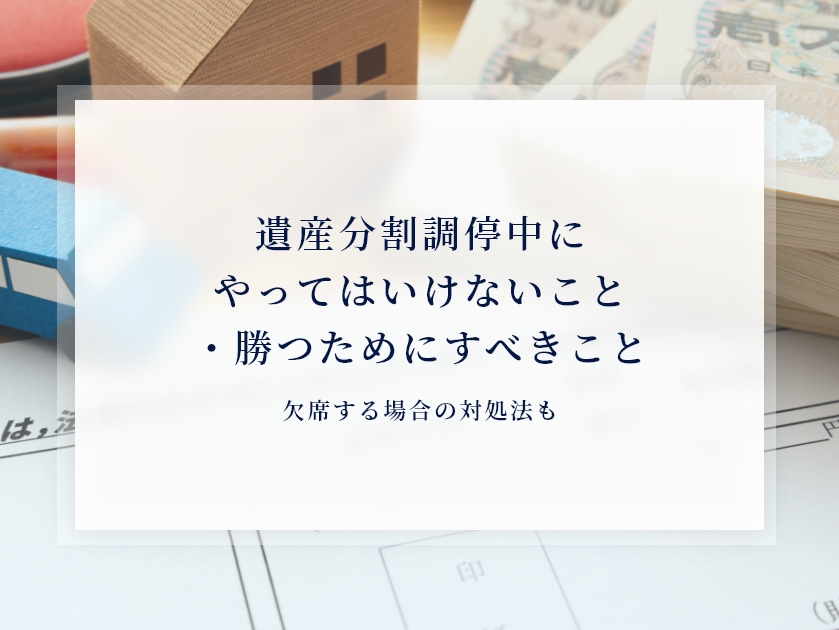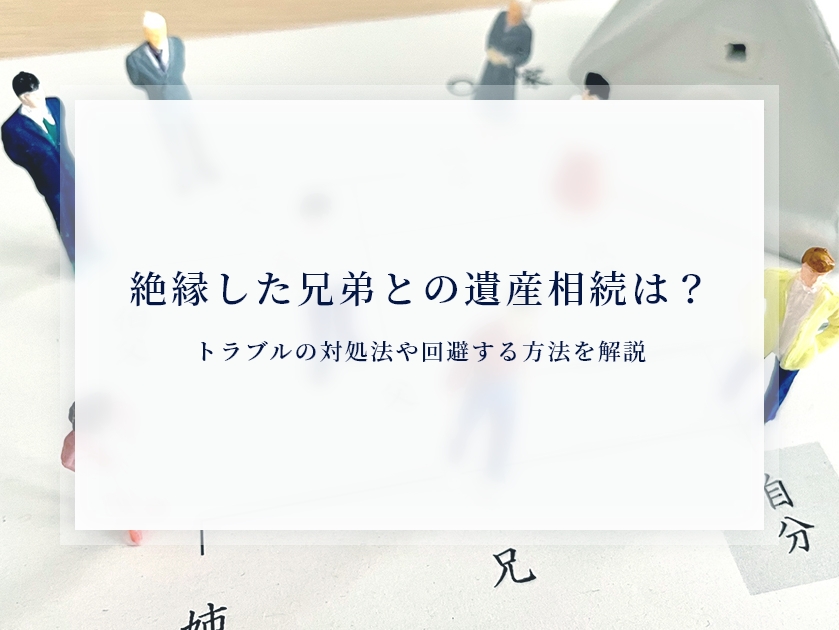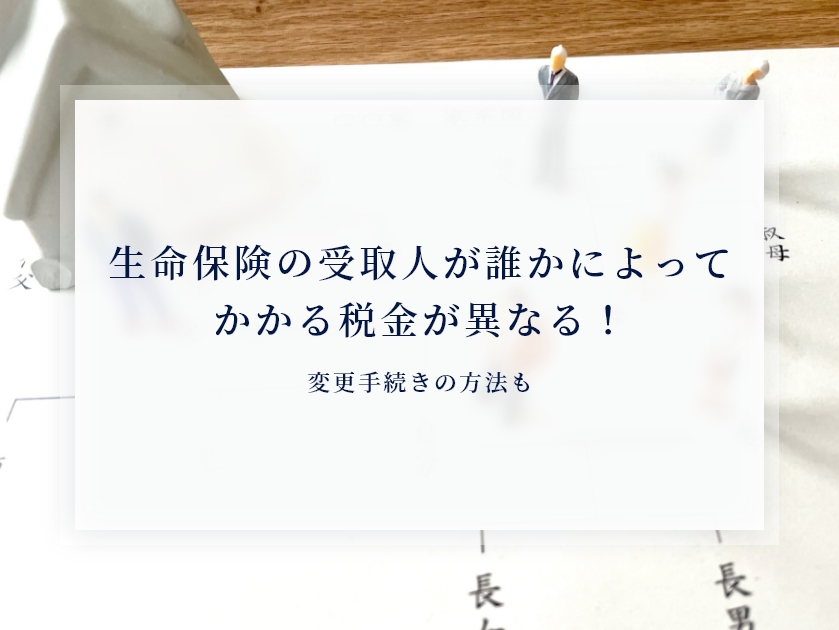土地の相続│相続した土地の名義変更の手続きや注意点などを解説
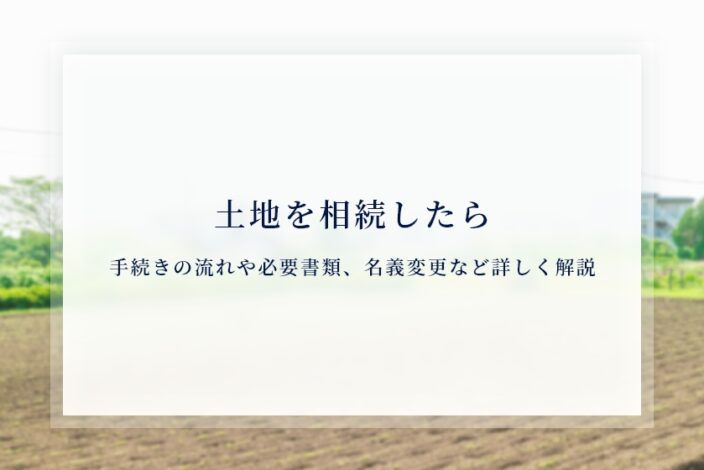
相続には土地がつきものですが、土地を相続するというのは、単に土地をもらって終わり、というわけではありません。土地の相続手続きに関しては、名義変更の手続きや相続税の申告手続きなど、さまざまな手続きが必要になってきます。
また、土地は分割の方法や内容についても、相続人間でのトラブルに発展しやすい相続財産です。土地のような不動産の場合、現金とは異なり簡単に分割できないため、どういった方法で分割するのか、争いになるケースが少なくありません。
また、相続税の計算や申告手続きも煩雑なので、正確な知識がなければ損をしてしまうこともあります。
そこで、この記事では、土地を相続する際に必要な名義変更の手続きを中心に、土地の相続登記について弁護士がわかりやすく解説させていただきます。
「相続手続きで土地について揉めているけど、何から手を付ければ良いのかわからない・・・」といった時に、本記事が手続きを進める一助となりましたら幸いです。
目次
土地の相続
(1)土地の相続の流れ
土地を相続する際の手続きの一般的な流れは以下の通りです。
- 遺言書の有無を確認する
- 相続人を確定する
- 相続財産を確定する
- 遺産分割協議で遺産の分割方法を決める
- 名義変更を行う
- 相続税の申告・納付を行う
それぞれについて、以下で詳しく解説していきます。
①遺言書の有無を確認する
まず、遺言書があるかどうかを確認することが重要です。遺言書には、土地を含む財産の分配方法や、誰に相続させるかなど遺産分割の内容が記載されているため、遺言書があれば、その内容に基づいて相続手続きを進めることになります。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、土地などの相続財産の分配方法を話し合って決めることになります。
なお、相続開始時には遺言書が見つからなかったが、後に遺言書が発見されたというような場合には、遺言書の内容が優先されるため、既に進めていた手続きが無効になる可能性があります。
このような事態を避けるためにも、遺言書の有無について入念に確認することが大切です。
②相続人を確定する
遺言書の有無を確認したら、次に相続人を確定させます。
遺言書がない場合、被相続人の財産は、法律で定められた範囲の親族(法定相続人)によって相続されることになります。そのため、まずは亡くなった人の戸籍謄本や除籍謄本を取得し、誰が相続人となるのかを正確に特定する必要があります。
通常、配偶者、子供、親、兄弟姉妹など、被相続人と血縁関係または婚姻関係にあった人が相続人となります。これらの相続人全員が相続人になるのではなく、相続順位に従って、該当する人が相続人となります。相続人の確定は、後の遺産分割協議や相続登記などの手続きの基礎となるため、慎重に行いましょう。
相続人を確定させたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。もし、遺産分割協議をした後に新たな相続人が発覚した場合、すでに行われた遺産分割協議をやり直すことになってしまうため、最初の段階で正確に相続人を把握するようにしましょう。
③相続する土地を確定させる
次に、相続する土地を確定させます。
抜け漏れなく相続手続きを行うためには、被相続人の財産を網羅的に把握する必要があります。
相続財産には、不動産、預貯金、株式、生命保険金などがありますが、特に土地や建物といった不動産の場合、相続人が把握していない不動産があることも少なくありません。
例えば、自宅の近隣の私道について持分があったり、自宅のある土地とは別に農地を持っていたりと、相続人が把握していない土地を被相続人が所有していた可能性があります。
被相続人の所有していた不動産を把握するためには、「名寄帳(なよせちょう)」や固定資産税評価証明書を活用しましょう。
名寄帳とは、固定資産税の課税のために、市区町村で作成される固定資産税課税台帳を、不動産の所有者ごとにまとめたものです。
土地の相続に際しては、固定資産税評価証明書や名寄帳などの書類を用いて、被相続人の所有していた不動産を確認します。同じ市区町村内の不動産を一覧で確認することができるため、納税通知書に記載されていない不動産についても確認することができます。
ただし、名寄帳を取得した市区町村以外に存在する不動産については記載されないため、複数の市区町村で名寄帳を確認しなければならない場合もあります。ですので、名寄帳とあわせて、固定資産税評価証明書や、土地の権利書、登記簿謄本などを確認することが重要です。
相続人の調査では全ての不動産を把握することが難しい場合は、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
④遺産分割協議で土地の分割方法を決める
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議は、相続人が一人でも欠けた状態では合意が成立しないため、全員の参加が必要です。遺産分割協議では、土地などの相続財産について、誰がどういった割合で引き継ぐかを話し合い、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
土地の分割方法にはいくつかの方法があり、分割方法によって相続登記のやり方が異なったり、相続税の金額にも影響が出たりします。詳しくは、本コラムで後述いたしますので、このままお進みください。
⑤名義変更を行う
遺産分割協議で土地の分配について決まったら、実際に名義変更の手続きを進めていきます。
相続人間で話がまとまったとしても、法務局に名義人の変更届けを行わなければ、不動産は被相続人の名義のままとなってしまいますので、忘れずに被相続人から相続人への名義変更手続きである「相続登記」を行ってください。
⑥相続税の申告・納付を行う
不動産の名義変更が終わったら、相続税の申告手続きと相続税の納付を行います。
相続税は、不動産を含む遺産の総額が基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える場合に発生します。相続税が発生するかどうかを確認するためには、まず被相続人の財産の総額を把握し、基礎控除額と比較する必要があります。
相続税の申告と納付の期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限内に申告や納付が行われないと、追徴課税が発生したり、罰則が科せられたりする可能性があるため、名義変更後はすぐに申告手続きを進めて納付するようにしましょう。
さて、以上が不動産に関する相続手続きの全体的な流れになります。
それでは次に、そもそも不動産をどのように遺産分割できるのか、基本的な4つの分割方法を把握しておきましょう。
(2)相続した土地の分割方法
①現物分割
現物分割は、相続財産をそのままの形で各相続人に分割する方法です。
例えば、預貯金を長男、有価証券を長女、実家を次男に渡すといったように、各種財産を相続人で物理的に分配します。この方法のメリットは、手続きがシンプルでわかりやすく、思い入れのある財産をそのまま残せる点です。
一方、現物で分けようとすると、法定相続分に従って公平に分けるのが難しいというデメリットがあります。また、一人の相続人が土地や家といった高額な相続財産を相続すると、他の相続人の取得分が少なくなり、不公平感が生じやすいです。
特に、土地に関しては、法定相続分通りに平等に分割することも可能ですが、土地が広くない場合、分割によって売却が困難になるほか、活用が難しくなるというデメリットもあります。
したがって、現物分割を選択する際には、財産の種類や相続人の状況を考慮し、不公平感が生じないよう配慮することが重要です。
②換価分割
換価分割は、相続財産を売却して現金化し、その金額を基に相続人間で分割する方法です。特に、相続財産の大部分が不動産の場合に適しています。
この方法のメリットは、現金に換えることで公平な分割がしやすくなることです。例えば、土地が3,000万円で売れた場合、相続人が子供3人とすると、1人あたり1,000万円ずつ分配することができます。
ですが、不動産の売却には時間と費用がかかってしまいます。
また、その不動産に人が住んでいる場合や、すぐに買い手が見つからない物件の場合は、売却自体が困難になるというデメリットもあります。
換価分割について、下記記事で詳しく解説しておりますので、ぜひご一読ください。
③代償分割
代償分割は、特定の相続人が土地などの特定の財産を単独で相続し、他の相続人に対してその代償として金銭を支払う方法です。特定の相続人が財産を保持でき、現金での分割が可能なため、分割が困難な土地や建物などの財産に適しており、特定の相続人がその財産を一人で取得したい場合に有効です。
例えば、父親が残した土地が4,000万円の価値がある場合、長男がその土地を相続し、母と次男にそれぞれ2,000万円と1,000万円の代償金を支払うことになります。
一方で、代償金を支払う相続人には相応の資金力が必要となり、また、代償金の額の算定には公平な評価が必要となるため、紛争の原因となってしまうこともあります。
下記記事で代償分割について詳しく解説しておりますので、本記事と合わせてご参照ください。
④共有分割
共有分割は、相続財産である土地などを相続人全員で共有する方法です。この方法では、土地を実際に分割せず、相続人それぞれが一定の持分を持つことになります。
例えば、父親が残した土地を、母、長男、長女の3人で共有する場合、それぞれの持分は1/2、1/4、1/4となります。
合意した割合でそれぞれが持分に応じた財産を持つことになるため、相続人間で公平性を保ちやすいのがメリットです。
一方で、将来的に土地を売却したい場合や利用方法を変更したい場合に、共有者全員の同意が必要となるため、意見の相違がトラブルの原因となりやすいというデメリットが挙げられます。また、次の世代への相続が発生した場合、権利関係がさらに複雑化する可能性があります。
(3)土地を相続したくない場合
ところで、ここまでは土地を相続することを前提に解説してまいりましたが、土地を相続したくない場合もあるかと思います。預貯金は相続したいが、土地だけ相続したくない・・・といった場合に活用できる制度が令和5年から始まりましたので、簡単にご紹介させていただきます。
令和5年4月27日より、相続した土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
これは、相続または遺贈によって土地を取得した人が、一定の負担金を納付することを条件に、土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。土地利用ニーズの低下などにより、相続した土地を手放したいと考える人が増加していることから、この制度が導入されました。
相続土地国庫帰属制度を利用することで、不要な土地を国に引き渡すことが可能となります。
なお、全ての土地ではなく、所有者の申請に基づき、法務局による一定の審査を経て、要件を満たしていると判断された土地のみが国庫に帰属することになります。対象となる土地は、管理が困難であることや利用ニーズが低いことなど、一定の条件を満たしている必要があります。
相続土地国庫帰属制度の詳しい内容については、法務省のホームページで解説されていますので、そちらをご覧ください。
参考:相続土地国庫帰属制度について(法務省)
相続した土地の名義変更の手続き
それでは、相続した土地の名義変更手続きについて、詳しく見ていきましょう。
(1)必要書類
法務局で名義変更の手続きを進める前に、以下のような必要書類を準備しましょう。
|
必要書類 |
説明 |
取得方法 |
|---|---|---|
|
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本および除籍謄本 |
結婚や転籍などで変更がある場合もすべて含む戸籍謄本。 |
被相続人の本籍地の市区町村役場で取り寄せ。 |
|
相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本 |
相続人が生存していることの証明。 |
各相続人の本籍地の市区町村役場で取り寄せ。 |
|
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 |
被相続人の登記簿に記載されている住所から死亡時の住所との繋がりを証明。 |
被相続人の最後の住所地の市区町村役場、または本籍地の役所で取り寄せ。 |
|
名義人となる相続人の住民票 |
新しい名義人の現住所を証明。 |
新しい名義人の住民登録地の市区町村役場で取り寄せ。 |
|
固定資産評価証明書 |
不動産の価値を証明。固定資産税納税通知書のコピーでも可。 |
不動産を管轄する市区町村役場で取得、または固定資産税納税通知書で代用。 |
|
遺産分割協議書および相続人の印鑑証明書 |
相続人全員が署名し実印を押した遺産分割協議書と、その実印を証明する印鑑証明書。 |
遺産分割協議書は相続人が作成、印鑑証明書は各相続人の住民登録地の市区町村役場で取り寄せ。 |
(2)土地の名義変更の手続きの流れ
①必要書類を集める
上記の手続きに必要な書類を揃えます。
②登記申請書を作成する
法務局のホームページで公開されている様式を使い、登記申請書を作成します。(法務局HP:「不動産登記の申請書様式について」)
申請書の後ろには、登録免許税を支払うための収入印紙を貼付した白紙の紙をつけます。
各種添付書類を綴じる際には、名義変更後に書類の原本を返却してもらいたい場合に備え、コピーを作成しましょう。原本を返却してほしい書類をコピーし、コピーに「原本と相違ありません」と記載し、署名と捺印します。署名捺印したコピーが返却されない代わりに、原本を返してもらうことが可能です(原本還付)。
申請書や添付書類の作り方については、法務局で相談することもできますので、疑問があれば問い合わせてみると良いでしょう。
③法務局に提出する
全ての書類が準備できたら、法務局に提出します。提出する法務局は、その不動産の所在地を管轄する法務局となります。
原則として窓口に持参しますが、法務局に行くことが難しい場合は、郵送による申請も可能です。郵送の場合、登記申請書に登録免許税分の収入印紙を貼り、添付書類と返信用封筒を同封して送ります。書類の紛失を防ぐために、書留やレターパックなどを使って郵送しましょう。
ただし、郵送の場合でも、補正が必要な場合は窓口に赴く必要があるので注意してください。
提出後、書類の審査が行われます。提出書類に不備があった場合は、法務局から補正の指示がありますので、指示に従って書類を訂正し再提出しましょう。書類に不備がなければ、1~2週間程度で「登記完了証」と「登記識別情報通知書」が交付されます。交付予定日には法務局に取りに行く必要があります。
土地の名義変更にかかる費用
相続した土地の名義変更にかかる費用は、主に「必要書類の取得にかかる手数料」「登録免許税」「司法書士報酬」の3つです。それぞれの費用の概要については、以下の表の通りとなります。
|
費用の種類 |
費用の内容 |
費用の目安 |
|---|---|---|
|
必要書類の取得にかかる費用 |
戸籍謄本(1通450円)や住民票(1通300~400円)印鑑証明書(1通300円)などの取得に必要な費用。 |
数千円~1万円以内 |
|
登録免許税 |
土地や建物の評価額に基づいて算出される税金。評価額の合計に千分の四を掛けた金額。100万円以下の土地は非課税。 |
評価額一千万円の場合は4万円 |
|
司法書士報酬 |
名義変更手続きを代行してもらう場合の報酬。内容の複雑さや相続人の数、不動産の個数によって変動する。 |
約10万円前後 |
(3)相続した土地の名義変更は義務
ところで、この土地の名義変更手続きですが、もし名義変更手続きをしなかった場合は、どうなってしまうのでしょうか。
そもそも、従来は相続による不動産の所有権移転登記は義務ではなく、相続人の判断で登記を行うかどうかが決められていました。しかし、登記がなされないまま放置された不動産が年々増加し、所有者不明の土地問題や相続登記未了による相続トラブルが社会問題化していたのです。
こうした背景もあって、令和6年4月の不動産登記法の法改正により、相続登記が義務化されることとなりました。
具体的には、不動産登記法第76条の2第1項により以下のように定められています。
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない
遺産分割協議によって土地・不動産を相続した場合も、遺産分割協議の成立日から3年以内に手続きをしなければなりません(不動産登記法第76条の2第2項)。
この所有権移転登記申請の期限を正当な理由もなく守らなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります(不動産登記法第164条)。
なお、令和6年4月以前に相続した不動産についても、名義変更をしていない不動産については義務化の対象となっているので、申請忘れがないか十分に注意してください。
(4)土地を相続したら相続税に注意
さて、相続した土地の名義変更が終わりましたら、最後に税金の申告と納付の手続きがあります。土地を相続すると、どれくらいの税金がかかるのでしょうか。
相続した土地に関する税金としては、主に相続税と固定資産税があります。
固定資産税は、土地や建物などの不動産を所有している人が毎年支払う税金で、市町村が徴収します。相続した土地については、名義変更後に相続人が固定資産税の納税義務者となります。
一方、相続税とは、被相続人の死亡により相続が発生した際に、相続人が支払う税金のことです。
亡くなった親から土地や建物を相続する場合、名義変更の費用だけでなく、こうした相続税が発生する可能性があるため、注意が必要です。
相続税は、故人の遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額に対して課税されます。基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」と定められています。
例えば、被相続人の配偶者と子ども2人が相続人である場合、法定相続人の数は3人となるため、基礎控除額は「3000万円+(600万円×3)=4800万円」となります。この場合、遺産総額が4800万円を超えなければ、相続税は課税されません。
しかし、遺産総額が基礎控除額を超える場合には、超過分に対して相続税が課されます。相続税の税率は、相続財産の額に応じて変動し、最高で55%に達することがあります。
また、相続税が課せられる場合でも、相続した土地が「小規模宅地等の特例」の要件を満たすと、一定の条件のもとで減税されることがあります。
小規模宅地の特例で相続税を引き下げられる
「小規模宅地等の特例」を活用すると、相続税の負担を軽減することができます。
この制度は、相続によって土地を取得した際に、その土地の評価額を下げて節税できるというものです。特に、被相続人が自宅として利用していた土地を配偶者が相続する場合には、土地の評価額を最大80%引き下げることができます。
この特例を適用できるかは、土地の利用状況や相続人によって異なります。
例えば、自宅用地以外にも、事業用地や賃貸用地など、特定の条件を満たす土地に対しても、小規模宅地等の特例が適用される場合があります。また、相続人が配偶者だけでなく、直系卑属(子供や孫)などである場合も、一定の条件下で小規模宅地等の特例を利用できます。
土地を相続する際には、まず、この小規模宅地等の特例が適用できるかどうかを確認することが大切です。適用できる場合は、相続税の負担を大幅に軽減することができます。
相続税に関する詳細な計算方法や小規模宅地等の特例の適用条件については、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
なお、相続税の計算は、相続した土地の相続税評価額が基準となります。相続税評価額は、土地の実際の市場価格とは異なり、市場価格より低くなるのが一般的です。
土地の評価額については、下記記事で計算方法などを解説しております。本記事と合わせてぜひご覧ください。
【注意点】土地を相続したら
手続きの具体的な内容をご理解いただけたところで、土地の相続に関するいくつかの注意点をおさえておきましょう。
まず、名義変更はなるべく早く行ってください。相続した土地をすぐに売却する予定でも、土地を売却する前に、必ず被相続人の名義から相続人の名義に変更しておく必要があります。これは、土地の所有権を明確にしておくためです。たとえ相続人が土地を利用せずに売却する場合でも、名義変更は必ず必要です。
名義変更をしないままでいると、10万円以下の過料が科される可能性がある他にも、以下のようなデメリットやリスクが発生してしまいますので、注意してください。
①権利関係が複雑になる
遺産分割協議で決まったにもかかわらず、名義変更の手続きしないままだと、不動産を他の相続人を含む全員で共有している状態になってしまいます。また、名義変更をしないまま相続した人が亡くなると、所有権は配偶者や子供に移行してしまい、共有する人数が増えてしまいます。
そうなると、遺産分割協議をまとめることが一層困難になってしまいます。
②子孫の相続で大変になる
次の世代に引き継がれた際、次の世代の相続人は「祖父母の代」「親の代」の2世代分の名義変更手続きが必要です。そうすると、相続関係を示す戸籍等や印鑑証明の収集など、より複雑な手続きとなってしまい、手間も時間もかかってしまいます。
③土地を売却できない
相続登記が出来ていないと、相続人は不動産の権利者でないため、不動産の売却もできません。また、担保を設定することもできません。不動産の相続方法が確定したら、なるべく早めに名義変更の手続きを済ませておくようにしましょう。
④売却時に税金がかかります
土地の売却には、登録免許税、印紙税、譲渡所得税(所得税+住民税)がかかります。印紙税は売買契約書を作成する際に発生します。譲渡所得税は土地を売却して利益が出た場合に課税されます。
⑤売却は3年以内に
相続した土地を売却する場合、3年以内に売却すると、譲渡所得税が軽減されます。また、固定資産税の支払いも免除されます。
相続した不動産の売却を検討されている方は、下記記事もあわせてご覧ください。
土地の相続トラブルを回避するために
①兄弟で話し合っておく
兄弟で土地を相続する際には、何かとトラブルが発生しがちです。
まず、親が存命中に、兄弟間で話し合っておくことが重要です。将来的な土地の管理や処分について、協議しておくことが大切です。特に、土地を兄弟の共有で相続する場合、土地の利用方法や売却を決定する際に、兄弟全員の同意が必要となるため、早い段階で管理方針を決めておくことが、将来的なトラブルを防ぐポイントとなります。
とはいえ、共有状態での相続はトラブルが発生しやすいので、あまりお勧めできません。
そこで、遺産分割協議を通じて、共有ではなく具体的に分割する相続方法を決めておくと良いでしょう。分筆して土地を物理的に分けるか、他の兄弟に代償金を支払うことで単独所有とするか、複数の選択肢が考えられます。
遺産分割協議の話し合いでは、感情的な対立が発生しやすく、なかなか兄弟間で合意に至れない場合もあります。ですので、遺産分割協議の話し合いは、弁護士に代理人として協議してもらうことをお勧めします。
②遺言書を作成しておく
なお、相続手続きに関するトラブルを回避するためには、相続人だけではなく、被相続人の立場からも対策を取っておくことが重要です。
生前に取り得る対策としては、主に「遺言書」と「生前贈与」の2つの生前対策がありますので、簡単にご説明いたします。
遺言書の作成は、生前対策としても比較的簡単で一般的です。
遺言によって被相続人自身の意思を明確に示しておくことで、相続人間の争いを防ぐことができます。また、遺言には法的効果があるため、相続手続きがスムーズに進むなどのメリットがあります。
遺言には一般的に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の二つの形式があります。
公正証書遺言は、遺言者が公証人の前で作成する遺言書で、最も信頼性が高いとされています。この形式の遺言書は、遺言者が考えた遺言内容を公証人が文書にまとめ、公証役場にて証人2名の立会いのもと作成されます。
遺言書の原本は公証役場で保管されるため、偽造や紛失のリスクが低い点が大きな利点です。そのため、法的な保証が強く、家庭裁判所での検認手続きが不要とされています。遺言書の検認とは、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所が自筆証書遺言などの遺言書の存在を確認し、その内容が改ざんされたり破損されたりしていないかを確認するための手続きです。ですので、相続開始後に速やかに遺言書の内容を執行できるというメリットがあります。一方で、公証人手数料などの作成費用が必要です。
自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文を自ら書き、署名・押印を行う遺言書です。形式的には簡便で、公証人手数料のような費用もかからないため、多くの人に利用されています。
一方で、内容や形式に不備があると無効になる可能性があるため、慎重に作成する必要があります。また、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認手続きが必要で、その分相続手続きに時間がかかることがあります。
自筆証書遺言は公証人役場で保管されないため、遺言書が紛失したり、偽造されたりするリスクがあることが大きなデメリットとされています。ですが、令和2年から自筆証書遺言保管制度が始まったことで、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになりました。このため、遺言の紛失や偽造を防ぐことができるようになりました。
また、法務局で保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認手続きが不要とされています。
これらのメリットとデメリットを比較し、自身に最適な方法で遺言書を作成することをお勧めいたします。
②生前贈与しておく
生前贈与とは、財産を持っている人が生きている間に、自分の財産を他の人に無償で譲渡することを指します。その中でも、暦年贈与による生前贈与を活用すると、税金対策をしながら土地を贈与することができるのです。
暦年贈与とは、毎年一定額以下の財産を贈与することで、贈与税の非課税枠を利用して贈与税を節約する方法です。現在の制度では、年間110万円までの贈与が非課税となっています。この枠を利用して、毎年少しずつ土地の持分を贈与することで、贈与税の負担を軽減しながら、ゆっくりと土地を移転することが可能です。
暦年贈与のメリットは、生前に自分の意思を反映させて土地を譲りたい人に贈与できる点です。また、贈与を受ける側にとっても、生前に土地を受け取ることで、将来の相続時におけるトラブルのリスクを減らすことができます。
なお、これまでは被相続人が亡くなる3年前までの生前贈与が相続税の加算対象とされていましたが、令和6年に相続税法の改正があり、亡くなる「7年前」まで、と相続税の加算対象となる期間が延長されました(相続税法第19条1項)。相続税の加算対象になってしまうと、節税の意味がなくなってしまいますので、暦年贈与をする場合はなるべく早めに始めると良いでしょう。
また、生前贈与を行う際には、贈与する土地の評価額や贈与税の計算方法、非課税枠の活用方法など、さまざまな点に注意が必要です。そのため、生前贈与を検討する際には、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
土地の相続に関するQ&A
Q1.土地の相続手続きの流れを教えてください。
A:土地の相続手続きの流れですが、まず、遺言書があるか確認し、相続人を確定するために必要な戸籍謄本や除籍謄本などを取得します。
次に相続財産を調査します。土地を調べるためには、固定資産税評価証明書や名寄帳を取得します。
遺言書がある場合は遺言書に従って遺産分割し、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行って分割します。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成しましょう。
最後に、土地の相続登記の申請を行います。相続登記が完了すれば、土地の名義変更手続きは終了です。
Q2.相続した土地の名義変更はいつまでにする必要がありますか?
A:相続人は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権の取得を知った時から3年以内」に名義変更しなければなりません。
2024年から、相続した土地や建物の名義変更が義務化されましたので、正当な理由なく名義変更を怠った場合、10万円以下の過料に処される可能性があります。
また、2024年4月1日以前に亡くなり、まだ相続人名義に変更されていない土地や建物についても対象となるので、注意が必要です。
Q3.相続した土地を売却すると税金はどうなりますか?
A:相続した土地を売却する場合、売却益に対して所得税と住民税が課税されます。これを譲渡所得税と呼びます。譲渡所得は、売却価格から取得費(相続時の評価額など)と譲渡費用を差し引いた金額で計算されます。また、相続してから3年以内に売却した場合は、短期譲渡所得として税金が軽減されることがあります。税金の計算は複雑なため、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
まとめ
土地の相続は、戸籍謄本の取得から始まり、遺産分割協議書の作成、相続登記の申請や相続税の納付と、さまざまな手続きが必要です。こうした土地の相続に関する手続きは何かと複雑で時間や手間がかかるため、慌ただしい中で進めていくのは骨の折れることと思います。
また、相続税の申告においては、本記事でも解説した「特例」の適用可否によって、税額が大きく変動することがあります。
さらに、相続した土地の名義変更は令和6年4月から義務化されたため、期限内に手続きを完了させるよう注意しなければなりません。
このように、土地の相続は面倒なことが多いです。スムーズに手続きを進めるためにも、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による初回相談を無料で行っております。本ホームページのWeb予約フォームやお電話にて、お気軽にお問合せください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。