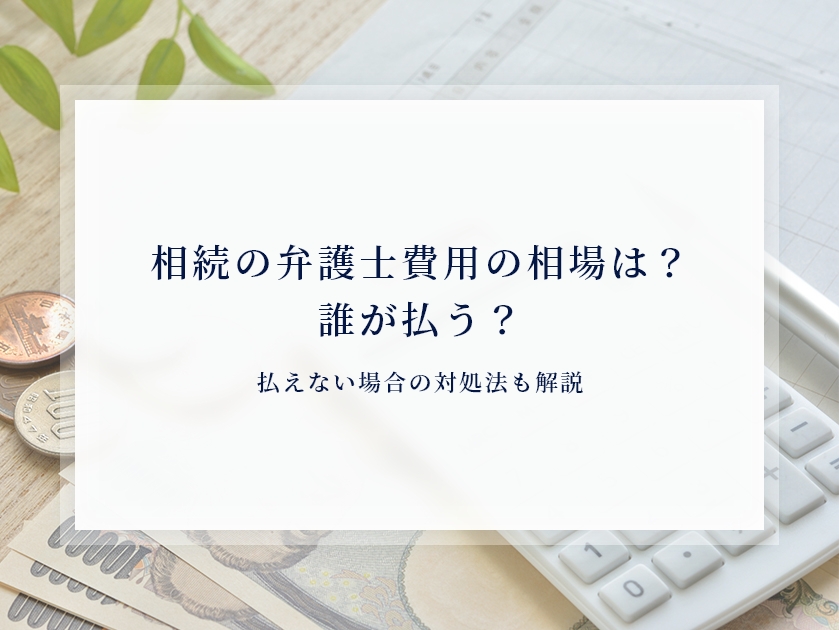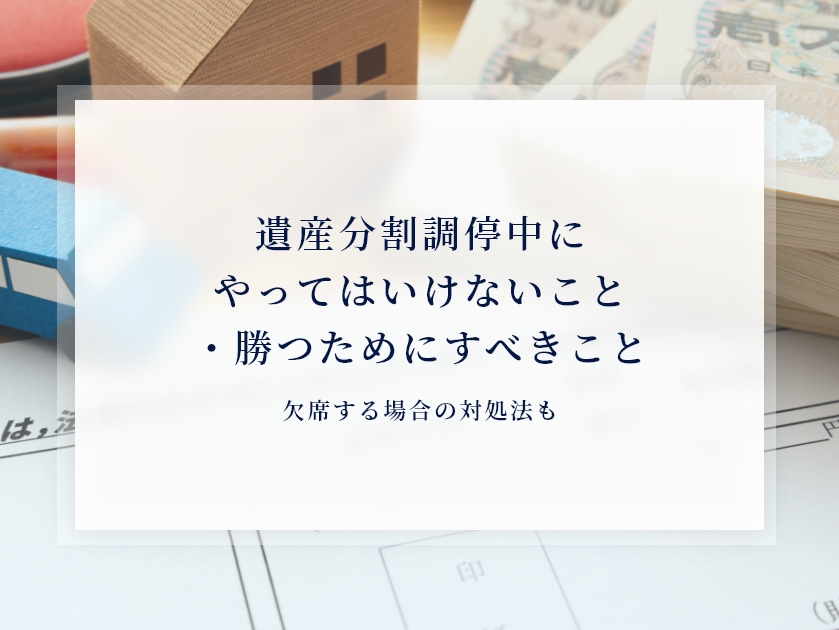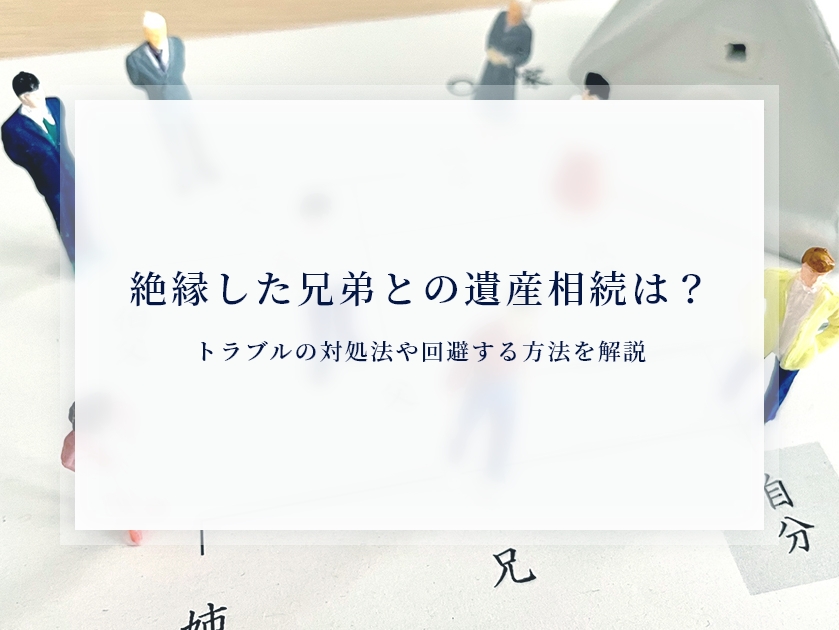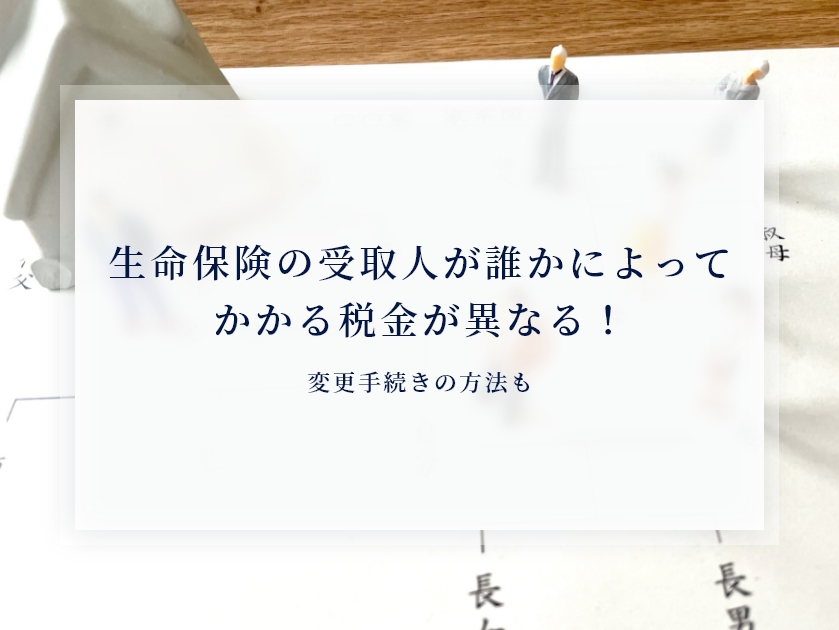遺産分割調停|遺産分割調停とは?申立ての流れや管轄、費用なども弁護士が解説
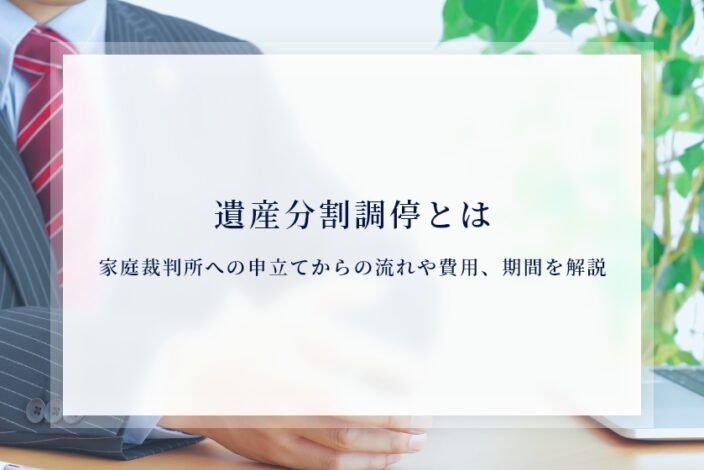
遺産相続では、相続人の間で意見が対立してしまい、なかなか遺産分割を進められないことも少なくありません。
そうした場合に利用されるのが、家庭裁判所で行う遺産分割調停です。
遺産分割調停とは、被相続人が残した財産の分割について、中立的な第三者である調停委員を通じて、家庭裁判所で話し合う手続きです。
家庭裁判所での手続き、と聞くとハードルが高く感じられるかもしれませんが、メリットも多いので、ぜひ知っておいていただきたい手続きです。
そこでこの記事では、遺産分割調停とはどういった手続きなのか、弁護士が解説させていただきます。申立てに関する基本的な知識に加え、遺産分割調停申立てから調停成立するまでの流れ、必要となる費用や期間などについて、わかりやすく解説させていただきます。
遺産分割調停を検討中の方にとって、本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。
目次
遺産分割調停
遺産相続争いはドラマやフィクションの中だけ、と思われているかもしれませんが、相続人同士でもめてしまうことは、意外に少なくありません。
そんなときに利用するのが、家庭裁判所での「遺産分割調停」です。
遺産分割調停とは
1.遺産分割調停とは
遺産分割調停とは、被相続人の遺した財産について、公平かつ中立的な立場の調停委員が当事者の意見を調整し、相続争いの解決を目指す家庭裁判所の手続きです。
遺産分割について相続人間で話し合いで解決できないときや、協議をすることができないときに、相続財産の分割を家庭裁判所に請求することができるとされています(民法第907条2項)。
(遺産の分割の協議又は審判)
民法第907条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
遺産分割調停の特徴は、裁判所が直接判断を下す裁判とは異なり、当事者双方が自らの意思で合意に至ることを目指す、という点にあります。
そして、この合意による解決を目指す↑で非常に重要な役割を果たすのが「調停委員」です。
調停委員は、当事者から詳細な事情を聞き出し、提出された資料や証拠を確認し、紛争の背景から各当事者の立場、相続する財産の内容について詳細に把握します。場合によっては相続財産について専門的な鑑定を行い、客観的な資料に基づいて遺産分割方法の案を検討します。
相続人がどのような遺産分割を望んでいるのかを把握し、公平な解決策を提示することで、相続人全員が合意できるように手助けをするのが、遺産分割調停なのです。
なお、遺産分割調停を進める裁判所と調停委員は、あくまで中立的な立場です。申立人と相手方のどちらかに味方する、といったことはありません。
どういった場合に遺産分割調停をやるべき?
遺産分割調停は、話し合いで解決できなかったときや、話し合いが難しいときに利用するのが一般的です。
例えば、遺産分割の話し合いがまとまらなかった場合や、遺産分割の話し合いが長引き、なかなか合意の目途が立たない場合、そもそも遺産分割の話し合いに参加しない相続人がいる場合などには、遺産分割調停を検討することになるでしょう。
連絡の取れない相続人がいる場合などにも、遺産分割調停で解決を図ることが考えられます。
参考:遺産分割調停(家庭裁判所)
2.遺産分割調停の申立人・相手方
遺産分割調停の当事者を確認しておきましょう。
2-1.遺産分割調停の申立人
裁判所のホームページによれば、次の三者が遺産分割調停の申立人と記載されています。
- 共同相続人(民法第907条2項)
- 包括受遺者(民法第990条)
- 相続分譲受人(民法第905条)
共同相続人は、遺産分割中の法定相続人のことです。通常はこのケースが一般的でしょう。
包括受遺者とは、遺言によって、被相続人の財産の全部または一定の割合で示された部分を与えられる人のことです。
相続分譲受人とは、文字通り、相続人からその相続分を譲り受けた人を意味します。とはいえ、相続分を譲り受けるケースというのはそう多くありません。
また、この三者以外にも、以下のような人が遺産分割調停を申し立てることがあるとされています。
- 相続人の債権者(名古屋高判昭和 43年1月 30 日)
- 遺言執行者(民法第1012条)
2-2.遺産分割調停の相手方
一方、遺産分割調停の「相手方」となるのは、申立人以外の相続人全員です。
争う意思のない相続人がいたとしても、遺産分割自体は終わっていないため、その相続人も「相手方」となります。
なお、遺産分割調停は、原則として当事者は全員参加しなければなりません。もし行方不明の相手方がいる場合に、遺産分割調停を進めてしまうと、その調停は無効となってしまいます。この場合、裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうか(民法第25条)、失踪宣告の手続き(民法第30条)を取る、といった対応が考えられます。
2-3.遺産分割調停中に当事者が死亡した場合
遺産分割調停が進行している期間中に、当事者である相続人が死亡した場合は、原則として調停手続は終了しません。死亡した当事者の相続人が、その手続上の地位を承継し、遺産分割調停に参加することになります。
この点については裁判例も、「調停事件の係属中に当事者の一方が死亡しても、原則として調停事件は終了せず、死亡当事者の一般承継人が調停手続上の地位を承継する。」と判断しています(東京地判昭和32年1月31日)。
3.遺産分割調停の期間
遺産分割調停の申立てから終結までに要する期間ですが、多くの場合、平均して約1年程度の期間がかかるといわれます。
ケースによっても異なりますが、調停は通常、月に1回程度のペースで開かれ、各期日では1時間から2時間程度の話し合いが行われます。最初の調停期日は申立てから約1~2か月後に設定され、その後は大体1か月ごとに調停期日が設けられます。
遺産分割調停の期日の回数に関しては、司法統計「遺産分割事件数―終局区分別審理期間及び実施期日回数別―全家庭裁判所」(令和元年度)によると、一般的な回数は6回から10回とのことです。
ただし、これはあくまで平均的な期間です。実際には数回の期日で合意できて半年以内に終わる場合もありますし、反対に複雑なケースで争点も多い場合だと、3年以上かかることもあります。
4.遺産分割調停のメリット・デメリット
4-1.遺産分割調停のメリット
遺産分割調停のメリットを一言でいいますと、感情的な対立を避けながら、公平かつ効率的に遺産分割の問題を解決できる点にあります。
①冷静な話し合いができる
遺産分割調停では、相続人同士が直接顔を合わせることなく、調停委員を通じて意見を交換することができます。
調停委員がまず相続人Aの意見を聞いた後、別の場で相続人Bの意見を聞くなど、同じ空間で相続人同士が対話することのないように配慮されているためです。
これにより、相続人は互いの立場を理解しながら、効率的な話し合いができ、感情の行き違いによるトラブルを防ぐことができるのです。
②公平な解決策を提案してもらえる
遺産分割調停では、相続人らと利害関係のない第三者である調停委員が中立的な立場で関与することで、当事者間の感情的な対立や偏見を排除した公平な遺産分割方法を提案してもらえます。
各相続人の個別の状況や希望も十分に考慮してもらえます。ですので、単に法律に従った形式的な解決ではなく、各当事者にとって実質的に公平な結果が得られるよう、工夫された提案が期待できます。
③法律的にも妥当な遺産分割が期待できる
調停委員は、単に当事者の話をすり合わせるだけでなく、法的な知識や実務経験に基づいて、裁判所とともに合理的かつ妥当な解決策を検討します。
そのため、法律的に見ても妥当で公平な遺産分割を実現することが期待できるのです。
以上の通り、遺産分割調停にはこうした大きなメリットがありますが、一方で下記のようなデメリットも存在します。
4-2.遺産分割調停のデメリット
①時間の制約があり、長期化する可能性がある
調停は裁判所の調停室で行われるため、基本的に裁判所が開庁している平日の昼間に期日が開催されます。平日の夜間や土日は裁判所が開いておりませんから、調停期日に出席するためには、働いている人は仕事を休まなければなりませんし、小さい子供がいる場合は託児についても調整しなければなりません。
さらに、当事者、調停委員、裁判所のスケジュールの調整が必要となるため、次の期日が開かれるまでに時間がかかってしまうことも珍しくありません。
このように、時間の制約がある中で進めていかなければならず、長期化する可能性があるのです。
②自分の希望通りの結果が得られるわけではない
当事者同士の話し合いでは、全員が納得すればどのような内容の遺産分割でも可能です。
しかし、遺産分割調停は、調停委員や裁判官のもとで話し合いが進められるため、法的に正しくない主張は「そんなことは認められない」と退けられる可能性が高いです。法的にも正しい主張を調停委員や裁判所に伝えることができなければ、かえって不利な内容で調停成立となってしまうことも珍しくありません。
③調停不成立の場合もある
遺産分割調停は、当事者の話し合いによる合意が大前提です。そのため、一人でも合意しない相続人がいれば、調停不成立となってしまうこともあります。
調停不成立となったら、遺産分割審判の手続きに移行することになります。
遺産分割調停の流れ
1.遺産分割調停の手続きの流れ
以下では、遺産分割調停の申立てから、調停成立または不成立までの流れを順に説明させていただきます。
1-1.必要書類を準備する
遺産分割調停を申し立てる際には、以下のような必要書類を家庭裁判所に提出する必要があります。
| 必要書類 | 内容 | 書式・取得方法 |
| 遺産分割調停の申立書 | 申立書1通及びその写しを相手方の人数分 | |
| 事情説明書(遺産分割) | 遺言書の有無や相続人の範囲、遺産について等、遺産分割の前提となる内容を記載 | Excel |
| 進行に関する照会回答書 | 調停期日の希望日や、相手方の出頭の可能性等を記載 | Excel |
| 当事者目録 | 申立人・相手方の住所氏名を記載 | |
| 送達場所等届出書 | 裁判所から書類を受領する送達場所を記載 | Word |
| 土地遺産目録 | 遺産全て(不明なもの、分割済遺産目録に記載するものを除く)を記載 | |
| 建物遺産目録 | ||
| 現金,預貯金,株式等遺産目録 | ||
| 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て | ①相続人が配偶者・子・親の場合:被相続人の出生時(被相続人の親の除籍謄本又は改製原戸籍等)から死亡までの連続した全戸籍謄本 | 市区町村役場 |
| ②相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合:被相続人の父母の出生時(被相続人の父方祖父母及び母方祖父母の除籍謄本又は改製原戸籍等)から被相続人の死亡までの連続した全戸籍謄本 | 市区町村役場 | |
| ③相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者(甥姪)が含まれる場合:上記①②のほかに、本来の相続人(子又は兄弟姉妹)の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本 | 市区町村役場 | |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 発行から3か月以内の原本 | 市区町村役場 |
| 被相続人の住民票の除票 | 原本 | 市区町村役場 |
| 相続人全員の住民票 | 発行から3か月以内の原本 | 市区町村役場 |
| 遺産目録記載の不動産についての資料 | 登記事項証明書(3か月以内の原本) | 法務局 |
| 固定資産評価証明書(3か月以内の原本) | 市区町村役場 | |
| 遺産目録記載の不動産以外のその他の遺産についての証拠資料 | 預貯金の残高証明書写しまたは通帳、証書の写し | 金融機関等 |
| 株式の残高証明書写し | 証券会社等 | |
| 自動車の登録事項証明書の写し又は車検証写し | 運輸支局 |
参考:遺産分割調停の申立書(裁判所)
1-2.管轄の家庭裁判所を確認する
遺産分割調停を申し立てる管轄の家庭裁判所を調べましょう。
調停を行う裁判所を「管轄」といいますが、裁判所の管轄は、事件の内容や当事者の居住地などによって決まります。
「職場に近い裁判所に申し立てよう。」などと自由に決めることはできません。
基本的に、以下の2つの内、いずれかの裁判所が管轄の家庭裁判所になります。
- 相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所
- 当事者全員が合意して定めた家庭裁判所
なお、管轄を調べる際には、裁判所のホームページ「裁判所の管轄区域」をご確認ください。
調停期日の当日は、申立て先の裁判所に出頭する必要があります。
そのため、特に相続人が複数いる場合などは、どの家庭裁判所に申立てれば調停をスムーズに進められるかを考慮し、どの裁判所で遺産分割調停を進めるか、あらかじめ話し合って決めておくことが望ましいです。
1-3.管轄の家庭裁判所で申立て手続きを行う
あらかじめ調べておいた管轄の家庭裁判所で申立て手続きを行います。
窓口では、軽微な不備はその場で直して提出することも可能なため、安心です。申立ては郵送ですることもできますので、自身の都合に応じて、最適な方法で申立てを行いましょう。
申立てをすると、裁判所から申立人や相手方に、書面や電話による実情の照会がなされることもあります。裁判所から連絡があったら、落ち着いて対応しましょう。
遺産分割調停の申立てに期限はある?
なお、遺産分割調停の申立て自体には、民法で厳密な請求期限は定められていません。
ですが、原則として、相続開始から10年を経過した後にする遺産分割については、特別受益や寄与分に関する民法の規定が適用されなくなります(民法第904条の3)。
(期間経過後の遺産の分割における相続分)
民法第904条の3 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
この場合は、「法定相続分」または遺言による「指定相続分」によって、画一的に遺産分割されることになります。
1-4.呼出状が送付される
家庭裁判所は、遺産分割調停の申立てを受理すると、担当する裁判官と調停委員を決めます。
遺産分割調停を進行する調停委員会は、裁判官1名と調停委員2名の、合わせて3名で構成されています。
調停委員の選任後、家庭裁判所が初回の調停期日を決定します。調停期日は、申立て後およそ1~2か月以内に指定されることが一般的です。調停期日は、裁判所の開庁時間である月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前10時から午後5時の間で指定されます。
調停期日が決まれば、申立人と相手方に、初回の期日が書かれた「呼出状(調停期日通知書)」が送られてきます。相手方には、呼出状に加え、申立書の写しや照会書なども同封されます。相手方は、照会書に自身の主張を記入して、裁判所に返送します。
1-5.調停期日を繰り返す
遺産分割調停が1回の期日で終わることはほとんどないため、何度か裁判所に通って、合意に向けた話し合いを行う必要があります。
調停委員の信頼を損ねるような言動は避ける必要があるため、たとえ仕事で忙しいとしても、調停期日に遅刻したり、無断で欠席したりすることのないよう注意しましょう。
遺産分割調停は、具体的には次のような手順で進行していきます。
①相続人の範囲の確定
遺産分割調停ではまず、相続人の範囲を確定します。戸籍謄本などを用いて、誰が相続人であるかを確定し、遺産分割協議の当事者を明確にします。養子縁組や婚姻など相続権の有無に争いがある場合は、遺産分割調停とは別に、家庭裁判所に人事訴訟を提起する必要があります。
②遺産の範囲の確定
次に、遺産目録および財産に関する添付書類を基に、遺産の範囲を確定します。遺産目録に記載されていない遺産が存在すると主張する場合には、その主張を裏付ける証拠を提出する必要があります。
③遺産の評価の確定
その後、遺産分割の対象となる財産の価値を算定します。不動産や非上場会社株式など、評価が難しい財産については、鑑定人による鑑定を行うこともあります。この際、調停の申立て費用とは別に、鑑定費用がかかります。
④特別受益と寄与分の確定
法定相続分や指定相続分(被相続人の遺言によって指定された相続分)を基準に、特別受益や寄与分などを考慮して、各当事者が取得する財産の割合を決めます。
⑤遺産分割方法の確定
これまでの調停期日で話し合った内容をもとに、各当事者が取得する財産の具体的な内容を記載した遺産分割案を作成します。遺産分割案に相続人全員が合意すれば調停が成立し、合意内容を記載した調停調書が作成されることになります。
1-6.調停の終了
調停成立の場合
遺産分割調停で、相続人間での話し合いが合意に至った際は、「調停調書」が作成されます。
調停調書は、遺産分割に関する合意内容が詳細に記載された書面です。調停調書は遺産分割協議書と同じように、第三者に対して「相続人全員が合意した」ことを証明する書類になるので、相続手続きで利用することができます。
調停不成立の場合
遺産分割調停で当事者間での話し合いがまとまらない場合には、調停不成立という結果になります。
不成立かどうかの判断は、調停委員が行います。不成立と判断されると、調停手続きは終了し、自動的に審判手続きへと移行します。
審判手続きでは、調停とは異なり、裁判官が当事者から提出された書類や様々な資料をもとに事実関係を検討し、遺産分割の方法を決定します。つまり、審判手続きでは、調停のように当事者の意思を尊重した話し合いは行われないのです。
調停はあくまでも話し合いなので比較的柔軟に進行しますが、審判では当事者の主張立証、法律、証拠に基づいて、裁判所が厳格に判断することになります。
2.遺産分割調停で聞かれること
さて、遺産分割調停の全体的な流れは上記の通りですが、このように遺産分割調停を進めていく中で、調停委員からそれぞれの相続人に対して、さまざまな質問がなされます。
具体的には、誰が相続人なのかという関係性や、遺産としてどのような財産があると認識しているか、などを確認されます。
また、それぞれの相続人がどのような分割方法を希望しているのか、その理由についても質問されます。
他の相続人の主張に対して、どのような意見を持っているか、譲れるポイントや譲れないポイントがあるかどうかなど、各自の意見を調整するために必要なことに関して、詳しく聞かれることになります。
調停委員は、こうしたやり取りで丁寧に確認しながら、相続人同士の意見の調整を進めていくのです。
遺産分割調停の費用
1.印紙と郵券が必須
遺産分割調停の手続きを進めるにあたっては、手数料などの費用がかかります。遺産分割調停の申立てを検討する際には、一般的に以下の費用がかかることを考慮しておきましょう。
|
費用の種類 |
費用の概算 |
説明 |
|---|---|---|
|
申立費用 |
1,200円 |
申立書に貼付する収入印紙の費用。 |
|
予納郵券 |
数千円程度 |
連絡用の郵便切手として裁判所に事前に納付。 |
|
必要書類の取得費用 |
数千円~数万円程度 |
戸籍謄本や不動産登記簿謄本などの公的書類取得費。 |
|
不動産鑑定費用 |
20~60万円程度 |
不動産の価値評価に鑑定人を依頼する際の費用。 |
なお、遺産分割調停を弁護士に依頼することもあるかと思います。
ですが、弁護士に依頼するにはいくらかかるのか、高額になるイメージがあって不安、という方もいらっしゃるかもしれません。
自分で遺産分割調停を進める場合よりも費用が必要となってしまいますが、お金にはかえられないメリットもあるため、まずは無料相談をして弁護士に依頼すべきか熟考していただくことをお勧めいたします。
2.遺産分割調停の費用負担はどっち?
遺産分割調停のような家事事件の手続費用は、原則として当事者が各自で負担することとなっています(家事事件手続法第28条1項)。
(手続費用の負担)
家事事件手続法第28条 手続費用(家事審判に関する手続の費用(以下「審判費用」という。)及び家事調停に関する手続の費用(以下「調停費用」という。)をいう。以下同じ。)は、各自の負担とする。
2 裁判所は、事情により、前項の規定によれば当事者及び利害関係参加人(第四十二条第七項に規定する利害関係参加人をいう。第一号において同じ。)がそれぞれ負担すべき手続費用の全部又は一部を、その負担すべき者以外の者であって次に掲げるものに負担させることができる。
一 当事者又は利害関係参加人
二 前号に掲げる者以外の審判を受ける者となるべき者
三 前号に掲げる者に準ずる者であって、その裁判により直接に利益を受けるもの
3 前二項の規定によれば検察官が負担すべき手続費用は、国庫の負担とする。
なお例外的に、裁判所は、事情によっては各自負担の原則によらず、手続費用の全部または一部を、本来負担すべき者以外の当事者や利害関係人などに負担させることができる、とされています(家事事件手続法第28条2項)。
遺産分割調停の注意点
最後に、遺産分割調停をなるべく有利に進めるために、心がけておきたい注意点を確認しておきましょう。
①調停委員には真摯に対応する
遺産分割調停を有利に進める上で、調停委員に対する礼儀正しい態度も大切です。
調停委員は公正と中立性を保ちつつ、当事者の意見を聞きますが、礼儀正しく、誠実な対応をすることで、より良い心象を与えることができます。
具体的には、調停委員に対して以下の点を心掛けましょう。
- 相手の質問に対しては、真摯に回答することで、誠意を示しましょう。
- 無礼な態度や強引な主張を避け、敬意を持って接し、冷静に対応しましょう。
- 相手の悪口を控え、調停委員の指示には適切に反応し、相手方への理解を示しましょう。
もっとも、調停委員は、法律のプロではないことが多く、法的に間違ったことを言ってしまうことや、意図せず不公平な対応になってしまうこともありえます。その時には、しっかりと意見して、法的に適正に手続きを進めてもらえるようにしましょう。
②事前準備
遺産分割調停の期日にはしっかりと準備して臨みましょう。
準備不足は、過度な緊張や感情的な発言につながり、調停委員に対する印象を悪くする原因になりかねません。また、主張したいことを十分に伝えられないリスクもあります。
具体的な準備としては、自分が伝えたいポイントや主張を、メモ書きにして整理しておくと良いでしょう。調停期日という限られた時間の中で、伝えるべきことを明確に伝え、スムーズにやり取りを進めることが可能になります。
③相手方の意見も理解し譲歩することも必要
相手方の主張や立場を理解し、譲歩できる部分があれば、柔軟な姿勢を示すことが、調停をスムーズに進めるためには不可欠です。
相手方の意見を聞き、時には譲歩することは、調停委員に対して好印象を与えます。それだけでなく、相手方からの歩み寄りも引き出すことが期待できます。こちらが譲歩の姿勢を見せることで、相手も自身が譲れる部分について考えるきっかけになり、双方が納得できる解決に繋がるでしょう。
そのためには、自分の主張の中で譲れるポイントと譲れないポイントを明確に区別し、優先順位をつけておくことが大切です。そうすることで、調停の場で冷静に自分の立場を主張しつつ、相手方の提案に対しても柔軟に対応できるようになるでしょう。
④法的知識をもとに主張する
遺産分割や相続に関わる問題では、単に個人の希望を述べるだけでは不十分です。調停委員や裁判官に納得してもらうためには、法律に基づいた主張を行う必要があります。
具体的には、法定相続分、寄与分、特別受益など、相続問題に関する基本的な知識を身につけ、自分の主張が法律的に妥当であることを立証する必要があります。
とはいえ、遺産分割が始まってからすぐに法的知識を身につけるのも大変です。こういった場合には、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
⑤客観的な証拠を提示する
当事者の意見が対立する中で自分の主張を通し、相手方の主張を否定したいのであれば、客観的な証拠が不可欠です。客観的な資料や証拠を用いて、相手方の主張のどの部分が矛盾しているのか、自分の主張が正当であるのかを具体的に指摘することが必要です。
「簡単だから、全部の財産を売却して現金化して分けよう。」などと単に主張するだけでは、相手方や裁判所を納得させることができません。主張を裏付ける客観的な資料を事前に準備しておき、適切なタイミングで積極的に活用しましょう。
迷ったときは弁護士にご相談ください
遺産分割調停は、時に数か月から数年に及ぶ長期間にわたることがあり、心身にかかるストレスは計り知れません。迷ったときには一人で抱え込まずに、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士は、遺産分割調停の申立て、必要書類の収集・作成などの手続きを代行するため、個人で進めるよりも時間と労力を大幅に節約できます。法律に詳しくないと、日常生活と並行して必要書類を準備するのは大変ですが、弁護士に依頼すれば、その負担を軽減できるでしょう。
また、遺産分割調停の期日には弁護士が同席し、法的根拠に基づいて依頼者の主張を説明します。調停で自分の意見を適切に伝えるには法的知識が不可欠ですが、弁護士が代理人として交渉や説明を行うことで、法的にも適切な主張を行うことが可能です。
弁護士に依頼していただくことで、遺産分割調停を有利に進めることが期待できるでしょう。
遺産分割調停に関するQ&A
Q1.遺産分割調停とは具体的にどのような手続きですか?
A: 遺産分割調停は、遺産分割協議では相続人が合意できなかった場合に利用される、家庭裁判所の調停手続きです。実際の遺産分割調停の期日では、調停委員が相続人それぞれから主張を聞き、中立的な立場から意見を調整し、相続人全員が納得できる遺産分割案を提案してくれます。
Q2.遺産分割調停の期間はどれくらいかかりますか?
A: 遺産分割調停の期間はケースによって大きく異なりますが、一般的には調停申し立てから約1年程度はかかるとされています。しかし、相続財産の内容や相続人間の意見の対立度合いによっては、数か月で解決する場合もあれば、複雑なケースでは3年ほどかかることもあります。円滑に解決したい方は、必ず弁護士に相談しましょう。
Q3.遺産分割調停にかかる費用はどれくらいですか?
A: 遺産分割調停にかかる費用は、調停の申立てにかかる手数料、書類を取り寄せる費用や交通費といった実費のほか、弁護士に依頼する場合は弁護士費用が必要となります。
申立費用の収入印紙代や送達用の予納郵券代、必要書類の取得費用などの実費は、数千円から数万円程度となることが一般的です。
弁護士に依頼する場合の費用は、相談料、着手金、報酬金、実費、日当などがあり、依頼する弁護士の方針や相続財産の価値に応じて、数十万円から数百万円と幅広いです。事前に弁護士との契約内容を確認し、費用について明確にしておくことが重要です。
まとめ
遺産分割調停は、被相続人が残した遺産の分割方法について相続人間で意見が合わない時に、家庭裁判所に申し立てを行い、中立的な調停委員を介して合意に至ることを目指す手続きです。
自分の望みを出来るだけかなえたい場合や、出来るだけストレスを減らしスムーズに解決したい場合は、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士は、さまざまな法的手続きを代行することが可能です。専門的な知識に基づいた主張や交渉のサポート、調停手続きにかかる心理的負担の軽減など、多くのメリットがあります。
また、調停が不成立となった場合には、遺産分割審判や訴訟へと移行しますが、これにはさらに時間と費用がかかってしまう可能性があります。そのため、遺産分割調停での解決を目指すことが望ましいでしょう。
相続人同士ではなかなか話がまとまらず、長期化するケースも多いです。
弁護士にご依頼いただくことで、早期解決が期待できます。
遺産分割調停を迷われている方は、ぜひ一度、弁護士法人あおい法律事務所にご相談ください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。