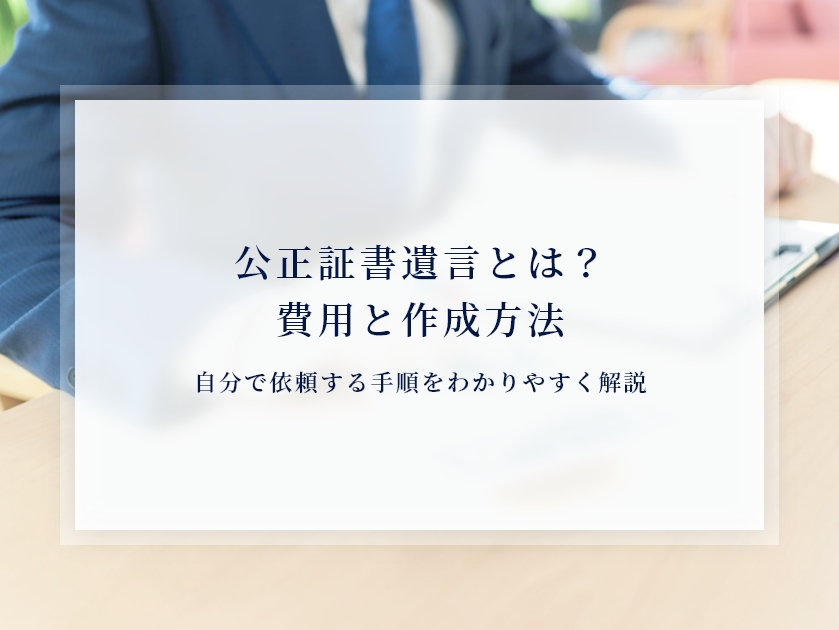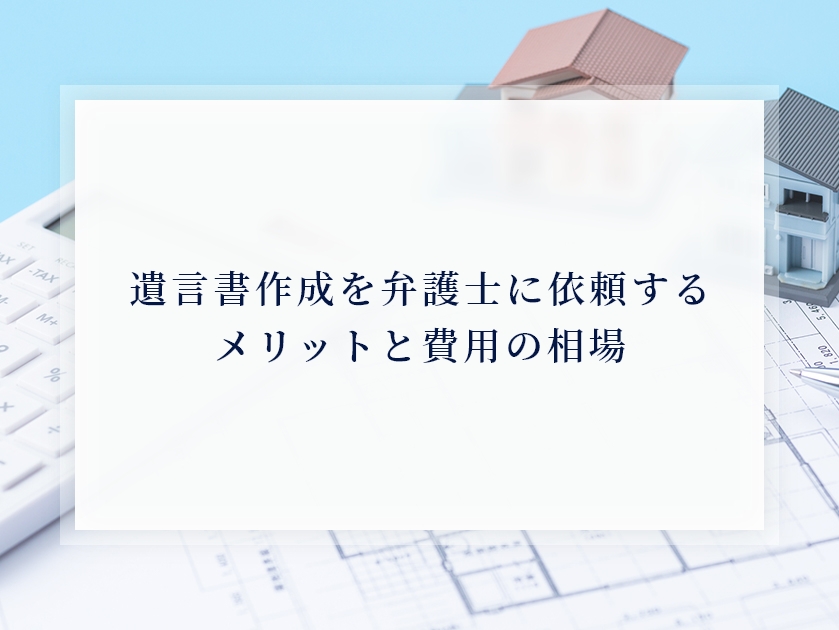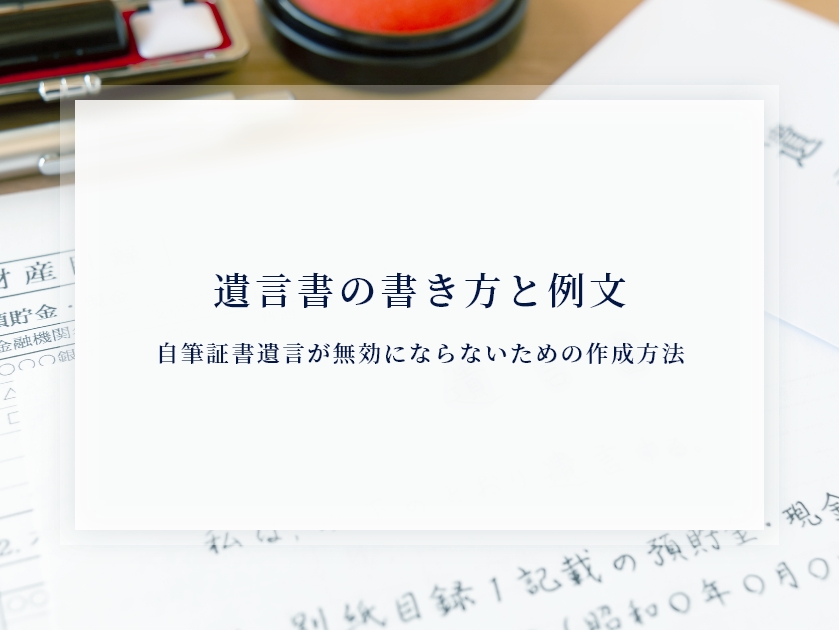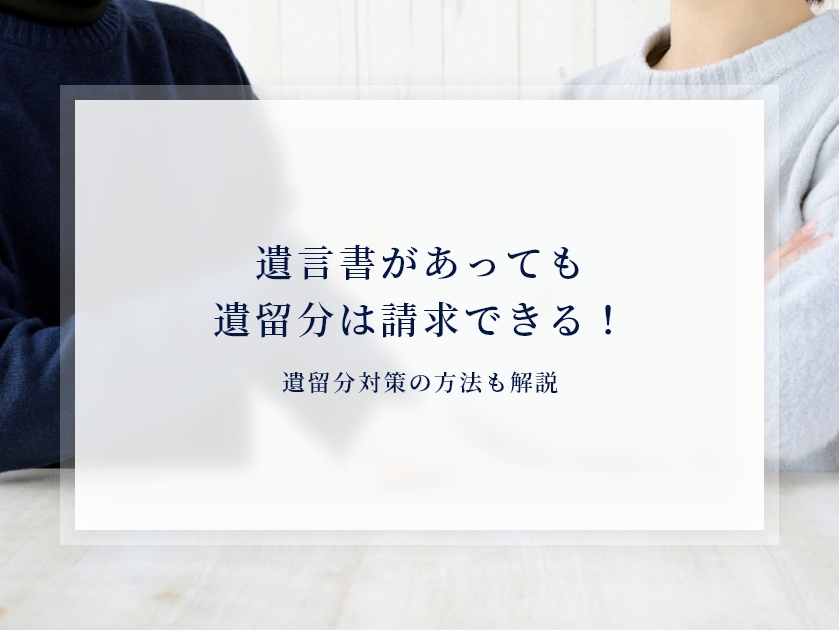公正証書遺言があってももめる?無効や遺留分がトラブルの原因に
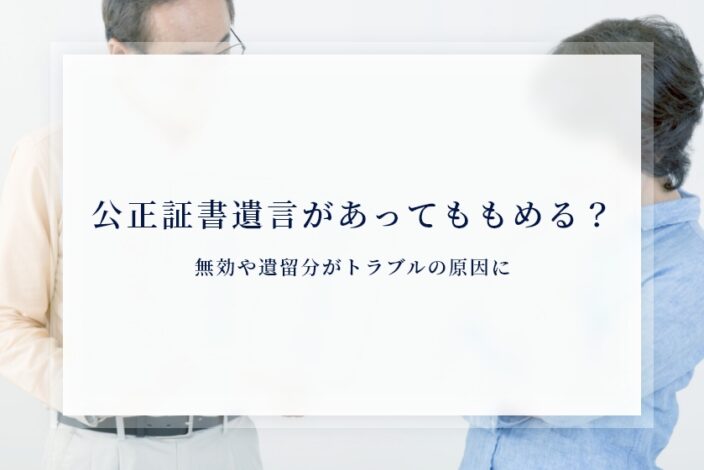
公正証書遺言は、遺言者が公証人の前で遺言内容を確認し、法的に有効な形で作成されるため、もめることが少ないとされています。しかし、現実には公正証書遺言があってもトラブルが発生するケースが少なくありません。例えば、遺言の内容が不明瞭である場合や、相続人の一部が遺留分を侵害されていると主張する場合などが考えられます。
さらに、公正証書遺言自体の有効性が争われることもあります。特に、遺言作成時の遺言者の意思能力や、遺言の内容が法律に違反しているかどうかでもめることがあります。この記事では、公正証書遺言がもめる原因と、それに対する対策について詳しく解説します。
目次
公正証書遺言を作成していても、もめるケースはある
公正証書遺言は無効になるリスクが少ない遺言書
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を文書にまとめ、公正証書として作成する遺言書の形式であり、その信頼性と法的効力から多くの人に選ばれています。遺言者は公証役場で公証人に対して遺言の内容を口述し、公証人がその内容を正確に文書化します。この方法は、遺言内容の改ざんや紛失のリスクが低く、無効になるリスクが少ないため、安全確実な遺言書を残す手段として非常に有効です。遺言者は署名捺印するだけで、公証人が書式や法律の不備を確認するため、確実に有効な遺言書を作成することができます。
「公正証書遺言とは」については下の記事で詳しく解説しております。あわせてご覧ください。
しかしもめるリスクはある
しかし、公正証書遺言を作成したからといって、もめるリスクをゼロにすることはできません。その理由は大きく分けて二つあります。まず、公正証書遺言を作成したとしても、遺言書が無効になる可能性はゼロではありません。たとえば、遺言者が作成時に意思能力がなかったと主張される場合や、内容が法的に問題がある場合、遺言書が無効とされるリスクがあります。
次に、公正証書遺言は遺言書の形式的な有効性を保証するものですが、その内容までを保証するものではありません。遺留分を侵害する内容が含まれていた場合、相続人が遺留分を請求してもめることがあります。さらに、遺言の内容に不満を持つ相続人が遺言書の有効性を争うこともあります。
このように、公正証書遺言を作成することで、もめるリスクを軽減することはできますが、完全にゼロにすることはできないのが現実です。したがって、遺言内容を慎重に検討し、相続人間の事前のコミュニケーションも重要となります。
以下では、公正証書遺言があってももめるケースについて、具体的な例を挙げて解説していきます。
公正証書遺言があっても、もめるケース│①無効であることを争う5つの事例
公正証書遺言は公証人が関与して作成されるため、形式的な不備はほとんどありません。しかし、公正証書遺言があってももめることは避けられない場合があります。有効性に疑問が生じた場合、相続人などから「遺言無効確認訴訟」が申し立てられることがあります。これは、遺言書が無効であることを裁判所に確認してもらう手続きです。公正証書遺言が無効だと主張されるケースは、遺言者の意思能力の欠如や強制的な作成、法律に反する内容など様々です。
以下では、公正証書遺言の有効性に疑問が持たれる主なケースを詳しく解説します。
遺言書作成時に「遺言能力がなかった」場合
公正証書遺言が作成されても、その遺言者に遺言能力がなかった場合には、無効とされることがあります。遺言能力とは、遺言の内容を理解し、その効果を判断できる能力のことを指します。認知症などの理由で遺言能力が欠如している場合、その遺言は無効とされる可能性があります。実際の裁判例でも、認知症の遺言者が作成した公正証書遺言が無効とされたケースが多く見られます。
第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
(e-Gov法令検索「民法963条」)
例えば、遺言者が高度の認知症と診断されていたにもかかわらず、複雑な内容の公正証書遺言を作成した場合、その遺言能力が疑われることがあります。こうした場合、遺言無効確認訴訟が提起され、裁判所で遺言の有効性が争われることになるのです。遺言能力がなかったと主張する相続人が、医師の診断書やその他の証拠を提出して、遺言無効を立証しようとすることが一般的です。
なお、認知症であっても必ずしも遺言能力がないと判断されるわけではありません。遺言者の認知症の程度や遺言の内容、その作成時の状況などを総合的に考慮して判断されます。したがって、遺言者の遺言能力が争点となり、公正証書遺言が無効とされるかどうかはケースバイケースで決定されます。
証人が欠格事由の該当者であった場合
公正証書遺言を作成する際には、証人として2名以上の立会いが必要です。しかし、証人には欠格事由があり、特定の人物が証人になることは法律で禁止されています(民法第974条)。公正証書遺言があっても、証人が欠格事由に該当する場合、その遺言は無効となり、もめる原因になります。
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
(e-Gov法令検索「民法974条」)
欠格事由に該当する者として、遺言者の父母や祖父母、配偶者、子、孫、ひ孫、さらに受遺者の家族や推定相続人の配偶者などが挙げられます。たとえば、遺言者の子や受遺者の友人の子などは証人になることができません。公証人が証人の続柄を確認する際、口頭で「証人は親族でないですか?」などの質問を行いますが、遺言者の誤解や確認不足により、欠格事由に該当する者を証人としてしまうことがあります。
もし欠格事由に該当する者が証人となってしまった場合、その公正証書遺言は無効とされます。
口述要件を欠いていた場合
公正証書遺言を作成する際、遺言者は公証人に対して自ら遺言の内容を口述する必要があります。これは、遺言者の真意が確実に反映された遺言書であることを担保するためです。この口述要件を欠いた場合、公正証書遺言は無効とされる可能性があります。
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
(e-Gov法令検索「民法969条」)
具体的には、遺言者が公正証書遺言の内容を事前に確認しておらず、作成当日に内容を説明され、ただうなずくか「はい」と返事をするだけでは口述要件を満たしているとは認められません。実際の裁判例でも、このようなケースにおいて遺言者の口述がないと判断され、公正証書遺言が無効とされた事例があります。(大阪高判平成26年11月28日判タ1411号92頁)
口述要件を欠く公正証書遺言は、遺言者の意思に基づいて作成されたことが保証されないため、遺言無効確認訴訟が提起されることがあります。
遺言の内容に錯誤があった場合
公正証書遺言があっても、遺言者が遺言内容について勘違いや誤解をしていた場合、その遺言は無効とされることがあります。これは、遺言者の意思に基づいて作成されたとは言えないからです。錯誤による無効は、改正前の民法では無効とされていましたが、改正後の民法では取消し可能とされています。
具体的な裁判例として、遺言者が自分の財産をすべて施設Xに遺贈する内容の公正証書遺言を作成したケースがあります。遺言者は、この遺言によって施設Xが自分の障害のある子どもたちに必要な金銭を支払う義務を負うと誤解していました。しかし、実際には施設Xにそのような義務はなく、遺言者の意図とは異なる結果になることが判明しました。裁判所は、この遺言が錯誤に基づいてなされたものであるとして、公正証書遺言を無効と判断しました。
遺言者が遺言内容を正しく理解していない場合、その遺言は遺言者の真意を反映していないため、公正証書遺言であっても無効となる可能性があります。このようなケースでは、相続人同士が遺言の有効性をめぐってもめることが避けられないでしょう。
遺言の内容が公序良俗に反する場合
公正証書遺言があっても、その内容が公序良俗に反する場合には、民法第90条により無効となります。「公序良俗に反する」とは、社会的あるいは道徳的に認められない内容を指します。具体的には、正式な妻子がいるにもかかわらず「愛人に全財産を譲る」といった遺言を残し、妻子の生活基盤が脅かされるような場合が挙げられます。このようなケースでは、公序良俗違反が認められる可能性があります。
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
(e-Gov法令検索「民法90条」)
しかし、どのようなケースが公序良俗違反となるかはケースバイケースであり、判断が難しいことが多いです。公序良俗違反が認められるかどうかは、具体的な事例や社会的な背景に依存するため、事前に弁護士に相談することが重要です。
公正証書遺言があっても、もめるケース│②遺留分を侵害している場合
公正証書遺言が有効であっても、その内容が相続人の遺留分を侵害している場合には、相続人同士や受遺者との間でもめることがあります。遺留分とは、遺言者の配偶者や子ども、直系尊属(親や祖父母)に法律上保障されている遺産の最低限の取り分のことです。この遺留分は、公正証書遺言によっても奪うことはできません(なお、兄弟姉妹には遺留分はありません)。
たとえば、遺言者に妻と2人の子ども(長男と長女)がいる場合、「遺産のすべてを妻に相続させる」という公正証書遺言を作成したとします。この場合、長男と長女の遺留分はそれぞれ遺産の1/8ですが、全財産を妻に相続させる遺言内容では、この遺留分が侵害されています。このような状況では、長男と長女は妻に対して遺留分の請求をすることができます。具体的には、遺留分相当の金銭を支払うよう求めることになります。
遺留分を侵害された相続人が遺留分請求を行うことで、公正証書遺言があっても相続人同士でもめることが生じます。遺留分請求は法的に認められた権利であり、公正証書遺言によってもこの権利を制限することはできません。このため、遺留分をめぐるトラブルが発生することが避けられない場合があります。
公正証書遺言に不満がある場合の対処法
公正証書遺言を無効にしたい場合の対処法
①相続人全員で話し合う
公正証書遺言が作成されている場合でも、その内容に納得いかない相続人がいることがあります。このような場合、まずは相続人全員で話し合いを行うことが重要です。他の相続人に遺言に従うべきかどうかを確認し、全員が遺言に従わないことに合意すれば、裁判を経ずに遺産の分割方法を協議することが可能です。
例えば、父親が公正証書遺言を作成し、その内容に対して兄弟姉妹が不満を持っている場合を考えます。兄弟姉妹全員が遺言に従わないと感じているならば、相続人全員で遺産分割協議を行うことができます。この協議で新たな遺産分割の方法を決定することができます。
しかし、相続人の中に一人でも遺言に従うべきだと主張する者がいる場合、話し合いで解決するのは難しくなります。この場合、公正証書遺言の無効を主張して裁判所に申し立てる必要があります。また、相続人以外に遺産を譲られる受遺者がいる場合、その同意も必要です。受遺者も遺言に不満を持っている場合、その意見を考慮して遺産の分配方法を再度検討する必要があります。
このように、公正証書遺言の無効を求める場合、まずは相続人全員で話し合いを行い、全員が合意できるかどうかを確認することが大切です。相続人全員が合意すれば、裁判を避け、円満に遺産分割を進めることができます。
②合意できない場合は調停を行う
相続人全員での話し合いがまとまらず、公正証書遺言の無視について合意が得られない場合、次のステップとして家庭裁判所に調停を申し立てることが一般的です。調停とは、調停委員会が第三者として間に入り、相続人同士の話し合いを仲介する手続きです。調停委員会は中立の立場から提案や助言を行い、全員の同意が得られる解決策を見つける手助けをします。
調停で全員の同意が得られれば、公正証書遺言を無視して、新たな遺産分割協議を行うことができます。この方法は、裁判を避け、相続人同士の関係をできるだけ良好に保ちながら問題を解決する手段として有効です。
しかし、調停での解決が見込めない場合や、話し合いがどうしても折り合わない場合には、調停を経ずに直接訴訟を提起することもあります。
③最後には訴訟で決着をつける
調停でも相続人全員の合意が得られない場合、最終手段として「遺言無効確認訴訟」を提起し、裁判で決着をつけることになります。この訴訟では、公正証書遺言が無効であるかどうかを裁判官に判断してもらいます。訴訟を提起する際には、遺言者の意思能力の欠如や証人の欠格事由など、公正証書遺言の無効を主張するための具体的な証拠を集める必要があります。
遺言無効確認訴訟は、法律の専門知識や手続きが求められるため、弁護士に依頼することが重要です。弁護士は、遺言無効の証拠を整理し、法廷で効果的に主張するためのサポートを提供します。裁判は時間がかかることが多く、相続人同士の関係がさらに悪化するリスクもありますが、法的に確定した判決により、公正証書遺言の有効性が最終的に決定されます。
このように、公正証書遺言を無効にしたい場合、調停で解決できなければ、遺言無効確認訴訟を通じて裁判で決着をつけることが必要です。裁判を進める上で、弁護士の専門知識を活用し、適切な証拠をもとに主張を行うことで、無効を勝ち取る可能性が高まります。
遺言の内容に納得いかない場合の対処法
公正証書遺言の効力や遺留分について争いがない場合でも、その内容、特に遺産の分け方に不満を抱く相続人がいることがあります。このような場合、公正証書遺言の内容に従わず、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で遺産の分け方を決める方法があります。
まず、不満を持つ相続人は他の相続人を説得する必要があります。説得の結果、相続人全員が公正証書遺言の内容に従わないことに合意すれば、相続人全員で遺産分割協議を行い、新たな遺産分割の方法を決定することが可能です。
ここで重要なのは、相続人全員の同意に加えて、遺産を譲られる受遺者全員の同意も必要である点です。受遺者とは、法定相続人ではない親族や、被相続人が生前に世話になった相手などを指します。例えば、「長男に全財産を譲る」といった遺言がある場合でも、長男と次男が「遺産を半分ずつ相続しよう」と合意すれば、遺言書の内容に従わずに遺産を分割することができます。
ただし、公正証書遺言に遺産分割協議が禁止されていないことが前提です。また、遺言執行者が指定されている場合、その同意も必要です。遺言執行者は遺言の内容を実行する責任を持つため、その同意なしに遺言の内容を変更することはできません。
もし相続人全員と受遺者全員が合意に至らない場合や、話し合いがまとまらない場合には、次のステップとして家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停は、家庭裁判所が第三者として間に入り、相続人同士の話し合いを仲介する手続きです。調停で全員の同意が得られれば、公正証書遺言を無視して、新たな遺産分割協議を行うことができます。
遺留分を侵害されている場合の対処法
❶ 遺留分侵害額を特定するための財産調査を行う
まず、遺留分侵害額を特定するために被相続人の財産調査を行います。遺産の総額を把握し、遺留分を計算します。この段階で、遺留分を具体的に算出するための資料を集めることが重要です。
❷ 配達証明付き内容証明を送る(相続開始から1年以内)
遺留分侵害額が特定できたら、相続開始から1年以内に配達証明付き内容証明郵便で遺留分侵害額請求を行います。口頭で「請求します」と伝えても有効ですが、後で「言った言わない」や「いつ言ったか」が争点にならないよう、証拠が残る形で請求することが望ましいです。
❸ それでも決着しない場合は調停の申立
内容証明郵便で請求しても解決しない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では、調停委員会が第三者として仲介し、話し合いで解決を目指します。調停が成立すれば、裁判を避けることができます。
❹ それでも決着しない場合は、訴訟の提起
調停でも決着がつかない場合、最終手段として訴訟を提起します。裁判所で遺留分侵害額請求訴訟を行い、裁判官に判断を仰ぎます。この過程では、遺留分侵害額を証明するための具体的な証拠が求められます。
遺留分侵害額請求の時効について
遺留分侵害額請求には時効があります。相続開始と遺留分侵害を知ってから1年で請求権が消滅し、相続開始から10年が経過すると自動的に権利がなくなります。したがって、遺留分侵害に気付いたらできるだけ早く請求権を行使することが重要です。
さらに、遺言の無効を主張する場合でも、遺留分侵害額請求権の時効は進行します。遺言無効が認められなかった場合、時効が過ぎてしまえば遺留分侵害額請求を行うことができなくなります。したがって、遺言の無効と遺留分侵害額請求は同時に進める必要があります。
遺留分侵害額請求につていは、下記記事で詳しく解説しております。検討される方は参照してください。
公正証書遺言でもめないためには
弁護士に相談のうえ遺言書を作成する
公正証書遺言でもめないためには、相続に詳しい弁護士に相談して遺言書を作成することが非常に重要です。相続に関する専門知識を持つ弁護士は、遺言書がどのような場合に無効となりやすいか、またどのようにすれば相続人同士のトラブルを避けることができるかを熟知しています。そのため、もめごとを防ぐための適切なアドバイスを受けることができます。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 無効になるリスクを回避
遺言書が無効とならないよう、法的に有効な形式で作成する方法を教えてもらえます。弁護士は、遺言書の内容が法律に反していないかを確認し、無効になるリスクを回避します。 - トラブルの予防
相続人同士のトラブルを予防するための具体的なアドバイスが得られます。どのような内容がもめごとの原因になりやすいかを理解し、それを避けるための注意点を提供してくれます。 - 手続きの代行
公正証書遺言の作成手続きを弁護士に依頼することもできます。これにより、原案の作成や公証人との打ち合わせなどの面倒な手続きを代行してもらえます。弁護士が関与することで、手続きがスムーズに進み、確実に有効な遺言書を作成することができます。
公証人も遺言書作成の手続きを行いますが、公証人は遺言書の形式的・外形的な正しさを確保する役割に留まります。公正証書遺言の内容について具体的なアドバイスを求めることはできません。そのため、遺言書の内容が適切かどうか、相続人間のもめごとを避けるための対策については、相続に詳しい弁護士に相談することが最善です。
弁護士に遺言書作成を依頼するメリットについては下記の記事でも詳しく解説しております。あわせてご覧ください。
遺言者が認知症の場合は主治医の診断書を取得しておく
遺言者が認知症の場合、公正証書遺言でもめることを防ぐために、主治医の診断書を取得しておくことが非常に重要です。認知症や認知症が疑われる場合、遺言者の遺言能力を証明するための証拠を準備しておくことで、遺言の有効性を巡る争いを未然に防ぐことができます。
遺言者が公正証書遺言を作成する際に認知症であった場合、その遺言が有効かどうかは後々争いの種となる可能性があります。相続開始後、遺言能力の有無を巡って家庭裁判所で争いが起きた場合、裁判所は遺言者の年齢や病状、遺言の内容、主治医の診断書などを総合的に考慮して判断します。この際、主治医の診断書は特に重要な証拠として扱われます。
具体的には、主治医の診断書には、遺言者が公正証書遺言を作成した時点での認知機能や意思能力について詳細に記載されていることが求められます。この診断書があることで、遺言者が遺言内容を理解し判断する能力があったことを示す重要な証拠となります。
ただし、主治医の診断書があれば必ず遺言能力が認められるわけではありません。遺言能力の有無は、個々の状況に応じた裁判所の判断に委ねられます。そのため、認知症の方の遺言を作成する場合には、相続に詳しい弁護士に相談し、遺言が有効となるよう慎重に手続きを進めることが重要です。
遺留分に配慮する
公正証書遺言でもめないためには、遺留分に配慮した内容の遺言書を作成することが重要です。遺留分とは、法定相続人に法律で保障された最低限の取り分のことです。遺留分を侵害すると、相続人同士のトラブルの原因となります。以下の対策を講じることで、遺留分に関するトラブルを防ぐことができます。
①遺留分を侵害しない内容の遺言を作成する
遺留分を侵害しない内容の遺言を作成するためには、まず、それぞれの相続人の遺留分を確認する必要があります。遺留分の計算は一般の方には難しいため、弁護士に相談して正確な遺留分を把握しましょう。弁護士は、遺留分を考慮した適切な遺言書の作成をサポートしてくれます。
②遺言書の付言事項を活用する
特定の相続人を優遇する必要がある場合、遺言書に付言事項を記載する方法があります。付言事項とは、遺言者の意図や希望を記載するもので、法的な拘束力はありませんが、他の相続人に遺言者の意図を理解してもらう手助けとなります。
例えば、ある相続人が重度の障害を持ち、生活費の全てを年金で賄っている場合、他の相続人が安定した収入と資産を持っているならば、遺言書に「なぜこの特定の相続人を優遇する必要があるのか」という具体的な理由とともに、「他の相続人に対して遺留分侵害額請求をしないようお願いする」旨の希望を記載することができます。このように付言事項を活用することで、他の相続人が遺言者の意図を汲み取り、遺留分侵害額請求を控える可能性があります。
ただし、付言事項は法的な拘束力がないため、他の相続人が遺留分侵害額請求を行うことを止めることはできません。付言事項に記載された希望に従うかどうかは、最終的には各相続人の判断に委ねられます。
遺言執行者を指定しておく
公正証書遺言でもめないためには、遺言執行者を指定しておくことが効果的です。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことを指します。遺言者自身だけでなく、相続人や他の利害関係者も遺言執行者を指定することができます。
相続人が遺産の手続きを行う場合、相続人同士の不信感や対立が生じる可能性があります。このようなもめごとを防ぐために、相続人以外の中立な第三者を遺言執行者に指定することが考えられます。中立な第三者が遺言執行者となることで、相続手続きが公平かつスムーズに進むことが期待できます。
遺言執行者には、未成年者や破産者以外の者であれば誰でも指定できます。しかし、遺産や相続人の状況によっては、高度な専門知識や膨大な書類の取得が必要となる場合があります。そのため、相続に詳しい弁護士などの専門家を遺言執行者に指定することをおすすめします。弁護士が遺言執行者となることで、法的な手続きが適切に進み、相続人同士のもめごとを最小限に抑えることができます。
遺言執行者については下記記事で詳しく解説しております。あわせてご覧ください。
相続人とよく話し合っておく
公正証書遺言でもめないためには、相続人とよく話し合っておくことが重要です。遺言は遺言者が単独で作成できるものであり、遺言書を作成するにあたって推定相続人の承諾を得る必要はありません。
しかし、将来のもめごとが予見される場合には、遺言の内容についてあらかじめ推定相続人と話し合っておくことが有効です。遺言者の意図や理由を直接家族に伝えることで、家族の納得を得やすくなります。例えば、家族が集まった場で予定している遺言の内容を口頭で説明し、遺言者の思いや背景を理解してもらうよう努めると良いでしょう。
このように、事前に相続人と話し合うことで、遺言の内容についての理解を深め、相続人同士の不信感や誤解を解消することができます。これにより、公正証書遺言が実際に執行される際に、もめごとが発生するリスクを減らすことができます。
公正証書遺言でもめるケースについてのQ&A
Q1.公正証書遺言が無効とされる主な理由は何ですか?
A: 公正証書遺言が無効とされる主な理由にはいくつかあります。まず、遺言者の意思能力が欠如している場合です。遺言作成時に遺言者が認知症などで遺言内容を理解する能力がなかったと証明されると、遺言は無効となる可能性があります。また、証人が欠格事由に該当する場合も問題です。さらに、遺言者が自ら遺言内容を口述していない場合や、遺言内容が公序良俗に反する場合も無効とされることがあります。例えば、「全財産を愛人に譲る」という内容が家族の生活を脅かす場合、公序良俗に反するとして無効となることがあります。
Q2.公正証書遺言の無効を主張するにはどのような手順が必要ですか?
A: 公正証書遺言の無効を主張するには、まず遺言の無効理由を明確にし、必要な証拠を集めることが重要です。無効理由には、遺言者の意思能力の欠如や証人の欠格事由、口述要件の欠如などがあります。無効理由を証明する証拠を集めた後、家庭裁判所に遺言無効確認訴訟を提起し、裁判官に判断してもらいます。この過程で弁護士のサポートを受けることが推奨されます。
Q3.公正証書遺言の内容に納得いかない相続人がいる場合、どう対処すればよいですか?
A: 公正証書遺言の内容に納得いかない相続人がいる場合、まずは相続人全員で話し合いを行うことが重要です。不満を持つ相続人は他の相続人を説得し、全員が遺言に従わないことに合意すれば、新たな遺産分割協議を行うことができます。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることが次のステップとなります。調停でも解決しない場合には、最終的に訴訟で決着をつけることになります。
まとめ
公正証書遺言があってももめることは少なくありません。遺言の無効を主張する場合や遺留分を巡るトラブル、さらに相続人間の不満が原因で紛争が発生することがあります。
公正証書遺言が無効とされる主な理由には、遺言者の意思能力の欠如、証人の欠格事由、口述要件の欠如、そして内容が公序良俗に反する場合が挙げられます。また、遺留分を侵害する内容の遺言がトラブルの原因となりやすく、相続人同士で話し合いがまとまらない場合には、調停や訴訟に発展することもあります。
公正証書遺言でもめることを防ぐためには、相続に詳しい弁護士に相談し、遺言内容を慎重に検討することが重要です。特に遺留分に配慮した内容の遺言を作成し、遺言者の意図を明確にすることが求められます。また、遺言執行者を適切に指定し、相続人同士の話し合いを促進することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
公正証書遺言があってももめることを避けるためには、事前の準備と適切な専門家のサポートが欠かせません。相続問題に直面する前に、しっかりとした対策を講じておくことが、円滑な相続手続きと家族間の平和を保つための鍵となります。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。